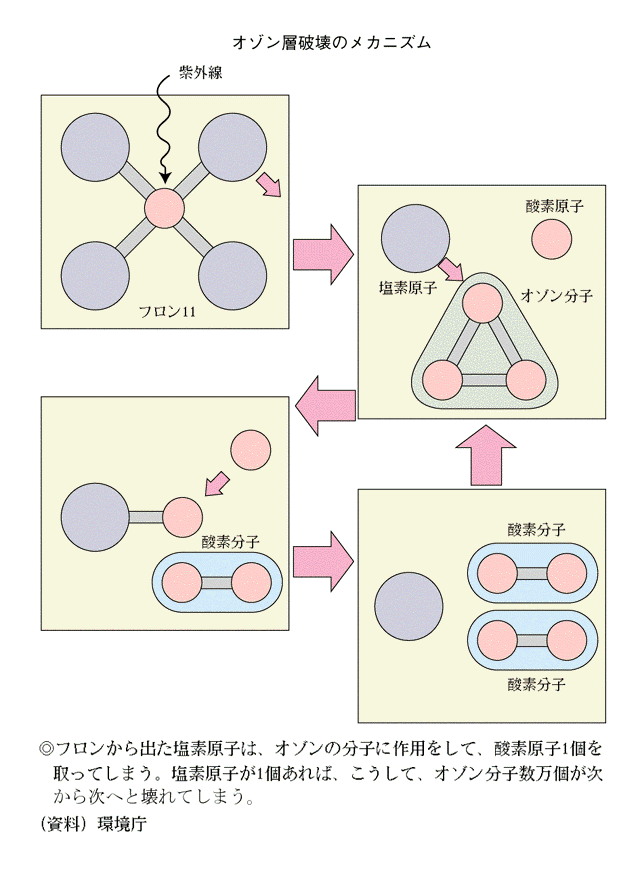
1 大気の組成等の変化による地球規模の大気環境の現状
被害・影響が地球規模にまで広がる大気環境の問題として、地球温暖化、オゾン層破壊などがある。このうち地球温暖化問題については第1章で詳しく述べたので、ここではオゾン層の破壊の問題について見てみる。
オゾン層の破壊
オゾン層破壊の問題とは、クロロフルオロカーボン(CFC、いわゆるフロンの一種)等のオゾン層破壊物質が成層圏に達し、そこで分解されて生じる塩素原子や臭素原子によりオゾン層が破壊され、オゾン層に吸収されていた有害な紫外線の地上への到達量が増加することによって、人の健康や生態系に悪影響を及ぼす問題である。
CFCの他には、ハロン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、臭化メチル等が、オゾン層を破壊する物質として知られている。
成層圏に到達する塩素等の量は、人為起源であるものが自然からの寄与によるものを遥かに凌いでいる(第4-1-1図)。
Box34 CFCによるオゾン層破壊のメカニズム
CFCは、無毒性、不燃性、化学的安定性等の利点から洗浄剤、冷媒、発泡剤、噴射剤等として幅広く利用されてきた。この利点である安定性のために、大気中に放出されても対流圏では分解されないが、成層圏に達すると太陽からの紫外線によって分解され塩素原子を放出し、この塩素原子が触媒作用によって次々と連鎖的にオゾンを破壊していく(図)。
南極においては、1970年代末から毎年春(北半球では秋にあたる)に成層圏オゾンが著しく少なくなる「オゾンホール」と呼ばれる現象が起きている(第4-1-2図(口絵),第4-1-3図)。1979年(昭和54年)から1996年(平成8年)までの各年のオゾンホールの面積の極大値の推移を見ると、1996年(平成8年)のオゾンホールは、過去最大の2,600万km2を記録し、最低オゾン全量、オゾン破壊量の値も過去4年と同程度に最大規模のものであった(第4-1-4図)。また前年に引き続き、オゾンホールの消滅時期は遅くなる傾向があり、オゾン全量の長期的傾向については全球的にほぼ減少傾向にある(第4-1-5図、第4-1-6図)。
しかしながら、国連環境計画(UNEP)の報告では、すべての締約国が1992年(平成4年)の改正モントリオール議定書を遵守すれば、対流圏中のCFC等の量(有効塩素量)は1994年をピークにその後減少に向かい、成層圏中のCFC等の量(有効塩素量)も1997年から1999年までをピークに減少に転じ、これに伴い、来世紀初頭からオゾン層は回復に転じ、南極のオゾンホールも、2045年頃までには出現しないようになると予測されている。実際の観測結果においても、米国海洋大気局(NOAA)の報告によれば、対流圏中のCFC等の量(有効塩素量)は、1994年の始めをピークに、1995年には初めて減少したことが確認されている。
こうしたオゾン層の破壊は、地上への有害紫外線(UV-B)到達量の増大をもたらし、有害紫外線によって引き起こされる皮膚がん、白内障、免疫抑制などの人の健康への影響や陸上植物及び水界生態系等への影響が心配されている。有害紫外線の地上照射量は、天候の状態に大きく左右されるため、現在のところ、有害紫外線の地上照射量の日積算値の増加傾向は確認されていないが、オゾン以外の条件が変わらなければオゾンの減少に伴い、UV-Bの地上到達量が増加することが確認されている。全球的にオゾン全量の減少傾向が見られることから、これに伴ってUV-Bの地上到達量の増加が懸念されるため、今後も引き続き監視を続けていく必要がある。
近年の深刻なオゾン層の状況を受けて、国際的な対策の枠組みが検討され、1985年(昭和60年)に「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が、1987年(昭和62年)には、この条約に基づく「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(以下「モントリオール議定書」という。)が採択され、CFC等の生産及び消費の段階的な削減を行うことが合意された。
これを受け、我が国では、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下、「オゾン層保護法」という。)を1988年(昭和63年)に制定し、CFC等の生産規制等を実施しており、1993年(平成5年)末にはハロンの生産が、1995年(平成7年)末にはCFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン及びHBFCの生産がそれぞれ全廃された。
また、1995年(平成7年)のモントリオール議定書第7回締約国会合では、HCFCの生産全廃時期の前倒し、臭化メチルの生産全廃時期の確定、それまで規制が猶予されていた開発途上国に対するオゾン層破壊物質の生産規制スケジュールの設定等が決議された。
一方、CFC等のオゾン層破壊物質の生産規制等に加え、現在、機器等に充填された形で存在しているCFC等の回収・再利用・破壊の促進が重要な課題となっており、我が国では、関係18省庁からなる「オゾン層保護対策推進会議」が平成7年6月に「CFC等の回収・再利用・破壊の促進について」を取りまとめ、CFC等の回収等の促進を図っている。また、環境庁は平成8年5月に「CFC破壊処理ガイドライン」を公表し、適切なフロン破壊処理に向け積極的な取組を促している。さらに、通商産業省においては、プラズマ分解処理技術及び燃焼法分解処理技術の研究開発が進められている。現在、政府においては、平成7年6月以降の状況の変化を踏まえ、オゾン層保護対策推進会議において、CFC等の回収・再利用・破壊の一層の促進方策について検討を進めているところである。
なお、通商産業省は、平成9年3月に化学品審議会オゾン層保護対策部会回収再利用等対策分科会において、「特定フロンの回収等に関する今後の取組の在り方について」をとりまとめ、同省はこれを受け、関係省庁と連携をとりながら、関係業界等に協力を要請する等、CFCの回収・再利用・破壊の促進に努めることとしている。