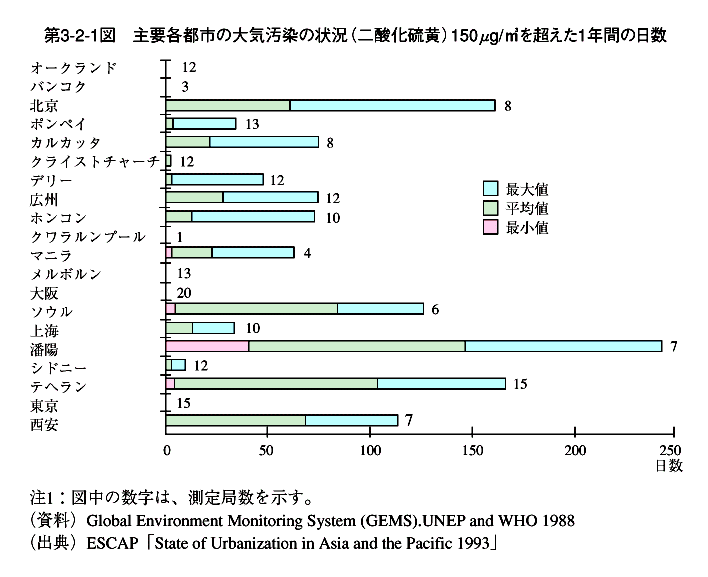
3 開発途上地域との国際協力の推進
開発途上地域において環境保全を進めるためには、法規制等の制度、環境管理に関する幅広いノウハウ、対策実施のための人材、環境モニタリング等の技術、さらに環境教育・環境学習等の各種基盤の整備が重要である。ここでは、こうした基盤整備のための国際協力について考える。
(1) 開発途上地域の環境問題の深刻化
開発途上地域の中には様々な開発レベルの国があり、また、環境の状況も地域ごとに異なっている。しかし、一般に、開発途上国においては、急激な速度で人口が増加し、環境に対する圧力が高まっている状況にあると言える。
ア アジアの状況
アジアにおいては、1970年頃から韓国、台湾、香港、シンガポールが、1980年代からはタイ、マレーシア、インドネシアなどの東南アジア諸国と中国の急速な経済成長が始まり、今やアジアは21世紀の世界経済の成長センターと目されるに至っている。しかし、これらの国々では、「圧縮工業化」と呼ばれる短期間での急激な工業化によって、かつて我が国が経験したような従来型の産業公害が深刻化している。第3-2-1図は、世界の主要都市における二酸化硫黄による大気汚染の状況を示したものであるが、濃度150μg/m3を超える日数が多いのは、圧倒的に、日本を除くアジア諸国の都市である。ESCAPの「アジア太平洋地域における環境の状況1995」によると、アジア地域における二酸化硫黄排出量は、2010年には1995年の2倍に増大することが予測されている。
また、アジア諸国は従来型の産業公害に直面する一方で、地球温暖化等の地球環境問題等への対処も大きな課題となっている。
イ 中南米の状況
中南米諸国においては、急激な産業の近代化、海外投資の増大、一極集中型の都市化が進行している。メキシコのメキシコシティ、チリのサンチャゴなどの主要都市では都市施設の整備が追いつかず、大都市特有の大気汚染、有害廃棄物処理等の都市公害問題が深刻化している。
ウ アフリカの状況
アフリカの開発途上諸国は、一般的に他の開発途上地域よりも開発レベルが低く、労働人口の80%以上が農業などの一次産業に従事するという産業構造であり、気候変動に大きな影響を受けやすい状況にある。また、人口増加率の高い国々が多いため、必然的に限られた自然資源への圧迫がある。こうした中で、薪炭材の過剰採取等による森林破壊や、1968年から73年にかけてサハラ砂漠南縁のサヘル地域を襲った大干ばつや、過耕作、過放牧等による砂漠化等が進行している。
エ 国際協力の必要性
開発途上国においては、環境保全対策の基礎となる科学的調査研究が行われることは稀であり、また、環境保全のための組織や法律が存在しても、効果をもたらすよう実際に動かすことができない状況にある。これは、物的な生活水準の向上を実現するために、開発に政策上のプライオリティが置かれ、環境の保全は後回しにされている場合が少なくないことに加え、環境保全のための資金、技術、人材等が不足していることに大きな原因がある。このように、資金提供、技術協力、人材養成等の面で、先進国の途上国支援が必要不可欠なものとなっている。
(2) 環境保全のための国際協力の取組
ア 我が国の国際協力の在り方
開発途上国における公害をはじめとする環境問題の深刻化は、人類共通の課題として取り組まなければならない問題である。我が国は、深刻な公害を克服してきた国として、その経験とこれまでに培ってきた技術を、成功例にとどまらず、失敗事例やその解決の過程における困難、そしてそれを克服してきた努力などを含めて開発途上国に提供し、その国々が同じ過ちを繰り返すことのないようにすることが重要である。また、地球温暖化や砂漠化の防止など地球環境を保全するための努力は、ひとり我が国における国内努力のみならず、国際的な協力が不可欠な課題であり、我が国は、国際社会に占める地位に応じて、国際的な環境協力を推進していかなければならない。
イ 効果的な援助の実施
我が国は、平成4年に閣議決定した政府開発援助大綱(ODA大綱)において、基本理念として環境の保全を掲げるとともに、環境と開発の両立を援助の実施原則として位置付けるなど、環境の保全を重視した政府開発援助を実施する姿勢を明確にしている。また、同年に開催された地球サミット(国連環境開発会議 UNCED)において、我が国は環境分野への二国間及び多国間政府開発援助(環境ODA)を、平成4年度から5年間で9千億円から1兆円を目途に大幅に拡充・強化することを世界に向けて表明している。これらを受けて、我が国は環境ODAの拡充・強化に努め、平成4年度から7年度までの4年間の総額は、約9,800億円となり、地球サミットの際に表明された目標額は4年目で既に達成された(第3-2-2表、第3-2-2図)。
また、開発途上国への援助を効果的に行うためには、途上国自身の自助努力の支援を基本とし、援助形態について考慮することが重要であることから、我が国は、環境分野において有償資金協力及び無償資金協力を弾力的に運用するとともに、これら資金協力と技術協力との有機的連携を図り、各形態の特性を最大限生かした援助に努めているところである。
これに加え、実施機関においては、環境配慮のための各種ガイドラインによって、環境に留意した援助を行っている。なお、有償資金協力においては、平成7年から、通常の貸付金利よりも低い「環境特別金利」を創設し、開発途上国の環境保全事業の推進を促している。
一方、総務庁は、平成9年3月、円借款における環境問題への対応について、公害対策や自然環境保全に係る案件が少ない状況であること、公害対策に係る案件等については迅速な実施が必要であるにもかかわらず、急遽追加要請を行っても既要請案件の後回しにされることを懸念した開発途上国が、他の先進国に要請を行った例がみられることなどを指摘し、これらの改善のために、政策対話の推進や借款条件の緩和等の検討、公害対策に係る案件についての円借款手続の弾力化などが必要であるとして、関係省庁に勧告した。これらの状況を踏まえ、環境問題への対応をより一層効果的かつ効率的に実施する必要がある。
ウ 技術・ノウハウ等の移転
開発途上国において有効な環境保全対策が講じられるためには、途上国自身が環境問題の処理能力を持ち、問題の解決に主体的に努力していくことが必要である。したがって、開発途上国側の技術受入基盤を考慮せずに、ハードを中心とした対策技術の部分のみの移転を先行させるのではなく、相手国の技術レベルに適合した対策技術の導入や、相手国の環境分野における行政能力と長期的な技術教育等による技術基盤の育成などに努めていかなければならない。また、対策技術の移転に際しては、その技術が開発されるようになった背景等に関する情報も併せて提供していくことが肝要である。さらに、民間レベルの国際協力を推進し、民間部門の有する技術・ノウハウ等の移転を図るとともに、我が国の民間団体等による技術協力や途上国の民間団体等の自主的取組を支援することも重要である。
我が国では、こうした考え方に立って、様々な環境保全に関する国際協力を積極的に推進している。
(ア) JICA等による技術的基盤の育成のための国際協力の推進
国際協力事業団(JICA)では、政府開発援助として、関係省庁、地方公共団体等の協力の下に、開発途上国に対する様々な環境協力を行っている。開発途上国の行政機関・研究機関等への技術協力を行うための専門家の派遣や、環境保全に関する専門的な知識等を有する行政官や技術者を養成するための途上国からの個別研修員の受入れ、環境に係る分析・モニタリング等の機材の提供、さらに、これらを組み合わせたプロジェクト方式技術協力などは、こうした環境協力の一つである。
近年、プロジェクト方式技術協力に、環境センター等の設立・運営のための無償資金協力を組み合わせ、開発途上国における技術者の育成等の「人づくり」や社会環境基盤整備等に重点を置いた環境協力が積極的に行われている。
Box29 日中友好環境保全センター
中国は、1978年から改革・開放路線に転換し、経済特別区の設定や外資の導入が積極的に押し進められた結果、急激な経済成長が進み、これに伴い、大気汚染や水質汚濁等の環境問題が深刻化している。中国政府は、1979年から環境保全対策に取り組みつつあったが、環境管理手法や環境観測技術の確立、人材養成が喫緊の課題となっていた。
こうした背景の下、1988年、日中平和友好条約10周年記念事業として、日中友好環境保全センターの建設が決定し、まず、90年から95年にかけて、日本から105億円の無償資金協力を行い、並行して92年から95年までセンター職員となる中国側メンバーに基礎技術を移転するためのプロジェクト方式技術協力「日中友好環境保全センタープロジェクト(フェーズ?)」を実施した。96年2月、センターの開所を前に本格的協力として「フェーズ?」が開始されている。
同センターは、国家環境保護局に6部(室)の体制で、96年5月に開所し、環境庁、通商産業省、新潟県、北九州市等から各分野の専門家が派遣され、環境観測技術の標準化、中国の実情に合致した公害防止技術の研究、環境に係るデー夕の集積・解析等の技術の確立、環境保全に係る人材の養成、一般への普及啓発等に取り組んでいる。
こうした協力形態のさきがけとなったのは、平成2年から実施しているタイにおけるプロジェクトであり、環境研究者・技術者の技能・技術の向上を図るため、無償資全協力と技術協力により「環境研究研修センター」を建設し、専門家チームの派遣、研修員の受け入れ等を行っている。また、公害問題が深刻化している中国においても、モニタリング・システムとデータ処理の水準を高めるとともに、環境分野の研究・研修を推進するため、平成4年から「日中友好環境保全センタープロジェクト」を開始している。同年、インドネシアにおいても「インドネシア・環境管理センタープロジェクト」が実施されているほか、平成7年からは、チリ及びメキシコにおいても同様の環境協力が開始されている。
また、国際協力事業団以外にも、農用地整備公団など、それぞれの分野で専門的な技術・ノウハウ等を有する公団などにおいても、開発途上国に対する様々な環境協力の取組が行われている。
Box30 農用地整備公団による砂漠化防止のための国際協力
農用地整備公団は、1985年から、農林水産省の補助金を受けて、アフリカのサヘル地域において砂漠化防止対策のための調査を行っている。この調査は、砂漠化しつつある土地の潜在的生産力を引き出し、地域の自然等の現状認識の方法、農地保全・植林・水資源開発等の技術、地域の開発計画の策定方法等、砂漠化防止の技術パッケージを確立し、これを基に、国際機関、二国間援助機関、各国政府等による具体的な事業化を期待しようとするものである。
同公団は、まず、砂漠化の原因分析等の基礎的な調査を行い、次いで、ニジェールの首都ニアメ近郊のマグー村に実証ほ場を設けて、技術研究を行い、技術マニュアルと砂漠化防止モデル計画を整備した。現在、サヘル地域各国の自然、社会及び経済に関する情報の収集分析、各地域のモデル計画の策定、マグー村技術マニュアルの汎用化等を進めている。
この調査を実施するに当たっては、伝統的社会制度や住民意識との調和に配慮がなされるとともに、パッケージされる技術については、現地の人々が容易に使用し得るものが選択され、設置される施設の整備・維持管理についても、現地の経済力の範囲内で可能な水準のものが選択されるなど、地元の技術的な受入基盤や経済的な状況への適合性が重視されている。
(イ) 環境庁による環境モニタリング体制の整備のための国際協力の推進
開発途上国における環境保全対策の実施が急務となっている中で、途上国が自ら主体的に環境保全を推進するには、まず、自国の環境の状況を客観的に把握し、その状況に応じた対策が講じられなければならない。
環境庁では、我が国の環境モニタリング、とりわけ、有害化学物質の環境モニタリングの経験を踏まえて、平成6年度から、中国、フィリピン等を対象に「西太平洋地域化学物質環境モニタリング支援事業」を実施している。同事業は、調査対象物の選定、調査地点・調査媒体の考え方、調査試料の扱いなどについて、国情に合致した化学物質の環境モニタリングのための標準指針を作成することとしている。
また、こうした取組を実りあるものとし、有効な環境保全対策を実現させるためには、環境測定分析データの信頼性を向上させ、環境の実態が正確に把握されることが不可欠である。
我が国においては、精度の高い環境測定分析データを得ることを目的として、昭和50年度から、共通の環境試料を同時に多数の測定分析機関で測定し、その分析結果を解析し、分析値のばらつきの要因を究明して分析手法等の改善を行うことにより、環境測定分析に係る精度管理を推進してきた。
環境庁は、こうした我が国の精度管理手法の途上国への技術移転を図るため、平成7年度から「アジア地域途上国の環境測定分析に係る精度管理体制の整備支援事業」を実施しており、タイ、中国等におけるモデル調査等を通じて、当該地域の現状に応じた精度管理を実施するためのマニュアルを作成することとしている。
エ 民間団体による環境協力の推進とその支援
地球環境を保全していくためには、国レベルでの国際協力のみならず、民間レベルでの協力も重要である。民間団体の中には、開発途上地域において環境保全活動を進めている団体が少なくない。こうした団体では、途上地域の実情に合わせた様々な活動が行われているが、とりわけ、近年は、植林などの実践的活動に加えて、環境保全活動を現地住民が主体的に行うことを目指した環境教育や環境学習を併せて行う事例が日立っている。
1の(4)のウで述べたように、環境事業団に設置された地球環境基金は、国内での環境保全活動のみならず、内外の民間団体が開発途上地域において現地の住民等の参加を得て行う環境保全活動にも資金助成を行っている。
Box31 海外で活躍するNGOへの支援
地球環境基金が資金助成を行っている活動の一つに、北九州市のアフリカ教育基金の会(AEF)による活動がある。同会は、アフリカの戦災犠牲者や帰還難民の救済のため、医療・保健衛生・環境保全等の活動を行っている団体で、平成5年から7年にかけて、干ばつ被災地であるケニア北東部のマンデーラ県において環境研修センターを建設し、保健衛生・環境に関する教育を行うと同時に、住民と共同で植林活動を行ってきた。平成8年からは、内戦の主戦場となり荒廃の著しいソマリア南部のアフマド県において、同様の取組を進めている。
また、地球環境基金が資金助成を行っている海外の民間団体の活動として、中米グアテマラのグアテマラ野生生物救護保護協会(ARCAS)が、平成4年(1992年)からハワイ自然保護区において行っているウミガメの保護繁殖活動が挙げられる。同会による活動は、卵の乱獲等により絶滅の危機に瀕しているヒメウミガメやオサガメを救うため、国連世界食糧計画(WFP)から寄付されたコーンをウミガメの卵と交換する「FOODFOR EGGS店」を開設し、卵を回収する活動が中心となっている。