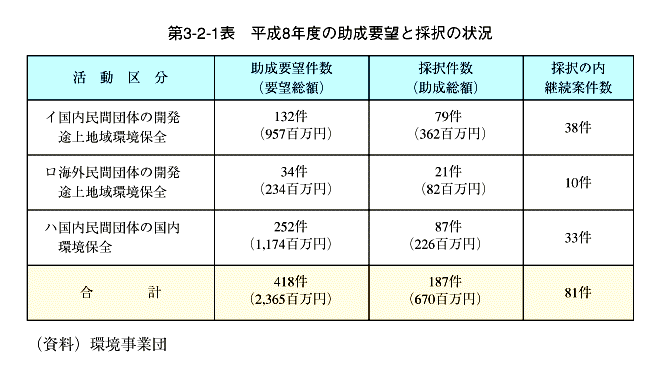
1 環境教育・環境学習の振興と民間の活動の支援
(1) 環境教育・環境学習の取組の経緯
環境教育については、1972年にストックホルムで開催された国連人間環境会議において採択された「人間環境宣言」の中で、その重要性が明確に指摘されたのを契機として、UNESCO/UNEPを中心として、環境教育の国際的な取組が進められた。1975年にはベオグラードで「国際環境教育ワークショップ」が60カ国、96名の環境教育専門家の参加を得て開催され、その際にとりまとめられた「ベオグラード憲章」において、「環境とそれにかかわる問題に気づき、関心を持つとともに、当面する問題の解決や新しい問題の発生を未然に防止するための知識、技能、態度、意欲、遂行力を身に付けた人々を育てること」の重要性とそのための環境教育の内容、在り方等のフレームワークが示された。これらの成果は、その後の環境教育に関する理論的な規範となっている。
ア アメリカの取組
アメリカでは、既に、1970年に「環境教育法(EnvironmentalEducation Act)」が制定され、教育省、福祉省、保健省の教育局が環境教育の事業に当たること、カリキュラムの研究、開発、普及や環境教育の指導者の研修などについて規定されていた。同法は、その後、1981年に廃止されたが、地球環境問題に対する論議が高まる中で、1990年に新しい「環境教育法」が制定された。同法では、環境保護庁(EPA)が連邦諸機関の中心となって、環境教育プログラムの開発、環境教育プロジェクトに対する補助金の交付、大学からの実習生や現職教員への政府機関での研修・研究機会の提供、顕彰制度の運営等の施策を行うこと、環境教育・研修財団を設立すること等が規定された。
イ 我が国の取組
我が国で、環境教育の取組が急速に広まったのは、昭和60年代に入ってからである。昭和63年3月、環境庁の環境教育懇談会が、環境教育の基本的考え方を明らかにして以降、国において積極的な環境教育・環境学習の取組が進められた。当時、環境教育・環境学習への関心が高まり始めた背景には、特定の発生源に対する厳しい環境規制が効果を発揮して産業公害が一応沈静化しつつある一方で、日常生活や通常の事業活動が大きな原因となっている都市・生活型公害については改善が見られず、むしろ悪化していたことが挙げられる。
平成5年に成立した環境基本法では、「環境の保全に関する教育及び学習の振興」を環境保全のための主要な施策の一つとして規定し、我が国においても、環境教育・環境学習の重要性が法制上位置付けられた。
また、地球温暖化の大きな原因であるエネルギーの利用に関して、国民の理解を深めることが重要な課題となっており、平成9年4月1日開催された「第26回総合エネルギー対策推進閣僚会議」においては、ライフスタイルの見直しを含めた、一人ひとりのエネルギー問題への一層の取組が不可欠であり、資源・エネルギーに関する教育の充実などを図ることとされた。
(2) 環境教育・環境学習の理念
環境教育・環境学習の目指すところは、まず、?今日の環境の状況を認識し、?環境問題がエネルギーの消費等人間の経済活動や日常的な活動に由来しているという人間と環境とのかかわりを理解し、?社会全体の生活様式や経済活動の変革の必要性を学ぶことである。そして、その上で、?これを単なる環境に係る知識の習得にとどめるのではなく、習得した知識を踏まえて、自らの行動と環境とのかかわりを常に意識し、可能な限り環境に負荷を与えない生活を実践していく能力(=環境リテラシ一)を養成することである。20世紀が産業化、近代化に向かった躍進の世紀であるなら、21世紀は環境リテラシーの養成によって、環境保全型社会を構築する世紀にしなければならない。
環境教育・環境学習は、国民一人ひとりが自ら学習する主体であるとの認識の下に、幼児から成人・高齢者へのライフ・ステージに合わせ、生涯学習として展開されることが必要である。
また、生涯学習としての環境教育や環境学習は、国や地方公共団体といった行政からの働きかけや、学校教育によってのみなされるものではない。行政、NGO、事業者、国民等多様な主体が連携を取りつつ、学校、家庭、地域、職場、野外活動の場等、多様な場において多角的に展開される必要がある。
(3) 次世代を担う子ども達のための環境学習の推進
次世代を担う子ども達の環境教育は、人間形成の最も基礎的な段階で、人間と環境とのかかわりについての幅広い理解を深め、環境保全意識を体得し、さらには、豊かな感性や環境問題への感受性を養うものであり、極めて重要である。
農薬汚染をテーマに取り上げた『沈黙の春』で環境問題の警鐘に貢献したとされるレイチェル・カーソンは、死後にまとめられた最後の著書の中で、自然の持つ神秘さに目を見はる感性を「センス・オブ・ワンダー」と呼んだ。まさにこのセンス・オブ・ワンダーを育むことこそが、子ども時代の環境教育で大切なことである。
子ども達の環境教育を推進する目的は、当然のことながら、今日の環境問題の解決を将来世代に託すことにあるのではない。現在の世代は、環境問題という負の遺産を清算した上で将来世代にバトンを渡す義務があり、その環境を将来にわたって維持することにこそ、子ども達の環境教育を推進する意義があるのである。
ア 学校教育における取組
学校教育においては、従来から社会科、理科、保健体育科等を中心に、小・中・高等学校を通じて児童生徒の発達段階に応じて、環境に関する内容が取り扱われてきた。学習指導要領においても、昭和40年代から公害問題等が取り上げられてきたが、昭和52年の学習指導要領の改訂では、環境にかかわる内容が各学年において盛り込まれ、さらに、平成元年の学習指導要領の改訂により、小学校低学年に身近な環境についての理解を深める生活科が新設されたことをはじめ、多くの教科等において環境教育にかかわる内容の一層の充実が図られている。
また、文部省では、各学校での取組を推進・支援するため、環境庁等の協力により教師用の『環境教育指導資料』を平成3年、平成4年及び平成7年に作成した。さらに、平成3年度から「環境教育シンポジウム」を開催し、平成6年度からはこれを「全国環境教育フェア」に発展させ、小中学校における環境問題に関する各種活動成果の発表・展示会等を行っているほか、学校・家庭・地域社会が一体となって環境教育の推進に取り組む「環境教育推進モデル市町村」の指定やGLOBE計画に基づき「環境のための地球学習観測プログラムモデル校」の指定、「環境教育担当教員講習会」も実施している。
平成8年7月、中央教育審議会において、「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」(第一次答申)が出されたが、この中で、社会の変化に対応する教育として、環境問題に対応し、学校や地域社会における環境教育の一層の改善・充実を図ることが提言されている。こうした答申を受け、平成9年1月、文部省は教育改革プログラムをとりまとめ、この中で、環境保全の視点が教育においても重要であるとして、環境やエネルギーへの理解を深め実践する態度や能力を育成できるよう体験的な学習を重視し、学校における環境教育の一層の充実、環境教育についての教員の指導力の向上、関係機関や関係団体等との連携などを図ることとしている。
イ 地域社会等における取組(こどもエコクラブ)
グループ活動を通じた環境教育・環境学習や様々な環境保全活動は、学校以外の地域社会の場においても活発化してきている。
平成7年6月から、環境庁では、次世代を担う子ども達が地域の中で仲間とともに地域環境や地球環境のために自主的に環境保全活動や環境学習に取り組むことを応援するため、全国の小中学生を対象として「こどもエコクラブ」への参加を呼びかけ、その活動を支援している。
同クラブでは、それぞれのクラブのメンバーの興味・関心に基づいて自らの活動内容を決めて自主的に行う「エコロジカルあくしょん」を中心的な活動としている。この活動は、水生生物調査、星空観察、空き缶や空き瓶などのリサイクル、昆虫生息調査、河川の水質調査、環境の観点から生活を振り返る「くらしのエコチェック」などを具体的な内容としており、地域の環境に密着した多様な活動が展開されている。その他に、食べ物と地球のつながりを考えたり、町と暮らしのウォッチングを行うなど、自主活動をより豊かなものとするためにこどもエコクラブ全国事務局から紹介される「エコロジカルとれーにんぐ」と呼ばれる全国共通の活動も展開されている。
また、全国事務局では、全国のクラブのコミュニケーションを図るため、各地の活動情報や環境に関する様々な情報を提供する「こどもエコクラブニュース」の発行や、各クラブの交流を深める「こどもエコクラブ全国フェスティバル」の開催を行っている。さらに、クラブのメンバーとアジアの子ども達との交流やシンポジウムなどを行う「こどもエコクラブアジア会議」も開催している。
平成9年3月末現在、全国のこどもエコクラブ数は、約2,950団体にのぼり、約45,000人が活動している。
Box26 市民主導の運営を図る西宮市「2001年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや」
兵庫県西宮市が平成4年4月に発足させた「2001年・地球ウォッチングクラブ.にしのみや(EarthWatching Club 略称EWC)」は、こどもエコクラブの基本モデルとなったクラブ方式の環境学習システムである。EWCは、「エコチャレンジ活動」と呼ばれる身近な自然や町の観察活動を通じて、子ども達の環境学習や自主的な地球を守る活動を促進しようとするものであり、こどもエコクラブ参加団体の一つとして、平成8年度には、約170グループ、2,800人の会員が活動している。
このEWCの活動体制の特徴の一つは、様々な団体とのネットワーク化である。各学校を通じた会員募集や授業の中での活用により、教育委員会、学校現場、PTA等との協力体制を構築しているほか、青年会議所、公民館、自然保護団体、企業などと事業の共催化などを推進している。
もう一つの特徴は、市民ボランティアによる運営の推進である。学習プログラムの指導やニュースレターの作成等、EWCの全活動が100名近い市民ボランティアに支えられており、加えて、平成8年4月からは、民間企業に勤務する会社員が、勤務先のボランティア休業制度を利用し、市民専従スタッフとして事務局の連営を行っている。
こうした試みは、EWC自体を市民主導の全市的な環境学習システムへと発展させようとする先進的な取組として注目される。
(4) 環境教育・環境学習及び環境保全活動に係るシステムの構築
環境問題を解決するためには、一般市民が自ら環境学習や環境保全活動を継続的に実施していくことが極めて重要であり、そうした市民の主体的な行動を支援していくための仕組みの構築が求められている。このため、近年、国、地方公共団体等を中心にして、活動拠点の整備、指導者の養成、経済的な支援など、積極的な取組が行われ始めている。
ア 環境学習・環境保全活動の促進拠点の整備
環境学習や環境保全活動に対して意欲を持っている市民は多いが、その取組方法がわからず、具体的な行動につながらないことも多い。このような市民の意欲を行動につなげるためには、相談窓口の充実、情報の提供あるいは市民相互の交流の促進を図ることが必要である。こうした課題に応えるため、環境学習・環境保全活動の促進拠点の整備が各地で進められている。
(ア) 環境パートナーシップ形成支援拠点の整備
今日の環境問題を解決していくためには、平成8年版環境白書が指摘しているとおり、社会の各主体が、環境とのかかわりを理解し、それぞれが責任を分担して、公平な役割分担の下に、連携して環境保全に取り組む「パートナーシップ」が重要な鍵である。しかしながら、このパートナーシップの形成には、様々な阻害要因──情報が共有されていないこと、相互の立場の理解不足等のコミュニケーション・ギャップ、具体的な課題について対等な立場で話し合う場の不足等──が存在している。
環境庁は、こうした阻害要因を取り除き、様々な場面における様々な主体間のパートナーシップの形成を支援することを目的として、平成8年7月に、「環境パートナーシップオフィス(ENVIRONMENTALPARTNERSHIP OFFICE(EPO))」を、平成8年10月には、国際連合大学との共同事業として、「地球環境パートナーシッププラザ(略称環境プラザ)(GLOBALENVIRONMENT INFORMATIONCENTRE(GEIC))」を東京青山の国連大学本部施設内に開設した。
a 環境パートナーシップオフィス
環境パートナーシップオフィスは、環境庁、NGO、企業などが環境問題に対して連携協力して取組を行う拠点として開設され、運営方針を決定する「環境パートナーシップ協議会」と事務局で構成されている。協議会には環境庁、NGO、企業等が参加し、事務局にも各主体から派遣されたスタッフが常駐して運営に当たっている。オフィスは、?環境パートナーシップの理解と普及、?各主体の相互理解や情報の共有の促進、?市民による環境保全活動の支援等を活動の柱とし、具体的には、環境プラザへの情報の提供やプラザの活動に対する協力を行うとともに、セミナールームや作業スペースの提供など、交流の場の提供も行っている。
b 地球環境パートナーシッププラザ
環境プラザは、環境庁と国際連合の共同事業として開設されたものであり、次の3つの事業を実施することにより、環境パートナーシップの形成を支援している。
(a) 地球的規模での情報発信(GLOBAL PROJECT)
インターネット上にホームページ(アドレス http://www.geic.or.jp)を開設して国際的な環境政策の動向を紹介し、また、地球規模での環境政策の企画立案プロセスへの環境NGOの参加を支援するため、インターネット上での国際機関とNGOとの交流の場の提供を行っている。平成8年及び平成9年には、特に、地球温暖化をテーマとした国際的動向に関する情報の提供等を進めている。
(b) NGO、企業、行政等の社会の主体間のネットワークづくり
(NETWORKING)
各主体間のパートナーシップの形成を促進するため、NGO、企業、行政等の環境保全の取組に関する情報や地球温暖化に関する科学データ等の収集・提供、環境に関する様々な相談に対応する環境カウンセリング、交流会等のセミナースペースの提供等を行っている。
(c) 環境問題や環境保全の取組を紹介する普及啓発事業
(PUBLIC INFORMATION)
水俣病などの環境問題や、各地で行われているリサイクル活動や公園づくりなどの環境保全のための取組を紹介する展示や、環境に関するワークショップの開催等を行っている。
(イ) 地域独自の環境学習・環境保全活動促進拠点の整備
地域住民と直接かかわることの多い地方公共団体においては、地域特有の歴史や自然などを生かした、独自の拠点整備が進められている。
a 屋久島環境文化村
鹿児島県では、「縄文杉」などの貴重なヤクスギ巨木群等により世界遺産として登録された屋久島を舞台に、「屋久島環境文化村構想」を推進している。これは、屋久島において何千年にもわたって積み重ねられてきた自然と人間のかかわりを「環境文化」と呼び、学習や研究によってその価値を見直すことを通して、自然と人間とが共生する屋久島ならではの個性的な地域づくりを目指すものである。
この構想における先導的な事業として、平成8年7月、島内に「屋久島環境文化付センター」と「屋久島環境文化研修センター」を開設し、島の豊かな環境に身を置きながら、特有の自然、歴史、文化、産業などに触れて人と環境の在り方を学び、地域づくりに反映させていくような環境学習の拠点づくりを進めている。環境文化村センターでは、屋久島の自然・文化に関する総合的な情報や環境学習を推進するための情報を大型映像や常設展示により提供しているほか、島内外の人々やボランティアの交流の場の提供、学校や民間団体に対する島の基礎的な環境学習のレクチャー等も行っている。一方、環境文化研修センターは、環境学習を推進するための研修施設であり、屋久島全体を自然の博物館(フィールド・ミュージアム)としてとらえ、島の自然の仕組みや島における生活・生産活動を素材にした、五感による体験的な環境学習プログラムが展開されている。
b 名古屋市環境学習センター エコパルなごや
名古屋市では、平成7年12月、小中学生を核に、家族、一般社会人などを対象に、各人が身近なところから環境保全に取り組むための環境学習の拠点施設として、「名古屋市環境学習センターエコパルなごや」を開設した。同センターでは、環境学習の第一歩が人間と環境のかかわりを見つめ直すことから始まるという観点から、センターの壁画として我々の日常生活が描かれる一方、中央部には環境に配慮がなされた未来都市のオブジェが設置され、人間と環境との密接な関係に気づき、未来の街づくりへの想像をかき立てる趣向が凝らされている。また、様々な生物相互のかかわりや生物が果たしている環境上の役割などを体験的に学ぶことを目的に、日常生活では体験することができない土の中の探検などを、仮想現実(バーチャル・リアリティー)の手法により体験することを可能とした「バーチャルシアター」も設置されている。
イ 環境学習・環境保全活動のための指導者養成
近年、市民団体等による自主的な環境学習や環境保全活動が広がりつつあるが、我が国のNGOにおいては、高度な知識を有した人材や、組織管理能力を有する指導者の確保は非常に困難な状況にある。また、こうした市民団体等からは、その取組を展開するための手法や取組を推進して行く際の問題について、相談を行い、適切な助言を得る機会を求める声が上がっている。
このような社会的要請に応えるため、近年、環境学習や環境保全活動に係る指導者の養成に向けた取組が行われ始めている。
(ア) 指導者の研修
環境学習や環境保全活動を行う民間団体が、指導者としての人材を確保するに当たって直面する問題の一つに、専門的な研修カリキュラムの不足があり、こうした状況を解消するための取組が行われている。
a 地方公共団体の取組
東京都では、平成6年度から、地域の環境学習や環境保全活動を率先して行うリーダーを育成することを目的とした「東京都環境学習リーダー講座」を、東京都環境学習センターにおいて開設しているほか、平成2年度から講座を開設している埼玉県をはじめ、多くの地方公共団体において、指導者養成のための研修カリキュラムの提供が行われており、環境保全を市民レベルから進めるための人材養成が、各地で活発化している。
b 地球環境市民大学校
環境事業団では、平成9年度から、一般市民や環境保全活動に携わる民間団体等のメンバーに学習機会を提供する「地球環境市民大学校」を創設する。同大学校では、一般市民向けに、環境問題に関する基礎的知識の習得を目指した研修を行うとともに、環境問題全般にわたって高度で幅広い知識を持ち、組織管理能力に長け、民間団体等の環境保全活動を担うことのできる人材の育成を目的とした高度な研修を行うことを予定している。
(イ) 指導者・助言者の登録・派遣
近年、国や地方公共団体において、市民や民間団体、事業者の自主的な環境学習や環境保全活動を支援することを目的として、環境に関する知識や環境保全活動の経験を有し、かつ、地域で指導・助言を行うことができる人材をあらかじめ登録しておき、市民等からの要請に応じてこうした人材を派遣する取組が推進されている。
a 地方公共団体の取組
宮城県では、平成2年度から「環境保全活動アドバイザー制度」を設けて、環境保全活動で実績のある人材をアドバイザーとして委嘱し、住民等からの派遣依頼に応じて、廃棄物リサイクル、生活排水、自然観察、地球環境の保全等に関する講演会等の講師や実習指導者としてアドバイザーを派遣する取組を実施している。また、登録・派遣と併せ、委嘱したアドバイザーの研修を行い、指導能力の向上を図る取組も行っている。
b 環境カウンセラー登録制度
環境庁においては、平成8年9月、環境に関する広範かつ専門的な知識や豊富な経験を有する人材の発掘と把握を行い、さらにその能力を向上させつつ活用することを通じ、各主体の環境学習・環境保全活動を支援することを目的として、「環境カウンセラー登録制度」を創設した。 同制度は、自らの知識や経験を活用して環境に関する相談や助言等を行おうとする者を毎年度広く一般から公募し、一定の要件を満たす者を推奨すべきカウンセラーとして「環境カウンセラー登録簿」に登録するもので、この名簿を広く一般に公表することによって、市民や事業者からの環境保全活動等に関する相談・助言の要請や、環境学習に際しての講師派遣の依頼などに応えようというものである。
登録は、市民や市民団体等の環境保全活動を扱う「市民部門」と、事業者の環境保全対策や環境活動評価プログラム等を扱う「事業者部門」の2部門に区分して行われ、それぞれ書面と面接による審査が行われる。また、登録された者を対象として毎年度研修を実施する。平成8年度は、市民部門に約630名、事業者部門に約920名の申し込みがあり、それぞれ321人、665人が登録されている。
ウ 民間団体の環境学習・環境保全活動への経済的支援
民間団体の活動は、問題への機敏な対応や、地元に密着した活動ができるなどの利点を有するが、その反面、人材の確保と並んで財源の不足という問題を抱えており、民間団体の利点が十分に生かされていない状況にある。
こうした状況を改善するため、平成5年5月、環境事業団に、民間団体による環境保全活動への資金の助成等を行う「地球環境基金」が創設された。地球環境基金は、国、国民、企業等の拠出によって構成され、その運用益を民間団体の活動への助成などに充てている。
助成の対象としている事業は、?我が国の民間団体が開発途上地域で現地の住民等の参加を得て行う環境保全活動、?海外の民間団体が開発途上地域で現地の住民等の参加を得て行う環境保全活動及び?我が国の民間団体が国内で行う環境保全活動である。
平成8年度の助成要望と採択の件数は、第3-2-1表のとおりである。
(5) 自然とのふれあいを通じた体験的な環境学習の推進
ア 自然とのふれあいの重要性
環境教育・環境学習のベースとなるのは、自然や良好な環境に対する豊かな感受性と自然への愛情である。こうした感受性や愛情は読書や聴講だけで育つものではなく、自然や良好な環境とのふれあいの中で、その恵みを体感することによって初めて醸成されるのである。
Box27 活躍する環境NGO
財団法人広島県環境保健協会は、地球環境基金からの助成を受けて、環境家計簿によるCO2排出量の削減運動を行っている。これは、各家庭において、エネルギー使用量を同協会作成の環境家計簿である「エネルギー点検簿エコーノート」に記載し、CO2排出量の算出、比較を行うとともに、同協会が各家庭におけるエネルギー使用量の調査を実施し、結果を各家庭にフィードバックすることにより、地球温暖化を防止するための生活行動について、意識の高揚を図ろうという取組である。
また、日本の著名な漫画家でつくる「地球環境を守る漫画家の会」は、同基金からの助成により、「環境マンガ展」を開催し、非常にユニークな環境問題の啓発活動をしている。このマンガ展は、東京で開催された後、全国に巡回し、視覚を通して特に若い世代に地球環境の保全を訴えている。
かつて、こうした自然とのふれあいは、森や原っぱでの遊びなど、日常生活の中で自然に行われてきた。しかし、今日では、都市化の進展により身近な自然の消滅や質の低下が著しくなるとともに、生活の変化により自然の中で過ごす機会が減少し、日常生活における人と自然のかかわりがますます希薄になっている。こうした状況の下では、意図的、計画的に、豊かな自然を体験できる様々な場と機会を提供することが必要となってきていると言える。
また、自然とのかかわりの減少の中で、自然と向き合いながら充実した時間を過ごしたいという国民のニーズも増大してきている。
こうした中で、自然とのふれあい体験を重視した新たな視点からの総合的な施設整備や、様々な自然とのふれあい体験活動、学校教育の中での野外活動などが推進されている。
イ 自然とのふれあいのための総合的施設(ハード)の整備
国立・国定公園などでは、自然とのふれあいや自然の仕組みの理解などを目的として、従来から、ビジターセンターの整備等を進めてきているが、さらに、自然とのふれあいや自然体験学習などを総合的、体系的に実施するため、平成7年度から、公園の核心となる特に優れた自然景観を有する地域において、自然の保全や復元のための整備を一層強化するとともに、高度な自然学習や自然探勝のためのフィールドの整備等を行う「自然公園核心地域総合整備事業(緑のダイヤモンド計画)」、子ども達が自然とふれあい、自然を学ぶことができる「エコ・ミュージアム整備事業」などを進めている。
また、国立・国定公園外の身近な自然の地域においても、身近な自然を保全、活用することにより、国民が自然との共生を実感できる「ふるさと自然ネットワーク」の整備を進め、自然体験等の場の提供を図っている。
ウ 自然とのふれあい活動(ソフト施策)の推進
自然とのふれあいを確保するためには、自然とのふれあい活動のプログラムや指導者養成のプログラムの提供、ボランティア活動の支援等の国民参加を促進する仕組みの整備など、ソフト施策を充実させることが重要である。
(ア) 活動プログラムの開発等の取組
環境庁では、施設整備のみならず、施設整備と併せて自然とのふれあいを実体験するプログラムの開発等を行っている。
特に、平成9年度から、参加型自然教育施設として整備が進められる「ふれあい自然塾整備事業」と一体的に推進する「ふれあい自然塾活動推進事業」を実施することとしており、この事業を通じて、自然塾の立地環境等を生かしたふれあい体験活動プログラムや自然環境保全活動プログラム等の策定などを行うこととしている。
(イ) 自然とのふれあい活動の推進体制の整備 −自然解説指導者の養成及びボランティアによる自然解説活動等の推進・支援−
a 自然解説の必要性
自然解説活動(インタープリテーション活動)は、公園などの自然、文化、歴史等の資源と公園利用者とのコミュニケーション手段であるのみならず、人間を取り巻く環境に注意を向けさせ、それらに対する主体的なかかわりを促す活動であり、自然とのふれあい体験を推進するに当たって、自然と人間との架け橋になる活動として必要不可欠なものである。このため、自然解説を行い得る指導者を育成・確保することが重要な課題となっており、そのための仕組みを整備する必要がある。
また、国民の主体的な参加による自然とのふれあい活動を促すためには、民間団体が独自に行う自然解説活動や、国立公園等での自然解説活動へのボランティア参加が重要であるとともに、ボランティアによる取組を支援する仕組みを整備していくことが肝要である。
b 民間団体の取組
民間における自然解説活動としては、例えば、財団法人日本自然保護協会による活動が挙げられる。同協会では、自然解説指導者として自然観察指導員を養成し、指導員数は既に1万人に達している。養成された指導員はボランティアとして各地の自然観察会等で活動を展開している。
c 地方公共団体の取組
長野県では、県民の参加による自然解説活動と指導者養成を行う仕組みとして、平成5年度から「自然観察インストラクター」制度の運営を行っている。同制度は、一般からの公募等により、自然観察指導者を自然観察インストラクターとして「自然観察インストラクターバンク」に登録し、市町村、学校、子供会等が実施する自然とのふれあい活動へインストラクターを派遣するものであり、併せて、インストラクターの資質を向上させるための研修も実施している。また、インストラクターを活用した自然観察会等には、交通費の一部などの資金援助を行っており、加えて、県の出先機関には「自然観察インストラクター派遣事業推進会議」を設置し、インストラクターの派遣・活用の推進を図っている。平成7年度のインストラクター派遣実績は、278事業、のベ627人に上っている。なお、平成9年1月1日現在、インストラクターとして762人が登録されている。
d 環境庁の取組
環境庁においては、平成3年度から、全国のビジターセンターの職員等を対象に「自然解説指導者研修」を実施し、自然解説活動に従事する職員等の能力の向上を図っている。
また、昭和60年度から、国立公園の自然とのふれあい拠点において、公募されたボランティアが自然解説等を実施する「パーク・ボランティア」制度を設け、併せて、パーク・ボランティアの能力を向上させるために、自然解説研修等の実施や活動マニュアルの作成などの基盤整備も行っている。さらに、平成4年度からは、国費で保険に加入し、ボランティア活動の資金援助を行っている。パーク・ボランティアとして自然解説活動等に携わった者は、平成8年度には約1,700人に上っている。
エ 青少年の野外教育施策の推進
文部省では、青少年の育成にとって、学校外での活動、とりわけ大自然の中での自然体験活動が極めて重要であるとの観点から、青少年の野外教育振興のための様々な施策を講じている。
学校における野外教育としては、これまでにも青少年教育施設等を利用した「集団宿泊学習」、「林間学校」、「自然教室」などが学校行事として行われてきた。
文部省では、こうした従来からの取組に加え、昭和59年度から「自然教室推進事業」を推進し、人間的ふれあいと自然とのふれあいを深めるとともに、地域社会への理解を深めることを目的に、市町村が学校教育の中で児童生徒を豊かな自然環境の中で一定期間の集団宿泊生活を行う事業に対して国庫補助を行っている。