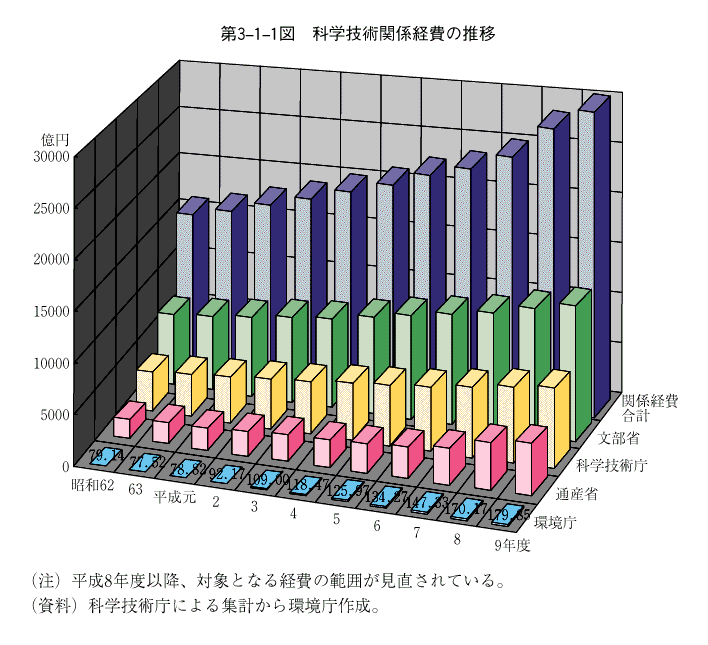
2 近年の科学技術と環境に関する政府の取組の進展
(1) 環境基本法及び環境基本計画における位置付け
ア 環境基本法における位置付け
地球環境時代の環境政策の総合的な枠組みを定めた「環境基本法」においては、基本理念の一つとして、環境の保全が科学的知見の充実の下に環境保全上の支障の未然防止を旨として行われなければならないと定めている。
また、環境保全に関する基本的施策として、環境の変化の機構の解明や負荷の低減に関する技術に加えて、環境が経済から受ける影響等を総合的に評価する方法の開発等、自然科学のみならず、人文・社会科学の分野も通した環境保全に関する科学技術の振興を図ることを規定するとともに、そのために国が試験研究体制の整備等の措置を講ずることを定めている。また、環境の状況の把握などのための調査の実施や監視等の体制の整備についても、国が講ずるべき施策として位置付けている。
イ 環境基本計画における位置付け
環境基本法に基づいて平成6年12月に閣議決定した「環境基本計画」でも、科学技術の振興を、環境保全に係る共通的基盤的施策の重要な柱と位置付けた。そして、具体的には、?人文、社会、自然科学の幅広い分野の調査研究や監視・観測等の体制整備等を推進すること、?環境保全の取組を支える技術体系の確立や省資源・省エネルギー技術の一層の開発普及などの適正な技術を振興すること、?機材や施設等の適切な整備、幅広い分野にわたる学術研究の推進、人材の質的・量的充実、関係機関相互の交流・連携等を図ることなどが必要であるとした。また、地方公共団体、民間団体等における取組の支援も重要であるとしている。
さらに、新しい技術の開発・利用に際して環境への配慮がなされるよう適切な施策を実施すること、先端技術の成果の環境保全分野への応用を推進することなども定められている。
(2) 我が国の科学技術政策の動向と環境
ア 科学技術政策大綱
人類が、安定し、充実した21世紀を築いていくためには、人間、社会及び環境との調和に配慮しながら、科学技術の一層の発展を図っていくことが必要不可欠である。このような観点に立って、政府は、平成4年4月に、新たな「科学技術政策大綱」を閣議決定した。
同大綱では、?地球と調和した人類の共存、?知的ストックの拡大、?安心して暮らせる潤いのある社会の構築の3つの目標を掲げて、これらの目標の実現のため、「科学技術と人間・社会との調和の確保」等7つの重点施策が定められている。これは、地球環境問題の解決に寄与することが、科学技術の重要な役割であるとの認識に立って、「地球と調和した人類の共存」が第一の目標に掲げられたものであり、環境保全の重要性が位置付けられている。
イ 科学技術基本法と科学技術基本計画
科学技術の振興の重要性に対する認識が高まる中、平成7年11月、21世紀に向けて科学技術創造立国を目指し、経済社会の発展、国民福祉の向上に寄与するとともに、世界の科学技術の発展と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的として、科学技術基本法が制定された。
この基本法の規定に基づき、平成8年7月、科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、科学技術政策大綱の精神を踏まえて、今後10年程度を見通した平成8年度から12年度までの5年間の科学技術政策を具体化するものとして、科学技術会議の議を経て、科学技術基本計画が閣議決定された。
同計画では、研究開発推進の基本的方向として、地球環境、エネルギー・資源等の地球規模の諸問題の解決に資する科学技術の研究開発を推進することが挙げられた。また、地球環境問題等への対応に資する科学技術に顕著に見られるように、自然科学と人文科学との相互のかかわり合いが重要であることから、両者の調和のとれた発展に留意することとされるとともに、環境や倫理に配慮する等人間の生活、社会及び自然との調和を図ることが定められた。
(3) 環境政策における科学技術基盤の強化
ア 組織体制等の現状
環境基本法や環境基本計画に定められたとおり、環境分野の科学技術に係る組織体制を整備することは極めて重要な課題となっている。
環境庁では、昭和49年3月に試験研究機関として設立した国立公害研究所を平成2年に「国立環境研究所」に改組し、同年10月には、同所内に地球環境研究・モニタリングの中核拠点として「地球環境研究センター」を設置し、研究の推進強化を図っている。
また、我が国の省庁別科学技術関係経費の状況は第3-1-1図、第3-1-2図のとおりである。環境庁の科学技術関係経費は、平成2年度から計上している地球環境研究総合推進費と国立環境研究所地球環境センター経費により、高い伸びを見せている。しかしながら、我が国の科学技術関係経費全体に占める割合は依然として極めて小さい状態である。
イ 今後の環境に係る科学技術基盤の整備の方向
(ア) 科学技術基盤の強化の必要性
地球温暖化等の地球環境問題や化学物質による健康影響の問題など、今日の環境問題の解決に向け、将来を見通した研究や新たな技術開発に対する期待が高まっている。
また、環境リスクの考え方に基づいた施策をはじめとして、環境政策を効果的に推進するためには、環境の状況の正確な把握、環境問題の機構の解明、環境の質や資源の賦存状況等の的確な将来予測、効果的な政策オプションの提示、施策の目標の設定、効果的な対策の確立と実施時期の選定、対策効果の把握などが極めて重要である。また、新たな環境政策の必要性について、国民をはじめ各主体の理解と協力を得るために、政策オプションや対策技術の効果を説得力を持ってわかりやすく提示することが必要である。このように、政策の企画立案、推進のあらゆる段階で、科学的知見を活用することの必要性が増大しつつある。
(イ) 科学技術基盤を強化するための視点
a 予見・予防型科学技術への脱皮の必要性
これまで、我が国の環境政策は、激甚な公害を解決してきた経験などから、与えられた問題に対して対症療法的な施策を検討し、その対策の実施を確保するための監視・測定体制を充実することが中心であった。そのため、環境分野における科学技術は、エンド・オブ・パイプ型の対策技術、大気汚染等個別事象に関するモニタリング技術等が中心となってきた。
環境基本法の制定は、今日の環境問題の解決のためにこうした環境政策からの脱皮を図るものであった。今後、環境政策にかかわる科学技術は、対症療法型のものから、使用エネルギーをいわゆるクリーン・エネルギーに転換する技術等環境への負荷自体を低減させる技術や、環境管理に係る技術などの予見・予防型のものに脱皮・転換を図ることが重要である。
b 全部門を対象とした科学技術の開発・研究の必要性
我が国では、産業公害への対処の経験から、これまでに取り組まれてきた科学技術の開発・研究は、特に、産業部門において顕著であった。しかしながら、地球温暖化問題に見られるように、原因物質の排出源が通常の経済活動や日常生活まで多岐にわたるような問題に対応するためには、産業部門のみを対象としていても不十分である。民生部門や運輸部門も含め、全部門について科学技術の開発・研究が推進されなければならない。
c 政策科学の分野における研究の重要性
前述のように、今日の環境問題の解決は、科学技術の発達によるブレークスルーのみに頼れる状況ではなく、社会経済システムの変革や国民一人ひとりの足下からの取組などが相まって、はじめて達成し得るものである。その上、こうした社会変革や意識改革にはかなりの時間を要する。したがって、自然科学のみならず、人文科学、社会科学の方法論を主体とした政策研究や、環境教育の在り方の施策等に関する研究の強力な推進を図ることが急務である。
また、政策検討のベースとなるような、政策の支援を直接の目的とした戦略的な監視・観測の実施や環境情報・統計の作成等、戦略的な研究開発も重要である。
d 新しい科学技術を支援するための取組の必要性
環境保全に関する新しい技術は、その研究開発に取組み、ビジネス展開を図るにはコスト面で困難な状況にあることが多い。環境保全に関する技術の革新を促すとともに、社会的普及を図るためには、当該技術の技術的優位を経済的成功に変えるような仕組みが不可欠である。こうしたことから、当該技術の開発・導入に係る資金助成や増加試験研究費税額控除制度等の研究開発活動促進に資する税制措置の積極的な活用を図るなど、新技術の開発・普及のための制度的・経済的な支援に関する取組が必要である。
(ウ) 科学技術基盤の強化に係る施策の方向
上述の視点を踏まえ、今後、我が国においては、21世紀を見通した環境保全に関する科学技術基盤の強化のための施策を展開していかなければならない。
環境庁が平成8年4月に発足した「今後の環境研究・環境技術のあり方に関する検討会」は、平成8年8月にとりまとめた中間報告で、環境庁をはじめとする国の機関が早急に取り組むべき施策の方向として、以下のような7項目を提案している。
? 民間企業やNGOなど環境研究に関与している様々な主体の活動を活性化させるとともに、情報通信ネットワークの整備、研究者・研究機関等の組織化を図る。
? 地方公共団体の環境研究機関を中心に、地域の発想に根ざした取組を推進するとともに、その支援措置を講じる。
? 国際的取組を推進するに当たっては、我が国の得意な分野に重点的に取り組み、また、研究交流や途上国への研究支援、技術移転を進めるとともに、持続可能な開発を地球規模で実現していくための研究機関として、「地球環境戦略研究機関」を早期に設置する。また、アジア太平洋地域における地球変動研究を推進するため、環境庁が事務局を務めるアジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)を今後とも主体的に支援していく。
? 科学技術基本計画に基づき、環境研究・環境技術に充当される資金の拡充を図る。特に、人文・社会科学的アプローチを主体とした政策研究、次世代の環境研究・環境技術の基礎となる知的資産を蓄積するための研究、具体的手法や技術としては未確立な研究等に係る経費の充実を図る。
? 人文・社会科学分野等の要員の確保をはじめ、研究者、研究支援者、海外からの人材等の養成・確保など、人的資源の質量両面からの拡充を図る。
? ライフサイクルアセスメント手法等、個別要素技術が集積した技術システムを含め、環境研究・環境技術の評価を体系的に行うとともに、成果の普及、優良環境技術の開発普及の促進措置を強化する。
? 環境研究・環境技術の重点的・効率的な展開を図るための、国としての総合的な計画の策定を行う。
以上のような施策を強力に推進することによって、環境保全に係る科学技術の基盤整備を図っていく必要がある。
(4) 地球環境戦略研究の推進
これまでに述べてきたとおり、地球環境の危機に対し、持続可能な開発を世界規模で実現していくためには、科学技術を地球環境問題の観点から再編・再統合するとともに、人文科学、社会科学的視点も加えて、地球環境問題に立ち向かうための戦略を総合的に研究していくことが喫緊の課題となっている。
こうした中で、内閣総理大臣の主催により開催された「21世紀地球環境懇話会」は、平成7年1月、「新しい文明の創造に向けて−21世紀地球環境懇話会提言−」の報告をとりまとめ、地球環境を巡る諸問題について、これまでの専門分野を越えて横断的に研究し、内外に向けて提言を行う「地球環境戦略研究機関」の設置を提言した。これを受けて環境庁が開催した「総合的な環境研究・環境教育の推進体制に関する懇談会」は、「地球環境戦略研究機関のあり方」に関する検討を進め、同研究機関の具体的な姿を報告した。
同研究機関は、物質文明の価値体系を見直し、新たな文明の基本的枠組みを創造し、これに即した社会経済の仕組み等の形成を図るための戦略研究を行い、これを具体化していく政策的・実践的な研究を行うこととしており、その設立は、21世紀の新たな地球文明創造の方途の一つとして期待されている。現在、同研究機関の目的、事業、組織、各機関との協力等を盛り込んだ国際的な設立憲章を作成し、世界に開かれた日本の民法法人として設立すべく準備が進められている。