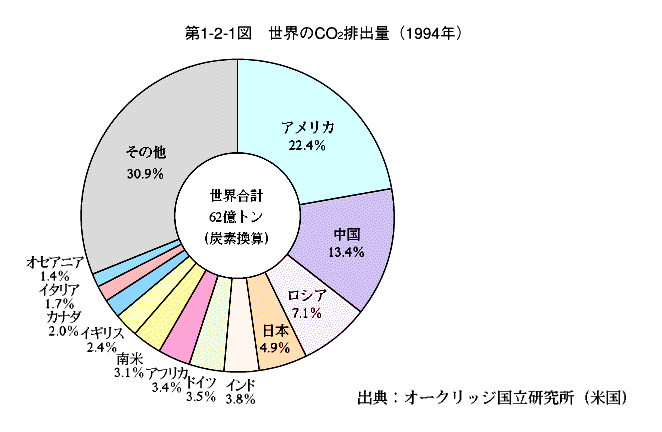
1 温室効果ガスの排出状況について
(1) 世界全体の温室効果ガスの排出状況
前節で述べたとおり、人為的に排出される温室効果ガスには、CO2、メタン、亜酸化窒素等があり、これまでの各物質の地球温暖化への寄与度(各物質による100年間の影響を考えた場合)はCO2が63.7%で最も大きく、以下メタン19.2%、CFC(クロロフルオロカーボン、フロンの一種)及びHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン、フロンの一種)10.2%、亜酸化窒素5.7%となっている(第1-1-2図参照)。
以下、これら温室効果ガスの排出状況の特徴について概観する。
ア CO2の排出状況
1994年(平成6年)現在のCO2年間排出量を各国別にみると、米国が約22%、中国が約13%、ロシアが約7%、日本が約5%で、この4か国だけで世界の約半分を占める(第1-2-1図)。
世界の排出量の推移をみると、産業革命以後、特に第2次大戦以降、大きく増大してきており、現在の世界のCO2総排出量は1950年(昭和25年)当時の4倍に達している。西側先進国は、1970年代の2度の石油危機により、経済成長にかかわらずCO2の排出が減少する時期を経験したが、近年は、基本的に漸増傾向にある。旧東欧・旧ソ連は、オイルショックの影響もなく逓増していたが、1980年代末の大きな政治変動以降、急激に減少している。これらを含めた先進国全体では、1980年代までは西側先進国の推移とほぼ同様の傾向をたどっていたが、1990年代に入り、旧東欧・旧ソ連の減少の影響により、若干の排出減少を示している。一方、開発途上国の排出量はほぼ一貫して増大しており、近年、特に増加傾向が激しくなっている。これらを合計した世界全体の排出量については、1980年代末までは各国の経済成長に伴い基本的に増加傾向にあったが、1990年代に入り、旧東欧・旧ソ連の減少により相殺され、横這いの状況にある(第1-2-2図)。温室効果ガスの濃度を安定化させるためには、IPCCが指摘するとおり世界全体での排出量を現状以下に削減していく必要があるが、今後、開発途上国などの経済成長を見込む必要があることから、先進国全体の排出量については十分な削減を可能な限り早い時期に実施することが必要であると考えられる。
イ 一人当たりのCO2排出量
一人当たりのCO2の排出量をみると、米国、カナダ、ロシアが大きい。我が国は、米国の約半分であるが、EUの平均を若干上回り、中国の約4倍、インドの約10倍となっている(第1-2-3図)。また、世界の人口の2割(22%)を占めるにすぎない先進国の人々がCO2排出量の6割(59%)を占めている。一人当たりでみれば、先進国の人々は、開発途上国の人々の約5.5倍排出している。
ウ GDP当たりのCO2排出量
GDP当たり排出量でみると、開発途上国では、エネルギー集約的な産業がエネルギー効率が低いまま操業している例が多く、大量交通機関の未整備などとあいまって、1人当たり排出量で見られたような先進諸国と開発途上国との間の格差はない。我が国は、米国、ドイツ、英国などより小さいが、イタリア、フランスよりも大きい(第1-2-4図)。
エ メタン、亜酸化窒素等の排出状況
メタン、亜酸化窒素の排出実態についてはCO2ほど十分には把握されていないが、IPCCによると、CO2同様産業革命以降際だって大気中濃度が増大しており(第1-1-5図参照)、その大部分が人間活動に起因しているとされている。
メタンの主な人為的発生源としては、農業(家畜の反すう、糞尿や水田等)や廃棄物の埋立地、燃料の燃焼・取扱時の漏出などがある。
同じく亜酸化窒素の人為的発生源には、化石燃料や薪等のバイオマスの燃焼、農業(施肥等)、工業プロセス(化学工業)などがある。
CFC等については、既にオゾン層保護の観点から規制が実施されており、CFCについては1995年(平成7年)末をもって生産が全廃され、HCFCについても全廃までの規制スケジュールが決まっている(詳しくは、第4章第1節1オゾン層の破壊の項を参照)ことから、今後は、既に利用されているCFC等の回収・再利用・破壊を促進することによって大気中への放出を防止することが重要になっている。HFC(ハイドロフルオロカーボン)については、CFC等の規制に対応した代替物質として、近年使用量が大幅に増加している。
温暖化係数の大きいSF6(六フッ化硫黄)についても、安全性等の理由から絶縁材などとして使用されてきている。
(2) 我が国における温室効果ガスの排出状況
我が国から排出される温室効果ガスの地球温暖化への寄与は、CO2が95%を占めている(ただし、CFC、HCFCによる寄与は除く。第1-1-3図参照)。また、CO2排出量のうち、91.7%がエネルギーの利用に起因している(第1-2-5図)。このため、エネルギーの利用に伴うCO2排出を中心に、我が国における温室効果ガスの排出状況を見てみよう。
ア CO2の排出状況
我が国は、世界第4位のCO2排出国(約4.9%)であり、一国でアフリカ大陸全体(約3.4%)、南米大陸全体(約3.1%)を大きく上回る量のCO2を排出している(第1-2-1図参照)。
CO2排出量の内訳を1994年(平成6年)度においてみると、エネルギーの消費に伴うものが91.7%を占め、工業プロセスによるもの(セメント製造工程等における石灰石の消費)が4.5%、廃棄物の焼却に伴うものが3.8%となっている。
我が国の1994年(平成6年)度のCO2の排出総量は、炭素換算3億4300万tであり、基準年である1990年(平成2年)比で約7.2%の伸びを示している(第1-2-1表)。
また、CO2排出量の大部分を占めるエネルギー消費に伴うCO2の排出量の推移を見てみると、高度経済成長期においては、GDPの伸びに伴いCO2排出量も同様に増大した。石油危機後は、石油価格の高騰などを背景にした産業界における省エネ努力によって、GDPの増大にもかかわらずエネルギー消費が増大せず、CO2の総排出量は横這いで推移した。しかしながら、1988年(昭和63年)から排出量は再び増加傾向を示している(第1-2-6図、第1-2-7図)。
イ CO2排出構造の特徴
先に見たとおり、我が国の一人当たりのCO2排出量は、先進国の中でも比較的小さいが、それは次のような要因によるものと考えられる。
(ア) 工場・事業場における省エネルギーの進展
第一に、個別の産業、あるいは工場内における省エネルギーが進み、一部の製造工程においては世界の中でトップクラスに達しているものも見られることがあげられる。第1-2-8図は、鉄鋼業のエネルギー原単位の国際比較を行なったものであるが、他の先進国のエネルギー消費原単位は我が国より3〜18%大きくなっている。
我が国の産業界で省エネルギーが進んだ理由は、国産エネルギーに乏しく、価格が高くかつ供給に不安があったことを背景に、工場の現場の技術者が、日々常にエネルギー利用設備の維持・点検に努めるとともに、創意工夫を重ねていることが挙げられる。工場内の省エネルギーは本章第3節5で詳しく述べているように、エネルギーの適切な管理が基本であるが、エネルギーを大量に使う工場のほとんどで、地道な省エネルギー努力が行われている。
なお、我が国においてこのような有能な技術者が多く輩出した理由の一つは、戦争直後、利用できるエネルギーが極めて少なかった時代に、エネルギーをできるだけ有効に使おうとする熱管理運動が工場の現場で行われたことが挙げられる。このような運動が背景となって、昭和26年に熱管理法が生まれ、それが石油危機を受けて昭和54年に制定された「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」につながっていったのである。
また、我が国の製造業では製品の高付加価値化、すなわち同じエネルギーを使った製品であってもより大きな付加価値を生み出すことができるようになってきたが、このことは、我が国のGDP当たりのCO2発生量の低減に資していると考えられる。
(イ) 少ない暖房用エネルギー消費
第二には、我が国の気候が比較的温暖であり、暖房用エネルギー消費、そしてこれが大きな割合を占める民生部門のエネルギー消費が比較的少なくてすむことがあげられる(第1-2-9図、第1-2-10図)。ただし、暖房用を含む我が国の1人当たりの家庭用エネルギー消費の近年の伸びは、他の先進国に比べ大きい(第1-2-11図)。
(ウ) 海運や鉄道の利用
第三には、我が国においては他の主要先進国と比較して、旅客輸送における鉄道のシェアが高く、また、周りを海に囲まれていることから貨物輸送における船舶のシェアが高くなっているなど(第1-2-12図)、エネルギー効率の高い大量輸送機関(第1-2-13図)のシェアが高いことが挙げられる。
ウ 近年のCO2排出量の増大
CO2の排出量の推移を部門別にみると(第1-2-7図参照)、産業部門からの排出量が下げ止まり、横這いで推移する一方、エネルギー転換部門では若干ではあるが増加しつつあり、民生、運輸部門では、大きく増加している。
(ア) エネルギー転換部門
エネルギー転換部門では、比較的CO2排出量の少ないLNGや、発電過程においてCO2を排出しない原子力の導入、火力発電の熱効率の向上、送配電ロスの低減といったCO2排出抑制対策が講じられてきた。この結果、発電電力量あたりのCO2排出量、すなわちCO2排出原単位(単位:tC/kWh)の全電力部門での平均値は減少傾向にあるが、電力需要の増大を背景とする発電電力量の増加により、CO2排出量自体は増加傾向にある。また、CO2排出原単位のうち、火力発電によるものを平均した値は、1980年(昭和55年)頃までは減少傾向にあったが、近年はほぼ横這いである。これは、LNG火力発電の拡大等の排出減少要因もある一方、熱効率の向上が頭打ちになっていること(第1-2-14図)や、石炭の使用量が、エネルギーセキュリティや経済性等の観点から政策的にも増大していること等の排出増加要因もあるためと考えられる(第1-2-15図)。
(イ) 産業部門
産業部門のCO2排出量も近年横這いで推移しているが、その背景としては、石油危機後主要産業におけるエネルギー原単位が急速に向上したものの、最近、エネルギー利用効率の改善が見られなくなり(第1-2-16図)、出荷額の増大に伴う排出増加要因の影響が、各種の排出減少要因により相殺されなくなったことがある。平成6年度の排出量は前年度より増加した。
(ウ) 運輸部門
運輸部門においてCO2排出量が増大しつつある背景には、我が国の輸送量が、経済成長に伴い着実に増加してきたことが挙げられる。昭和45年度から平成6年度までの間に、貨物輸送は約1.5倍、旅客輸送は約2倍にそれぞれ増加した。
輸送機関別の輸送分担率を見ると、モータリゼーションの進行に伴い自動車の比率が伸び、鉄道の比率が減少している(第1-2-17図)。
国内輸送機関のエネルギー消費量についてみると、このうち自動車による消費量が全体の86%を占め、また、そのほとんどが乗用車とトラックによるものである(第1-2-18図)。
また、平成6年度における運輸部門からのCO2排出量の内訳をみると、自動車からの排出が全体の87%とその大半を占めている(第1-2-19図)。
個々の自動車の燃費の状況をガソリン乗用車(新車)についてみると、石油危機後相当向上したが、昭和57年度をピークとしてそれ以降は少しずつ悪化している(第1-2-20図)。この背景には、ガソリン価格の下落等に伴う燃費性能への関心の低下とあいまって、ユーザーの大型車、RV指向、パワーステアリング、四輪駆動(4WD)、安全装置の装着率の向上等による車両重量の増加したこと等があると見られる。こうした状況から、運輸部門からのCO2排出量は着実に増加してきている。
Box6 我が国のモータリゼーション
我が国の人口当たりの自動車普及率は、世界的に見ても非常に高い。平成7年のデータで比較すると、広大な国土を有し、モータリゼーションの進んだ米国、カナダに比べてやや少ないものの、イギリス、フランス、ドイツ等の欧州諸国とほぼ同じ水準である。また、これはアルゼンチン、韓国、サウジアラビアの約3倍、エジプト、インドネシア、モンゴルの約20倍、中国の約60倍であり、平成2年のデータでは世界平均の4.3倍となっている。
(エ) 民生部門
我が国のCO2排出量の23.8%(平成6年度)を占めるに至っており、このうち家庭用が53%、業務用が47%を排出している。1970年(昭和45年)から1994年(平成6年)までの年平均伸び率が、家庭用4.1%、業務用が4.6%とどちらも一貫して大幅の増加を続けている。
この背景としては、エネルギー利用機器の普及が進んだこと(第1-2-44図参照)、個別の機器のエネルギー効率の改善が近年あまり進んでいないこと(第1-2-21図)、業務用については業務用床面積が増大していること(第3-3-11図参照)等が挙げられる。
a 業務部門
業務用についてみると、1970年(昭和45年)から1994年(平成6年)までの間、CO2排出量は、エネルギー需要量全体の伸びを上回る高い伸びを示しているが、この大きな原因は、家庭用と同様に消費エネルギーに占める電力の割合が増大していることである。電力化率は、1970年(昭和45年)の17%から1994年(平成6年)には42.5%へと、合計25.5ポイント増加している。(第1-2-22図、第1-2-23図)
b 家庭部門
家庭用についてみると、世帯当たりのCO2排出量の合計に占める用途別割合は第1-2-24図のとおりであり、照明・動力用、給湯用、冷房用の増加が著しい。
エネルギー消費の伸びでみても、第1-2-25図のとおりであり、1970年(昭和45年)と比べ1995年(平成7年)には冷房用が約9倍、給湯用が約2.6倍、照明・動力用が約1.9倍と著しく伸びている。冷房用エネルギー消費をもたらすエアコンの普及率の推移を見ると、昭和48年には一世帯当たり0.16台であったのに対し、平成元年に1世帯1台、平成6年には同1.5台とここ数年急激に伸びており、20年間で10倍近い伸びを示していることがわかる(第2-1-4図参照)。また、冷房用、照明・動力その他用は、電力を主に利用しているため、エネルギー消費量の増加率に比べ、割にCO2の排出量の伸びが大きくなっている。
エネルギー利用に伴うCO2