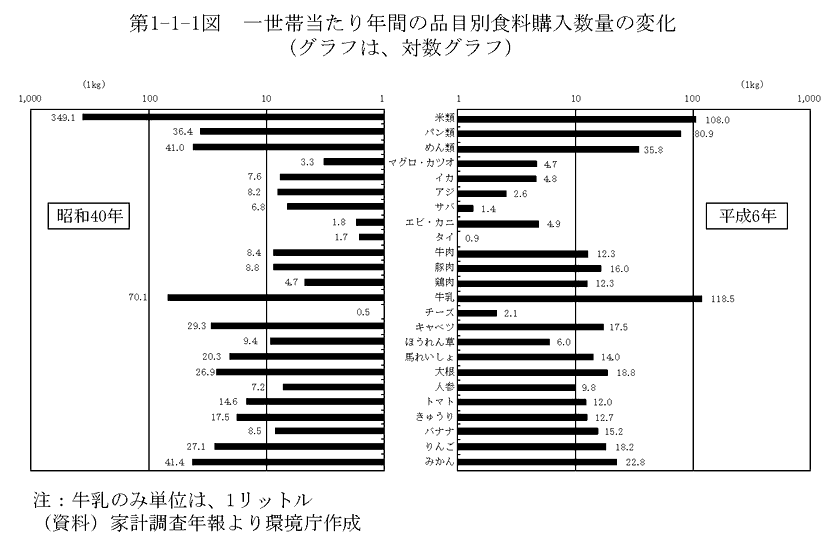
1 食と環境
戦後、食料供給の増大や経済発展により、我が国の食生活は、量と質の両面において著しい向上を見せるとともに、食の外部化をはじめとしてその消費形態においても大きく変化した。少しでも空腹をいやすことが最大の関心事であった時代から、豊富な選択肢の中から好みに合わせて食事を選ぶ時代となった。
今日、我々は国内はもとより世界中から取り寄せた様々な食品を好きな時に好きなだけ食べることが可能である。第1-1-1図は主な食品に対する一世帯当たりの年間食料購入数量の変化を昭和40年と平成6年とで比べてみたものであるが、この30年あまりで生じた我々の食卓の大きな変化を垣間見ることができる。
それでは、このような食生活をめぐる変化は環境という観点からはどのような意味を持っているのであろうか。以下では、食生活の変化に即して食と環境の関わりについて見るとともに、そのあり方について最近の取組なども交えながら考えてみたい。
(1) 食生活の変化とその環境への影響
ア 食料消費の量と質の変化
まず、我が国における食料供給が総体としてどのように変化してきたのかを見るために、供給熱量ベースでその変化を見てみよう。「食料需給表」によれば、国民1人1日当たりの供給熱量は、昭和35年度の約2,290kcalから昭和40年代後半には2,600kcalに近づいた後、一旦減少に転じ、しばらく安定的に推移した。その後、昭和50年代末頃より再び増加傾向に転じ、ここしばらくは2,600kcal台の前半で推移し、平成5年度には約2,620kcalとなっている。この結果、平成5年度と昭和35年度を比べると国民1人1日当たりの供給熱量は約16%の増加となっている(第1-1-2図)。
一方、国民1人1日当たりの摂取熱量の推移を「国民栄養調査」により見てみると、昭和35年に約2,100kcalであったのが、年ごとの増減はあるものの、40年代半ばに2,300kcal近くまで増加した後、緩やかな減少に転じ、平成5年には約2,030kcalとなり、35年に比べると、約3%の減少となっている(第1-1-3図)。
この二つの調査結果から、長期的な傾向を見ると、供給熱量については昭和40年代後半には現在の水準に近づいた後、近年では横ばいないし微増となっており、摂取熱量については40年代半ばまですう勢的に増加した後、減少ないし横ばいの傾向にある。これらのことから、我が国の食料消費はほぼ飽和水準に達していると言えよう。
摂取される食品の内容には質的にも大きな変化が見られる。
第1-1-4図は国民1人1日当たりの食品の摂取量を植物性食品と動物性食品に分けて見たものであるが、総じて前者が減少ないし横ばいであるのに対し、後者が大幅に増加している。例えば、米類の摂取量は昭和35年から平成5年にかけて約4割の減少、豆類がほぼ一定、野菜類が暫増(緑黄色野菜の増加による)等となっているのに対し、乳・乳製品、肉類がそれぞれ約4倍の増加、魚介類が約3割の増加等となっている。このような変化は、動物性食品を中心に日常的により多様な食品が摂取されるようになってきたことを意味し、我が国の食生活は主食である米を中心に畜産物、魚介類、野菜、果実等の多様な食品の組み合わせにより変化に富んだものとなってきた。例えば、東京都中央卸売市場で扱われる水産物の上位20%に占める品目数を比べると、昭和40年には4品目であったのが平成6年には8品目に、同じく上位30%では9品目から16品目に増加しており、供給面からも多様化が進んだことがうかがわれる(第1-1-1表)。
このように、食が質量ともに豊かになってきたことは、国民の栄養状態を改善し、国民生活の向上に大きく寄与してきた。
イ 食の平準化
このような食の変化を別の観点からとらえれば、季節や地域に関わりなく様々な食品を手に入れることができるようになったことが背景の一つにあるものと考えられる。ここでは、食材の季節的な変化(旬)の希薄化及び生産地と消費地の地理的な隔たりという点から、いわゆる食の平準化とも言える状況が進んでいることを見てみたい。
まず、「旬」の希薄化を野菜を例に見てみよう。第1-1-5図は東京都中央卸売市場におけるトマト、きゅうり、かぼちゃの入荷量の季節的変化を昭和40年と平成6年について示したものであるが、一見して季節感が薄れてきたことが分かる。昭和40年には、いずれの野菜も特定の月を頂点として入荷量が急峻な山型を見せていたのが、平成6年には山型が緩やかになり、入荷量の一番少ない月でも一番多い月の半分程度は確保されるようになっている。年間を通じた食材の供給が可能となった背景には、ビニールハウスなどの施設栽培の増加や海外からの輸入も含めた食品供給地の拡大がある。露地栽培を含めた全生産量に施設栽培(ガラス室及びハウス)が占める割合の推移を見ると、昭和51年時点で既にトマトが32%、きゅうりが41%、いちごが69%等となっていたのが、平成5年にはそれぞれ、70%、64%、93%と施設栽培の割合が急激に高まっている(第1-1-6図)。
また、食品の生産地と消費地の地理的隔たりも年を追うごとにますます拡大している。第1-1-7図は東京都中央卸売市場の産地別野菜取扱量の推移を見たものであるが、昭和40年と比べると平成6年には関東産の割合は約7割から5割に減少し、その分を他の地域、しかも北海道や九州、さらには海外といったより遠距離の産地が埋める形となっている。
ウ 食の外部化と個食化の進展
我が国の食生活はその内容面に加え、形態面においても大きく変化してきた。形態面の変化として第一に挙げられるのが食の外部化である。食の外部サービスとしては、調理冷凍食品やレトルト食品などの「加工食品」、惣菜、持ち帰り弁当や宅配サービスなどの「調理食品」、ファーストフードやレストランなどの「外食」があるが、いずれも現代の食生活に大きな位置を占めるに至っている。昭和40年代後半には主要なファミリーレストランやファーストフードチェーンの出店が相次ぎ、外食が一般化するとともに外食率も高まった。外食産業及び料理品小売業の市場規模をもとに食の外部化率を見ると平成5年には約4割にまで上昇している(第1-1-8図)。また、調理冷凍食品やレトルト食品の生産量もやはり昭和40年代半ば頃より大きな伸びを見せており、昭和45年と平成5年を比べると、(社)日本冷凍食品協会及び(社)日本缶詰協会によれば生産量はそれぞれ約15.5倍、約11.4倍となっている。
食生活の形態をめぐるもう一つの変化として、家族がばらばらに食事をする食の「個食化」がある。子供の塾通い等の増加、父親の長時間通勤や残業、母親の就労や習い事・地域活動への参加などにより、家族の生活パターンにずれが生じ、家族が揃って食事をする機会が減っている。第1-1-9図は3歳以上15歳以下の子供が誰と一緒に朝食を食べるかを昭和57年と平成5年で比べてみたものであるが、両親と食べる割合が約12ポイント減少し3割を切る一方、子供だけで食べる割合は約9ポイント増加し、逆に3割を越えている。
このような食生活の変化は、質量ともに我々の食を改善し、国民生活の向上に寄与してきたが、その一方では、日々の食生活が環境の恵みによって成り立っていることを実感しにくくしている。例えば、生産地と消費地の隔たりや旬の希薄化により、本来、自然の恵みを一番身近に感じられるはずの食物が、あたかも自然の営みと関連の薄い「製品」のように認識されやすい状況となっている面もあると考えられる。
また、食生活の変化が、一面では環境への負荷を増大させてきていることも指摘できる。例えば、施設栽培については、加温設備があるのが約3割であり、省エネルギー化も進められていることから、施設栽培の割合の高まりをそのまま環境への負荷の増大と考えるわけにはいかないが、(社)資源協会の試算結果によれば、生産に要するエネルギー量を比べると、夏秋どりの露地栽培ものと冬春どりのハウス加温栽培ものでは、相当の開きがある(第1-1-10図)。また、農作物の生産のためにビニールハウスその他で用いられたビニールの廃棄も大きな問題となっている。
さらに、生産地と消費地の隔たりは、輸送に伴う環境への負荷を増大させる一因となってきた面もある。
また、外食の増加は家庭内における調理を食品加工場やレストラン等において一括して肩代わりすることによってエネルギー消費等を低減させる要素となるとも考えられる一方、個食化の傾向とも相まって、ある者は家で食事をし、ある者は外食するという形態をとる場合は、家庭内における食事に伴う環境への負荷はそれほど減らず、全体として負荷を増大させる要素となるとも考えられる。さらに、加工食品や調理食品の購入に伴う包装廃棄物も看過できない問題である。例えば京都市のごみの組成を見てみると容積比では約6割が包装容器であり、その約7割が食料品・飲料用となっている(第1-1-11図)。また、スーパーやコンビニエンス・ストア等では、従来、裸で売られていた野菜なども個別に包装されて売られており、食生活に伴う包装廃棄物の増加の一因となっているものと思われる(第1-1-2表)。
さらに、調理や保存のための家電製品の普及は食生活の内容の変化と並行して進み、現在、冷蔵庫、炊飯器の普及率はほぼ100%、電子レンジについても80%を越えている。これらの家電製品の普及は、食生活の向上及び家事労働の軽減に大きく貢献した点で評価されるが、環境面からは、特に保存に係る機器を中心に負荷を増大させてきたものと考えられる。さらに、近年、より大型かつ多機能の製品が選択される傾向にあり、このような傾向は一台当たりのエネルギー消費効率等の改善を打ち消す方向に働いているものと推察される(第1-1-12図)。
また、機器の大型化はエネルギー消費以外の面でも環境との関わりを持つ。冷蔵庫の主流は現在、300リットル以上の大型のものに移りつつあるが、これに伴って食品の収納場所としての冷蔵庫の位置づけが高まっている。特に若い世代ほど食品を冷蔵庫で保存する割合が高く、冷凍食品等を上手に活用していると考えられる一方で、食品保存に関する知識が薄れた結果、「とりあえず冷蔵庫に入れておけば安心」ということで、必ずしも冷凍や冷蔵が必要ない食品までも冷蔵庫で保存する冷蔵庫への過剰依存がうかがわれる。また、賞味期限が過ぎた食品についても若い世代では無条件に廃棄する割合が高く、例えば、(財)食生活情報サービスセンターの調査によれば、賞味期限の過ぎた豆腐の扱いについてみた場合、中身を確かめずに捨てる割合が全体の平均では13%であるのに対し、20代では2倍以上の29%となっている(第1-1-13図)。平成6年版の環境白書では手つかずの食品がそのまま捨てられる割合が高まっていることを見たが、これらのことからは、冷蔵庫等の便利な機器が普及したことなども受けて、食品が食べられるかどうかを日付表示等のみに委ね、自らの五感によって判断しなくなっていることが示唆される。
(2) 世界の視点から見た食と環境
ア 食と環境をめぐる世界的な状況
持続可能な開発をめぐっては、環境への負荷を増大させている非持続的な生産・消費形態、及び貧困、人口増大などの問題の解決を図っていくことが世界で共通に取り組んでいくべき課題となっているが、食と環境との関わりで見ても、開発途上国においては、国連開発計画(UNDP)によれば、現在でも、ほぼ8億人が日常的に十分な食料を得ることができず、約5億人が慢性的な栄養失調の状態にあるとされ、貧困から環境をかえりみる余裕がない中で、人口の増加等に伴う食料増産圧力が大きな環境への負荷となっている状況が見られる。
現在、世界の穀物耕作地面積はほぼ横ばいとなっており、多くの場合、耕作に適した開墾しやすい地域は既に開拓し尽くされてしまっている結果、熱帯林や半乾燥地域、急斜面の山腹等の環境保全上脆弱な地域を開拓せざるを得ない。
例えば、世界資源研究所(WRI)によれば、フィリピンでは環境上脆弱な高地地帯の森林が人口移入に伴って耕地に転換され、高地地帯の耕地面積は1960年(昭和35年)当時の58万2,000haから1987年(62年)には390万haに増加したとされる(第1-1-3表)。森林地の土壌浸食は年間1ha当たり2トン以下であるのに対し、新規に開拓された農地のそれは、1ha当たり122トンから210トンほどに達したものと見積もられている。
また、世界各地で、不適切なかんがいによる塩類の集積、移動耕作における休閑期短縮による土壌の疲弊、過放牧に伴う砂漠化等が進行している。国連環境計画(UNEP)の資金援助の下に国際土壌評価センター(ISRIC)が実施した調査によると、世界の土壌劣化の原因としては森林減少及び土地利用の転換、過放牧、農業活動が3大要因となっているが(第1-1-14図)、いずれも食料生産と深く関わるものである。
さらに、開発途上国は農業国との印象が強いが、実際には先進国向けの商品作物を栽培する一方で穀物に関しては大半を先進国からの輸入に頼っているという国々もある。このような構造が環境破壊や国内自給作物の衰退の要因となっているとの見方もある。
今後、人口増加等を背景に、中長期的には食料需給が逼迫するとの見方もある中で、この貧困、人口増加、環境破壊の状況はより厳しさを増していくものと考えられる。
イ 開発途上国における輸出向け食料生産に伴う環境破壊
開発途上国においては、輸出向け食料生産が不適切な方法で行われることによる環境問題が生じている事例が見られる。平成4年の環境白書においては、マングローブ林を開墾して輸出用のエビの養殖池にした結果、マングローブ林の豊かな生態系が破壊され、これによって支えられてきた周辺海域の豊かな漁業生産を低下させ、マングローブ林によって守られてきた海岸地域が高潮などの危険にさらされた事例を取り上げたが、このような不適切な方法による輸出向け食料生産に伴う環境破壊の事例はほかにも見られる。
(ア) サンゴ礁におけるシアン化合物を用いた漁法と環境影響
食の高級化に伴い、食べる寸前まで魚を生け簀で飼育しておくことが広まり、活魚の需要が拡大している。香港などでは、生け簀の魚を客が自ら選んで調理してもらう形態のレストランがあり、観光等に際して我が国国民の利用も見られるが、これらの魚はその多くが東南アジアのサンゴ礁で大きな環境影響を伴いながら捕獲されたものであるという。
米国の環境保護団体であるネイチャー・コンサーバンシー(TNC)の報告書によれば、高値で取り引きされるナポレオンフィッシュ(メガネモチノウオ)やロック・ロブスターなどの特定の魚を生け捕るために極めて毒性の強いシアン化合物が使用され、生態系に大きな影響が生じているとされる。この漁法は、ダイバーが目的の魚を発見するとそれをサンゴ礁の洞に追い込み、そこへシアン化合物の水溶液を流し込んで魚を麻痺させ、サンゴを壊して目的の魚を捕獲したり、浅いサンゴ礁にシアン化合物を投入したりするものであるが、これにより、そこに生息する多くの小魚やサンゴを含む無脊椎動物が死んでしまう。また、捕獲された魚は、専用の船や飛行機により香港等の消費地に運ばれるが、その間に死んでしまう割合もかなりの量に上るという。このため、現在、東南アジア地域のサンゴ礁産の活魚の貿易量は年間20,000〜25,000トンと推計されているが、実際の影響は統計に現れる以上のものと考えられている。なお、我が国へはサンゴ礁産の魚は観賞魚として多数輸入されており、その中にも、このような破壊的な漁法で捕獲されたものが含まれると言われる。
現在、サンゴ礁産の活魚はフィリピンでは枯渇し、インドネシアが最大の供給地となっているが、同地域からの供給も今後3〜5年で減少すると見込まれ、パプア・ニューギニア方面への進出が図られていると言われる。これらの地域はサンゴ礁の分布の中心をなしており、シアン化合物を用いた漁法により特定魚種にとどまらない、生態系そのものへの影響が懸念されている。これらの需要の背景には、生きた、それも養殖ものではない野生の魚を珍重するという消費者側の嗜好が強く働いており、その一端が天然ものと養殖ものの卸売価格の差に見て取れる(第1-1-4表)。
(イ) プランテーションにおける農薬の影響
食品輸入の拡大に伴い、我が国では既に販売が禁止された農薬やポスト・ハーベスト(収穫後に使用される農薬)が食品に残留しているケースも報告され、健康への影響が懸念されている。このため、残留農薬基準の設定数の拡大や輸入食品の検査体制の強化などにより、国内に流通する食品については安全性の一層の確保を図っていくこととしている。一方、我々は、輸入食品に対する農薬の影響については関心が高いが、その背景で、それらの食品を生産するために、直接農薬の散布等に関わっている人々が存在することに思い至ることはほとんどない。
特に我が国への食料輸出の多いアジアの国々では、先進国で禁止されている農薬が未だに広範に使われていたり、使用が規制されても実際には使用が継続されているケースが見られる。
農薬散布作業者への健康影響も深刻であると言われる。農薬問題に関わる国際的NGOである「国際農薬監視行動ネットワーク」(PAN)が1991〜93年(平成3〜5年)にかけて、アジア各国の農業に従事する女性2,500人以上を対象として行った調査によると、多くの女性が農薬の散布や調合への従事を通じて農薬に接しており、めまい、筋肉の痛み、やけど、水膨れ、吐き気、目の痛み、爪の変色などの影響を受けているとされる。第1-1-5表は、マレイシアのプランテーションで我が国では使用が禁止されているリンデンの散布に従事している女性を対象に実施した調査結果をとりまとめたものであるが、「時々」と「よく」を合わせるとほとんどの女性が農薬の影響を受けていることが察せられる。この背景には、農薬は適正に使用されなければ危険な場合があることを知らされていない、注意書きが読めない、防護服が支給されない、防護服があっても熱帯性気候のため着用しない、農薬を浴びてもそれを洗い流す施設がプランテーションに整備されていない、などの点が挙げられている。また、農薬の影響を被っている人でも、生活のためには引き続き農薬散布に従事せざるを得ないという事情があるとされる。なお、プランテーション等における農薬使用の実態については調査を行うこと自体が非常に困難であり、情報が不足している。
ウ 世界の環境と結びつく我が国の食
我が国の食生活は現在その大きな割合が輸入によって成り立っている。食料輸入は戦後ほぼ一貫して増加しており、物量ベースでは昭和35年から平成6年の間に10.7倍に増加し、食料(供給熱量)自給率は昭和40年度の73%から平成6年度には46%に低下している。このような食料輸入の増加は、それを生産する世界の環境により多くを我が国が依存するようになってきたととらえることが可能である。対日輸出に充てられる海外の作付面積などもその一例である。平成4年度には、我が国が輸入する主な農産物8品目を生産するのに国内作付面積の約2.3倍に相当する約1,030万ha、小麦1品目に限っても四国より広い面積が用いられたと推計されている。
このような食料輸入は、環境問題と関わりが深い窒素循環の中でも大きな流れを形成している。ここでは農業環境技術研究所の試算に従って、平成4年の我が国の食料生産・消費に伴う窒素循環を追ってみよう(第1-1-15図)。図中の矢印の太さは窒素の流れの大きさを表しているが、流入として大きいのが、食料輸入(83万トン:穀物、肉・乳製品等、水産物の合計)、化学肥料(61万トン)、そして漁獲物(26万トン)である。これに対し、排出としては、し尿・雑排水(67万トン)、家畜ふん尿(37万トン)、農耕地からの溶脱(34万トン)が大きく、合計ではほぼ170万トンもの窒素が何らかの形で環境中に放出されている。昭和30年には環境中への窒素放出量は約77万トンであったことから約2.2倍の増加であるが(第1-1-16図)、この間の総たんぱく質供給量は1.7倍にとどまり、環境に放出される窒素の増加は供給量の増加より大きい。もちろん、し尿や家畜ふん尿等は法律でその処理が義務づけられており、農耕地からの窒素も脱窒作用により空気中に還元される部分もあることから、放出される窒素すべてがそのまま環境への負荷の増加につながっている訳ではない。しかし、窒素放出量の増大とその背景にある食料輸入や生活雑排水等の増大は自然界の窒素循環を大きく改変し、地下水の硝酸性窒素汚染、湖沼や内湾の富栄養化などの環境問題の遠因となっているものと考えられる。
(3) 自然の循環の一部を担う食生活への変革
本来、生物にとって「食」とは、自然からの恵みを体内に取り入れ、同化し、不用物を再び自然に戻すという一連の流れの中に位置づけられるものであり、自然の循環の一環を担うものである。人間はこれに社会的、文化的な意味合いを付け加えたが、それによって食と自然とのつながりが断ち切られたわけではない。むしろ、多くの食文化はこのような食と自然との関係を的確にとらえてきたものであると考えられる。ところが、現代においては生産と消費が遠くかけ離れてしまった結果、そのつながりが非常に見えにくくなり、食物とそれが生産される環境を結びつけて考えることが困難になってきている。
野菜や果物を選ぶ際に色や形、虫食いの有無等の外見を過度に重視する傾向があると言われる。しかし、生物の本質が多様性にあることにかんがみれば、農産物にも個体差があることが自然な状態なのであり、むしろ、皆が一様に整っていることに疑問がもたれるべきとも考えられよう。現在、農薬使用の目的の一つがこのようなきれいな外見の重視にあることにかんがみれば、実際上の環境への負荷の軽減の観点からもこのような傾向の見直しは重要な課題であろう。総理府の「食生活・農村の役割に関する世論調査」によれば、「価格が多少高くても、包装、外観のよいものであれば購入する」という設問には、約8割が「そうしていない」と回答しており、本調査による限り、消費段階では必ずしも外見が重要な商品選択の基準とはなっていない(第1-1-17図)。
このような食と自然の分断とも言うべき状況の中で、徐々にではあるが、食と環境の結びつきを再確認し、食生活を自然の循環の一部を担うものへと変革していこうとする動きが我が国でも見られるようになってきている。
ア 家庭における取組
台所からの環境保全に向けた試みとして「エコ・クッキング」と呼ばれる取組が広がりを見せている。エコ・クッキングといっても特別なものではなく、買物、調理、食事、片づけ、排水やごみ処理などの過程に応じて、ちょっとした工夫をしたり、思いやりをかけることによって食生活からの環境への負荷をできる限り少なくしようとする試みと考えられている。石川県などを先駆けとして、各地の地方公共団体や料理学校、ガス会社、近年では農林水産省等でエコ・クッキングのためのパンフレットを作成したり、講習会を開催したりしてその普及に努めている。その中では、普段は捨てていた野菜の皮や芯なども利用して旬の食材を余すことなくおいしく食べるための料理、油や洗剤の上手な使い方、鍋底を拭いてから火にかけることによる省エネルギーなど、台所でできる様々な工夫が取り上げられている。このような工夫の中には少し前までは当然のこととして行われ、家庭内で伝えられてきたものも多いと考えられるが、そのような機会が減少した今、エコ・クッキングの試みは新たな知識習得の機会として意義あるものであろう。また、食材を余すことなく使うことは、より一層の関心を食材に向けることとなり、必然的にその生産方法等にも目が向けられ、ひいては、流通、販売方法、さらに排水やごみの最終的な行方にまで目を行き届かせ、食生活全般と環境を結びつけるきっかけとなると考えられる。
調理に関する取組として、もう一つ「ソーラー・クッキング」を見てみよう。ソーラー・クッキングは文字どおり太陽のエネルギーを利用して調理を行うもので、日照が特に多いとはいえない我が国においても、手製の簡単な装置によって約2〜3時間でご飯やおかゆ、ゆで卵、焼き芋などができる(第1-1-18図)。ソーラー・クッキングは特に日常的に調理のための燃料が不足している開発途上国において積極的に活用されることが期待される。アフリカ等では調理用燃料として大量に薪炭材が切り出され森林破壊が進むとともに、安全な飲み水の確保も困難な状況にある国々が見られるが、ソーラー・クッカー(太陽熱調理器)を用いることにより、薪炭材を使わずに調理と水の殺菌を行うことが可能である。このような観点から米国ではソーラー・クッキングを普及するための市民団体が組織され、国際会議を開催したり、難民キャンプに太陽熱調理器を導入して講習会を行うなどの活動を進めている。このような取組の輪は我が国を含む世界中に広がりつつある。
イ 生産・流通における取組
食に対する安全を求める声や環境保全に対する意識の高まり等を背景に、化学肥料や農薬等の使用を控え、自然の物質循環に依拠した農業が広がりを見せている。このような環境保全型の生産形態を支える大きな原動力となっているのが産直などを通じた生産者と消費者の顔と顔の見える関係である。生産者と消費者が結びつくことによって、ただ単においしくて安全な食料を望んでいた消費者も、それが食料を提供してくれる環境が保全されてはじめてかなうことを自覚するとともに、生産者にも、食べる人の健康を預かっているのは自分であり、そのためには生産基盤である環境を守っていかなくてはならない、という強い気持ちが働く。いわば、生産者と消費者の間に、共に生産の責任を分かち合い、地域の自然を共有するという関係が生じ、自然との結びつきを確認するきっかけとなるものと考えられる。特に、多くの産直運動では産地交流会や農作業体験の機会が設けられており、直接に自然との結びつきを実感できる場となっている。例えば、大阪の市民生協と北海道十勝の農場との産直を通じた交流では、毎年組合員の子供たち約30人が農場を訪問し、農家に1週間程度ホームステイする中で北海道の食について知り、それを育む自然環境を体験している。
一方、産直が社会的な広がりを見せる中で、環境保全型の有機農産物を高付加価値の特別なものと考えず、市民団体が生産者、加工業者、流通・販売業者等と一体となって自主的な環境保全型生産基準を設定し、環境への負荷の少ない食料その他の生活必需品を開発・普及していこうとの試みも見られる。産直は宅配などの環境面からは負荷の大きい輸送手段の発達によって発展してきた面があり、必ずしも環境保全の観点から無条件に礼賛されるものではないが、身近な食生活と環境を結ぶ動きとして今後とも注目されよう。
いわゆる「フェア・トレード(公正貿易)」は、途上国の生産者と先進国の消費者を結び、貿易に伴う環境への負荷が生じていないこと、生産者が正当な利益を得ていること等の通常の貿易ではうかがいしれない部分を保証する貿易形態であり、扱われる産品の素性が知られている点では、国際的な産直という側面を持つ。コーヒーや紅茶等の農産物、工芸品等を現地NGOなどの組織を通じて生産者と直接取引することにより、生産者の健康や環境への影響を防止するためのコストを加味して原価を算定し、より多くの利益が生産者にわたるようにしている。欧州では1960年代後半のオランダを発端として、非常に活発な運動として展開されており、スイスでは人口100万人に対し、店舗など600カ所でフェア・トレード商品が販売され、オランダでは更に多いと言われる。我が国でも市民団体等を通じてバナナその他のフェア・トレード商品が取り扱われるようになっており、最近では、マングローブ林の破壊や地下水のくみ上げ等の面で環境に悪影響を与える場合が見られる集約型の養殖場で生産されるエビに対して、伝統的な粗放型の養殖池のエビをフェア・トレードで輸入する動きもある。
先に見たように、食品に伴うものも含め容器包装は一般廃棄物全体の中でも大きな割合を占め、その減量化に向けた取組が急務となっている。このため、平成7年6月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が制定され、再商品化の義務の実施等の規定は平成9年4月より段階的に施行されることとなっている。同法では、消費者は分別排出、市町村は分別収集を行い、事業者は市町村が分別収集した分別基準適合物を自ら又は指定法人やリサイクル業者に委託して再商品化することとされている(詳細については第3章第3節参照)。
一方、環境基本計画では、廃棄物・リサイクル対策の考え方として、まず第1に廃棄物の発生抑制、第2に使用済み製品の再使用、そして第3に回収されたものを原材料とするリサイクル及び環境保全に万全を期しつつエネルギーとしての利用を推進し、最後に、発生した廃棄物について適正な処理を行うこととしている。したがって、リサイクルを行うよりもまず、廃棄物の発生抑制と再使用(リユース)が求められる(第1-1-19図)。
我が国では、ビールびんや一升びん等が昔から再使用されており、ビールびんは約99%と高い回収率を誇っている。しかしながら、近年は消費者意識の変化等に伴う缶ビールや紙パックの増大によりびんビールや一升びんのシェアは低下し、全体として再使用されるびんの量も減少してきている。このような中で、生活クラブ生協連合会等全国の4つの生協(組合員数100万世帯)が「びん再使用ネットワーク」を組織し、びん回収業者、飲料等の製造業者等と協力して再使用を進めている。内容量に応じて複数のびんを使い分けているが、ジュースや醤油等に共通のびんを使用することにより汎用性を高め、再使用の促進を図っている。また、一部ではデポジット制度を導入し回収の効果を高めている。しかしながら、ワンウェイ(使い捨て)容器を回収あるいは処理する場合には行政負担となるのに対し、リターナブルびん(再使用されるびん)の回収は生協組合員の負担となることから、再使用を自前で続けていくのは厳しい状況にあるとの声もある。また、びんは分別回収に出してカレットとして再生利用すれば良い、という消費者の再使用の意義に対する理解が不十分な面も見られるという。このようなことから、再使用を推進するためには、消費者や事業者をはじめとする国民的合意を醸成していく必要がある。
包装廃棄物対策は、欧州をはじめとする地域で、まず如何に廃棄物自体を減らすかという観点から一層徹底した取組が進められている。食品に係る容器包装は衛生上の観点もあり単純に無くせば良いというものではないが、ドイツのスーパーマーケットでは、例えば、チーズやバターなども外箱なしで販売されるとともに、牛乳、マヨネーズ、ケチャップ等に共通のリターナブルびんがデポジット分を上乗せして販売されているほか、果物等も量り売りとなっており、個別包装はしていない。
食生活が自然の循環の一部を担うようにしていくためには、いわゆる資源ごみだけでなく、野菜くずや食物残渣なども自然に返して有効利用していくことが望ましい。各地の地方公共団体において、家庭からの厨芥ごみの減量化を図るためにコンポスト容器への助成や講習会の開催等が実施されており一定の成果を挙げている。東京都板橋区等の都心の地方公共団体においても取組が進められ、同区がコンポスト容器のモニターに対し行ったアンケートでは、「できた堆肥を家庭菜園で使うのが楽しみ」等の声が聞かれ、単にごみの減量化にとどまらず、日常生活と環境を結びつける機会となっていることがうかがわれる。また、国では、家庭、事業所等から排出される生ごみ等を生分解性プラスチック製のごみ袋を用いて収集し、コンポスト化するモデル事業なども進められている。さらに、農家、流通業者、商社などが一体となって任意団体を組織し、生ごみのリサイクルを進める試みがある。これは、量販店や外食産業から出る生ごみをたい肥化して、農家の野菜作りに役立て、さらにできた野菜を量販店などが販売・利用することを目指すものであり、たい肥の製造に当たって量販店等で発生する可燃ごみを燃やした熱を利用することを特徴としている。平成8年2月に東京の中堅スーパーがたい肥製造プラントの導入実験を開始した。今後、一般市民も含めて活動を拡げていきたいとしているが、食に関わる新たな循環型システムとしてその進展が期待される。
これまで見てきたように、今日の我々の食生活の裏には環境への負荷の高まりが見られ、また、今日の食生活をめぐる状況は、日々の食生活が環境の恵みの下に成り立っていることを実感しにくいものとしてきている。
しかし、食物は環境を直接の基盤として生産されるものであり、食と環境を切り離して考えることはできない。日々の食生活の中において、その背後にある環境との関係を再確認することは、今日の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の在り方に目を向け、それを考え直す第一歩となるのではないだろうか。