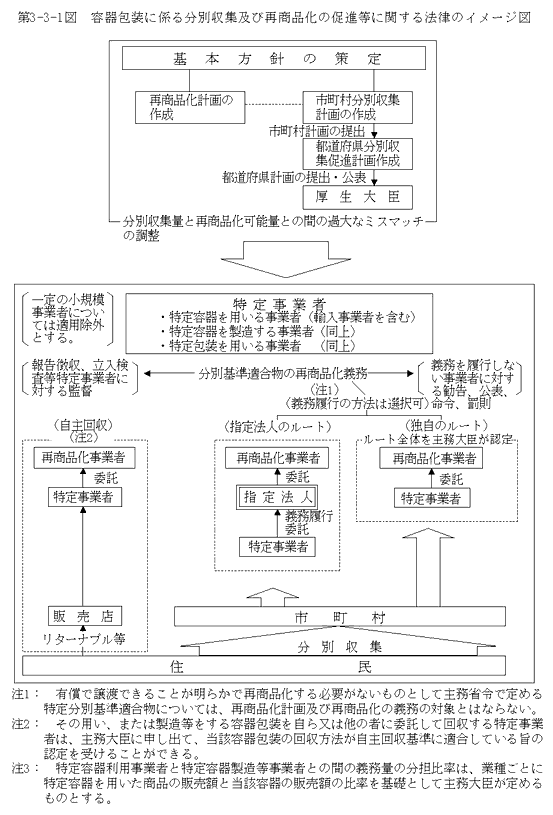
1 最近の事例にみる役割分担による施策
本節では、様々な主体が人間活動と環境との関係について共通の理解を持ち長期的な目標の実現に向けて長期的・総合的に取り組んでいくことを確保する政策手法、公平な役割分担の下で広範な社会経済活動に環境を織り込む政策手法について見てみよう。
我が国においては、経済活動と国民生活の向上等に伴い、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場が逼迫(ひっぱく)しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化している。その一方で、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られたものを資源として有効に利用していくことが求められている。平成3年に「再生資源の利用の促進に関する法律」が制定されたが、このような状況において、快適な生活環境と健全な経済発展を長期的に維持していくためには、関係者の適切な役割分担の下で、一般廃棄物の減量と再生資源としての適切な利用を図っていくことが重要であるとの観点から、平成7年12月、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が施行された。同法では、容器包装を「商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」と定義し、びん、缶、紙、プラスチック製のもの等、原則として商品に付されたすべての容器包装を対象としており、国、地方公共団体、国民、事業者等による役割分担の下で、社会経済活動に環境保全の配慮を織り込んでいくルールを進めるものといえる。以下では、その役割分担を概観してみよう(第3-3-1図)。
(1) 国の役割
主務大臣は家庭等から廃棄物として排出される容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、その分別収集及び再商品化の促進に関する基本的な方向等について、基本方針を定めることとしている。また、事業者によって行われる再商品化が、基本方針に則して円滑かつ確実に促進されていくように、主務大臣は、事業者の行う再商品化の量の見込み、施設の設置に関する事項等について再商品化計画を定めることとしている。
さらに、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進の意義、事業者が負担する再商品化に要する費用の消費価格への適正な反映の重要性について、国は、国民の理解と協力を得るように努めることとしている。
(2) 市町村及び都道府県の役割
容器包装廃棄物の分別収集を実際に行うこととなる市町村は、その実施に際して、その区域において廃棄物として排出される容器包装の量の見込み、そのうち市町村の分別収集により得られるものの量の見込み等について、分別収集に関する計画を定めることとしている。また、都道府県は、これに対して市町村に必要な技術的援助を与えるとともに、都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画を定めることとしている。
(3) 事業者の役割
容器包装の利用及び製造等の事業を行う者は、毎年度、容器包装の利用量、製造量等に応じて、市町村の分別収集により得られたものの再商品化の義務を負うとともに、関係事業者は、その再商品化を促進するための措置を講ずる義務を負うこととなった。また、消費者と同様、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するように努めることとされた。
(4) 指定法人の役割
事業者の負う再商品化の義務の履行を円滑かつ容易にするため、主務大臣は再商品化業務を適正かつ確実に行うことのできると認められるものを再商品化業務を行うものとして指定し、この指定法人への再商品化の委託により、事業者の再商品化の義務は履行されたものと見なすこととされた。
(5) 消費者の役割
繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するように努めることとされた。
このように「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」では、廃棄物等の問題に対し、それぞれの経済主体が役割を分担しあうことで、これに対処することとしている。次に、やはり公平な役割分担の下で社会経済活動に環境を織り込んでいくために有効であると考えられている経済的手法と環境影響評価について見てみたい。