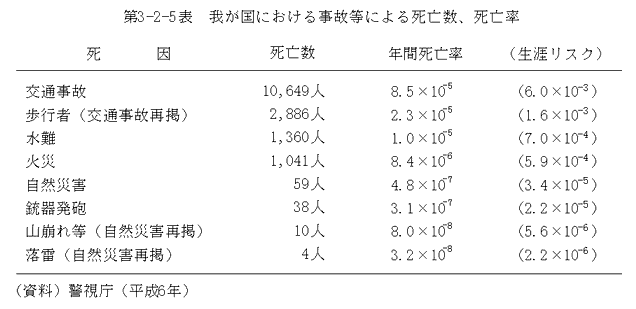
2 不確実性を伴う環境問題への対応−環境リスク
現代社会において、我々は様々な技術によって作られる製品やサービスに支えられて、便利な日常生活、経済活動を営んでいるが、他方で、社会経済活動の中で事故や火災、あるいは自然災害に遭う可能性がある。こうした事故等による人身の被害については、例えば、統計的な年間の死亡数とそれを基に算出した生涯における死亡のおそれ(リスク)という数字によって比較して表すことができる(第3-2-5表)。ここで、例えば交通事故の生涯リスクが(6.0×10-3)とは我が国に住む人が一生涯に交通事故で死亡する確率が1000分の6であることを意味する。我々は、こうしたリスクの大きさと蓋然性についてできるかぎり定量的に理解することを通じて、これを防ぐための政策を決める際に優先順位を明らかにし、あるいは日々の生活においてリスクを避けるように努めたり、保険をかけることによってその被害の経済的負担を分散させたりすることができる。
今日の環境問題、とりわけ、経済社会で広く用いられている化学物質による健康・生態系への悪影響、オゾン層の破壊、気候変動等の地球環境問題等については、多数の因子が複雑にからむ因果関係とその予測される結果を科学的に明らかにし、適切な政策を進めなければならないが、種々の不確実性が存在することは避けられない。こうした環境問題について、リスクの考え方を基礎にして、不確実性も考慮に入れたうえで科学的解明を進め、得られた知見に基づいて予見的な見地から政策を決定・実施していくための政策手法が内外で根付いてきている。以下では、このような環境リスクの考え方とその応用について考察することにしよう。
(1) 環境政策と環境リスク
本来、リスクとは、人間の活動に伴う、望ましくない結果とその起こる確率を示す概念である。すなわち、人間にとって好ましくない事象をその「発生の不確かさの程度」と「影響の大きさの程度」の両面から評価し、その程度に応じて対応していこうというのがリスクの考え方の基本である。最近ではより広義にリスク概念がとらえられるようになってきている。例えば、リスクは「ある技術の採用とそれに付随する人の行為や活動によって、人の生命の安全や健康、資産ならびにその環境(システム)に望ましくない結果をもたらす可能性」と定義され、環境リスクも自然災害リスク、都市災害リスク、食品医療品リスク等と並ぶリスクの類型の一つを構成するものとして考えられる(池田、盛岡「リスク分析の考え方とその方法−特集−:リスク学のアプローチのまとめ、日本リスク研究学会誌、5(1)1、1-7(1993))。
このようなリスクの考え方が環境政策の主要な課題の一つとなってきた背景と意義はどこにあるのであろうか。
ア 環境リスクの考え方の背景
かつて我が国が激甚な公害を経験した時代には、著しい産業公害の状況が明らかにされ、これによる健康や生活環境の被害も差し迫ったものであったため、公害の防止が主たる政策課題とされ、その達成手段の選択にも広範な合意があった。原因となる物質や事業活動その他を特定し、排出の規制を中心とする対策が講じられ、その克服に相当の成果があった。その一方で、拡大高度化する経済活動、一層便利になる消費生活を支えるために様々な化学物質が広範に用いられるようになり、これらに起因する環境問題への関心が次第に大きくなってきた。例えば、欧米では、1970年代後半から80年代前半にかけて、アメリカのラブカナル事件(1979年(昭和54年))、インドのボパール事件(1985年(60年))といった深刻な問題の発生もあって、様々な有害化学物質による健康と環境へのリスクが国民の関心の的となった。特に有害化学物質に発がん性が認められるときには、従来のように人間が取り入れる量を一定の許容量以下に抑えれば安全という考え方では十分に対処できなくなったことから、こうした問題を解明する科学的方法と政策的対応のあり方が大きな問題となった。このような状況の下、アメリカでは国立科学アカデミーと国立研究財団の共著によるリスクアセスメント/リスクマネジメントの報告(1983年(58年))がまとめられ、これに沿った科学的調査と政策決定の仕組みが論議され、法律や行政規則等を通じ具体的な手法として定着していった。また、同時期に、オゾン層の保護に関して、科学的な解明を進めながら、その国際的規制のための条約と議定書が策定されたのは、地球環境問題についてリスク・アセスメント/マネジメントの考え方を適用した先駆的な事例と言われる。
今日、全世界で登録されている化学物質数は約1,700万種に及び、商業目的で生産されているものだけでも約10万種に上ると言われる。我が国においても生産、使用されている既存の化学物質は約48,000種を越え、労働安全衛生法による製造・輸入の新規の届け出件数は、毎年400〜500種に上るとされる。これらの物質は、日々の生活と社会経済活動のために大量に生産され、使われ、最終的には環境中に放出されるが、その態様によっては、健康、生活環境、生態系に悪影響を及ぼすおそれがある。このような問題について、環境の変化や汚染を通じて生ずるリスク(以下、「環境リスク」という)の考え方を適用していく意義を次に見てみよう。
イ 環境政策における環境リスクの意義
第1に、環境リスクの考え方により、不確実性を伴う環境問題について科学的知見に基づいて様々な環境への影響を予測、評価して、政策的判断の根拠を明らかにすることができる。化学物質については、人間や生態系が微量の物質に複雑な経路を通じて長期間にわたり曝露されることから生ずる健康と環境に対する影響が問題となるが、これを検出し、その原因を特定するのは極めて困難である。地球温暖化は、さらに空間的にも時間的にも広範囲、長期に及ぶ複雑な問題である。こうした問題については、確率論的な考え方を用いて、不確実性を考慮に入れながら問題が見えるようにし、政策判断の基礎とすることが必要である。環境基本法第4条は「科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれること」を旨とするとの未然防止の原則を定めているが、環境リスクはこの原則を実行していくうえで重要かつ不可欠な手法である。
第2に、環境リスクの考え方により、多数の物質あるいは要因に対する政策と取組の優先順位を客観的に明らかにすることができる。従来、環境汚染物質の安全性に関する基準は、ある一定レベル以上の環境濃度になると悪影響が生ずるという値(閾値という)を基にして決められてきたが、一般に閾値がないとされる物質(例えば遺伝子毒性のある発がん性物質)については、ごく微量に存在しても健康影響(発がん)の可能性を否定できない。一方、環境リスクを生じさせる要因となる物質は、人の生活にとって必要とされるものも多く、これらをすべて使用禁止にすることは実際上不可能となってきた。このため、限られた資金や人的資源の中で、健康影響の発生確率を低減し、「実質的に安全とみなすことのできる」環境リスクのレベルを目標として、政策判断をするという考え方が広く受け入れられるようになってきている。例えば、物質の有害性は強いがほとんど住民が曝露されないような場合と中程度の有害性で多数の住民が曝露される可能性のある場合の環境リスクを比較することにより、政策決定に有効な基礎を与えることができる。
また、地域の環境状況と社会的経済的条件等によって問題となる環境リスクの種類と程度が異なる場合もあることから、問題間の比較衡量を可能にする環境リスク概念の導入により、地域の状況に応じたよりきめ細かな対応も可能となる。
第3に、環境リスクの考え方を応用すれば、大気、水、土壌などをまたがるクロスメディアの汚染や、各分野の対策を横断して、より効率的、整合的に環境リスクを削減できる。化学物質や地球環境問題は発生過程が複雑であり、複数の環境メディアにまたがり、地域から地球規模にまで広がる問題として、正にこのような対応が求められる。例えば、化学物質による水質汚染を改善していくために、別の環境メディアにその汚染を移転させるような政策は、真に環境リスクを減らすことにはつながらない。こうした複雑多岐にわたる問題について、環境リスクの考え方、とりわけ、例えば「損失余命」のようなリスクの共通の物差しを用いることを通じて、総合的にリスクを評価し、より整合的、効率的な政策手段を選び、実施していくことができる。
このように環境リスクの概念は今日の環境政策にとって極めて有効であると考えられる。環境基本計画では、このような考え方に立って環境リスクを「(化学物質による)環境の保全上の支障を生じさせるおそれ」と定義し、「(環境リスクを)できる限り定量的に評価し、環境リスクを総体として低減させることを目指し、各般の施策を実施する」としている。人間活動によって環境に加えられる「環境への負荷」が、環境中の経路を通じ、ある条件のもとで、健康や生態系等に影響を及ぼす可能性(おそれ)が環境リスクであると言ってもよく、環境リスクの概念は環境基本法及び環境基本計画の体系下で重要な位置づけを持つものである。アジェンダ21でも、その第19章で、有害化学物質に伴うリスク対策を国際的な協調の下で促進すべきことを規定している。
ウ 環境リスクが対象とする範囲
環境リスクを「環境の保全上の支障を生じさせるおそれ」としてとらえれば、人の健康への影響、生態系への影響、生活環境への影響すべてを環境リスクの対象としてとらえることが可能である。また、環境リスクを生じさせる要因という観点からは、化学物質から自然環境の開発行為まで環境保全上の支障の原因となるすべての要因が対象となりうる。環境政策への活用面からは環境リスクの対象をできるだけ広範にとらえることが望ましいが、実際には、どこまで客観的かつ定量的に環境リスクが評価できるかにその適用対象は依存し、科学的知見の充実等に応じて拡大されるべきものと考えられる。
(2) 環境リスク対策の手順
リスクへの対応は、科学的な知見によってリスクを客観的に評価・判定するリスク評価(リスク・アセスメント)、政策決定過程としてリスクの低減を図るリスク管理(リスク・マネージメント)の2つの段階(第3-2-9図)、及びリスクを正しく伝達し相互理解を促進するリスク・コミュニケーションによって構成される。リスク評価過程は科学的なリスク研究の成果に基づいて科学的な評価を行うものであるのに対し、リスク管理過程は政策判断によって意思決定を行うものであることから、両者は作業的には明確に分離されるべきものとされる。ただし、リスク評価はリスク管理に用いられることに社会的意義があり、その意味でリスク評価とリスク管理は一連の流れの中でとらえられるべきものである。以下に見るリスク評価、管理等の手順は、人の健康に関する環境リスクのみならず、生態系に関する環境リスク等にも等しく適用されるものであるが、ここでは、リスク概念の導入が最も進んでいる化学物質(発がん性物質)による健康影響を中心として見ていくこととしよう。
ア 環境リスクの評価(リスク・アセスメント)
リスク評価は一般に次の4つの手順に従って行われる。
(ア) 有害性の確認(定性的評価)
ある特定要因(化学物質等)が人に対して有害性を持っているか否かを同定する。有害性を確認する際は、一般環境における人への影響に関する知見に基づいて判断されることが望ましいが、実際にはそのような知見は少ないので、労働環境における曝露の知見や動物実験の結果から一般環境における影響が推定される。
(イ) 量−反応評価(定量的評価)
化学物質等の曝露量と健康への影響との定量的な関係を明らかにする。すなわち、どの程度の曝露によって、どれくらいの影響が生じるかを評価する。
評価の方法は、人間を対象とする点で疫学的データを用いるのが望ましいが、この目的に耐えるような疫学調査の実施は困難が多い。また、リスク対策の意義が予測的作業に基づく未然防止にあることにかんがみれば、実際に起こった事象から得られる一般環境における疫学的データのみでは十分でない。そこで、一般的には、労働環境における疫学的データや動物実験に頼らざるを得ないが、その際、実験の行いやすい高濃度から実際の環境に相当する低濃度への外挿の問題や、動物実験のデータを用いる場合には種の異なる動物からヒトへの外挿の問題が存在し、その手法の改善に力が注がれている。
(ウ) 曝露評価(定量的評価)
対象とする化学物質等に人がどの程度曝露されているかを定量的に評価する。
曝露量の評価は、環境濃度の測定値や予測値、個人サンプラーによる個人曝露量の測定値、血液や尿中に含まれる化学物質あるいはその代謝物量の測定値などに基づき推定される。曝露評価に当たっては、化学物質等が環境中のどこにどの程度存在するかとともに、生活様式等の違いによりどの程度曝露の機会があるかの両方を考慮する必要がある。
(エ) リスクの判定
上記の(ア)(イ)(ウ)の結果から、人に対する影響の種類、程度を明らかにするとともに、必要に応じて健康影響の発生確率を推定する。例えば、ある化学物質のユニットリスク(量−反応評価から得られた単位当たりのリスク、すなわちある物質に1μg/立方メートルの濃度に生涯曝露されたときの発がんの確率)が3×10-6(μg/立方メートル)-1、我が国の全人口(1億2千万人)が当該化学物質に曝露しておりその生涯曝露レベルが2μg/立方メートルであったとすると、全人口の生涯における発がんリスクの推定は、
3×10-6×2×1.2×108=720
となり、平均寿命を70歳とすると当該化学物質による1年間の過剰発がんリスクは、720/70=10.3、すなわち約10人となる。
このような手順を踏まえて、各種の化学物質等の環境リスクが評価される。
イ 環境リスクの管理(リスク・マネジメント)
環境リスク管理とは、リスク評価によって判定された環境リスクを低減させるための方策を検討、決定し、実施することを言い、政策判断を含むプロセスである。
重要なことは、リスク管理のあり方は、リスク評価の結果を踏まえて、経済社会の情勢や世論等も考慮して総合的に判断されるべきものであることである。そして、リスク評価は先に見たように多くの前提に基づく不確実性を含んでいることから、その不確実性を十分に認識した上で有力な判断材料の一つとして用いられるべきことであり、また、常に新たな知見をフィードバックする機構が保証されるべきである。
また、リスク管理に当たり、リスクを比較する際には、リスクが生じる要因が自発的(voluntary)なものか、非自発的(involuntary)なものかを区別する必要があり、例えば、前者に相当する自己のドライブに伴う交通事故のリスクは受容されやすく、後者に相当する公害に伴う健康リスクは受容され難いため、単純に比較することはできない。
(ア) 環境リスク管理の考え方
一般的に環境リスクの管理に当たっては次の3つの原則が考えられる。
i) ゼロリスクの原則
環境リスクをゼロにすることを指し、閾値のある物質についてはこの原則が適用されている。閾値が明確に定められないものには達成が非常に困難な目標である。また、リスクをゼロにするため製造を禁止若しくは規制した場合、その代替品がより有害性の強い、または、より管理困難な環境リスクを持っていることもあり得るので、これらについても考慮する必要がある。
米国の食品衛生分野では、発がん性のある食品添加物は一切使用が禁止されており、我が国においても原則禁止となっているが、これらは、ゼロリスクの考え方を反映したものである。
ii) リスク一定の原則
すべてのリスクの大きさを一定のレベル以下に抑えるという原則であり、その基礎には非常に小さな一定以下の環境リスクは実質的に安全と見なそうとの考え方がある。例えば、一生涯曝露されたときに10万人に1人にがんが発生する程度以下のリスクは他の種々のリスクと比較して実質的に安全と見なそうというものである。具体例には、例えば、WHOの飲料水ガイドラインがあり、遺伝子毒性のある発がん性物質は生涯リスクを10万分の1以下にすることに基づいて指針値が決められている。我が国の水道水質基準もこの考え方をおおむね踏襲している。
しかし、個々のリスクの大きさを同じ確からしさで知ることが困難であること等から、この原則の適用が困難な場合もある。また、具体的な対策を講ずるに当たっては、手法により環境リスクを一定に抑えていくためのコストが異なることを勘案する必要がある。
iii) リスク・ベネフィットの原則
環境リスクの要因が持つ便益(ベネフィット)と環境リスクの大きさを比較し、様々な環境リスクについてリスク・ベネフィット分析を行い、その大きさによって許容される環境リスクを求めたり、対策の優先順位を決定したりする考え方がある。金銭的な尺度で表現される場合には一種の費用便益分析となり、リスク削減のための対策によって生じる費用(リスク削減によって失われる便益を含む)と、リスク削減によって得られる便益が比較衡量される。費用便益分析の例としては、米国環境保護庁(EPA)が1986年度(昭和61年度)からガソリン中鉛濃度の規制強化を実施するのに先立ち、鉛削減のための費用等と自動車維持費の節約等の便益を比較した試算がある。規制強化による健康被害の低減についても一部価額評価されているが十分なものではない。
このようなリスク・ベネフィットの考え方は、今後、広範多岐にわたる環境リスク対策を限られた人的・経済的資源の中で進めていくための有効な判断材料となることが期待されるが、リスク・ベネフィット分析は未だその手法が確立しているとは言えず、環境リスクが大きな場合にはリスク・ベネフィット分析によることなく対策を講じる必要があるといったリスク・ベネフィット原則の適用条件に関する検討等も今後進めていく必要があろう。
(イ) 環境リスクの管理手法とその体系的な実施
従来用いられてきた環境中の有害物質に対する管理手法としては、?製造・使用の禁止又は制限、?排出抑制、?環境浄化、?曝露防止対策、?対策効果の監視などがある。
?は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)や農薬取締法等において、難分解性、高蓄積性、慢性毒性の高い化学物質や残留性の高い農薬に対して用いられている。?は、大気汚染防止法や水質汚濁防止法で、排出基準や排水基準を定めることにより用いられている。ただし、現在用いられているこれらの手法には定量的なリスク評価に基づかないものもある。?としては、水系汚染物質や大気汚染物質のモニタリングが実施されているが、モニタリングはリスク評価における曝露評価の手法としても重要なものである。
これらの伝統的手法に加え、以下で見るリスクコミュニケーションや経済的手法なども、新たなリスク管理手法として期待されるものである。
さらに、今後は、各々の環境リスク管理手法を相互に連携させて、環境リスク要因の発生からその影響までを視野に入れ、各段階で対策を行っていくことが効果的に環境リスクを低減していく上で重要である。化学物質を例にとると、化学物質の環境リスク管理は、リスク要因の発生までの対策、環境中での対策、曝露防止対策、曝露後の対策の4つに大別される(第3-2-10図)。従来は、健康影響が発現してからの診断、治療、救済が主であったが、今後、環境リスクによる影響を未然に防止し、最小限に抑えるために、環境リスクの評価に基づき、製造・使用の事前審査段階から曝露防止対策まで体系的に実施していく必要がある。
(ウ) リスクの総合的管理の必要性
人の健康や生活環境、生態系が受ける影響は個々のリスクを総合した結果として顕れる。したがって、リスク対策を真に効果的なものとするためには、個々の要因に対する環境リスクの管理に加えて、環境リスクが全体として低減されるようにリスク管理を実施していく必要がある。
しかしながら、化学物質に限っても、現在、環境リスクが評価されている物質はわずかであることから、リスクの総合的管理を推進していくためには、着実に個々の要因についてのリスク評価を進めるとともに、評価されていないリスクや個々の要因が合わさった場合の複合的な環境リスクの推定方法等について検討していくことが求められる。また、様々な環境リスクを合算し総体として表示するための手法の開発が必要である。その上で、リスクの総合的な管理目標の設定等の検討とも併せ、具体的な環境リスク低減策を検討する必要があろう。
ウ リスク・コミュニケーション
(ア) リスク・コミュニケーションの意義
加害者と被害者が明確に存在した従来の産業公害とは違って、現在の環境リスクは、自動車利用や化学物質を用いた製品の使用など日常生活を含めた経済社会活動全般から生じている側面が強い。したがって、このような環境リスクを低減するためには、行政のみならず、国民、事業者、研究者等の関係者がリスクに関する正しい知識とお互いの意見を理解した上で、一体となって取り組む必要がある。このためには、各主体相互の情報交換を通じて、リスクに関する情報や認識を共有し、適切な行動を促すというリスク・コミュニケーションが重要であり、リスクの大きさが社会的に正しく認知されることが、新たな対策を実施するための合意形成の前提となる。
また、リスクに関する情報が適切に伝えられることは、事業者や市民が環境リスクを自主的、積極的に削減していくのを促す上で重要である。規制等の対策がとられるに至らない環境リスクであっても、その要因と大きさが明示されることで、市民は自らの判断でリスクをなるべく回避するような行動をとることが可能となる。例えば、建物の高断熱、高機密化等を背景に、室内環境の化学物質濃度は屋外よりも高い場合が見られるが、これらについては、換気の励行や建築の際にできるだけ薬剤処理をしていない建材を選ぶなど個人レベルで対応できる部分も多く、そのような判断を助ける情報提供や環境教育が行政、事業者には求められる。
また、社会的にリスクが広く認知されていれば、事業者等が行うリスク削減のための自主的な取組の意義が世間一般に理解され易い。このため、環境リスクが定期的に公表されれば、環境保全に積極的な企業の社会的な評価が高まり、自主的な取組の一層の促進が期待できる。さらに、現在の技術水準では対応できないような環境リスクであっても、そのリスクの大きさが示されれば、当該リスクを削減する技術を開発すれば多大な利益が得られるということで、技術開発の強力なインセンティブが働くと考えられる。
(イ) リスク・コミュニケーションのあり方
リスク・コミュニケーションの基本方針は、リスクに関する情報の公正な伝達と双方向の交流にあるが、リスクを正しく伝えることは実際には容易でなく、専門家が科学的に正確な表現をするのとは別の配慮が必要とされる。
リスク・コミュニケーションが的確に行われるためにはまず、確率的表現で示されるリスクという概念自体が十分に理解される必要がある。特に、これまで社会的・文化的な一様性に慣れ親しんできた我が国では、多様性と不確実性の中で個人が深刻な選択を行う機会は少なく、「安全」と「危険」を相互に相容れない二分法的なものとしてとらえがちであった。しかしながら、通常の社会経済活動を営む中で生じる今日の環境問題に対処していくに当たっては、危険を完全に排除することはもはやできず、むしろ安全と危険を連続したものとしてとらえ、その上で如何に安全性を高めていくかが課題となっており、行政と国民がともにリスク概念の理解と実践に努めていく必要があると考えられる。そして、環境リスクが示される際には、そのリスクの評価方法とともにリスク評価自体が不確実性を伴ったプロセスであることが併せて示されることが重要である。
また、人間の認知能力は数学的な確率論と合わない場合も多いとされる。社会心理学的研究によれば、人のリスク認知の仕方は、恐ろしさ、未知性、関与者数(被害の大きさ)などの要素に依るとされ、恐ろしさ(dreadrisk)と未知性(unknown risk)を軸に様々なリスクを平面上に表してみると、原子力発電所の事故のようなこれらの要素の高いものの方が喫煙のようなものよりもリスクが高いと認知される傾向があるとされる(第3-2-11図)。また、利益が大きいほどリスクが小さい(リスクの大きいものほど利益が小さい)と認知される傾向があると言われる。このようなリスク認知の仕方が非合理的なものとして一方的に排除されるようではリスク・コミュニケーションは成功しない。
環境リスクに関する情報を十分に伝達するためには、情報提供者側からの一方的な情報提供だけでは限界があり、リスク情報に関わる知的所有権等にも留意しつつ、リスク評価・管理の経過を追って順次情報が提供され、かつ受け手側からの情報がフィードバックされるような双方向性を持った仕組みとしていくことが重要であろう。その際、科学的なリスク評価が妨げられないようにしなければならないが、リスク・コミュニケーションは相手を説得するためのプロセスではなく、情報の提供者と受け手がお互いをパートナーとして共に考え結論を導くためのプロセスととらえられる必要がある。リスク・コミュニケーションがうまくいかないと、リスク評価など他のすべてのプロセスに対する信頼性が損なわれる可能性がある。
(4) 化学物質等に係る環境リスク対策の新たな流れ
以下に見る化学物質等に係る新たな取組は、環境リスクの低減、あるいは環境リスクの考え方に基づく環境政策を推進する基礎となるものとして注目されるものである。
ア PRTR(環境汚染物質排出・移動登録制度)
化学物質等に係る総合的な環境リスク対策を進めるには、いわゆる規制物質を含む多数の化学物質の排出や移動の動向が定期的に把握されていることが基礎となる。現在、米国、カナダ及び欧州の数カ国で導入されているPRTRは、化学物質の工場・事業場からの排出量、廃棄物としての移動量を行政に登録させる制度であり、事業者の自主的な排出量の抑制努力を促すとともに、行政における適切な政策立案に活用されるなど、大きな成果を上げている(第3-2-6表)。
現在、PRTRを導入している各国の制度は、政策立案のための情報収集という点で共通性を有するが、それ以外の目的において2つに大別される。一つは、住民への情報公開及び企業の自主的な取組の促進に主眼を置いた米国型の制度で、もう一つは排出規制に主眼を置いた欧州型の制度である。両タイプの差異で特徴的なのが届け出されたデータの扱いで、米国型では各事業者から届け出された施設毎のデータがそのまま公表されるのに対して、欧州型ではデータは集計等の処理を経て公表されるため、個々の施設毎のデータは基本的に公表されない。
化学物質の排出・移動に関する情報は、化学物質の適正管理の重要な基礎資料であることから、アジェンダ21では第19章でPRTRの意義を確認するとともに各国政府にその導入を推奨している。また、OECDでは国連化学物質安全国際計画(IPCS)の要請を受け、1994年(平成6年)1月以来、5回にわたり、各国政府、産業界、NGOの参加の下にワークショップを開催し、各国がPRTRを導入するに当たってのガイダンス文書をとりまとめた。そして、1996年(8年)2月のOECD環境大臣会合では同ガイダンスを踏まえ、加盟各国に対してPRTRの導入に関する勧告がなされている。
イ 地方公共団体の取組
化学物質に関する国際的、国レベルの取組が進む中で、各地の地方公共団体においても、国が規制対象としていない化学物質を含めて化学物質管理指針を整備する動きが見られる(第3-2-7表)。その背景には、有害化学物質による地下水の汚染、先端技術産業の進出、ゴルフ場農薬による周辺環境の汚染等の環境汚染問題が直接のきっかけになっているものが多いが、先端技術産業の健全な育成、誘致を図るための環境汚染の未然防止、化学物質の総合的な排出抑制を目的とするものも見られる。
化学物質管理指針では、地域における化学物質の総合的な環境安全性の確保が目指され、事業者による自主管理の徹底を基本として、事業者がとるべき対策や行政の役割等が示されている。これらの指針の多くは、行政区域内で使用頻度が高く、人の健康や環境への影響等が懸念される未規制物質を含む化学物質を対象とし、従来型の排出段階における規制に加え、製造、使用、保管、廃棄、輸送等の各段階を含めた化学物質管理に係る組織体制や管理規定類の整備、化学物質管理計画等の策定、緊急時対策、化学物質に関する情報整備、排出抑制対策等の多岐にわたる包括的な対策の自主的な実施を行政区域内の事業者に要請する内容となっている。また、指針では、事業者による自主的取組の実効性を確保するため、自主管理マニュアルの概要等、行政に対して各種の報告を求めており、大阪府では化学物質等の使用量等を定期的に報告することとされている。
このような事業者の取組を支援するため、地方公共団体による情報提供も進められている。例えば、神奈川県では、化学物質の環境面・安全面に関する情報を「神奈川県化学物質安全情報提供システム」(オンラインでのアクセスが可能なデータベース)として提供している。
ウ 事業者による取組
上述のような国際的、国内的な政策の動きに応じ、事業者においても、化学工業界を中心として自主的な取組がはじまっている。これは、化学物質を扱うそれぞれの企業が化学製品の開発から製造、使用、廃棄に至るすべての過程で、環境保全と安全を確保することを公約し、安全・健康・環境面の対策を継続的に改善していこうとする活動であり、「レスポンシブル・ケア」と呼ばれる。
レスポンシブル・ケアは1984年(昭和59年)にカナダ化学品生産者協会により提唱され、その後、米国、欧州、我が国の化学工業界とともに1990年(平成2年)に設立された国際化学工業協議会(ICCA)によって国際的な連携を持った取組として推進されている。1995年(平成7年)10月にICCAは、「リスクに基づく政策決定の原則」を公表し、政府、産業界及びその他関係者の協力、社会、経済、環境の3要素すべてを考慮した適正な判断に基づくリスク対策の優先順位付け、科学的なリスク評価、未然防止原則に基づく費用効果的なリスク対策や公共政策の実施における一般市民の参加の重要性を産業界として確認している。我が国においても、このような国際的な動きと歩調を合わせ、1990年(平成2年)に日本化学工業協会が環境・安全に関する基本方針を策定するとともに、1995年(平成7年)4月には日本レスポンシブル・ケア協議会が設立された。今後、本格化すると見られる環境管理・監査の流れも踏まえ、行政や国民との連携の中でレスポンシブル・ケアが実効性のあるものとして発展することが求められる。
化学物質による環境リスクを効果的に低減させていくためには、上記のような国、地方公共団体、事業者が役割を分担しながらパートナーシップの下に対策を進めていくことが重要である。
その一例として、米国環境保護庁(EPA)が1991年(平成3年)から1995年(7年)にかけて実施した「33/50計画」という有害化学物質削減のための計画があり、連邦政府、州、事業者の協力の下で大きな成果を収めた。同計画は優先度の高いベンゼンなど17物質の排出と敷地外への移動を1988年(昭和63年)を基準年として1992年(平成4年)までに33%、1995年(7年)までに50%削減することを目標とし、EPAの要請の下、事業者が自主的に計画に参加し、削減量を公約することにより、削減を図る仕組みとなっている。米国のPRTRである有害物質放出目録(TRI)が同計画の基礎となっており、EPAでは、定期的に計画の進捗状況を公表するとともに大きな削減を行った事業者については個別に報告書を作成・公表することにより、そのような事業者の取組を奨励している。最終的に約1,300の企業が参加し、33%削減の中間目標は1991年(3年)に達成され、50%削減の目標も1994年(6年)に1年前倒しで達成されたと評価されている(第3-2-12図)。計画実施以前から有害化学物質の排出量は減少しているが、計画の対象物質と対象外物質の削減率を比べると、計画実施前には対象物質の削減率は対象外物質に比べ低かったのが、実施後は逆に対象物質の削減率が大幅に高まり、計画の有効性が示されている。
エ 未規制物質の総合的な環境リスク対策
化学物質全体の環境リスクの低減を図るためには、未規制物質を含めた総合的なリスク管理が重要である。
そのような中で平成8年1月に中央環境審議会から出された「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」(中間答申)は、大気環境保全の分野に限ったものではあるが、環境リスクの考え方を明示的に取り入れたものとして注目される。中間答申では、「有害大気汚染物質は、種類が多く、性状が多様であること、低濃度ではあっても長期間にわたる曝露による発がん性等の健康影響が懸念されること、(中略)発生源及び排出形態が多様であること等、従来の大気汚染防止法の規制対象物質とは異なる態様を有する」として有害大気汚染物質の特徴を確認した上で、健康リスクの程度に応じた対策を構築する必要があるとし、有害大気汚染物質を健康リスクの程度に応じて3種類に分類し、各分類ごとに排出抑制のための対策のあり方を示している。例えば、「我が国において環境目標値(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい大気環境濃度で示された目標値)を設定した場合、現に環境目標値を越えているか、又は越えるおそれがある等、健康リスクが高く、その低減を着実に図るべき物質群」とされる最も健康リスクの高い物質群については、国民の健康を守る観点から、健康リスクの早急かつ確実な低減を図るため、行政及び事業者が共通の枠組みの中で協力して排出抑制の取組を進めることが求められるとしている。また、環境目標値については、定量的な評価結果に基づき、閾値がある物質については最大無毒性量に基づいて定めることが適切であり、また、閾値がない物質については曝露量から予測される健康リスクが十分低い場合には実質的に安全と見なすことができるという考え方に基づいてリスクレベルを設定し、そのレベルに相当する環境目標値を定めることが適切であるとし、従来の環境基準設定物質とは異なる性質を有する物質であることに留意しつつ、環境基本法に基づく環境基準とすることを含め、その設定を検討する必要があるとしている。
この答申の実現に向けて、本年3月に有害大気汚染物質対策を含む「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出された。
オ 生態系に関する環境リスク対策
生態系は生命を恒久的に保存するシステムであり、生物と環境の複雑な相互作用によって系全体の安定性を保っている。生態系の中では人類もその系を構成する一要素に過ぎず、系全体が保全されてはじめて人類も存続が可能なことについては第2章第1節で見た。化学物質による生態系への影響は、直接、人への健康影響として現れないため見過ごされがちであるが、やがては人類を含む生物全体の存立基盤を脅かすものとして看過できないものである。例えば、DDT、PCBなどの高濃度の生物学的濃縮が起こる物質は、食物連鎖を通じ魚や更に高次な生物に有害性を発現させ、先進国では1970年代早期に規制策がとられたが、難分解性のため微量ながら北極、南極に至る地球の広い範囲で検出されている。また、船底塗料や漁網防汚剤として使用されていた有機スズ化合物は、水生生物への強い毒性が指摘され、先進国では使用自粛等の措置が講じられているが、港湾・漁港等の水域を中心に汚染が認められている。
このような中で化学物質による生態系への環境リスク対策が徐々に進められつつある。生態系に関する環境リスク全体を現時点で完全にとらえることは困難であるが、OECDが定めた水生生物を用いた生態影響試験ガイドラインが欧米を中心に広く利用されている。同ガイドラインは、第3-2-8表に掲げる10個の試験法を定め、そのうち藻類(201)、ミジンコ(202)、魚類(203)を用いた試験を市場に出される前の最小安全性評価項目(MPD)として定め、初期段階のスクリーニングの目的に使用している。さらに、OECDでは土壌微生物、ミツバチ・クモ等の有益な節足動物、鳥などを用いた多様な短期・長期試験法を検討している。EUでは、新規化学物質の生産量に応じて生態影響試験が要求されており、OECDガイドラインのMPD3試験及び微生物に対する試験が指定され、さらに各種の追加試験を設けている。
一方、我が国においては、農薬取締法に基づき水産動植物に対する被害防止の観点からコイ、ミジンコに対する急性毒性の評価を農薬の登録時に行っているほか、環境庁においてOECDガイドラインのMPD3試験などに基づき化学物質の系統的な生態影響試験とその結果を用いたリスク評価を開始している。しかしながら、環境基準の設定や化審法に基づく化学物質の審査には生態系への影響の観点が組み込まれておらず、法体系の整備を含めて体系的な化学物質の生態影響対策を進めることが課題となっている。
また、生態系に対する環境リスクには、化学物質以外にも土地利用の転換や開発に依るものが大きいことから、これらを総合的に評価し管理していくことが将来的な検討課題として重要であろう。