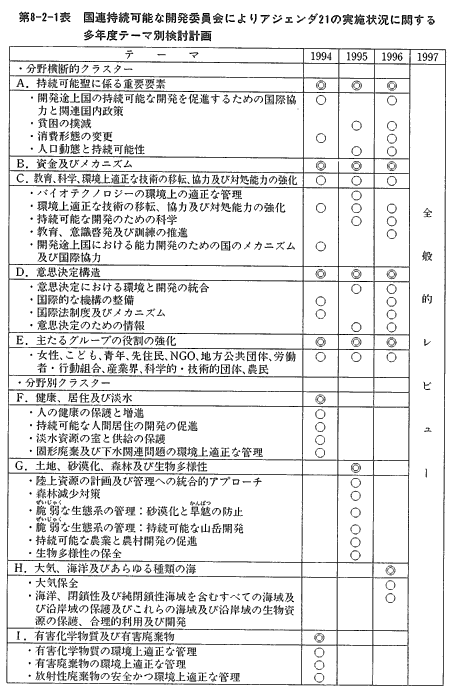
1 地球サミットのフォローアップ
(1) 国際的な取組
ア 持続可能な開発委員会(CSD)
1992年(平成4年)の地球サミットにおいて採択されたアジェンダ21において、「ハイレベルな『持続可能な開発委員会』を国連憲章第68条に従い、設立すべきである」とされた。これを受け、同年の第47回国連総会において、「地球サミットのフォローアップに関する機構整備」の中で設立を要求することが決議され、1993年(平成5年)2月国連経済社会理事会の下に「持続可能な開発委員会」(CSD)が設立された。
CSDは我が国を含めた国連加盟国53か国から成り、その主要目的は、?アジェンダ21及び環境と開発の統合に関する国連の活動の実施状況の監視、?各国がアジェンダ21を実施するために着手した活動等についてまとめたレポート等の検討、?アジェンダ21に盛り込まれた技術移転や資金問題に関するコミットメント(約束)の実施の進捗状況のレヴューと監視、?リオ宣言及び森林原則声明に盛り込まれた諸原則の推進、?アジェンダ21の実施に関する適切な勧告の経済社会理事会を通じた国連総会への提出、等である。
第1回会合は、1993年(平成5年)6月に開催され、1997年(平成9年)に開催が予定されている国連環境と開発特別総会に向けて、アジェンダ21の実施状況について総括的な評価を行うとの「多年度テーマ別検討計画」が合意された(第8-2-1表)。
第2回会合は1994年(平成6年)5月、メンバー国53か国(内約40か国より閣僚レベル)及び非メンバー国他の多数の参加を得て開催された。
会合においては、第1回会合において決定された「多年度テーマ別検討計画」に従い、分野横断的なテーマとして、貿易と環境、資金、技術移転、持続可能な消費パターン、分野別のテーマとして、健康、人間居住、淡水、有害化学物質、有害廃棄物等についての検討が行われ、最終的に14の決定及びハイレベル会合の「議長総括」を採択した。
イ 持続可能な開発に関する高級諮問評議会
持続可能な開発に関する高級諮問評議会の設置については、1992年(平成4年)の地球サミットで採択されたアジェンダ21の第38章(国際的な機構の整備)で勧告されたものであり、科学分野も含め、環境と開発に造詣(ぞうけい)の深い有識者が個人の資格で参加するものであるが、政府間の機構であるCSD等と並び、地球サミットのフォローアップにおいて、重要な役割を担うことが期待されている。
これを受け、1993年(平成5年)7月、ブトロス・ブトロス・ガーリ国連事務総長より高級諮問評議会の設置が発表され、9月には第1回会合が、1994年(平成6年)10月には第3回会合が開催された。
(2) アジア・太平洋地域における取組
ア アジア・太平洋環境会議(エコ・アジア'94)
環境庁は、1994年(平成6年)6月21日、22日に埼玉県大宮市において、アジア・太平洋地域諸国の環境担当大臣等の参加のもと「エコ・アジア'94」を開催した。本会議は1991年(平成3年)にアジア・太平洋地域から地球サミットに対するインプットを議論するために開催した「エコ・アジア'91」及び1993年(平成5年)に地球サミットにおける合意事項の実施に向けた地域協力の在り方を明らかにするため開催した「エコ・アジア'93」に引き続き開催したものであり、地球サミット後2年間における世界の状況を踏まえ、持続可能な開発を実現していくための、アジア・太平洋地域の役割及び同地域における新たな協力の在り方、エコ・アジア'93で実施が合意された「長期展望プロジェクト」の進捗状況と推進方法等について議論し、地球環境保全に関する取組の新たな展開に貢献することを目的としたものである。
会議には、アジア・太平洋地域から5か国の大臣を含む17か国の政府高官及び10国際機関の代表者を始めとする多数の参加があった。会議においては、持続可能な開発を実現するための具体的な行動を始める必要性、地方公共団体の役割の重要性等が認識された。さらに、エコ・アジアを継続すること、1995年(平成7年)は高級事務レベルの参加による会合とすること等が合意された。
イ 環日本海環境協力会議
北東アジア地域の環境問題に関する環境行政レベルでの情報交換及び政策対話を行い、アジェンダ21で強調されている地域協力の促進を図るため、1992年より毎年、「環日本海環境協力会議」が開催されている。
1993年(平成5年)9月ソウルにて開催された第2回会議の成果を受け、環境庁は、1994年(平成6年)9月、兵庫県との共催により第3回会議を開催した。会議では、CSDのフォローアップ、持続可能な都市、生物多様性の保全等のテーマについて活発な議論がなされ、各分野における協力の強化等について合意が得られた。
(3) 国内における取組
ア 地球サミットでの合意を受けた条約への対応
我が国は、地球サミットにおいて気候変動枠組条約及び生物多様性条約に署名したが、1993年(平成5年)5月、両条約を受諾し、締約国となり、条約の責務に対応するための国内における取組を推進している。
また、地球サミットによって条約交渉が開始された砂漠化防止条約は、1994年(平成6年)6月に採択され、我が国は同年10月、パリで開催された砂漠化防止条約署名式典において同条約への署名を行った。
イ 「アジェンダ21」行動計画の実施
アジェンダ21の国別行動計画については、地球サミットにおいて採択されたアジェンダ21においてその準備及び検討が示唆されており、1992年(平成4年)のミュンヘン・サミット及び1993年(平成5年)の東京サミットにおいて、1993年末までに策定し、公表することとされた。
これを受け、政府は平成5年12月に開催された地球環境保全に関する関係閣僚会議において「『アジェンダ21』行動計画」を決定し、CSD事務局に提出した。
この「『アジェンダ21』行動計画」は、「アジェンダ21」の章立てに応じたプログラム分野(第8-2-2表)ごとに我が国が今後実施しようとする具体的な事項を行動計画としてとりまとめたものである。本行動計画では以下の項目について重点的に実施していくこととしており、これに則り、持続可能な開発の達成に向けた種々の取組がなされている。
(ア) 地球環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築及び国民のライフ・スタイル自体を環境配慮型に変えるための普及、啓発等への努力
(イ) 地球環境保全に関する実効的な国際的枠組みづくりへの参加、貢献
(ウ) 地球環境保全に向け、地球環境ファシリティ(GEF)を始めとする資金供与の制度の整備のための国際的取組に積極的に参画
(エ) 環境上適正な技術移転の促進等の実施を通じた開発途上国の環境問題への対処能力の向上への貢献
(オ) 地球環境保全に関する観測・監視と調査研究の国際的連携の確保及びその実施
(カ) 中央政府、地方公共団体、企業、非政府組織等広範な社会構成員の効果的な連携の強化
ウ ローカルアジェンダ21
アジェンダ21においては、その実施主体として地方公共団体の役割を期待しており、地方公共団体の取組を効果的に進めるため、ローカルアジェンダ21を策定することを求めている。環境庁は、ローカルアジェンダ21の策定のための指針を作成するために「ローカルアジェンダ21策定指針検討会」を開催し、検討を進めてきたが、平成6年6月に「ローカルアジェンダ21策定に当たっての考え方」として指針を取りまとめ、公表した。