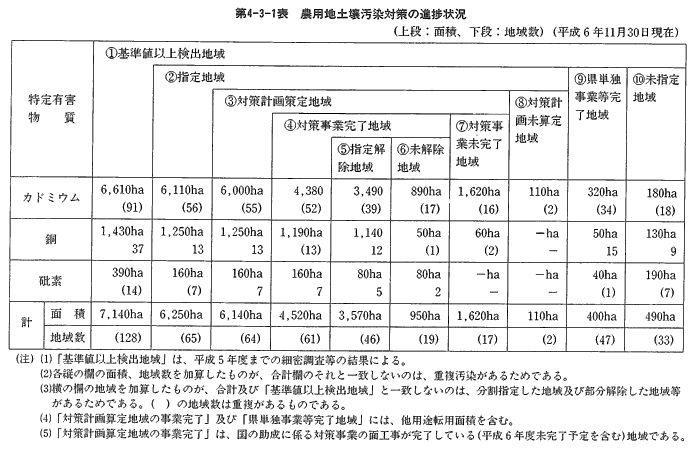
2 土壤汚染対策
(1) 環境基準の設定
環境基本法第16条に基づく土壤の汚染に係る環境基準は、原則として農用地の土壤を含めたすべての土壤について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で望ましい基準を定めたものであり、土壤の汚染状態の有無を判断する基準として、また、汚染土壤に係る改善対策を講ずる際の目標となる基準として活用されることを目指している。
土壤環境基準は平成3年8月に、カドミウム等10項目について設定し、その後6年2月に有機塩素系化合物15項目を追加し、現在合計25項目について設定している。
(2) 農用地土壤汚染防止対策
基準値以上検出地域のうち平成6年11月30日現在までに6,250ha(65地域)が対策地域として指定され、そのうち6,140ha(64地域)について対策計画が策定された。排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業等(国庫補助)により4,520haで対策工事が完了し、県単独等の事業による完了面積400haと合わせて4,920haで対策事業が完了(平成6年度末完了予定を含む。)している。基準値以上検出地域面積に対する対策事業の進捗率は68.9%である(第4-3-1表)。
なお、カドミウム汚染地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、汚染米の発生防止のための措置が講じられている。
このほか、重金属類による農用地の土壤汚染の全般的な状況を把握するため、定点において土壤環境基礎調査が実施されている。
また、農用地の土壤が汚染されている地域等において、客土、土壤改良等の効果について現地改善対策試験が実施されている。
さらに、近年、下水汚泥等を原料とする再生有機質資材の農用地における利用が増加する傾向にあるため、農用地における土壤中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準に基づき、土壤汚染の未然防止に努めている。
(3) 市街地土壤汚染対策
市街地の土壤については、環境基準の達成維持に向け、土壤の汚染が明らか又はそのおそれがある場合及び土地改変等の機会を捉えて環境基準の適合状況の調査を実施し、汚染土壤の存在が明らかになった場合には可及的速やかに環境基準を達成するために必要な措置が講じられるよう、事業者等の自主的な取組を促進することとしている。このため、平成6年11月には、土壤・地下水汚染の調査・対策を的確に行うための手順・手法等をとりまとめた「重金属等に係る土壤汚染調査・対策指針」及び「有機塩素系化合物等に係る土壤・地下水汚染調査・対策暫定指針」を都道府県に示した。また、地方公共団体自らが実施する環境基準の適合状況の調査のための経費を助成するとともに、民間事業者による市街地土壤汚染対策の円滑な実施に資するため、対策に必要な経費について、環境事業団が融資事業を行っている。
さらに、重金属、トリクロロエチレン等により汚染された土壤の新しい浄化技術の確立を図るための調査、土壤環境基準未設定物質の分析法等の知見を集積するための調査等を行った。
(4) 鉱害防止対策
金属鉱業等においては、「鉱山保安法」に基づき鉱害防止のための措置を講じている。また、金属鉱業等に係る鉱山の施設には、操業停止後も引き続き鉱害を発生するおそれがあるため、「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく鉱害防止事業の計画的な実施及び確実かつ永続的な坑廃水処理の実施体制の整備に努めてきているところである。平成5年度には、同法に基づく今後10年間の鉱害防止事業に関する基本方針を改正し(平成5年4月1日施行)、計画的な鉱害防止事業を図るとともに、以下の措置を講じた。
ア 休廃止鉱山に係る鉱害防止のため、休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金制度により、当該防止工事の促進を図ってきている。
平成5年度には、義務者不存在鉱山の鉱害防止工事(堆積場の覆土・植栽等)32鉱山及び廃水処理24鉱山、また、義務者存在鉱山の坑廃水処理47鉱山についてそれぞれ助成した。
イ 金属鉱業事業団では、使用済特定施設の鉱害防止事業に必要な資金及び土壤改良事業に係る事業者負担金に対する融資・債務保証、鉱害防止積立金及び鉱害防止事業基金の管理・運用、鉱害防止技術の開発のための調査研究、地方公共団体の実施する鉱害防止事業に対する調査指導及び設計等の指導支援の業務を実施している。