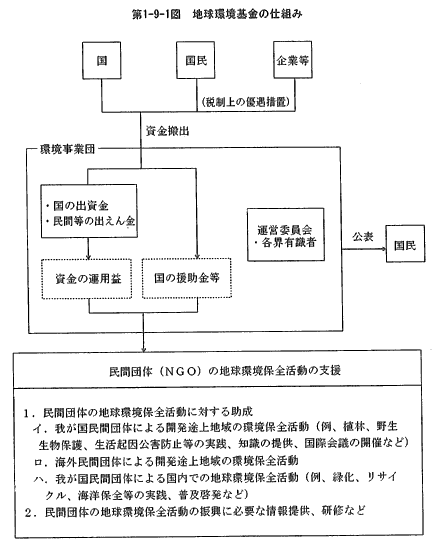
2 環境保全活動の推進
(1) 環境保全活動一般
現下の環境問題を解決していくためには、日常生活や事業活動一般に起因する環境への負荷を低減していくための努力が、国民、企業など様々な主体によって自主的かつ積極的に行われるようになることが重要であり、環境基本計画においても、自主的な環境管理の促進、望ましい活動の推奨等を行っていくこととしている。
近年においては、環境問題に対する関心の高まりとともに、環境保全活動に参加したいと考える国民が増加しており、企業においても環境保全型の活動に対する関心が高まっている。しかしながら、どのような活動が「環境にやさしい」のか、どのようにしたら環境保全活動に参加できるのか等、実行段階で様々な混乱や問題点が生じており、適切な情報提供を行うとともに社会的な条件整備を図る等、国民、事業者等による環境保全活動を一層促進して行くための施策を充実していくことが必要となっている。
国民による環境保全活動の促進については、環境庁では、平成6年度、埼玉県において「環境保全活動研究会」を実施するとともに、地域環境保全基金等による地方公共団体の環境保全活動促進施策を支援するため、関連する情報の収集、提供等を行った。さらに、環境に配慮した消費行動を促進するため、エコマーク制度の指導育成を行い、平成6年度には、エコマーク制度をはじめとする環境保全型製品について、「環境保全型製品の新たな展開に関する検討会」を開催し、ライフサイクルアセスメントの考え方の導入、環境政策サイドからの類型設定等の検討に着手した。
また、事業組織による環境保全活動の促進については、環境庁において、平成5年2月に公表した「環境にやさしい企業行動指針」の普及に努めるとともに、平成3年度以降、毎年企業における環境保全活動の現状を調査し、関連する情報の提供を幅広く行った。
また、製品等による環境への負荷を生産−消費・使用−廃棄という一連のプロセスにおいて定量的、科学的、客観的に把握・評価する手法(ライフサイクルアセスメント:LCA)についても、関係省庁において国際標準化機構(ISO)における標準化のための検討状況を踏まえ、その技術的側面についての調査を行っている。
通商産業省では、平成5年4月(一部平成5年8月)に施行された「エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律」に基づく措置及び平成5年6月に施行された「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく各種支援措置等を講じている。また、同省は、4年10月に「環境に関するボランタリープラン」の策定を要請したが、6年12月に中間取りまとめ調査を行ったところ、6年10月現在、362社の企業が策定していることがわかった。今後とも増加することが期待される。
国際的には、国際貿易の円滑化のため国際規格化を推進する非政府間機関である国際標準化機構(ISO)によって環境管理に関する国際規格化の作業が進められており、我が国においても、平成5年6月ISOに加盟している日本工業標準調査会(JISC)のもとに、環境管理規格審議委員会(学識経験者、産業界、消費者がメンバー)を設置して検討を行い、この作業に積極的に参加しているところである。
(2) 民間団体による地球環境保全のための活動の推進
近年、欧米諸国を中心として、民間団体による地球環境保全のため様々な活動が活発となっている。我が国においても、国内の環境保全にとどまらず、開発途上国を中心とした海外においても、植林や野生生物の保護などの環境保全活動を展開する民間団体が増えており、これらの活動に対する国民各界の関心も高まってきた。地球環境保全のためには、こうした草の根の環境協力や幅広い国民の参加による足元からの行動が極めて重要であり、特に我が国においては、自らの経済社会活動の見直し、開発途上国への支援強化の両面で民間団体(いわゆるNGO)の活動の強化が必要であることから、これらの活動を支援することが喫緊の課題となっている。
平成6年12月に閣議決定された環境基本計画においては、各主体の自主的積極的行動のための主要な施策として、「環境保全の具体的行動の促進」を掲げ、「民間団体の活動の支援」を行っていくこととしている。
環境事業団は、平成5年5月に政府の出資及び民間の出えんにより開設された「地球環境基金」により、内外の民間団体が開発途上地域において行う植林、野生生物の保護等の活動や我が国の民間団体が国内で行う緑化、リサイクル等の活動に対する助成及びこれらの活動の振興に必要な調査研究、情報提供等を実施した(第1-9-1図)。
このうち、助成事業については、平成6年度において、各方面の民間団体から寄せられた合計363件の助成要望に対し、157件、総額約6.3億円の助成決定が行われた(第1-9-1表)。
なお、外務省のNGO事業補助金及び草の根(小規模)無償資金協力、郵政省の寄附金付郵便葉書等による寄附金の配付及び国際ボランティア貯金制度等においても、対象の一部として民間団体の環境保全活動が取り上げられ、支援が行われている。
(3) リサイクル活動の推進
「再生資源の利用の促進に関する法律」及び廃棄物の再生を明記した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正法が整備されたことを受けて、様々な主体によるリサイクル活動の一層の促進を図ることが必要となっている。
このため、毎年10月の「リサイクル推進月間」において、リサイクル関係省庁である経済企画庁、環境庁、大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省及び建設省は、再生資源の利用の促進に関する国民の理解と協力を得るため、広範な普及啓発活動を実施することとしており、平成6年度においても、各種シンポジウムの開催、リサイクル推進功労者の表彰等を行った。
環境庁では、リサイクルに関する各種の調査研究を進めるとともに、リサイクルに係る普及啓発資料を作成・配布した。
経済企画庁では、各都道府県に設置されている省資源国民運動地方推進会議を通じ、リサイクル活動団体への支援を行った。
厚生省では、地方公共団体における体制整備を推進するため、ごみの資源化ルートの構築や組織づくり等に関する事業に対して補助を行うとともに、平成5年度より5月30日から6月5日までの1週間を新たに「ごみ減量化推進週間」と定める等、廃棄物の減量化や再生利用を促進するための各種啓発活動を行った。
また、リサイクルの一層の促進を図るため、関係省庁において、リサイクルに関連する経済的手法のあり方についての検討がそれぞれ進められた。環境庁では、平成4年度から引き続き当該手法の検討を進め、平成6年4月には「リサイクルのための経済的手法検討会」報告書を公表した。
(4) 空き缶の散乱防止
缶飲料の生産量は急速に増大し、昭和56年には100億缶程度であったものが、平成5年には318億缶を超える状況にある。これら缶飲料の空き缶の一部が道路、海岸・河川等に散乱し環境美化の観点から問題となっている。環境庁が平成5年度に全国の約700市区町村について実施した調査の結果では、散乱状況に改善は見られず、おおむね横ばいで推移していたここ数年に比し、かなり悪化した状況にある。
空き缶散乱防止対策としては、それぞれの立場から様々な取組が行われている。地方公共団体においては、それぞれの地域の実情に応じた各種の対策を講じており、空き缶散乱防止に関する条例や要綱の制定、投げ捨て防止のキャンペーン、清掃の強化等のほか、一部の地方公共団体等においては、空き缶回収機を活用して、一定の枚数を集めると図書券等に交換できる補助券を発行する方式や預り金方式などの導入により空き缶回収等を行っている例もみられる。
国においては、関係11省庁から成る「空き缶問題連絡協議会」における申合せに基づき、普及啓蒙活動の充実を図っているほか、環境庁及び厚生省は「環境美化行動の日」の設定を地方公共団体に呼びかけ、空き缶散乱防止を含め、広く環境美化のための国民各層の積極的行動の推進を図っている。