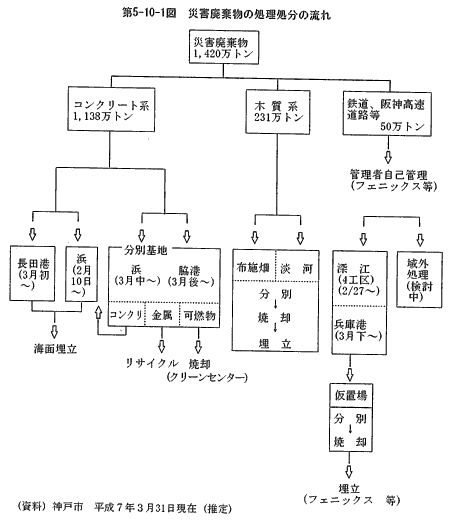
5 阪神・淡路大震災による環境への影響
(1) 震災による被害
平成7年1月17日、兵庫県南部を中心に強い地震がおき、戦後最大の痛ましい人的被害をもたらすとともに、家屋の崩壊、高速道路の倒壊、電気、水道等のいわゆるライフラインの断絶など日常生活に計り知れないほどの影響を与えた。また、地震による被害に伴って有害物質を原因とした大気汚染や水質汚濁による二次災害が懸念された。
被災各地においては、建物の倒壊にともない1,800万トンを超える膨大な量のガレキ等が発生している。ガレキ等の除去・倒壊家屋の処理については、自治体の回収・処理能力を超えたため一時各地で野焼きが行われ、2月には住民から煙による眼やのどの痛みを訴える苦情が報告された。国の阪神・淡路復興委員会ではガレキ等の除去・倒壊家屋の処理を復興のための基礎的事業と位置付け、国・県・市町の協力の促進、復興のための様々な事業を促進するための計画的面的(街区)な除去、収集された鉄・アルミニウム・コンクリート等のリサイクルなどについて2月に提言を行い、兵庫県をはじめとするその他の市町において、この提言を取り入れた処理計画が策定されている(第5-10-1図)。
工場・事業場においては、地震による公害防止施設などの損壊に伴って、アンモニアや塩酸の流出、港から合成樹脂等の原料の入ったドラム缶の落下が報告されている。なお、有害物質の漏出が懸念されたが、平成7年3月現在では被害は確認されていない。
ビルやマンションの崩壊・解体現場ではアスベスト(石綿)の飛散が懸念されている。アスベストは繊維状に結晶した鉱石で、絶縁、断熱性に優れているため断熱材、自動車部品などに使われている。ところが、粉じんとなって大気中に浮遊したアスベストは、吸入することにより発がん等の健康影響が懸念されているため、「大気汚染防止法」及びその他の法律において、工場からの排出規制、専門の作業員による除去作業、除去後の厳重な管理などが定められている。被災地では、復旧のためのビルなどの解体・撤去作業が進行中であり、これに伴うアスベストの飛散防止のため、石綿対策関係省庁連絡会議においてアスベスト飛散防止対策を取りまとめ、関係省庁が関係自治体と連携協力してその徹底に努めている。
また、地震による地盤の液状化現象によって地下から吹き上げられた砂の微粒子や、解体作業に伴うコンクリートなどの粉じんが大気中に多く浮遊することが予想されており、散水等の対策を行うよう指導している。
なお、倒壊建物中のフロン使用機器からは、残留している特定フロンの大気中への放出が懸念されたため、県・市町・事業者等が協力して可能な範囲でこれらのフロンの回収を進めている。
神戸市の下水処理場のうち1ヶ所では、地震によって下水処理施設が大きな被害を受け、汚水の高級処理が不可能となり下水処理に支障を来した。このため、十分な処理の行われていない汚水が海にそのまま流れ込むことになり、海洋汚染、特に夏場の赤潮の発生が懸念されたため、2月に運河に仮沈殿池を設置し、沈殿・滅菌のうえ放流するという応急措置を行った。
被災地のうち、神戸市、尼崎市等には、公害健康被害の補償等に関する法律の旧第1種地域があるが、同法に基づく認定患者の保護を図るため、公害医療手帳を紛失した場合でも通常どおり医療を受けられるようにする措置、被災した認定患者からの相談に応ずる窓口の設置、認定患者の所在確認や被災により期限内に認定更新申請ができなかった患者を救済するための特例措置を設ける同法の改正を行ったほか、保健婦による患者への巡回相談を3月より始めた。さらに、公害健康被害補償予防協会は、防じん及び風邪の予防に役立ち、気管支ぜん息等の予防に資するとの観点から、健康被害予防事業の一環として被災地に約30万個のマスクを送付した。
(2) モニタリング緊急調査
被災地におけるこのような環境悪化が懸念される状況を踏まえ、環境庁は二次災害を未然に防止する観点から、平成7年2月及び3月の2回にわたり大気環境及び水質のモニタリング調査を行った。
2月に行った大気環境モニタリング調査では、神戸市、尼崎市、北淡町ほか10市町50地点においてアスベスト、塩素、有機塩素化合物等20項目を対象として調査を行った。この調査結果によると、アスベストについては、測定された環境濃度は、我が国の都市地域において測定される環境濃度の変動の範囲に概ねおさまっているものの、一般的な観測値よりやや高目の値も出ており、飛散防止対策が講じられていないビル解体撤去作業現場の近辺では周辺よりも高い濃度が検出された(第5-10-1表)。また、アスベスト以外の物質については、測定された環境濃度は概ね我が国の都市地域の環境濃度の変動の範囲に入っており、有害物質の漏出等によって直ちに健康影響が問題になるような二次汚染は現在のところ生じていない(第5-10-2表)。
同じく2月の水質モニタリング調査では、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の4市の河川・海域37地点、井戸29地点において健康項目23項目、pH、BOD等の生活環境項目6項目を対象に調査を行ったが、有害物質の漏出等による著しい水質汚濁は認められなかった。
(3) 今後の対応
阪神・淡路大震災による被災地域は、従来から公害が著しい地域であり、こうした状況を踏まえ様々な公害対策が熱心に進められてきた地域でもある。今回の震災においても、一部の地域においては、環境保全のための対策の一環として設けられていた公園などの緑地が延焼を防いだとの報告がなされている。今後、環境面での良好な街づくりは、地震等の災害に強い都市づくりと、緑地や公園の整備、低層密集市街地や住工混在地区の改善等相通じる面が多いとの認識の下で、復興段階における環境配慮を推進しつつ、災害に強く、環境にやさしいまちづくりをしていくことが求められる。