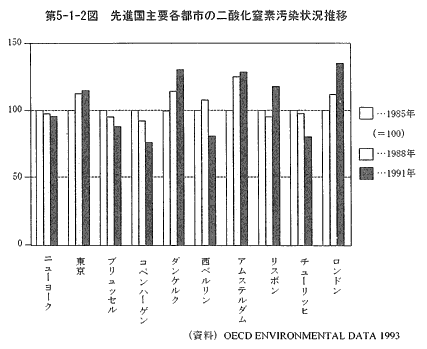
1 大気環境の現状
我が国の大気汚染状況については、二酸化硫黄、一酸化炭素は、近年良好な状況が続いているものの、二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、大都市地域を中心に環境基準の達成状況が低い水準で推移しており、光化学オキシダントは全国的に厳しい汚染状況にある。
(1) 窒素酸化物
一酸化窒素(NO)・二酸化窒素(NO2)などの窒素酸化物(NOx)は、主に化石燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源としては工場のボイラーなどの固定発生源や自動車などの移動発生源がある。窒素酸化物は、酸性雨や光化学大気汚染の原因物質となるばかりでなく、二酸化窒素は高濃度で呼吸器に好ましくない影響を与えることが知られている。
我が国では、窒素酸化物のうち二酸化窒素について「1時間値の1日の平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること」という環境基準(人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準)を設け、対策の目標としている。平成5年度は、一般的な大気汚染の状況を把握するために設置された一般環境大気測定局(以下「一般局」)1,419局と道路周辺における状況を把握するために沿道に設置された自動車排出ガス測定局(以下「自排局」)346局において、それぞれ二酸化窒素濃度の測定が行われた。
昭和45年以降(自排局は昭和46年以降)の継続測定局における二酸化窒素濃度の年平均値は、54年度以降減少傾向が見られたが、61年度以降増加し、平成5年度においても高い水準で推移している(第5-1-1図)。なお、近年の傾向について、第2部第2章第1節で詳述する。全国の環境基準達成状況を見ると、二酸化窒素の濃度が環境基準のゾーンの上限である0.06ppmを超えた環境基準非達成局数は、一般局で4年度では1,406局中37局(2.6%)が1,419局中63局(4.4%)、自排局336局中96局(28.6%)が346局中114局(32.9%)といずれも増加した。
大気汚染防止法によって、工場等の固定発生源についてNOxの総量規制制度が導入されている東京都特別区等地域、横浜市等地域、大阪市等地域の3地域における環境基準非達成局数は、一般局では4年度の118局中35局(29.7%)が118局中47局(39.8%)、自排局では4年度の72局中53局(73.6%)が73局中65局(89.0%)と一般局、自排局ともに増加した。また、自動車NOx法の特定地域(首都圏特定地域、大阪・兵庫圏特定地域)の環境基準非達成局数は、一般局では4年度の313局中36局(11.5%)が315局中62局(19.7%)、自排局では4年度の152局中82局(53.9%)が155局中100局(64.5%)と、いずれの局においても増加した。
このように、大都市地域を中心に環境基準の達成状況は依然低い水準で推移しており、一層強力な対策の推進が必要となっている。工場などの固定発生源に対しては、施設の種類や規模ごとの排出基準と高汚染地域における工場ごとの総量規制基準とによる規制が行われている。また、移動発生源である自動車については、自動車一台ごとの排出ガス規制の強化が進められるとともに、自動車NOx法により特定地域において、総量削減計画に基づく各種施策や窒素酸化物の排出量のより少ない車種への代替を促す車種規制などが行われている。また、低公害車の普及を促進するため各種の助成等の措置が講じられている。さらに、石油製品の輸入拡大を契機として、自動車燃料について大気保全上必要な品質の確保を図るとともに、広く国民に対して自動車の適正な使用等を求めることを内容とする「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」を第132回国会に提出したところであり、本法律の成立を受けてその適切な施行を図ることとしている。
諸外国については、1985年以降1990年代にかけて、ダンケルク(フランス)、アムステルダム、リスボン、ロンドンなどの先進国主要都市において窒素酸化物による大気汚染の状況は悪化しており、汚染防止対策は十分進んでいない(第5-1-2図)。
(2) 浮遊粒子状物質等
浮遊粒子状物質(Suspended Particulate Matter 、SPM)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉じん、エアロゾルなど)のうち粒径が10μm以下のものをいう。SPMは、微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して高濃度で呼吸器に影響を及ぼす。浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と硫黄酸化物・窒素酸化物などのガス状物質として放出されたものが大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子がある。その発生源は、工場などから排出されるばいじんやディーゼル車の排出ガスに含まれる黒煙などの人為的発生源によるものと、土壤の巻き上げなどの自然発生源によるものとがある。
我が国では、浮遊粒子状物質については「1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m
3
以下であること」という環境基準を設定し、環境基準の達成に向けて工場・事業場からのばいじん・粉じんや自動車からの黒煙の排出規制を行っている。
昭和49年以降(自排局は昭和50年以降)の継続測定局における浮遊粒子状物質濃度の年平均値は、ここ数年は横ばいとなっている(第5-1-3図)。なお、近年の傾向について、第2部第2章第1節で詳述する。環境基準の達成率は、一般局では4年度の57.6%(1,408局のうち811局)が58.3%(1,440局中839局)、自排局では4年度の33.5%(182局中61局)が40.5%(190局中77局)となっており、いずれの局においても増加したものの、依然低い水準で推移しており、特に、関東地域における達成状況が芳しくない。また、九州・中国・四国地域の環境基準達成率の低下が目立つが、これは黄砂による影響と推定される。
浮遊粒子状物質については、汚染機構の解明、汚染予測手法の開発等の調査研究を推進し、総合的施策の検討を行っている。
浮遊粒子状物質のうち、健康影響の面から特に注目されているディーゼル排気微粒子(DEP)については、ヒトに対する発ガン性や気管支喘息・花粉症との関連性が懸念されているため、現在その研究・調査が進められている。
環境庁では、従来よりDEP対策として黒煙の自動車単体規制を実施してきたが、平成5年度から黒煙に加え粒子状物質排出量全体の規制を開始しており、また、粒子状物質排出量をさらに6割以上削減することを求める平成元年12月の中央公害対策審議会答申で示された長期目標に対し、早期達成に向けて技術評価等を行っている。また、ディーゼル車から排出される粒子状物質について総合的な低減施策を検討していくこととしている。
また、第132回国会に提出した「大気汚染防止法の一部を改正する法律」の成立を受けて、大気保全上必要な自動車燃料の品質の確保のため燃料性状等に関する許容限度の設定等の必要な措置を講ずることとしている。
物の破砕や選別、堆積にともない飛散する大気中のすす・粉じんなどの粒子状物質のうち比較的粒が大きく沈降しやすい粒子は降下ばいじんと呼ばれ、平成5年度における状況については長期間継続して測定を実施している16測定点における年平均値は4.1トン/km
2
/月(4年度3.5トン/km
2
/月)となっている。
スパイクタイヤ粉じん問題は、スパイクタイヤが凍結路面において優れた操舵性・制動性や簡便性を持つことから積雪寒冷地域で急速に普及したのをきっかけとして、昭和50年代の初めから発生し、粉じんが不快感や衣服・洗濯物の汚れをもたらすだけでなく、人の健康への影響も懸念されたために大きな社会問題となった。現在では、スパイクタイヤの製造・販売は中止とされ、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」による使用禁止地域の指定も進み、スパイクタイヤに係る降下ばいじん量については著しい改善を見せている。
(3) 二酸化硫黄
二酸化硫黄(SO2)は、硫黄分を含む石油や石炭が燃焼することにより生じ、四日市ぜんそくなどの公害病の原因物質として知られているほか、酸性雨の原因物質ともなる。
我が国では、二酸化硫黄については「1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること」という環境基準を設け、平成5年度は、一般局(1,610局)及び自排局(87局)において測定を行った。
昭和40年度以降(自排局は昭和48年度以降)の継続測定局における二酸化硫黄濃度の年平均値は、42年度をピークとして全般的に減少を続けている(第5-1-4図)。なお、近年の傾向について、第2部第2章第1節で詳述する。また、環境基準の達成率は、一般局では、4年度の99.6%(6局で非達成)が99.8%(3局で非達成)、自排局では4年度の98.7%(1局で非達成)が100%(全局で達成)であった。
二酸化硫黄による大気汚染は、高度成長期の化石燃料の大量消費によって急速に悪化したため、昭和44年2月に初めて環境基準が設定され、ばい煙発生施設ごとの排出規制、燃料中の硫黄分の規制、全国24地域における工場ごとの総量規制など様々な対策が講じられた。また、企業においても、こうした規制を受け、低硫黄原油の輸入、重油の脱硫、排煙脱硫装置の設置などの積極的な対策を押し進めた。こうした結果、大気中の二酸化硫黄濃度は、長期間測定している局についてみると、42年度のピーク値0.059ppmから年々減少し、平成5年度には0.008ppmと著しい改善を見せた。
諸外国について見ると、OECD諸国では大幅に改善されているが、北京、メキシコシティー、ソウルにおいてはなお深刻な問題となっており、地球モニタリングシステムによると世界の都市の約3分の2の住民がWHOの定めた環境SO2濃度の規制値を超える都市に住んでいる(第5-1-5図)。
(4) 一酸化炭素
大気中の一酸化炭素(CO)は、燃料等の不完全燃焼によって生じるもので、主に自動車が発生源となっている。一酸化炭素は血液中のヘモグロビンと結合して酸素を運搬する機能を阻害するなど人の健康に影響を与えるほか、温室効果のあるメタンガスの寿命を長くすることが知られている。
一酸化炭素については、昭和45年2月に「1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること」という環境基準を設定するとともに、自動車の排出ガス規制を行っている。
昭和46年度以降の継続測定局における一酸化炭素濃度の年平均値は40年代より改善され、近年は低いレベルで推移している(第5-1-6図)。なお、近年の傾向について、第2部第2章第1節で詳述する。また、環境基準の達成状況は一般局・自排局ともに3年度、4年度に引き続き全局で達成している。
(5) 光化学オキシダントと非メタン炭化水素
光化学オキシダントは、工場や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び炭化水素類(HCs)を主体とする一次汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応をおこすことにより二次的に生成されるオゾンなどの強い酸化力を持った物質である。光化学オキシダントは、いわゆる光化学スモッグの原因となり、高濃度では粘膜への刺激や呼吸器への影響などが知られており、農作物など植物への影響も報告されている。また、オゾンは二酸化炭素よりもはるかに強力な温室効果を持つと言われている。
光化学オキシダントについては、昭和48年5月に「1時間値が0.06ppm以下であること」という環境基準が設定された。光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件から見てその状態が継続すると認められるときは、都道府県知事等が注意報を発令し、報道、教育機関等を通じて、住民、工場・事業場等に対して情報の周知徹底を迅速に行うとともに、ばい煙の排出量の減少または自動車の運行の自主的制限について協力を求めることとなっている。
平成6年の光化学オキシダントの注意報発令延日数は5年の71日から175日へ、光化学大気汚染によると思われる被害届出人数は5年の93人から564人へと大幅な増加となり、特に首都圏地域及び近畿圏地域に注意報の発令が集中している(第5-1-7図)。
光化学オキシダントの原因物質の一つである非メタン炭化水素については、光化学スモッグの発生を防止するための濃度の指針(午前6時〜9時の3時間平均値が0.20ppmC〜0.31ppmC)が定められている。昭和53年以降(自排局では昭和52年以降)の継続測定局での午前6時〜9時における年平均値は、一般局6局で平成4年度0.49ppmCが5年度は0.46ppmC、自排局9局で4年度0.46ppmCが5年度0.43ppmCであった。非メタン炭化水素は、自動車から排出されるほか、炭化水素類を成分とする溶剤を使用する塗装・印刷等の工場・事業所からも排出されるため、自動車に対する排出規制や排出抑制に向けた工場等への指導等が行われている。光化学オキシダントについては、このほか、汚染機構等に関する調査研究を進めるとともに、広域的な監視システム整備を進めている。
(6) その他の大気汚染物質
カドミウムや塩素など「大気汚染防止法」で有害物質として規制されている物質については、発生源の工場・事業場に対してばい煙発生施設の種類ごとに排出基準を定めて排出規制を実施している。また、その他に長期的に推移を把握していく必要のある大気汚染物質については、昭和60年度から未規制大気汚染物質モニタリング調査を実施している。平成5年度においては、平成3年度と同様、アスベスト(石綿)、水銀及び有機塩素系溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素等)について調査を行った。
平成5年度の調査結果では、アスベスト(石綿)及び水銀については、前回の調査結果と比較すると概ね低い値であった。有機塩素系溶剤については、住宅・商業地域及びバックグランド地域においては概ね低い値であったが、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの発生源の敷地境界及びその周辺においては高濃度事例が見られた。今後とも引続きモニタリングを実施するとともに、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、発生源の実態把握等に努めることが必要である。
化学物質はその用途・種類が多岐にわたり、工業用に生産されている物質だけでも現在数万種に及ぶ。環境庁では、一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベル把握を目的として、平成元年度より新たに始まった第二次総点検調査で、既存化学物質の残留状況を効率的、体系的に調査している。平成5年度の調査においては、調査対象20物質のうち6物質が検出されたが、検出濃度レベルは低く、直ちに問題を示唆するものではないと考えられる。
有機塩素系溶剤等の有害大気汚染物質については、健康影響の懸念から注目されており、金属脱脂洗浄剤・溶剤等を用途とするトリクロロエチレン及びドライクリーニング溶剤・金属脱脂洗浄剤・フロンの原料等を用途とするテトラクロロエチレンについては、我が国の大気において広い範囲で検出されているほか、環境庁が行った調査によると、その発生源の周辺では局所的ではあるものの比較的高い濃度が検出される事例があることが判明している。環境庁では、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについて人の健康を保護する上で維持されることが望ましい指針として「大気環境指針(年平均値でトリクロロエチレンは250μg/m
3
以下、テトラクロロエチレンは230μg/m
3
以下 暫定値)」を平成5年4月に定めており、また、その2物質の大気中への排出に係る暫定対策ガイドラインについて取りまとめ、都道府県知事・政令指定都市市長に対して実態の把握・濃度測定・排出の抑制等を要請している。
諸外国においては、アメリカで「大気清浄法」が1990年(平成2年)11月に改正され、有害大気汚染物質を現行の9物質から189物質へと大幅に拡大するなど規制の強化が図られているほか、各国際機関においても化学物質のリスク評価及びリスクの削減の取組が行われてきている。OECDでは、安全性データの少ない既存化学物質に関する安全性点検を各国が分担して実施する国際プロジェクトを推進しており、現在648物質がその対象となっている。また、UNEPにおいても、化学物質の人及び環境への影響に関する既存の情報を国際的に収集し蓄積するとともに、国際有害化学物質登録制度を設け化学物質の各国における規制に係る諸情報を提供することなどを行っている。
環境庁では、大気環境を通じて人の健康等に影響を与えるおそれのある各種の有害大気環境汚染物質について、優先的に取り組むべき物質に関して健康影響や発生源に係る知見等を充実し、体系的な取組を進めることとしている。