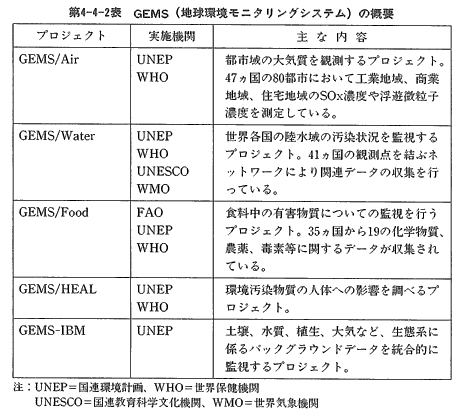
2 環境情報の整備と活用
(1) 環境政策の効果を高めるための環境情報の活用
カナダで開催された「21世紀に向けての環境情報国際会議」では、意思決定者の側から見た環境情報について、「環境の状況・傾向を評価するため、政策の方向を決定・調整するため、及び資金を投資するために、意志決定者が必要とするデータや統計その他の質的・量的材料」と定義している。健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築するには、まず環境に関する広範囲の情報を把握し、その特性を踏まえた「環境計画」を策定し「環境管理」を行っていくことが望ましい。また、国際的な環境対策に限らず、都市計画や開発事業などに対する投資に際しても、こうした適切な環境情報に基づく環境保全の適切な配慮が欠かせないものとなっている。
一方、市民の側で必要とする環境情報も、工場排水中の成分や濃度などかつては限られた人々を対象とした公害関連の観測データなどが中心であったが、地球環境問題の顕在化や環境問題に対する市民意識の向上などにより、地球規模での環境影響や将来世代における影響など広範にわたるものが求められ、さらに分類・解析された付加価値の高いものも望まれるようになってきている。
こうした情報は、環境行政や地域レベルでの計画遂行に不可欠であるばかりでなく、広く一般に提供することにより国民、民間団体による自発的な環境保全活動の促進に資することを含め環境保全に関する様々なニーズに応えることになり、よりよい環境づくりに有形無形の貢献をするものである。市民の情報収集や情報利用が容易になれば、市民活動への参加促進、ライフスタイルの改善、行政への提言の活発化なども期待されよう。
こうした効果は、データの収集・処理・補完・分析・報告などにかかる費用に見合うものであり、また見合うように活用する必要がある。
一般に情報というものは、意識の啓発や教育といった無形の効果が大きいため、その便益の計量は本質的に難しい。
東京都では平成元年以降ごみ減量キャンペーンを行ってきている。このキャンペーンは、ポスターや啓発紙、テレビ・ラジオ放送を用いて情報提供及び啓発活動を展開しているもので、都ではこの関連事業に約13億円(平成5年度)を充てている。東京都のごみ処理費用は、年間約1,900億円であり、キャンペーンの成果として家庭からのごみの排出量が減り、これにより仮に処理費用が1%しか減らなかった場合でも費用面から見て効果的な施策であったと考えることができよう。長期的には、年間約800億円に上るとされる施設設備費用の低減効果や埋立費用が今後さらに高くなることなどを併せ考えると、本キャンペーンの効果は注目されよう。
環境情報は、上記のような環境行政の支援、住民への情報提供のみでなく、環境指標開発を目的としても注目され始めている。
国際的にも、最終的にマクロ経済政策に環境配慮を盛り込むことを目的として、OECDにおいて1993年(平成5年)より環境指標の具体的項目が検討されているところである。ここで検討されている項目は、気候変動、富栄養化、排出有害化学物質など環境汚染に関するものから、森林資源や水資源などの自然資源など多岐にわたっている。
こうした動向に対応するためにも、地域ごとに保有されている環境情報を地域比較、国際比較が可能となる形式で収集・分析することが望ましい。さらにこれら構築された情報データベースは相互にアクセスでき、データの結合が行える統合ネットワークシステムとなるよう、長期的計画のもとで実行されるべきであろう。ネットワーク化は、情報を利用する者の利便性を向上させるのみでなく、情報・収集の効率化を図る手段としても有効なものである。
また、情報提供システムは、情報の収集(モニタリング)、情報の分類・分析、情報の普及という処理手順を踏むものである。したがって、情報システム全体を、より有効に機能させるためには、そのデータベースを作成・更新していくための維持負担の少ない情報収集システムの開発、環境保全に取り組むさまざまな主体が自由にこのデータベースにアクセスするための情報提供システムの構築という点についても重きを置く必要がある。特に、だれもが容易にアクセスできる体制づくりは、効果の面から見ても重要であり、このためにはシステム自体の工夫にとどまらず、環境情報センターや環境情報コーナーなどの「場」の提供、オフラインでも提供できるサービス窓口の設置、認知度向上のための広報など、積極的な取組が期待されよう。
(2) 環境に関する情報の収集・普及の現状
1992年(平成4年)のUNCED(環境と開発に関する国連会議)で採択された「アジェンダ21」の中では、「意思決定のための情報」に関する行動計画の項目として、「データ格差の解消(持続可能な開発の指数開発及びその国際的使用の推進など)」及び「情報提供の改善」が掲げられている。これは、「持続可能な開発」を進める上で、国際的レベルから個人レベルまでさまざまなレベルにおける意思決定が、十分かつ正確な情報に基づくことを確保する必要があるとの認識を反映したものである。
このように、環境問題に関する十分かつ正確な情報の収集と普及のための仕組み作りは、今後官民を挙げて取り組むべき重要な課題の1つであり、具体的には環境情報データベースや環境情報システムの整備・拡充が望まれているところである。
ここでは、国際機関、国、地方公共団体、民間の4つのレベルにおける、環境問題に関する情報収集・普及活動の現状をまとめる。
ア 国際機関の取組
地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題は、ある国から排出される環境汚染物質が他の国にも影響を及ぼすという性格をもつため、その対策には政府レベルから草の根のレベルまで、国際的な協力が不可欠である。このため、地球環境問題に関する情報は、世界各国の政府から市民まで効果的に活用できるよう提供されるべきであり、国際的枠組みでの環境モニタリング(観測)体制の整備や環境情報データベースの構築は、重要な課題となっている。また、世界各国のさまざまな機関で収集される環境情報を、誰もが容易に入手できるようにするための、「情報源のデータベース」も必要となっている。
以下、現在実施中の具体的な取組のうち、代表的なものを見てみよう。
(ア) 地球環境モニタリング
代表的な取組としては、UNEP(国連環境計画)が中心となって進めている「GEMS(地球環境モニタリングシステム)」がある。これは、気候、越境汚染、再生可能資源、海洋、汚染による健康への影響といった5つの分野を主要な対象とするモニタリング計画であり、第4-4-2表に示す個別プロジェクトから構成されている。
さらに、WMO(世界気象機関)による世界気象監視計画やWMOによる全球大気監視計画などの取組がなされている。
これら既存の個々のモニタリングを基礎とし、地球のシステムを長期的な観測により全体的に捉えようとする、GCOS(地球気候観測システム)、GOOS(地球海洋観測システム)、GTOS(地球陸域観測システム)という、相互に関連した3つの地球観測システムの整備がICSU(国際学術連合会議)や国連諸機関を中心として進められている。こうしたモニタリングにより得られたデータは、地球環境保全のため、世界各国の研究者や政策決定者に幅広く提供・活用される必要があろう。
(イ) 環境情報データベース
環境情報データベースのグローバルな取組の具体例としては、UNEPのプロジェクト「GRID(地球資源情報データベース)」が挙げられる。これはリモートセンシングデータ等、環境に関する様々なデータを統合し、世界中の研究者や政策決定者に提供することを目的として構築されているデータベースである。
GRIDのデータは、我が国においては国立環境研究所の「GRID−つくば」により、地球環境問題を扱う研究機関などに提供され、活用されている。GRID−つくばに登録されているデータの主なものを第4-4-3表に示す。さらに、気象庁の「WMO温室効果気体世界データセンター」において、世界中の温室効果気体の観測データの収集・解析、及び提供を行っている。
(ウ) 環境情報源のデータベース
代表的なものとしては、UNEPが運営している「INFOTERRA(国際環境情報源照会システム)」がある。これは、環境に関する情報を保有し、外部からの照会に応じることのできる機関を登録した世界的規模のデータベースである。INFOTERRAの本部はナイロビに置かれ、参加各国に代表機関が設置されている。我が国では、国立環境研究所環境情報センターが代表機関として登録されており、国内の研究機関等への情報提供に努めている。今後は、より幅広い層へのさらなる情報普及を図るため、パソコン通信を活用した情報提供などが検討されている。
イ 我が国の取組
環境基本法では、その第二十七条において、国は環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益に配慮しつつ環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努める旨規定している。
これを受けて、環境庁では、民間保全活動や地方公共団体等における環境行政を推進するため、情報提供や環境施策の推進に必要な情報基盤の強化に着手している。
具体的には、国民、NGO、地方公共団体等に対し、環境の状況や行政の取組に関する情報、環境教育や環境保全活動等に関する情報及びこれらに関する情報源情報等の情報をパソコン通信やFAX通信を用いて提供する「環境情報提供システム」が、環境庁環境情報企画官室及び国立環境研究所環境情報センターを中心に開発されているところである。 また、環境庁内の情報システムの強化により環境情報提供システムの運用支援と行政事務の情報化が行われることとなっている。さらに、CD-ROM等の電子メディア、マンガ、音声等様々な媒体を用い環境白書に盛り込まれている情報等の普及を試みている。
ウ 地方公共団体の取組
地方公共団体は、自然環境や生活環境などの地域環境に関わる情報を詳細に把握し得るため、これを環境政策に適切に反映させていくことが求められる。また、地方公共団体は、近年盛んになっている住民主体の環境保全活動と連携して、より有効な環境保全施策を展開するため、地域環境に関する情報の住民への積極的な提供に努めることが重要である。
こうした背景から、環境情報システムの構築など、環境情報の管理を進める動きが見られる。例えば、第4-4-4表に示すとおり、近年の都道府県における環境情報管理関連予算は、予算全体から見れば少額ながら、概ね年率10%強の高い伸び率で増加している。
地方公共団体のもつべき環境情報システムは、その内容、形態別に第4-4-1図に示すタイプに分けられる。
「日常業務支援系」の情報システムは、地域環境に影響を及ぼす施設設置の届け出の管理や苦情の処理など、地域環境行政の日常業務に関わる情報の管理を行うものである。
「計画推進支援系」の情報システムは、地域の個別の環境管理計画の遂行に資するために、計画の目的に沿った形で、環境の現状把握、目標設定・管理や施策影響評価を行うための情報を管理・分析するものである。
「情報交流支援系」の情報システムは、環境保全に関わるさまざまな主体の間の情報の交流を促進するためのものである。形態別に見れば、公共団体の収集・管理する情報を一方向で市民に提供する「情報提供型」と、住民からの情報提供も活用するため双方向の情報の流れを基本とする「住民参加型」が考えられる。近年盛んになっている住民主体の環境保全活動と連携していくことは、地域の環境行政にとって有益であると考えられるため、今後は、特に情報交流支援系の中の、「住民参加型」の情報システムの構築・拡充を推進する必要があろう。この点に関して、国立環境研究所で開発された都市再開発後の景観等に関してシミュレーションを行う景観画像処理システムがある。実際に多数の再開発案を示すとなると多額の費用が必要になると考えられるが、本システムの活用により、より効果的具体的に住民が認識することができ、こうした情報の活用によっても効果的に政策を進められると考えられる。
地方公共団体における環境情報システムの具体例として、横浜市の例を見てみよう。
横浜市では、昭和61年に策定した「横浜市環境管理計画」の支援システムとして、昭和62年に環境情報システムが整備された。この環境管理計画は、安全で快適な市民生活が送れる良好な都市環境の実現を目指して、環境配慮指針等を示したものである。同計画策定時に作成された環境特性図やその基礎図を中心に、土地利用や都市施設、法規制、生物分布等の横浜市の環境に関する情報を収録、データベース化したものを環境特性の分析や評価に活用するため、環境情報システムが構築された。平成3年度末現在では、第4-4-2図に示すデータが収録されている。この環境情報システムは、「環境特性図利用サブシステム」や「法令・条例等検索サブシステム」など、18種類のサブシステムから構成され、利用者の利用しやすさに配慮している点が特徴である。現在はまだ初期段階にあり、行政内部における利用がほとんどであるが、今後はさらなるシステムの改善により、住民の積極活用が期待される。
エ 民間の取組
総合的かつ効果的な環境保全対策を進めていくためには、これまで見てきたような行政による取組に加え、民間レベルにおける情報交換も重要であり、積極的な取組が増えつつある。
1992年(平成4年)のUNCED(環境と開発に関する国連会議)の開催中に、同じブラジルのリオデジャネイロにおいて、165カ国の7,500ほどのNGO(非政府組織)が参加した「グローバル・フォーラム」が開催され、環境問題に関する情報交換が活発に行われた。これを契機として、民間レベルにおける環境保全活動は、世界規模での連携をもつことになり、今後さらに効果的な活動へと発展していくことが期待されている。
こうした世界規模での市民の連携は、先端的な情報通信の活用によってさらに発展していくものと思われる。例えば、米国のゴア副大統領の提唱による「GLOBE」計画では、世界各国の学校の生徒や教師を結ぶ情報通信網を構築し、天候や地域の自然などを共同観測することが構想されている。これは国の主導による情報網構築の動きではあるが、学校の生徒や教師など一般市民が主役となる取組として注目される。
また、企業においても環境に関する情報の提供・普及に取り組む動きが見られる。例えば、ある大手電機メーカーでは、世界的なコンピュータネットワークである「インターネット」を通じて、自社の脱フロン化などの環境関連技術に関するデータの提供を始めるとしている。環境分野における自社の知名度を高めるとともに、他の研究機関や企業との技術交流の活発化を促進することができ、メリットは大きいと考えられる。この他、企業の環境関連情報をオンラインで人々に提供し、投資の際の判断に役立てる取組を行っている米国の投資情報会社など環境問題に関する情報化についての企業レベルでの取組は活発化しつつある。また、近年各地の科学館等で大画面映画等の導入が進んできており、環境保全に関する優れたフィルムの製作も活発化していることも注目される。
(3) 今後の課題
ア 地球環境問題と情報に関する今後の課題
地球環境に関わる情報の今後の課題としては、特に以下の事項が挙げられる。
(ア) 統一的基準に基づく観測・測定と情報の流通の促進
現在のように、各国で測定基準や測定方法がまちまちの状態では、国別の状況比較等ができず、有効な対策を打ち出しにくい。今後は、各国が統一的な基準に基づく観測・測定を行い、その結果を比較分析して地球規模の環境変動の解明や有効な環境対策の検討を行えるよう、基準の策定やデータの流通の促進に努めるべきであろう。
(イ) 地球環境モニタリングの強化
現在も取組が進められているが、その観測網は十分に整備されているとは言いがたい。今後は、地球環境に関する最適情報量が得られるように観測網を拡充すると共に、各観測点における観測精度の向上に努めていくべきであろう。
(ウ) 途上国への支援(環境モニタリング体制の整備)
地球環境問題の動向に大きな影響力をもつ開発途上国では、適切な環境管理を遂行していく上で不可欠な地球環境観測体制の整備が遅れている。先進工業国は、自国における地球環境モニタリング体制を拡充していくことがまず求められるが、有効な地球環境保全施策の推進のためには、開発途上国における環境モニタリングの充実にも注力する必要がある。開発途上国の環境モニタリング体制整備のための支援は、今後、先進国が積極的に取り組むべき課題と言えよう。
イ 地域環境問題と情報に関する今後の課題
地域環境問題に関わる情報の今後の課題としては、特に以下の事項が挙げられる。
(ア) 環境情報システムの構築促進
上記のように、いくつかの地方公共団体では既に環境情報システムの構築が進められているものの、多くの地方公共団体で、本格的な環境情報システムの整備は今後の課題となっている。今後は、都市開発により失われつつある自然環境の保全や、快適な生活環境の創造のためにも、より有効な環境保全施策を実現するための環境情報システムの構築が、すべての地方公共団体に求められる。
(イ) 環境情報の双方向流通の促進
環境保全対策への住民の積極的参加を促すため、住民が行政の持つ情報を入手しやすく、かつ、行政が住民からの情報提供を受け入れやすい住民参加型の環境情報システムを構築していくことが特に重要である。このため、近年普及が著しいパソコン通信の活用やマルチメディアを活用したビジュアルで魅力的な情報提供などの工夫が求められる。また、この他にも、環境情報センターや環境情報コーナーなどの場の提供、住民の環境保全意識の高揚のためのイベントの開催、広報誌における環境保全関連記事の積極的な取扱いなど、情報機器によらない環境情報普及にも、注力していくことが求められる。
ウ 環境と情報に関するその他の課題
地球環境と地域環境の別に関わらず、集積されたデータはあらゆるレベルの人々に理解され、意思決定の基本的な判断材料となることが望ましい。データの適切な集約・加工を迅速に行い、国別や都市別の比較が行えるような指標を作成するなど、一般市民がより理解しやすい形で環境情報を提供できるよう努める必要があろう。