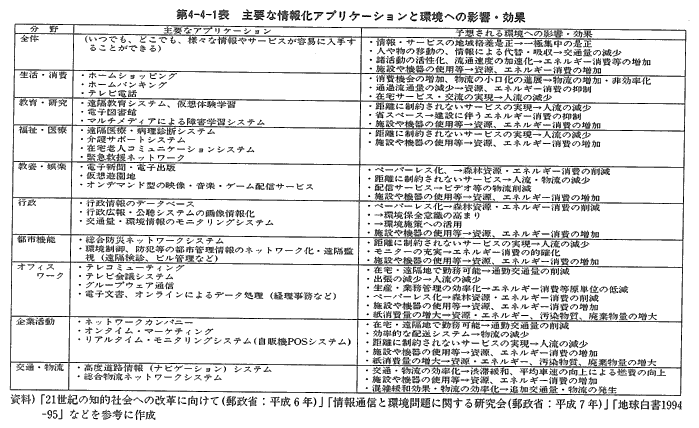
1 情報化の進展と環境
最初に、情報化の進展による環境への負荷について考えてみたい。情報化社会においては、生活の様々な場面で利便性が向上するものと考えられているが、同時に環境に対しても大きな影響を及ぼすものと予想される(第4-4-1表)。情報通信の活用は、人や物の移動の代替・吸収、ペーパーレス化、エネルギー消費の的確化等を通じ、様々な分野で省エネルギー効果を有し、二酸化炭素排出量を削減するなど、環境負荷の軽減につながることが期待される。
他方で、情報通信の活用は、情報提供による活動の動機づけ、効率化による余暇時間などの創出等により、諸活動の活性化を促すほか、情報通信設備の製造・運営に伴う資源やエネルギー消費を増大させるなど、環境への負荷を大きくすると懸念される事項もある。例えば、ホームショッピングサービスの実現は、流通経路の簡素化等から環境への負荷低減に資する一方、物流の小口化、長距離化によるエネルギー消費量、NOx、CO2排出量の増加の可能性が懸念されよう。したがって、情報と環境の関係を考える場合、プラスとマイナスの双方の効果を総合的に考慮する必要がある。
一例を見ると、TV会議システムの活用に関する郵政省の試算によれば、TV会議システムが約40,000端末普及した場合、出張回数の減少等を通じ、我が国の運輸部門における総CO2排出量の1990年度から1992年度の2年間の平均年間増加分の9.1%を吸収するとしている(CO2吸収量1端末当たり4.58t-c/年)。他方、このシステムによる環境へのマイナスの影響に関して、TV会議システムの使用等に伴うエネルギー消費についてはCO2排出量の推計が行われており(CO2発生増加量1端末当たり0.53t-c/年)、TV会議システムの活用が、環境負荷低減効果を持つと報告されている。ただし、本試算では、TV会議システムにより削減された移動時間等が他の活動に振り向けられること等による環境への影響等について、十分な試算が行われていないことに留意する必要がある。
次に情報化が飛躍的に進展するにつれて、それを支えているエネルギー消費が増加した例を見てみよう。例えば、我が国におけるコンピュータやファクシミリによる消費電力は、その冷房にかかる電力も含め、年間300億kwh以上に達するとみられ、これは電気事業者による全発電量の約5%、業務部門の総電力消費量の約22%にのぼる。ここ10年間の業務部門電力消費量は一貫して増え続けているがその増加分の約半分を、これら情報関連分野が占めている。
こうした情報関連の多量のエネルギー消費は、平成5年に納入台数ベースで300万台を上回ったコンピュータの急激な普及などによるものであるが、実際に機械を動かしているのはこれらの電力の一部分にすぎず、ほとんどの電力は、使用されていない時間にも通電されたままのコンピュータや、受信待ちのファクシミリ等により消費されているとされる。米国環境保護庁では、こうした問題意識から、省エネルギー効果に優れたコンピュータとプリンターの導入を推進し、発電所からの大気汚染を低減するため、「エナジースター・コンピュータ計画」を1992年(平成4年)6月から開始している。これによりパーソナルコンピュータで50-75%、レーザープリンターで30-50%の省エネルギー効果が見込まれている。1994年(6年)7月現在で米国のコンピュータメーカーの70%に当たる210社及びレーザープリンターメーカーの90%に当たる31社がこの計画に参加している。
これまで、情報化を含め社会経済活動の拡大・高度化により、人とモノの流れは加速化し、また相互に誘発され、物流量は高速化かつ拡大してきた。これにより、エネルギー消費等を通じた環境への負荷は増加し続けている。先に見たように情報化の一層の進展は、環境への負荷を削減する可能性を有すること、また、次に見るように環境情報の適切な活用による環境対策の一層の効率化に資するものと考えられる。しかしながら、これまでの情報化の過程で業務部門の電力消費は増大を続けていることも事実であり、今後は、より積極的に環境負荷低減の視点を踏まえて情報化を進めていくことが重要である。