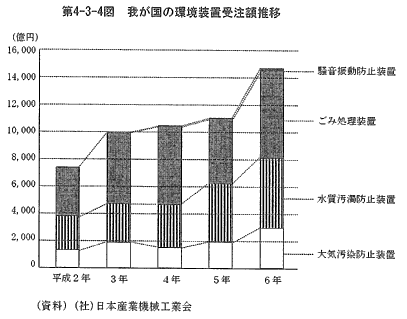
2 エコビジネス(環境関連産業)の動向
平成2〜6年の環境装置産業受注額は第4-3-4図のとおりとなっている。近年の環境装置の受注状況を見ると、受注額の過去ピークは昭和56年の6,626億円であり、その後民間需要及び官公需要の伸び悩みから低迷状態となったが、63年以降民間需要及びごみの増大等に伴う官公需要により連続して伸び続け、平成6年には1兆4,697億円(対前年比131.0%)となっている。
一方、世界の環境産業の市場規模は、OECDの推計によると1990年(平成2年)で2,000億ドル、2000年に3,000億ドルになると言われており、また、米国の環境ビジネス・インターナショナルによると、1992年(4年)で2,950億ドル、1997年(9年)で4,260億ドルと推測されている。環境ビジネス・インターナショナルの推計によると、1992〜93年(4〜5年)の米国の環境産業の事業部門別の市場規模と成長率は第4-3-5図のとおりである。各部門の最近1年間の収入を見ると、固体廃棄物処理、水道事業、資源回復といったサービス部門が上位を占め、また成長率でも、生産工程での汚染回避技術をはじめとしたサービス部門の高い成長率に対し、有害廃棄物処理や汚染防止装置の成長率がマイナスとなっている。このように、米国の環境産業は、サービス部門を中心とした市場が形成されつつあり、その需要により大きく部門間の成長率が異なっていることが言える。
我が国のエコビジネスにおいては、環境庁が行った平成5年度の調査によると、?環境負荷を低減させる装置、?環境への負荷の少ない製品、?環境保全に資するサービス、?社会基盤の整備等の4つの分野に分類されているが、これらのエコビジネスでは、その事業化及び開発の状況、今後の新規参入あるいは研究・開発の状況は今まで十分に把握されているとはいえない。このため、6年度に環境庁が実施した「環境にやさしい企業行動調査」(対象は全国の上場企業2,177社、回収数は906社で回収率は41.6%)では、エコビジネスの取組状況の把握を行った。この結果においては、企業の本業以外の事業も含み、事業の中には公表できないものがあると予想されるため、すべての取組状況を把握できたわけではないが、環境に関する事業活動の情報を積極的に公表していこうとする企業の姿勢が現れているものと考えられる。
(1) エコビジネスの事業化及び開発の状況
ア 環境負荷を低減させる装置等
調査回答企業906社中、この分野で事業化し売り上げを計上している(以下、「事業化」という)企業は146社(事業の合計件数は416件)であり、既に事業化されている件数は、水質汚濁防止装置の67件、大気汚染防止装置の55件、ごみ処理装置の44件、コージェネレーションシステムの34件、再資源化装置の26件などとなっており、各種公害防止装置の事業化が多い。また、開発が終了している(以下、「開発済」という)企業は96社(237件)であり、各種公害防止装置を開発している企業が多く、特に、燃料電池の15件やCO2分離技術の10件をはじめ、CO2関連技術の開発を行っている企業が見られた(第4-3-6図)。
イ 環境への負荷の少ない製品等
事業化している企業は154社(197件)であり、エコマーク商品の30件、古紙のリサイクルの24件、代替フロンガスの17件、再生プラスチックの16件、省エネ家電製品の14件など、廃棄物のリサイクル・省資源・省エネ関係の事業化が多い。低公害車においては、事業化している企業は少ない状況にある。また、開発済の企業は77社(116件)であり、事業化と同様、廃棄物のリサイクル・省資源関係での開発が多い。特に、電気自動車8件のほか天然ガス自動車6件など低公害車の開発企業が見られた。
ウ 環境保全に資するサービス等
事業化している企業は62社(102件)であり、廃棄物処理事業の27件、再生資源回収事業の15件、土壤・地下水汚染状況調査の11件、土壤・地下水汚染浄化事業と環境アセスメントの各9件などとなっている。このうち情報型エコビジネス等では事業化している企業は少ない。また、開発済の企業は18社(27件)であり、土壤・地下水汚染浄化事業の6件、土壤・地下水汚染状況調査の5件、環境教育と環境アセスメントの各4件などとなっている。環境維持管理・環境コンサルタント、情報型エコビジネス等では開発済の企業はほとんどなく、この分野での取組はあまり進んでいない。
エ 社会基盤の整備等に関する技術、機器及びシステム等
事業化している企業は89社(229件)であり、下水道整備関連事業の40件、廃棄物処理施設整備事業の22件、地域冷暖房システムの21件、下水処理水循環利用システムの18件、都市公園整備事業の16件、省エネルギー施設の15件などとなっている。また、開発済の企業は37社(57件)であり、地域冷暖房システムの9件、廃棄物処理施設整備事業の6件、省エネルギー施設の5件、植林事業と下水道整備関連事業の各4件などとなっている。
(2) エコビジネスの今後の参入あるいは研究・開発予定の状況
環境負荷を低減させる装置等において、今後、参入あるいは研究、開発に取り組もうとしている企業は98社(260件)であり、コージェネレーションシステムの46件、燃料電池の22件、ごみ処理装置の21件、未利用エネルギー活用システムの20件、再資源化技術の18件などとなっている(第4-3-7図)。
環境への負荷の少ない製品等においての今後の参入、研究・開発は、同様に91社(138件)であり、再生プラスチックの23件、生分解性プラスチックの19件、太陽光発電装置の12件、住宅の断熱化の10件などとなっている。特に、プラスチック関係の製品が注目を集めているのが分かる。
環境保全に資するサービス等においての今後の参入、研究・開発は、同様に53社(115件)であり、土壤・地下水汚染浄化事業の17件、廃棄物処理事業の16件、再生資源回収事業の15件、土壤・地下水汚染状況調査の13件、環境監査事業の10件などとなっている。環境監査事業、環境アセスメント、環境ビジネスコンサルティング及び環境リスクマネジメント等のソフト型の事業は今後進展していくものと考えられる。
社会基盤の整備等に関する技術、機器及びシステム等においての今後の参入、研究・開発は、同様に61社(127件)であり、地域冷暖房システムの15件、廃棄物処理施設整備事業及び屋上緑化の各14件、環境配慮型の道路・河川整備事業の10件、下水処理水循環利用システムの9件などとなっている。
以上、エコビジネスの事業化、研究・開発等の状況について見てきたが、今後のエコビジネスの進展に当たっては、未だ市場が確立されていないため、事業展開における不安も多いと考えられる。前述の企業行動調査においては、今後、エコビジネスが進展していくための問題点について、複数回答を求めたところ、「消費者やユーザーの関心がまだ低い」との回答が全体の36.2%を占め、「開発費が多額になる」が29.9%、「それぞれの分野の市場規模がわからない」が26.7%、「現状の市場規模では採算が合わない」が23.5%、「どの分野が有望であるか十分に把握できない」が20.1%などとなっている。
このようにエコビジネスを事業展開していくに当たっては、いくつかの問題点が指摘されている。エコビジネスの市場が確立されていなくても、ビジネスと結び付いた環境保全活動として自主的積極的取組を行っている企業が、エコビジネスの分野で様々な開発を行い、また事業化しつつあり、環境関連の新たな商品・サービス及び技術が生まれている。例えば、波力発電等の未利用エネルギー関連、発泡スチロール再生処理等の再生・リサイクル関連、その他の省エネ・省資源関連、環境への負荷の少ない商品及び環境測定分析等であり、エコビジネスの新規分野が開拓されつつある。
エコビジネスの市場動向を左右する個別分野の事業化あるいは開発の状況は現在、様々な産業の分野にわたっており、また、今後の新規参入及び研究・開発については、前述の調査によると総件数640件(84事業中81事業)と見込まれ、さらに活発化していくものと考えられる。
エコビジネスは、環境保全活動に積極的な企業が新たなビジネスチャンスとして環境関連分野でビジネス化を行ったものであり、環境庁の試算によると、定量的に把握できたエコビジネスの市場規模は1990年では約6兆円、2000年では約13兆円、2010年では約26兆円になると予測しており、今後も成長していくことが見込まれている。なお、平成6年6月の産業構造審議会地球環境部会の意見具申である「産業環境ビジョン」でも、環境産業の現状及び将来の市場規模の分析を分野別に行っており、推計対象及び方法の相違等により環境庁の試算とは異なるが、現状で約15兆円の市場規模が、2000年には約23兆円、2010年には約35兆円に達すると予測しており、環境関連事業を今後拡大が期待される戦略的事業分野として位置付ける動きが進展しつつあると指摘している。
企業の環境関連分野における事業化及び研究・開発の取組は、エコビジネスの市場を拡大し、あるいは新たな市場を創造する。他の産業と同様に、商品・サービス市場の競争原理を通じビジネスとしての展開が促進され、エコビジネスが産業活動の一部として位置付けられることにより、事業活動に環境への配慮を組み込む環境保全型産業活動が一層促進されるものと考えられる。エコビジネスの発展は、環境への負荷の少ない持続可能な社会を形成する上で重要な要素であり、企業の積極的な環境投資や技術開発等の取組、政府による適切な支援、今後の動向を把握するための環境関連情報等により、エコビジネスの成長が促されることが必要である。エコビジネスを通じ、産業界の環境保全型産業活動をはじめ、消費者の環境に配慮した消費行動や国及び地方公共団体の事業者・消費者としての環境保全行動など、各主体の環境保全に向けた取組が積極的に進められることが期待される。