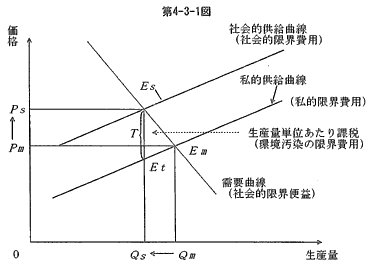
1 環境政策と市場メカニズム
(1) 経済的負担措置に関する理論的考察
我が国では、石油危機以降、産業分野を中心に省資源・省エネルギーが進んだが、その一方で、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動の様式が広まるとともに人口や社会経済活動の都市への集中が続いた。これらにより、都市・生活型公害、廃棄物の排出量の増大、地球温暖化等の環境問題が発生しており、なお一層の各主体による取組が必要な状況にある。そこで、環境政策に市場メカニズムを活用する考え方を見てみよう。
市場は、価格が一つのシグナルとなって複雑な資源配分を行う機能を有し、例えば、価格の上昇は需要を減少させ、供給を増大させるので、財の不足が解消される。このように財・サービスの過不足は価格の変動を通じて解決されるが、価格に適切に反映されない要因があると市場はその配分効果を有効に発揮できないこととなる。
このため、製品・サービスの取引価格に環境コストを適切に反映させることで、環境の観点から市場メカニズムの活用を図ることが可能になるものと考えられる。
生産やサービスに伴って発生した環境への負荷は、社会的費用となってマイナスの外部効果をもたらす。税・課徴金等の経済的負担を課す措置を用いてこれを市場の取引ルートに乗せて内部化を図るのが、いわゆるピグー課税の機能である。
環境への負荷に伴い社会に生じる費用(外部不経済)も本来は、当該財・サービスに適切に織り込まれることで市場価格に反映させるべきものである。しかし、環境への負荷を伴うあらゆる生産・サービスに関して、その被害者と加害者の直接交渉によって、外部不経済の内部化を行うことは不可能ともいえる。このため、この種の財・サービスの市場価格は、外部不経済の費用(限界費用)を適切に反映した生産量1単位当たりの社会的費用そのものとは一致せず極端な例としては、生産者の私的費用のみしか反映していないケースが想定される。したがって、過大な生産・消費が促進されることとなるのである。このことをグラフで見てみよう(第4-3-1図)。
私的供給曲線と需要曲線の交わる点Emが、現在の状態、すなわち外部不経済が内部化されていない状況を示している。生産量はQm、価格はPmで示されている。ここで、外部不経済を内部化するとしよう。その手段の一つが、単位生産量当たりの外部不経済の限界費用に相当する額を私的限界費用に付加して社会的限界費用に一致させることにより、市場価格を引き上げ、生産量(消費量)を抑制しようとする税・課徴金等の経済的手法の考え方である。付加される額は、C=Es-Etであり、これによって均衡点は、EmからEsへと移行する。新たな均衡点の下で、生産量はQmからQsへと抑制され、価格は、PmからPsへと引き上げられている。
環境政策上、税・課徴金等の経済的手法を用いる場合、汚染防止にかかる費用とそれによって得られる便益を比較する必要があろう。
縦軸に費用を、横軸に規制のレベル(規制が完全な状況からゼロの状況(100%))をとって、ある企業が汚染物質を排出するケースを考えよう。一般に少量の汚染に比較し、多量の汚染では一層甚大な損害が生じることが考えられる。つまり、限界損害額は、汚染排出量が多いほど増加する。これを図示すると(第4-3-2図)、限界損害費用(marginaldamage cost)が、右上がりの曲線として描かれる。また、より一層厳しい対策になればなるほど追加的に必要となる対策の費用が増加するため、限界対策(削減)費用(marginalabatement cost)は、右下がりの曲線として描かれる。
限界交点eを見ると汚染による追加的な損害費用と汚染の削減による追加的な便益が一致する。したがって、経済効率上はこのレベルで排出量をコントロールすることができれば、それが最も望ましいと考えられる。
資源の活用や日々の社会経済活動を持続可能なものとしていく上で、以上のように市場メカニズムを活用する視点は欠かせない。それは、環境政策の効果をより高める上でも有効性が期待できるからである。直接的な規制に比べ、理論的には経済的負担を課す措置は費用がかからないと言われる。その理由としては、一般的には費用の低いところから順次対策をとっていくことがあげられ、すべての汚染者に対して一律に削減を強いたり、特定の過程や技術を用いるよう義務づける規制に比べ、同じ削減量がより安い経済的費用で達成されることになる。
(2) 経済的負担を課す措置による環境保全効果
これまで経済的負担を課す措置の有効性について理論的な考察を試みた。ここではその活用と環境改善効果の関係について種々の事例を見てみよう。以下は、特にその環境改善効果が比較的明確に示されたといわれている例である。なお、こうした事例については、昨年の環境白書でもいくつか取り上げているところである。
・ ドイツにおける排水課徴金
ドイツの排水課徴金は、排水の水質改善のインセンティブを与えることを目的として1976年(昭和51年)に導入された。連邦により課徴金制度が営まれ、課徴金の対象となるのは、CODや重金属である。
課徴金の導入に先立つ数年に、公害防止投資が急激に増加したというアナウンスメント効果に関する示唆が得られている。
・ スウェーデンにおける窒素酸化物排出課徴金
スウェーデンでは、1995年(平成7年)の窒素酸化物の新たな排出ガイドラインの早期達成を目的として、1992年(4年)より窒素酸化物排出課徴金制度が導入された。これにより、1992年(4年)には、20-25%の削減を予想していたが、実際には予測を大きく上回る30-40%の削減が達成された。
・ フランスにおける大気汚染物質排出課徴金
フランスでは、1980年(昭和55年)に大気汚染の監視や大気汚染防除技術の開発等を目的とする「大気質公社」が設立され、同公社の事業のために、政府に対して特別課徴金を設ける権限が与えられた。1985年(60年)からの5年間で、フランス全土の硫黄酸化物総排出量比で約8%相当の量の硫黄酸化物が削減されたといわれる。
・ スウェーデンにおける国内航空機に対する環境税
スウェーデンでは、1989年(平成元年)より航空機からの排気ガスの減少を目的として、国内航空機に対して環境税を課している。これにより、航空機の燃焼室の交換が進み、炭化水素の排出量が90%減少したとの報告がなされている。
・ デンマークの廃棄物税
デンマークの廃棄物税は1987年(昭和62年)に導入された。特定の規制があるものを除いて、埋立及び焼却処分される廃棄物の重量に応じて課されるものである。税の副次的な作用として、行政上の要求を満たすことのできない多くの小規模処理業者が廃業を余儀なくされた。また、同税により1987年(昭和62年)から1989年(平成元年)に、廃棄物の排出量が12%減り、再利用される廃棄物量は7%増加した。1990年(2年)以降廃棄物の定義が拡張したが、課税の対象となる廃棄物の増加量は予想を下回っている。
さらに、予期しなかった効果として、建設廃材などの道路工事での活用(埋込材として)などが進んだ。
・ イタリアにおけるプラスチック製買い物袋への課税
イタリアでは、プラスチック製買い物袋に市場価格の200%の課税を行った。同国では、1983年(昭和58年)から1988年(63年)にかけてプラスチックの買い物袋の消費が37%増加したが、1988年(63年)にこれに課税したところ、その消費量が20-30%減少した。
なお、シンガポールの特定地域乗り入れ許可制度について触れてみる。同制度は、当初環境保全以外の目的で導入された措置であるが、当初の目的を果たすことにより副次的に環境の改善に資することとなったものである。
シンガポールでは、経済の発展に伴い自動車が激増し、都市部の交通円滑化を著しく阻害することとなった。そこで、同国は都市部の自動車交通の円滑化を目的として、1975年(昭和50年)に特定地域乗り入れ許可制度を導入した。
特定地域(ゾーン)に進入しようとする乗用車は、チケットを購入し、これをフロントに提示しておかなければならない。このチケットは、1日券及び1か月券があり(第4-3-1表)、道路沿いに設置されたブースまたは郵便局で購入することができるものであり、都市に乗り入れるためには料金を支払わなければならないという点で経済的措置と言えるものである。
この特定地域乗り入れ台数は、この制度の導入に伴い前年の約1/3に激減し、現在も経済の伸び率に比べ乗り入れ台数の伸びは低いものに止まっており、都市部の交通の円滑さが確保されている(第4-3-2表)。
(3) 経済的負担を課す措置の活用による経済的影響の視点
経済的負担を課す措置の活用による経済への影響について、OECD報告書を参考にその視点を挙げると、産業部門への影響、経済成長、価格、貿易、雇用効果、家計への間接的な効果、地域効果、技術革新がある。
こうした課題の中には、短期的に調整の済むものもあるが、より長期にわたって調整されていくものもあり評価に際して時間的なフレームをどの位で考えるかについては、検討が必要となる。
経済的負担を課す措置は比較的近年その活用が進んでいるものであり、長期的かつ広範な効果については、今後、経済モデルによるシミュレーション分析も含め、できる限り定量的な研究を更に進めることが有益であろう(第4-3-2表)。
(4) 海外における経済的手法の活用状況
? OECD諸国
ア 最近の動向
OECD加盟国における税・課徴金等の経済的手法の活用状況は、OECDによる調査SURVEYON ENVIRONMENTAL TAXES IN OECD MEMBER COUNTRIES"等によれば、次の通りとされている。なお、本書において、環境へ直接・間接に悪影響を与えるもの、環境汚染物質の排出を削減する狙いを持つ多様な税・課徴金を環境税と総称している。
近年のOECDにおける環境税を巡る大きな流れは、以下の2つに大別できる。
まず、デンマーク、オランダ、スウェーデン、ノルウェーでは、税制全体の改正という中で、環境税を取り入れている。例えば、デンマーク議会に対する提案の中で、課税対象を労働所得から環境に悪影響を与える消費や製品へと移行していくべきことが強調されている。
もう一つは、オーストリア、ドイツ、ベルギー及びフランスのように小規模で環境税を活用している国々である。大規模な税制改正の一貫としてではなく、新規のあるいは既存の税制を活用するところが増加している。
以下、報告書の整理に従い、?製品課徴金の多用、?エネルギー税制の改正、?検討委員会の活用の3点について見てみたい。
(ア) 製品に対する税・課徴金
財政的な理由から課される消費税と区別して、歳入的な目的からでなく特定の物品に課される税・課徴金を見てみたい。
ベルギーでは、いくつかの新しい税・課徴金が導入、または検討中の状況にある。例えば、使い捨てのカミソリ刃に対して10BFが課されている。これは、デポジット・リファンド制度の対象とならず、また再利用出来ない飲料容器に対する課税と同様に行われている。使い捨てカメラ、電池、産業用インク、のり、石油と溶剤(solvents)、紙そして殺虫剤や除草剤に対する課徴金が検討中されており、その一部については実施の日時については未定であるものの実施は合意されている。
デンマークでは、1994年(平成6年)1月に行われた税制改正によって、いくつか新たな課徴金が導入された。例えば、一般家庭による地下水及び表層水の使用に税が課され、家庭及び産業による排水に対する課税を1997年(9年)から導入する計画もある。またプラスチックないし紙製のショッピングバッグに対する新税が創設され、廃棄物課徴金が、引き上げられるとともに、それが焼却処分となるか埋立処分となるかで差別化が行われている。
カナダのプリンス・エドワード・アイランドでは、再生紙を利用すると税率が低くなる宣伝用のチラシ等に対する税を導入した。これによってこれらの発行者に新聞の再利用を動機つけることも狙いとしている。
イタリアでは、1994年(平成6年)3月にリサイクル促進の観点から、これまでのプラスチックバッグ税にかえて、バージン・ポリエチレンの使用に課税することになった。またイタリアの州では、廃棄物の処分と排出管理を目的とする特別な税を導入することが可能となった。
これと同様の制度は、1994年(平成6年)に環境浄化税が導入されたトルコでも見ることが出来る。税は廃棄物と排水に課され、家庭と非家庭が適用対象となり、その目的には、消費形態を変え、汚染を低減するとともに歳入の増加も含まれている。
またスイスでは、輸入品に対する広範な課税が法の下で認められていたが、競争力ないし環境上の理由がない場合には適用されないこととなっている。
また、例えば、ドイツ・カッセル市の包装税のように市町村レベルでの使い捨て容器等への税・課徴金等の経済的手法の活用も見られる。
(イ) 輸送税及びエネルギー税
英国においては、温室効果ガスの排出抑制に係る公約を満たすべく、今後数年間ガソリン税のインフレ率を上回る引き上げを行うことを表明した。
デンマークは10年以上使用した乗用車の所有者がこれをスクラップにする際に特典を与えているが燃料税の引き上げは、このスクラップ計画の費用を賄う財政的な側面も有する。
フィンランドでは燃料に関わる消費税は2つの部分に分かれる。すなわち財政面からのチャージと、炭素・エネルギー比その他の環境の観点からの環境のチャージである。キロメートル税は廃止され、標準、軽、都市内によって区別されたディーゼル燃料に対する特別な税に変わっている。
イタリアでは、特定の割合という制限の中で、植物から作られるディーゼル燃料は、消費税の対象から除かれている。1994年(平成6年)12月以前に環境に優しいディーゼル乗用車として登記されたものは、3年間に限り、道路税を免れることとされている。
(ウ) 検討委員会の活用
検討委員会の活用に関しては以下のように様々な事例が見受けられる。
カナダ・オンタリオ州では、産業及び環境担当組織を含めてタスクフォースを設置した。本タスクフォースの目的は、環境保全型の行動を妨げる要因を突き止め、環境保全のために経済的手法を効果的に活用する道を見いだすことである。
デンマークでは、産業に対してより集中的に環境税を活用する必要性について分析するため、1993年(平成5年)に関係省庁によるワーキングパーティーを設立した。ここでは、産業の国際競争力を維持するため歳入を再び活用することの重要性が強調されている。
スウェーデンでは、環境の観点をより多く盛り込んだ税制をいかに構築するのかという観点から議会に委員会を設置している。効果の評価、既存の環境税そしてより社会的に負担の少ない方法で歳入を増やすための課税ベースのシフトに関する将来展望についての検討が含まれる。
オランダでは、環境税のベースをさらに拡大するための可能性を検討するため、関係省庁による研究が行われている。
? アジア諸国
アジア諸国における経済的手法の活用状況は、OECDによる調査"APPLYING ECONOMICINSTRUMENTS TO ENVIRONMENTAL POLICIES IN OECD AND DYNAMIC NON-MEMBERECONOMIES"によれば、次の通りとされている。
廃棄物の収集処理への課徴金は東アジアでは未だなじみが薄いが廃棄物の量は増加し続けており処分地も希少となってきていることから、適切な廃棄物課徴金を導入し排出総量の抑制とリサイクルの促進を図ることが急務である。
ア 税・課徴金等
台湾では、公害防止等を目的として税・課徴金等の経済的負担措置の導入を積極的に検討しており、1991年(平成3年)には大気汚染防止法が改正され公害防止料金を賦課することができるようになった。
韓国では、規制基準を超えた排出に排出課徴金がかけられている。しかしながら、その水準が低いため企業は公害防止装置の設置を行わず課徴金を支払うという選択を行っている。
イ デポジット・リファンド制度
デポジットについては、韓国、台湾が制度を有している。
韓国では1991年(平成3年)に広範なデポジットシステムを始めたが十分なインセンティブがなく回収率は0.2%にとどまっている。
台湾では、ペットボトルの回収にデポジットシステムが使われている。4年目までに60%の回収率目標を掲げているが、3年目現在で41%となっている。
ウ 排出権売買
取引可能許認可については、シンガポールのCFCの輸入及び使用にかかる措置などがあるが、全体的には採用されていない。
エ 補助金、税制上の優遇措置等
台湾では、地方公共団体による廃棄物処理施設の建設や公害監視機器の取得などに広範な補助金が出されている。
韓国でも省エネ投資に対する税制優遇措置などが講じられている。
環境基金については、韓国でも排出課徴金を財源とした環境汚染防止基金を設置しており、公害防止機器投資への低利融資、公害健康被害者への補償を行っている。
差別課税については、タイで有鉛ガソリンと無鉛ガソリンの価格差をつけるための措置が採られている。
タイでは、現在クリーン生産工程技術の導入にまで低率関税措置を拡大すべく検討を行っている。また、電力企業の需要サイド管理計画(DSM)に基づくエネルギー節約措置に対し様々な補助を行うことが提案されている。
インドネシアでは、輸入排水処理施設の輸入税を軽減することを公表した。
? 東欧諸国
東欧諸国については、市場経済への移行過程にあることもあり、経済的負担を課す措置の導入事例がそのまま参考となるわけではないが、その活用状況は、国連による資料"THEUSE OF ECONOMIC INSTRUMENTS IN ENVIRONMENTAL POLICY IN CENTRAL ANDEASTERN EUROPE"によれば、次の通りとされている。
第4-3-3表にみるように東欧諸国においても、経済的負担を課す措置は様々な分野で活用されている。
ア 税・課徴金
(ア) 大気保全分野
チェコ及びスロバキアにおいては、中規模以上の産業発生源に対して、また、企業における小規模の発生源(ヒーティングシステム)に対して排出課徴金が課されている。前者は、監視官による確認が適宜行われる自己申請制度に基づき、歳入は国家環境基金を通じた大気汚染対策に使用される。後者は、固体化石燃料の種類に応じて課され、歳入は環境対策に使われる。
ポーランドでは、企業に対し、二酸化硫黄と窒素酸化物の直接排出に課徴金が課されている。違反した場合には、課徴金の10倍の罰金を課すことができる。
ハンガリーでは、新たな大気保全制度の導入の際に、大気汚染物質排出課徴金を導入する計画がある。
(イ) 廃棄物分野
・ 地方公共団体による使用者課徴金
ブルガリアでは、1951年(昭和26年)以降、廃棄物の処理に使用者課徴金が課されている。課徴額の計算は、廃棄物の発生量とは直接的には結びついておらず、また収入は、財政事情の厳しさから、廃棄物処理のみでなく公衆衛生や教育にも使われることが一般化している。
チェコでは、廃棄物の処理に課される使用者課徴金を1992年(平成4年)に大幅に引き上げた。プラハでは、1トン当たり14.53ECU(1993年)である。これにより、定量的な計測は困難であるが、廃棄物の量が減ったとされる。しかし、一方で不法投棄が増加したとされる。
・ 廃棄物処理課徴金
チェコ、スロバキア、ポーランドで廃棄物処理課徴金が見られる。
ポーランドでは、財源調達が目的であった。1992年(平成4年)には課徴金額の86%が支払われたが、1993年(平成5年)は、67%程度であろうとの予測がなされている。
(ウ) 水質保全分野
・ 排水課徴金
チェコでは、BOD、非溶解性物質、明白なアルカリ及び酸性物質等に対して許可制とともに排水課徴金が課されている。
ポーランドでは、財源調達目的からこの制度が導入された。1992〜1993年にかけて課徴金額の支払は半額程度であった。
ルーマニアでは、1991年(平成3年)から排水課徴金が導入されている。スロバキアでは、排水課徴金制度の導入によって、多量の排水を行っている企業が敷地内での排水処理を進めた等の報告がなされている。課徴金額は、毎年のインフレーション率を踏まえて調整されてる(第4-3-6表)。イ 排出権売買
ポーランドでは、ホージュッフ地区で試験的に排出権売買を行い、従来の方法よりも速く、少ない費用で成果をあげたが、より広範囲にその適用を増やすためには環境法の改正が必要とされている。
ウ デポジット・リファンド制度
チェコでは、ガラス制の飲料容器に対してデポジット・リファンド制度を適用している。回収率は70〜80%である。
ハンガリーでも同様の対象に対して、デポジット・リファンド制度を有している。
ポーランドでは、クリーム瓶、ビール瓶、ワイン用のボトル、ソフトドリンク用プラスチック容器が対象となっている(第4-3-7表)。