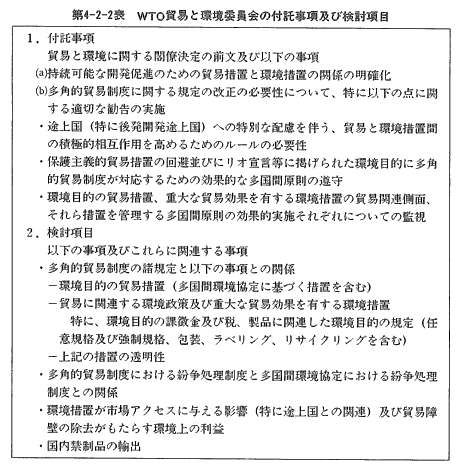
2 環境と貿易の相互支持化に向けた取組
(1) 環境と貿易の相互支持化に向けた国際機関等による取組
? GATT/WTO
GATT(関税及び貿易に関する一般協定)ウルグァイ・ラウンド交渉では、環境と貿易の問題は直接の交渉の対象ではなかったが、UNCEDの開催等を契機とする同問題に対する国際的な関心の高まりを反映して、環境関連事項についてもいくつかの重要な進展が見られた。まず、WTO(世界貿易機関)設立協定の前文では、生活水準の向上、完全雇用の確保等の従来の目標に加えて、環境の保護・保全及び持続可能な開発が新たに明記され、従来のGATT前文で「世界の資源の完全な利用」が目指されていたのが、WTO設立協定では「持続可能な開発の目的に従って世界の資源を最も適当な形で利用」することとされた。また、組織面では、新たに設立されたWTOの下に「貿易と環境に関する委員会」が1995年(平成7年)1月の第1回WTO協定一般理事会において設置された。同委員会は、WTO発効後2年以内に開催されることとなっている第1回閣僚会議に第4-2-2表に掲げる付託事項等について報告を行うこととなっており、今後、多角的貿易制度に関する規定の改正も含め検討が行われていくこととなる。また、ウルグァイ・ラウンドで合意・改訂された「貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)」等においても、一定の条件の下、環境保全のために必要な措置がとり得ること、例外的措置が認められること等の規定が置かれている。
? 経済協力開発機構(OECD)
OECDでは、従来より、「汚染者負担の原則(PPP)」等、環境と貿易に関連する基本的な考え方を示してきたところであるが、1991年(平成3年)以来、環境政策委員会と貿易委員会の間で合同専門家会合を設置して検討を行っている。1993年(平成5年)6月には、「貿易政策と環境政策の統合のための手続に関するガイドライン」がまとめられ、閣僚理事会で承認された。同ガイドラインは、()環境と貿易に関する政策決定の統合、非政府関係者との協議、情報公開の推進、()貿易及び環境に関する検討、審査及び事後点検、()越境的、地域的、地球規模の環境問題に対する国際協力、()紛争処理に際しての環境、貿易、科学等の専門知識の考慮、の4点について各国政府が従うべき指針を示し、手続面から環境と貿易の相互支持化を目指している。また、同ガイドラインとともに、今後の作業計画として、()貿易/環境政策の検討、審査及びフォローアップ方法、()貿易自由化が環境に及ぼす影響、()生産工程及び生産方法(PPM)、()環境保全を目的とした貿易措置の使用、()ライフサイクル・マネジメント(LCM)の概念と貿易、()環境基準の調和、()貿易及び環境に関する原則と概念、()経済的手段、環境補助金及び貿易、()環境政策、投資及び貿易、()紛争処理の10項目について分析・議論を進めていくこととされた。
その後、1994年(平成6年)の閣僚理事会での決定を受け、1995年(7年)の閣僚理事会には、上記の手続ガイドラインの実施状況及び実質的な結論を含む報告がなされることとなっており、OECDでの検討は、WTO等における検討の重要なバックグラウンドとなっていくものと考えられる。
? その他の国際機関等による取組
環境と貿易を巡る問題については、GATT/WTO及びOECD以外の国際機関等でもそれぞれの立場から積極的な取組が行われるようになってきている。
国連持続可能な開発委員会(CSD)では、1992年(平成4年)のUNCEDで採択された「環境と開発に関するリオ宣言」及び「アジェンダ21」で環境と貿易に関する国際的な基本認識が示されたことを受け、1994年(6年)の第2回会合では環境と貿易の問題についても検討がなされ、「貿易、環境及び持続可能な開発」に関する決定がなされた。同決定では、リオ宣言及びアジェンダ21の規定が確認されるとともに、自由貿易は持続可能な開発に大きな役割を果たしうること、環境保全上有害かつ貿易を歪曲している補助金の削減の必要性、環境コストの内部化及び経済的手法の活用の促進に努めること、GATT/WTOとCSDやUNEP、UNCTADその他の国際機関との緊密な連携の確保等が基本的視点として示された。また、今後の検討に当たって考慮すべき事項として、国ごとの環境規制の多様性には正当な理由があり、この多様性に基づく生産コストの相違が国際貿易の基礎をなすこと、環境保全に名を借りた偽装された保護主義の排除、環境基準及び規制の高いレベルでの調和を途上国へ配慮しつつ促進すべきこと、等の点が挙げられている。
国連環境計画(UNEP)及び国連貿易開発会議(UNCTAD)は、1994年(平成6年)2月及び11月に、先進国、途上国のハイレベルの出席者が率直に意見を交換しあう場として、「貿易と環境に関する非公式ハイレベル会合」を共催している。また、UNCTADにおいては、「貿易、環境及び開発に関するアドホック作業部会」を1994年(6年)5月に新たに設け、主に開発途上国の市場アクセスの改善の観点から、環境ラベリングや環境保全型商品について検討を進めている。
国際標準化機構(ISO)は、国際規格の標準化を通じ、物やサービスの貿易を容易にすることを目的に設立された非政府間機関であるが、1993年(平成5年)からは、環境管理に関する規格制定のための専門委員会(TC207)を設けて作業を行っている。同専門委員会の下には、環境管理システム、環境監査、環境ラベリング等の6つの分科会が設けられ、それぞれ完成目標年次を設定して検討が進められている。ISOの規格はいずれも任意のものであるが、事実上の国際標準として機能することから、環境と貿易という観点からは、手続面での国際的な調和を進める具体的な動きとして注目される。
この他、WWF(世界自然保護基金)等の環境NGOも環境と貿易を巡る議論の一翼を担っている。NGOの主張は多岐にわたるが、大まかにいって、環境コストの内部化の促進、貿易政策に対する環境面からの影響評価の実施、効果的な多国間環境協定が存在しない場合における一方的貿易措置の実施、生産工程の違いによる類似の産品の差別的取り扱いの承認、環境と貿易に関する検討の場(紛争処理過程を含む)へのNGOの参加の確保、南北間の公正な交易関係の構築等を含んでいる。
また、産業界においても環境と貿易に関する議論が行われており、例えば、世界産業環境会議(WICE)は1994年(平成6年)3月に「貿易と持続可能な開発:ビジネス展望」と題した報告書をGATT事務局に提出した。
? 我が国における検討
国際機関等による取組と並行して、我が国においても環境と貿易に関する検討が進められている。例えば、環境庁長官主宰による「地球的規模の環境問題に関する懇談会」では、約一年にわたり検討を行った結果、1995年4月に報告書を公表した。また、通商産業大臣の諮問機関である産業構造審議会の下にWTO部会を設置し、学識経験者等による議論を行っている。さらに、経済審議会世界経済委員会や大蔵省財政金融研究所等においても検討が進められ、その報告書で環境と貿易の問題を扱っている。
(2) 環境政策と貿易ルールとの調整
環境と貿易の相互支持化に向けた取組の中で具体的に大きな部分を占めるのが、環境政策と貿易ルールの調整である。GATT/WTO協定に代表される現行の貿易ルールの基本的枠組みは、環境問題が今日のような地球的広がりを見せる以前に構築されたものであることから、環境政策が貿易に与える影響に留意しつつ、地球環境問題を中心として、環境保全の観点を適切に貿易ルールの中に位置づけていくことが課題となっている。
? 多国間環境協定における貿易措置と貿易ルール
地球環境問題の進展とともに、多国間環境協定の中で貿易措置が重要な役割を担う例が見られるようになっている。有害廃棄物や野生生物の国際取引等、貿易が直接環境問題の要因となっているような場合には貿易措置が有効であり、先に見たようにバーゼル条約やワシントン条約が締結されている。また、オゾン層の破壊等、貿易が直接の原因とはいえない場合にも、条約へのフリーライディング(条約締約国の対策努力に対するただ乗り)を防止し、条約の締結を促す等条約の実効性を高める観点から、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」等では、条約非締約国に対する貿易制限措置を設けている。
この非締約国に対する貿易制限措置が、貿易ルールにおける最恵国待遇(GATT締約国やWTO加盟国間での差別的待遇を禁じる原則)との関係で特に問題となるが、条約の実効性の確保の観点から、一定の場合に非締約国に対する貿易制限措置が有効であることについては大方の合意があるものと考えられ、また、これまで、GATT上で具体的な紛争となったこともない。しかし、今後新たに多国間環境協定を締結する場合を含め、非締約国に対する貿易措置を含む多国間環境協定の法的安定性を確保するとの観点からは、そのような多国間環境協定の貿易ルールに対する位置づけを明確にしておくことが必要であると考えられており、そのための様々な方法が提案されている。その方法は大きくは、GATT25条のウェーバー(免除)条項を適用してケース・バイ・ケースで例外を認める方法と、予めGATT/WTO協定に抵触しないための条件を定めておく方法の二つに分けられるが、それぞれ長所、短所があり、この問題はWTOにおける今後の主要検討事項の一つである。
? 環境基準等とその調和
貿易政策上の観点からは、特に各国間で製品規格にばらつきがある場合には、生産者は各国の定める規格に応じて様々な製品を生産しなければならず、効率的でない。このため、貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)では国際規格が存在する場合には、正当な理由がある場合を除くほか、国際規格を用いることとされており、環境に関連した製品規格もこのルールに従うこととなる。これに対して、排出基準等の環境関連の実質的な基準や規則等(以下、「環境基準等」という)については各国の環境の状況や発展段階等に応じて異なりうるものであることから、各国間で環境基準等を調和させることは必ずしも必要でなく、また、現実的とは言えない面がある。したがって、先進国が途上国に対して一方的に高い環境基準を強制することは不適当であると同時に、高い環境基準等が直ちに非関税障壁として問題視されるべきではない。
しかし、各国が独自の環境基準等を採用しうることを基本とした上で、基準等の調和が必要と考えられる場合もある。酸性雨のような越境問題あるいは地球規模の問題の場合には、一国の環境基準等の高低が結果として他国に影響を及ぼしうることから、このような場合には、何らかの形で基準等の調和が図られることが望ましい。また、国内環境問題の場合であっても、1972年(昭和47年)のOECDの「環境政策の国際経済的側面に関する指導原則」の中で確認されているように、環境保護を強化するとの観点からは、他国より緩やかな基準を十分に正当化できない場合には、基準をより厳格化する方向へ努力することが望まれる。
環境基準等の調和の方法としては、全く同一の基準にそろえる「統一」、最低基準や段階的基準の設定、お互いの制度、基準等を認証し合う「相互認証」等の考え方がある。ただし、実際に環境基準等の内容について相互認証を行うことについては、科学的知見の充実など克服すべき課題も多く、基準等の内容ではなく、試験方法や評価方法等の手続面での調和がまず有用であるとの意見もある。
? PPM規制と貿易
ライフサイクルアセスメントの観点から、製品自体に加え、環境面から製品の生産工程に着目した製品規制が重視されるようになってきており、「PPM(Processesand Production Methods:生産工程及び生産方法)規制」と呼ばれている。PPM規制とは、具体的には例えば、オゾン層破壊の原因物質であるCFCで洗浄されたコンピュータチップ、持続可能でない森林経営の下で生産された木材、イルカを混獲して捕獲したマグロ等、環境保全的でない生産方法で生産された製品を規制の対象とするものである。
PPM規制が国内で生産される製品を対象として用いられる場合には、貿易上特に問題となるわけではない。しかし、PPM規制が貿易措置と結びつけられたり、貿易措置を伴わなくとも外国の製品が国内市場において一定のPPMの遵守を要求される場合にはPPMの域外適用の問題を生じ、貿易ルールとの関係で問題が生じうる。貿易ルールは、自国の領域外の環境問題に対処するためのPPMに基づく一方的貿易制限措置には否定的であるが、その理由としては、製品の製造方法を輸入国側で特定することは一般に困難であり、その運用が恣意的、保護主義的になりやすいこと、国による生産方法の違いは貿易上の比較優位をもたらす源泉の一つであり、賃金水準の違いなどと同様と考えられていること等が考えられる。また、自国の環境の状況等に従って設定されたPPM規制を環境の状況等が異なる他国に適用することは、環境保全上の観点からも望ましくない可能性がある。このような点から、自国の領域外の環境問題に対処するためのPPMに基づく一方的貿易措置は一般的には適当でないといえよう。しかし、地球環境問題に対応していくためには、多国間でPPM規制の調和が必要な場合も考えられる。また、多国間環境協定の下でPPMに基づく貿易措置が一定の役割を果たす可能性もあり、実際、モントリオール議定書は、オゾン層破壊物質を用いて生産された製品(製品に当該物質を含まないものに限る)について非締約国からの輸入制限を行う可能性を規定している。ただし、1993年(平成5年)の締約国会議では、現段階ではその実施可能性はないと判断された。
? 貿易に影響を及ぼしうる環境保全上の措置
環境基準等と同様、各国が独自に必要な環境保全措置をとることは基本的に認められているが、環境保全措置の中には貿易への影響を及ぼしうるものがある。ここでは、具体的な環境措置として、環境ラベリング、包装・リサイクル規制、税・課徴金等の経済的手法について見てみよう。
日本のエコマーク等の環境ラベリング制度は、消費者の自主性に訴える任意の環境保全措置としてその有用性が認められ、現在、インド等の開発途上国を含む20か国あまりで導入が進んでいる。しかし、環境ラベリング制度は適切に制度が構築されなければ、輸出に対する事実上の非関税障壁となりうるとして、特に開発途上国からの懸念が高まっている。また、最近の国際的潮流として、環境ラベルの認定基準に、製品の製造から廃棄までの環境負荷をトータルでみるライフサイクルアセスメント(LCA)的な手法を用いる傾向が強くなってきており、輸入国のPPM規制に合わせて製品の製造を求められる場合には、事実上のPPM規制の域外適用が生じる可能性が指摘されている。
また、包装・リサイクル規制は、廃棄物に伴う環境負荷の低減のため、使用可能な包装材の規制や包装材・容器の回収義務等を定めたり、製品への再生品混入率を義務づけたりするものであり、国内業者に比較して対応が困難と考えられる海外の事業者にとっては事実上の非関税障壁として働くのではないかと懸念を持つ者もいる。
環境ラベリング制度や包装・リサイクル規制を実効あるものとしていくためには、貿易への影響についても配慮することにより、これらの環境措置が貿易上の問題とならないようにすることが重要である。そのためには、海外の事業者に対するこれらの措置に関する透明性の確保等、そして、特に開発途上国に対しては、これらの制度に対応するための技術的、資金的協力が重要となる。
環境に係る税・課徴金等の経済的手法と貿易の関係についても主要な検討課題の一つとなっている。例えば、二酸化炭素排出抑制のため単独で炭素税等を導入すれば、自国製品の国際競争力の低下をもたらし、競争力の低下を嫌う企業が海外に生産拠点を移すことによって、いわゆる「炭素リーケージ」等が起こるのではないかという指摘もある。GATTでは、一般的に輸出国と輸入国の税率の差異による競争力上の影響を緩和するための措置として国境税調整(輸出に際しての免税及び輸入に際しての課税)が存在するが、ウルグァイ・ラウンド交渉の結果、具体的にエネルギー、燃料等の中間投入物が国境税調整の対象として明示されるにいたり、環境に係る税・課徴金などの経済的措置が国境税調整の対象となる余地が生まれた。ただし、具体的に調整されるべき税額の計算の技術的困難性等も指摘されており、今後、国境税調整がかかる経済的措置の効果に与える影響等とも合わせ、理論的及び実証的に更なる検討が必要となっている。
? NAFTAにおける環境規定
以上のように、環境保全と貿易ルールを巡る問題については様々な論点が提出され、現在もOECDやWTOなどにおいて議論が続けられている。このような中で1992年(平成4年)12月に成立した北米自由貿易協定(NAFTA)及びその環境補完協定は地域的な自由貿易の推進と環境保全との間の相互支持的な関係を生み出すための試みとして注目される(第4-2-3表)。
NAFTAでは、環境重視の立場から、いくつかの面でGATTルールよりも踏み込んだ規定を設けている。第一に、NAFTAでは、ワシントン条約、バーゼル条約等の多国間環境協定の貿易措置規定とNAFTAの規定とが不整合となった場合には、代替手段が存在する場合にはNAFTAの規定に最も抵触しないものを選択するとの条件の下、前者が優先することを明記している。第二に、環境基準の設定に関して、NAFTAの「衛生・植物衛生措置(SPS)」規定は、人、動物及び植物の生命・健康の保護のために、各締約国は「より厳しい措置」をとることを認めており、基準の調和を図る際にはその「水準を引き下げることなく」行われるべきとしている。なお、PPM規制についてはGATT以上の規定は置かれていない。第三に、紛争処理手続きの面では、NAFTA加盟国間で、環境・健康・安全措置等に関する紛争が起きた場合、被提訴国は、WTOではなく、より多くの環境保護規定を有するNAFTAの下での紛争解決手続きが選択可能である。また、NAFTAでは、NAFTA上の環境措置に関する紛争処理に関して、訴えを起こした国が、相手国のNAFTA違反を立証する責任を有する。さらに、NAFTAの紛争解決パネルでは、独立の科学的審査機関の設置や専門家の協力を得ることにより、紛争処理に係る環境問題の専門的情報が受け取り易くなっている。この仕組みは、ウルグァイ・ラウンドにおいて、GATTの紛争処理パネルに外部の専門家の意見を取り入れる仕組みを設けた際のモデルとなった。
また、NAFTAでは、協定本体とは別に、1993年(平成5年)9月に環境協力に関する補完協定が設けられ、紛争処理パネルの支援及びNAFTAの環境影響に対する公衆の問合せ等の窓口等を行う環境協力委員会、米・メキシコ国境地域の環境インフラ整備を財政面から促進する北米開発銀行等について規定している。さらに、NAFTAにおいては、その策定過程において貿易関係部局のみならず、環境関係部局が交渉に携わったこと、NAFTAがもたらす環境影響について調査・予測が行われ、報告書が公表されたこと等が特筆に値しよう。
(3) より包括的な取組による環境と貿易の一層の相互支持化に向けて
持続可能な開発に向けて環境と貿易を相互支持的なものとしていくためには、以上見てきたように、環境政策が貿易へ与える影響に配慮しつつ、環境保全の観点を適切に貿易ルールに位置づけることにより、必要な環境政策を講じていくための基盤を整備していくことが一方で重要である。他方、貿易に携わる各主体が適切な環境政策を実施、あるいは環境への配慮を徹底させることにより、環境コストの内部化を進め、環境問題が貿易上の問題として顕在化することを未然に防止していくためのより包括的な取組を推進していくことが重要である。
このような観点からまず求められるのは、環境政策を十分に行う余裕のない開発途上国に対して積極的な環境協力を行っていくことであろう。開発途上国といっても、その発展段階は様々であり、その状況に応じた協力を行っていく必要がある。例えば、人口増加、貧困、環境悪化の悪循環に陥っている多くの後発開発途上国については、この悪循環を断ち切るためにも経済発展の実現は重要であり、そのために貿易が果たす役割は大きい。ただし、経済発展が環境の改善につながるというのはマクロ的な視点であり、経済発展の段階で生じうる公害や自然破壊等のマイナスの環境影響の発生を最小限に抑える必要がある。また、ある程度開発の進んだ途上国に対しては、その環境対策に対する対処能力の向上のための資金的、技術的支援を行っていくことが求められる。これら開発途上国による環境政策を促進する上で、一定の場合に貿易措置が有効な場合もあろうが、その際にも、モントリオール議定書等に見られるように、貿易措置とともに資金供与や技術移転を総合的に組み合わせることにより、一層の効果が期待できる。
また、貿易活動の具体的主体である企業等による環境保全に向けた自主的な取組が一層促進されることが重要であろう。このような観点から、昨年12月に閣議決定された環境基本計画においても、事業者の役割として、技術移転等の国際協力を進めるとともに、海外における事業活動や貿易に際して環境配慮を行うことが明記された。また、市民レベルの取組も環境と貿易の問題に対して重要な役割を果たしうる。例えば、先進国の消費者がコーヒー等の農産物等を、途上国の生産者と直接取引することにより、途上国の生産者の自立を支援するための費用、低農薬で栽培するための手間賃等を含めた形で国際相場の数倍程度で購入する「フェアトレード」という動きがイギリスやドイツ等のヨーロッパ諸国、そして我が国においても広がりを見せているが、市民レベルで環境コストの内部化を進め、足下から環境と貿易の相互支持化を促進するものとして注目される。また、より一般的に、市民の環境と貿易に関する理解が深まり、市民の消費性向が環境保全型に移行していくことにより、環境と貿易の関係の改善が期待される。環境にプラスの影響をもたらすような製品の市場(グリーン・マーケット)の拡大が進めば、環境保全型の製品の製造、貿易が促進され、環境と貿易の問題に間接的にプラスの影響がもたらされると考えられることから、市民の環境意識の向上等により、このような動きを促進していくことも重要であろう。
さらに、環境保全目的の一方的貿易措置の行使が具体的な貿易上の紛争となる場合が多いことにかんがみれば、特に地球環境問題に対しては多国間での合意形成を積極的に推進することにより、紛争の未然防止に努めることが重要であろう。また、OECDの手続ガイドラインを踏まえ、環境、貿易両政策の関係当局の連携や政府と民間部門との意見交換を一層密にすることにより、国際レベル及び各国内レベルの両面にわたって手続面から環境政策、貿易政策の統合を進めていくことも重要である。
世界の持続可能な発展という観点から環境と貿易の問題に取り組んでいくためには、農林水産物のような一次産品をどのように扱っていくかも、重要なポイントの一つとなろう。すなわち、農林水産物等は、一般的に工業製品と比べてより環境に密着した商品であり、その生産基盤たる環境が持続的かつ健全に保たれて始めて、これら一次産品の生産・採取が可能となる。また、その生産基盤たる環境は、一次産品を生産・採取するという機能の他に、例えば森林では、水源かん養、野生生物の生息地、二酸化炭素の吸収・固定、快適な環境の提供等のいわゆる外部経済としての様々な複合的機能を有している。これらのことから、一次産品は環境コストの算定が特に複雑であるが、それに加えて、供給の価格弾力性が低く、価格変動の幅が大きいため、価格に環境コストを内部化することが難しい市場構造を持っている。このような特性から、農産物については、ウルグァイ・ラウンドの農業合意においても工業製品とは異なる配慮がなされ、食糧安全保障と並んで環境保護の必要性が非貿易的関心事項とされた。農林水産物等については、その環境との深いつながりに十分に考慮しつつ、国際貿易の中でこれら一次産品を適切に扱っていくための検討が今後とも必要とされよう。
これらの点にかんがみ、我が国としては、OECDやWTO等における環境と貿易の議論に今後とも積極的に参画・貢献するとともに、自ら適切な環境政策を積極的に進めていく必要があろう。また、同時に、貿易を促進するに当たっては、各国がそれぞれの社会・経済状況等を踏まえた上で、必要な環境政策を十分に講じる必要があるという認識を世界共通のものとしていくことが重要である。我が国は、このような認識に立って、途上国等が自国の環境問題へ対処し環境コストを内部化していく能力を向上できるように支援を強化するとともに、地球環境問題に対処するための多国間協力の形成に向けて積極的なリーダーシップを発揮していくことが重要であろう。その際、第2章で見たように、特に我が国と環境面、経済面ともに深いつながりを有するアジア・太平洋地域を中心として、取組を進めていくことが求められる。また、この地域で自由貿易の推進を図ろうとしているアジア太平洋経済協力(APEC)の枠組みの役割も念頭に置くことが望まれよう。