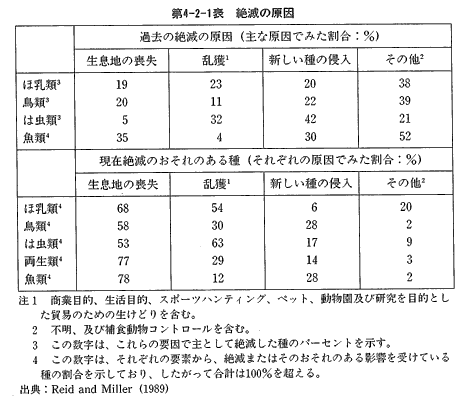
1 環境と貿易を巡る議論
(1) 貿易が環境に及ぼす影響
貿易は、多くの場合、それ自体が環境問題の本質的な原因ではないと考えられるが、現象面を見ると、貿易は需要と供給を国際的に結びつけるという機能を通じて、直接または間接に、環境に対してプラスの影響もマイナスの影響も及ぼすことがある。ここでは、その影響をいくつかの側面に分けて見てみることとしよう。
? 商品取引に直接伴う影響
商品取引に直接伴う環境へのマイナスの影響としては、有害廃棄物や有害化学品などの環境汚染物質が取引される際に、環境上適正な取り扱いがなされない場合、あるいはタンカーからの原油流出等不慮の事故が起きた場合における深刻な環境汚染が挙げられる。特に有害廃棄物については、1980年代後半に入って先進国から開発途上国への輸出が社会問題化する事例が見られるようになったため、1989年、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が採択され、環境保全の必要上から有害廃棄物の貿易が条約の管理下に置かれている(第5章第4節(3)参照)。
また、絶滅の恐れがある野生生物及びそれらの野生生物からつくられる製品も国際的に取引されている。種の絶滅の要因は生息地の破壊、乱獲等数多く存在するが、サイ角やオウムなどのように、外国の買い手の存在が乱獲の要因となる場合もある。1989年(平成元年)以前に絶滅したいくつかの種の絶滅の原因は乱獲(国際取引によるものには限らない)にあったとされる(第4-2-1表)。このため、国際取引が主たる乱獲の要因になっている場合には、貿易面からの管理も有効であることから「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」が締結されている(第5章第6節(2)ウ参照)。
さらに、世界的な熱帯林の減少については、統計上、熱帯木材生産全体のうち国際貿易に入る割合はそれほど高くはなく、全般的には貿易がその減少の主たる要因とはなっていないとされる。しかし、熱帯木材の貿易は、場合によっては熱帯林の減少に密接な関係があり、国際熱帯木材機関(ITTO)では、西暦2000年(平成12年)までに持続可能な形で生産された木材のみを貿易の対象とするとの目標を定め、熱帯木材生産国での環境への悪影響を及ぼさない持続可能な開発を促している(第5章第5節(3)ア参照)。
他方、環境へのプラスの影響としては、環境保全型の技術や環境保全型製品の取引があげられる。これらの技術や製品の普及をもたらす上で貿易は大きな役割を果たし、環境の保全に寄与し得る。環境保全技術市場は、今後大きく成長すると見られており、現在の市場規模が2,000〜3,000億ドル程度であるのに対し、西暦2000年時点にはその規模は6,000億ドル程度に拡大するとの予測もある。各国の現時点での環境保全機器の貿易収支は第4-2-2図のようになっている。
? 貿易規模の拡大による影響
貿易活動の活発化は一般に世界全体の経済規模を拡大させる。例えば、OECDによれば、ウルグァイ・ラウンドの終結に伴う富の増加分は年間2,000億ドル(2002年時点)に上ると推計される。しかしながら、その環境への影響となると必ずしも明らかでない。貿易を通じた所得の増加は、一方で、特に開発途上国において、環境保全のための資金的精神的余裕を生み、環境改善効果をもたらしうるとの研究結果がある。また、所得の増加は貧困、人口増加、環境破壊の悪循環を断ち切るとの観点からも必要である。他方、貿易の拡大は環境資源の使用を地球大に拡大し、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会活動を促進させるとの見方がある。
貿易規模の拡大は、また、輸送部門からの環境負荷を増大させる要因となる。ECのタスクフォースは域内市場の統合により、SO2及びNOxの排出量が2010年までに現在のレベルより8〜9%増加すると予測しているが、その主要部分は輸送部門からの排出によるとしている。
? 貿易による生産・消費構造の転換に伴う影響
貿易は国際的に生産・消費活動の位置と密度を変えることで環境に影響を及ぼす。例えば、東南アジアにおいては、我が国等におけるエビの需要の増加を背景として、貴重な生態系を育むマングローブ林のエビの養殖池への転換が大規模に進んだことが指摘されている。環境庁の試算によれば、タイにおいては、1979年(昭和54年)頃より急速に減少が進み、1989年(平成元年)までに1961年(昭和36年)のマングローブ林賦存量の約3割にあたる12万haがエビの養殖池拡大のために失われたと見積もられる(第4-2-3図)。
また、開発途上国からは、現行の国際貿易体制が先進国に有利なようにできており、それに基づく生産・消費の構造が持続可能な開発を妨げているとの主張もなされている。そして、その背景には、先進国による生産・輸出補助金が本来、国際的に競争力を持ち得ない農産物等に不当な競争力を持たせ、過剰な生産を助長することがあるとされ、それが、欧米の先進国においては土壤劣化等の環境影響を引き起こす可能性があるとともに、開発途上国においては環境コストを内部化できないような低い水準での一次産品輸出に依存せざるを得ない状況を生み出しているとされる。また、開発途上国の発展のための資金が、先進国市場へのアクセスを制限する関税・非関税障壁によって確保しにくくなっている可能性のあることが指摘されている。これらの点については、アジェンダ21でも言及がなされ、補助金削減についてはウルグァイ・ラウンドにおいて一定の成果を見るにいたった。
他方、資本の自由な移動が認められる場合には、企業は高い環境対策費用を避けて、環境規制の緩い国に投資を行うことにより、汚染集約的な企業の移転が進み(「ポリューション・ヘイヴン」の創出)、いわゆる「公害輸出」といった状況が生じるのではないかとの懸念が存在する。これに対し、これまでの実証的研究によれば、環境基準の高低は企業立地に際しての多くの勘案事項の一つに過ぎず、直接投資と環境基準の間に有意な連関は認められないとされている。ただし、北米自由貿易協定(NAFTA)の交渉過程においては、環境NGOからのアメリカ企業のメキシコへの移転とそれに伴う環境悪化への強い懸念に対応するために、NAFTA本文に、締約国が投資促進のために環境基準を切り下げない旨の規定が盛り込まれた。
(2) 環境と貿易の基本的関係
一般的に貿易は、比較優位の原則に従って、それぞれの国が他国より有利に生産できるものをより多く生産・輸出し、他国より非効率的な分野の生産を縮小・輸入することにより、最適地に最適規模の生産を配分し、世界的に効率的に生産を進める上で大きな役割を有するとされる。貿易が有するこのような性格は、資源の非効率的利用に伴う環境負荷を低減させ、環境容量の小さな国への環境負荷の高い産業の立地を回避させる等の点で、先に見た貿易がもたらす環境へのプラスの影響とも合わせて、環境保全の推進に寄与するものである。
ところが現実には、これまで見てきたように、貿易が環境破壊をもたらし、それを助長している場合がある。その要因は経済学的に見ると、天然資源の利用、環境汚染防止等の環境コストが商品やサービスの市場価格に適切に反映されないままに取引が行われ、不適切な環境利用が促進されることにある。そのため、各国において必要な環境政策を講じることにより、これらの環境コストが市場価格に内部化されれば、貿易を含む経済活動と環境破壊の直接的な関係を改善することが可能となる。したがって、国際的、国内的に適切な環境政策を実施することにより、環境コストの内部化を積極的に推進していくことが、貿易の基礎となる資源基盤を維持し、自由貿易を維持強化するという観点からも本質的に重要である。
しかしながら、経済的手法の活用等、環境コストの内部化を目指した環境政策は、環境コストの内部化が不十分な現状の下での「競争力」を変更する可能性があるものとして、自由貿易に対する障害として誤ってとらえられる場合がある。また、国際取引が主たる要因となって絶滅の危機に瀕している野生生物の保護等の場合のように、直接、貿易規制が必要な場合もある。このような場合には特に、環境政策と貿易政策の調整を通じて環境と貿易の問題に対処することが必要である。
国際的な検討の方向は、環境保全と貿易が相互に及ぼす影響を分析しつつ、持続可能な開発の実現に向け、いかに環境政策と貿易政策を相互支持的なものとしていくかに向けられている。貿易の環境へのマイナスの影響を最小にし、プラスの影響を最大にするために必要な環境政策のあり方、及び環境政策上の要請と自由貿易の要請が衝突する場合の調整が課題である。