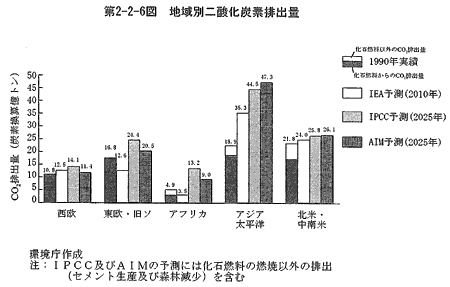
2 アジア・太平洋地域における環境負荷の高まりとその影響
人口の増加やエネルギー消費の増大を背景として、アジア・太平洋地域の21世紀の環境はどのように展望されるのであろうか。包括的な将来像を描くことは困難であり、今後の取組に待つ部分も大きいが、ここでは、モデルを使ったシミュレーション結果を中心として同地域の21世紀の環境を展望してみることとしよう。
(1) 二酸化炭素排出量の増大とその影響等
将来の二酸化炭素排出量については、世界の多くの機関によって予測がなされているところである。ここでは、その予測の例としてIPCC、OECD/IEA(経済協力開発機構/国際エネルギー機関)、環境庁国立環境研究所等によって開発された「アジア・太平洋地域温暖化対策分析モデル」(AIM)による推計について見てみたい。
第2-2-6図は、特段の排出抑制対策をとらなかった場合の各モデルによる、二酸化炭素排出量の推計結果を地域別に示したものである。IPCC及びAIMは2025年時点、OECD/IEAは2010年時点での推計である。IPCC及びAIMについては、1990〜2025年までの一年当たりの平均経済成長率を世界全体で2.9%、アジア・太平洋地域については3.9%と見込み、同じくOECD/IEAでは1991〜2010年の期間について世界全体で2.9%、アジア・太平洋地域で4.1%と見込んでいる。なお、OECD/IEAの推計はエネルギー起源の排出のみであり、IPCC及びAIMの推計はエネルギー起源の排出にセメント生産及び土地利用の転換(森林減少)からの排出を含む。
これによると、各推計に共通する傾向として、アジア・太平洋地域からの排出量が突出しており、同地域において大幅な二酸化炭素排出量の増加が見込まれていることが分かる。例えば、IPCCの推計によれば、世界全体では、二酸化炭素排出量は2025年まで年平均1.5%で増加するのに対し、アジア・太平洋地域からの排出量は、年平均2.5%と1.7倍の伸び率で増加すると見込まれている。その結果、世界全体の排出量に占めるアジア・太平洋地域のシェアは1990年時点での25%強から2025年には36%程度に増加するものと予想される。特に中国、インド、東南アジア諸国、韓国等のNIEs諸国における排出量の伸びが大きいと考えられ、中国については、将来的には、現在、世界の二酸化炭素排出量の約5分の1を排出する米国を越えて世界一の二酸化炭素排出国になると推計されている。
このように高度成長と人口増加を背景に著しい二酸化炭素排出量の増加が見込まれているが、アジア・太平洋地域は排出抑制のポテンシャルも大きい。適切な対策を併せて実施していけば、経済成長を図りつつ、同時に二酸化炭素等の排出抑制を果たしていける可能性もある。このような可能性について、AIMを用いた以下のような共同研究が進められている。AIMは、IPCCの参照モデルとして位置づけられており、温室効果ガスの排出、それに伴う気候変化、そしてその影響という一連のプロセスを統合して分析することが可能な政策評価のための総合モデルである。
第2-2-7図は、中国エネルギー研究所(ERI)と国立環境研究所との間で、AIMにより中国の鉄鋼部門からの二酸化炭素排出量の予測をした結果である。市場経済化が進み、効率の高い技術が導入されるが、経済成長は外生的に与えた値が維持されるとした場合、2000年以降に標準ケースに比べ約2〜3%程度の二酸化炭素排出量が抑制される可能性があることが分かった。さらに、導入された市場メカニズムを活用して省エネ技術の普及を促進させれば、中国の鉄鋼部門からの排出量の伸びが大幅に緩和される可能性が示唆され、このような促進策の分析が続けされている。また、第2-2-8図は韓国エネルギー経済研究院(KEEI)及び韓国環境技術開発院(KETRI)と国立環境研究所が共同で、同じくAIMを用いて、韓国の民生部門からの二酸化炭素排出量を予測したものである。それによると、太陽熱温水器等の太陽熱利用機器や断熱材の大幅な導入と普及によって、民生部門からの二酸化炭素の排出量を安定化させる可能性があることが示唆された。また、韓国においても鉄鋼部門からの二酸化炭素排出量の分析が進められているが、これまでの分析によれば、今の経済成長が続く限り排出量は増加し続ける見込みであり、革新的な政策や技術の検討の必要性が明らかとなった。
もとより、これらの可能性は、外生的に与えた経済成長や政策の実行可能性等、いくつかの前提の下で試算されたものであり、現実にこれらの前提が満たされるかどうかについては不確実な要因が多いが、アジア・太平洋地域での持続可能な発展を考えていく際に、このような具体的な方策を関係機関とともに協力して追求していくことは極めて意義が大きいといえる。
次に地球温暖化がアジア・太平洋地域に与えうる影響について海面上昇及び農産物の生産量への影響の面から見てみよう。
アジア・太平洋地域は、沿岸部の居住人口、社会資本の集中度合いも高く、また数多くの島嶼国を抱えることから地球温暖化に伴う海面上昇の影響が特に懸念される地域である。特に平均海抜が数メートル程度しかないモルジブや太平洋のサンゴ礁からなる島嶼国については、国家の存続そのものが危ぶまれる。そのような事態を回避するために、堤防のかさ上げ等の対策が必要となるが、対策費用の面からもこれら島嶼国は大きな負担を強いられることとなる。IPCCの試算によると、例えば、モルジブやツバル等の島嶼国においては、1メートルの海面上昇が今後100年の間に起きた場合、1年当たり、これらの国のGNPの14%にも上る対策費用が必要となると推計されている。これら島嶼国は地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出という点ではほとんど寄与していないため、その対策は各島嶼国の個別の問題としてではなく、世界全体の対策の枠組みの中で検討されていく必要があろう。
第2-2-1表は、アジア地域の各国において地球温暖化の影響を受けて、農産物の潜在生産量がどのように変化するかをAIMを用いて推計したものである。それによると、米については、中国やブータン等生産量が増加すると見込まれる国もあるものの、小麦やトウモロコシについては世界的に大きな生産地となっている中国やインド等の国で大幅な生産量の低下が見込まれる。例えば、中国は1991年度においては、世界の小麦の2割弱を生産する世界一の小麦生産国となっているが、地球温暖化の影響により、冬小麦については15%、春小麦については21%程度生産量が減少する可能性がある。また、インドについても世界の小麦の1割弱を生産しているが、地球温暖化の影響により、冬小麦で55%の大幅な生産量の減少が予測される。今後、人口増加等に伴い食糧需要の大幅な増加が見込まれることを勘案すると、このような地球温暖化の影響による穀物生産の減少は世界の食糧供給への影響を増幅させることが懸念される。第2-2-9図はアジア地域の冬小麦の潜在的生産量の変化を地理的に示したものであるが、赤からオレンジで表現される生産量の減少が見込まれる地域が、中国東北部、モンゴル、中央アジア、中国東南部、インド東北部からバングラデシュにかけて広がっているのが分かる。我が国については、米と冬小麦は微増、春小麦は微減、温帯性のトウモロコシについては5割の減少などが予想される。
(2) 二酸化硫黄排出量の増大
次に地域的な大気汚染、そして国境を越えた影響を及ぼす酸性雨の両方の原因物質として重要な二酸化硫黄の排出予測について見てみよう。二酸化硫黄の排出量の予測についてはどの程度の排出抑制対策を見込むかによって大きく変わってくるが、経済成長率をアジア・太平洋地域平均で4.1%、人口増加率を同1.4%とし、特段の対策をとらなかった場合を想定すると、アジア・太平洋地域からの排出量は、1990年から2025年の間に約5,200万トンSO2/年から約2億トンSO2/年へと3.8倍程度増加する可能性がある。二酸化硫黄の影響はその排出源の位置に大きく関わることから、中国における地域別排出強度(単位面積当たりの排出負荷)を人口移動を加味して地図上に表してみたものが第2-2-10図である。それによると、1985年に比べ2025年には北京、上海、重慶といった主要都市における排出強度が軒並み高くなっている一方、チベット等においては人口の減少を背景として逆に排出強度が下がるとみられる。
第2-2-11図は、中国の蹴る二酸化硫黄の地域別排出強度とその環境下に居住する累積人口を省を単位として予測したものである。前提として、人口については1985年に10.4億人であったものが、2025年には15.4億人となり、経済成長率を2025年までは年5.3%、それ以降は3.9%と置き、各種エネルギーサービス需要の増大によりエネルギー消費量が1985年の25EJから2050年には170EJ(一人当たりではほぼ現在のOECD諸国の水準)に押し上げられるとした場合を想定している。1985年における二酸化硫黄の排出強度は最大72トンSO2/(km2年)程度であり、半分の人々の住む地域(以下50%地域という)では、2.5トンSO2/(km2年)以上である。このような値の下でも、第1節で見たように中国の一部の都市部においては既に二酸化硫黄による大気汚染は深刻な状況にある。なお、我が国において最も大気汚染が激甚であった1960年代後半の単位面積当たりの二酸化硫黄排出強度(全国平均)は13トンSO2/(km2年)程度であった。人口の移動を考慮しなかった場合には、2025年には排出強度の最大値は160トンSO2/(km2年)を越え、50%地域(人口7.7億人に対応)の排出強度も15.7トンSO2/(km2年)に達すると考えられる。さらに、2050年には50%地域(人口8.1億人に対応)で20トンSO2/(km2年)程度となると推定される(図a)。さらに、これに人口移動を考え合わせると、50%地域の排出強度はあまり変化しないが、それより高い排出強度地域で著しい伸びが見られる(図b)。例えば、縦軸が2.5億人である排出強度は、2025年には人口移動がない場合50トンSO2/(km2年)であるのが、人口移動を考慮した場合には、70トンSO2/(km2年)と1.5倍程度の違いが生じ、都市への人口集中が大気汚染の影響をさらに大きなものとすることが予測される。
(3) 熱帯林の減少
熱帯林については、国連食糧農業機関(FAO)によると、1990年末の推定では、全世界で17億5,600万haが賦存しており、その52%が南アメリカ・カリブ海諸国、30%がアフリカ、18%がアジア・太平洋地域に存在している。地球上では毎年1,540万haに上る減少が生じているとされ、このうち、他の地域と比べ残存森林面積が少ないアジア・太平洋地域では毎年390万haの熱帯林が失われており、年平均の減少率では1.1%と最も高率となっている。熱帯林の減少の原因としては、農地への転換、過度の薪炭材の採取、不適切な商業伐採、過放牧等数多くの原因が指摘されているが、これまでの各種の研究結果によると、人口密度の増加と熱帯林の減少との間には、農地への転換等を通じて強い相関関係が存在することが示されている。第2-2-12図は、この点に着目し、国連による寿命や出生率等の予測を前提として各国の将来人口をAIMにより推計し、これに基づき将来の熱帯林の減少割合を推計してみたものである。これによると、人口増加を要因として、アジアにおいては2015年頃までは、毎年200万ha程度の割合で減少が続いたのち、徐々に減少面積が縮小して2050年には年間減少面積は100万ha程度、2100年には20万ha程度となると推計される。この結果、1990年から2100年の間にアジア地域の熱帯林賦存量は4割強減少し、3億1,100万haから1億8,000万haになると予測される。さらに、熱帯林の減少には、大規模開発等、直接人口増加と結びつかない要因も大きく作用することから、実際の減少面積は更に広大なものとなると想定される。減少面積自体は南米地域、アフリカ地域と比べれば小さいものの、残り少ない残存面積等の点にかんがみれば、その減少は、アジア・太平洋地域の熱帯林が果たしている地球規模の気候調整機能、生物多様性の保全機能、二酸化炭素吸収・固定機能等に大きな影響を及ぼすと考えられ、その保全を図っていくことが急務である。