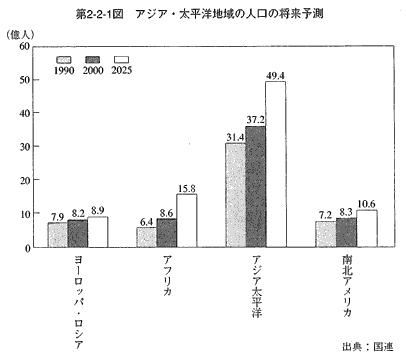
1 地球規模の環境負荷の増大につながるアジア・太平洋地域の社会経済活動の高まり
まず、環境への負荷を増大させる最も基礎的な要因である人口、経済規模及びエネルギー消費量について、今後これらがどのように変化していくと考えられているのか見ていくこととしよう。
(1) 人口の増大と都市集中
人口は人間活動の総量を表す基盤的な指標であり、その増加は様々な経路を通じて環境問題と深く結びついている。アジア・太平洋地域には、1990年現在、31億人あまりの人々が生活しているが、国連の中位推計によれば、2025年には49億人に達すると予測されている(第2-2-1図)。この間の同地域の人口の年平均伸び率は1.3%であり、アフリカ地域の2.7%を大きく下回るものの、もともとの母体が大きいため、絶対的な人口増加数では世界最高である。この結果、アジア・太平洋地域の全世界の人口に占める割合も約60%程度の高水準で維持される。同地域の人口増加の寄与率では、インド、中国の割合が高く、増加が見込まれる約18億人のうちこれら両国で5割強を占める。人口の増加は自然資源の消費と不用物の排出の増大を通じて多くの環境問題を深刻化させるほか、結果的に環境問題の影響を受ける人口の増大をもたらすことを通じて、場合によっては、環境難民等の発生が促され、社会的な不安定性を増すことも考えられる。これらの影響はアジア・太平洋以外の地域にも波及的な影響を及ぼしうるものである。
人口増加と相まって、アジア・太平洋地域においては、人口の都市集中が一層進展すると見られている。国連によると、アジアでは2025年には全人口の約6割が都市居住者となると予想される。都市における人口増加率は、全人口の増加率の2倍に達し、逆に総農村人口は減少が予想される。東アジアでは2005年頃に農村人口と都市人口が逆転し、2025年には総人口の63%が都市生活者となると考えられる。また、南アジアにおいても2025年頃には農村人口と都市人口が逆転すると推定される(第2-2-2図)。この結果、1990年〜2025年の間に都市人口は3倍に増加すると考えられる。巨大都市の数も急速に増加すると見込まれ、国連人間居住センター(UNCHS)によれば、この地域における人口400万人以上の都市の数は2000年には28に、さらに2025年には52まで増加し、都市人口全体に占める巨大都市居住者の割合も増加するとされる。都市への人口集中は、下水道や廃棄物処理施設、公共交通機関等に一層の負担を強いることとなり、これらの社会資本の増強に十分に対応していくことができない多くの都市では、大気汚染や水質汚濁等の環境問題の一層の深刻化が予想される。また、都市人口の増加に伴い、都市周縁部の無秩序な拡大が進み、都市近郊の農地や自然資源の減少が懸念される。
現在のところ、貧困層は農村においてより多く見られるが、都市人口の増加の結果、都市の貧困者数が増加すると見込まれる。現在でも、インドのボンベイやデリー、カルカッタといった都市においては人口の5割に上る人々が正式な住居を持たずに生活している(第2-2-3図)。ESCAPによると、ボンベイにおいてはスラム人口が全都市人口に占める割合が1976年から1981年の間に41%から51%に増加し、これが2000年には75%に達するだろうと予測される。スラムや河川・運河沿い、線路沿いといった場所に多く居住する貧困層は、上水道や下水道等の基礎的社会資本を欠き、安全な水の確保や衛生サービスを受けることも難しいことから、都市環境の悪化を真っ先に受ける立場にある。
(2) 経済規模の拡大
次に、人口とともに人間活動の規模を計る基礎となる経済規模が、アジア・太平洋地域において将来どの程度拡大すると見込まれるのか、世界銀行及び気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の推計に従って見てみよう。1990年現在、世界のGNPは約20兆ドルとなっており、その2割強に当たる4.4兆ドルをアジア・太平洋地域が占め、南北アメリカ、西欧に次ぐ経済規模を有している。それが、2025年には世界全体のGNPは約55兆ドルに拡大すると予測され、その中でアジア・太平洋地域については1990年代に4.2%、2000年以降2025年までについても平均3.8%という他の地域に比較して高い成長率が見込まれることから、世界全体に同地域が占める割合も3割に増加し、2025年には南北アメリカと肩を並べる経済圏に成長すると考えられている(第2-2-4図)。なお、最近の東アジア地域等における高成長を背景として、将来の経済成長を上方修正する動きが見られる。例えば、世界銀行は、本年4月、新たな経済成長の見通しを示し、東アジア地域については、今後10年間(1995年〜2004年)の年平均成長率の見通しを7.7%に引き上げている。
(3) エネルギー消費量の増大
経済成長と人口増加はエネルギー消費の大幅な増加をもたらすと予測される。エネルギー消費は、二酸化炭素や硫黄酸化物等の排出に最も直接的に関わるものである。エネルギー消費量の将来推計には多くのものがあるが、例えば、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の標準推計によれば、現在のエネルギー政策の枠組みが不変であるとすると、アジア・太平洋地域の2025年の一次エネルギー消費量は255.5EJ(Exajoules=10
18
J)/年になると予想され、これは1990年の消費量の約3.2倍に相当する。世界全体の伸びは2倍程度にとどまると予想されることから、世界全体のエネルギー消費にアジア・太平洋地域が占める割合も23%(1990年)から36%(2025年)に拡大し、同地域の消費量の増加が非常に大きなものであることが分かる(第2-2-5図)。さらに燃料別で見た場合には、消費量の多い方から石炭、石油、天然ガスという順位は変わらないものの、1990年と比べ石炭及び天然ガス消費量がそれぞれ2.8倍、4.3倍に増大するのに対し、石油消費量は1.8倍にとどまる。特に石炭は絶対的な消費量では58.5EJ/年と最も増加すると見込まれており、石炭の単位当たり炭素含有率は平均して石油よりも3割強高いことから二酸化炭素排出量を増大させる要因となる。逆に、天然ガスの単位当たり炭素含有率は石油より3割弱低いことから、石油から代替する限りにおいて二酸化炭素排出量の抑制に寄与する。他の燃料では水力、原子力とともに、バイオマス燃料や太陽エネルギーの大幅な導入が見込まれている。
なお、二酸化炭素排出量等と関わりの深いアジア・太平洋地域のエネルギーの需給見通しについて、現在、総合エネルギー調査会において検討がなされている。