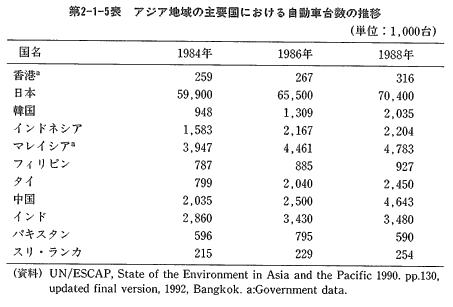
2 アジア・太平洋地域各国の環境の現状
中国は、ここ数年めざましい経済発展を続けており、工業化・都市化に伴い、全国各地で様々な環境問題が顕在化している。韓国では、都市への人口集中、急速な工業化等に起因する大気汚染、水質汚濁等が問題となっている。インドネシアでは、ジャワやバリ等の国土の中央部に位置する島嶼部において、人口増加や開発に伴う人口流入により水質汚濁等の環境問題が生じている。マレイシアでは、工業化・都市化に伴い水質汚濁や有害廃棄物等の環境悪化が起こっている。フィリピンでは、人口増加と都市化に伴う水質汚濁・大気汚染・廃棄物等の公害問題と森林減少・土壤劣化等の問題がともに起っている。タイでは、特にバンコック首都圏における工業化・都市化による水質汚濁・大気汚染や、森林減少・土壤劣化等の環境問題が顕在化している。
以下のアジア・太平洋地域の環境の状況を表す数値及び一部の記述については、特に出典を明示する場合を除き、中国については1993年(平成5年)の中国環境状況公報により、その他の国(ベトナムを除く)についてはESCAP加盟国にて開催されたアジア・太平洋地域の環境の状況に関する会合における各国報告書に基づくものである。環境の状況を表す数値及び一部の記述については、中国、韓国、インドネシア、マレイシア、フィリピン、タイ等の国々の状況及び取り上げた環境問題に限られるものではないが、アジア・太平洋地域の環境問題の特徴を考察する上で参考となることが期待される。なお、各国報告書のデータ等からの本文中の数値については、出典等の違いにより図表中の数値と必ずしも一致するものではない。
(1) 大気汚染
大気汚染の問題については、ジャカルタ、ソウル、マニラ、バンコック等の都市部において、自動車排出ガスによる汚染が大きな問題とされている(第2-1-5表)。また、工業地帯等においても、工場からの排出ガスによる汚染も進行している。
中国では、工業及び民間用の主要なエネルギー消費である石炭の燃焼に伴い発生する二酸化硫黄、ばいじん等による大気汚染が問題となっている。1993年(平成5年)の全国都市における総浮遊ふんじん(TSM、粒径100um以下)の年間日平均値の範囲は108〜815μg/m
3
であり、74都市のうち38都市が年間日平均値の国家二級基準(人間の健康を守り、また都市の動植物が長期にそこに存在しても何ら悪影響がない)を超え、特に吉林市、万県市、太原市、蘭州市等の値が著しいとされる。降下ばいじんは、73都市の年間月平均値4.0〜83.5トン/km
2
・月で前年より顕著に増加し、二酸化硫黄の77都市の年間日平均値の範囲は8〜451μg/m
3
で、前年に比べてほぼ横ばいとなっている。二酸化硫黄が国家二級基準を超えた都市は77都市中20.0%を占め、前年よりやや増えているとされる。窒素酸化物の77都市の年間日平均値は10〜147μg/m
3
で、前年に比べてほぼ横ばいとなっている。
韓国では、近年自動車台数が急増しており、1993年(平成5年)末現在、国内の全自動車の52%がソウルを含む6大都市に集中しているとされる。このため、自動車排出ガスが窒素酸化物、炭化水素等の主要な排出源となっており、全国の一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、二酸化硫黄の発生量のうち、自動車によるものはそれぞれ約65%、約83.3%、約43.8%、約6.1%となっているとされる。また、工業地帯と都市部では、光化学スモッグ現象が酸性雨とともに観測されている。
インドネシアの大気汚染問題は、ジャカルタ、バンドン、スラバヤなどの大都市で起こっており、ジャカルタとバンドンの場合、産業、自動車、ごみの燃焼等を発生源とするふんじん、二酸化硫黄、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素が発生しており、両都市では自動車がふんじんの主な発生源となっているとされる。
マレイシアでは、大気汚染物質の総発生量のうち自動車排出ガスが占める割合は、環境局によると炭化水素で約90%、窒素酸化物で約70%、全浮遊ふんじん(TSM)で約50%であり、工場、発電所、廃棄物の焼却場等の固定発生源からの大気汚染物質の排出も問題となっている。このほか、首都クアラルンプール等を含むクランバレー地域では、山火事、自動車排出ガス、工場の排煙、廃棄物の野外焼却等の影響と言われるが原因は特定されていないヘーズ(haze、もや)が発生し、近年社会問題となっている。
フィリピンの大気汚染については、その発生源は主に自動車と大気汚染防止対策が不十分な工場であるとされ、1987年(昭和62年)の国連開発計画と環境天然資源省の調査によると、大気汚染物質排出量に占める割合はそれぞれ60%、40%となっている。都市部、特にマニラ首都圏では、ディーゼル車や日本からの輸入中古車等の自動車が首都圏に集中しており、大気汚染が問題となっている。1993年(平成5年)のマニラ首都圏の大気汚染物質排出量は、粒子状物質(PM)124,929トン、窒素酸化物79,910トン、一酸化炭素577,197トン、二酸化硫黄88,456トンとなっている。
タイでは、バンコック首都圏における自動車排出ガスによる大気汚染が問題となっている。その背景には、1990年(平成2年)の全国自動車登録台数の4分の1以上がバンコックに集中し(自家用車が約30%を占め、その数は全国の自家用車の4分の3)、世界で最も深刻な交通渋滞の一つを引き起こしていることが挙げられている。一酸化炭素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、鉛が主な大気汚染物質であるが、特に鉛による大気汚染は、沿道住民等の健康被害を引き起こしていると言われている。
(2) 酸性雨
中国では、1993年(平成5年)の酸性雨による影響が一部地域に見られている。73都市の降水の年平均pH値の範囲は3.94〜7.63であり、平均pH値5.6以下の都市が49.3%を占め、重慶市や杭州市などの各地域では、酸性雨の出現頻度が70%以上を示しているとされる。また、四川省峨眉山の冷杉や重慶市郊外の南山地区の馬尾松など、酸性雨による森林の被害の問題化も指摘されている。第2-1-6表は、1991年(3年)から92年(4年)までの貴州省の降水pH値の観測結果である。
(3) 温室効果ガス
大気中の二酸化炭素その他の温室効果ガスは、農業及び産業革命以前の状態の1.2倍以上に達するほどのレベルで過去100年以上にわたり増加し続けてきた。1990年(平成2年)のアジア・太平洋地域の環境の状況に関するESCAP報告書によると、1980年代の初めには、ESCAP諸国は、世界の二酸化炭素排出量の4分の1であった。また、産業及び生物的発生源による二酸化炭素排出量への寄与は、それぞれ75%、25%と見積られている。第2-1-5図によると、アジア・太平洋地域の二酸化炭素排出量は、1950年(昭和25年)から1985年(60年)にかけて急激に増大し、1985年(60年)までにアジア・太平洋地域の排出量は西欧の排出量を超えていることがわかる。アジア・太平洋地域諸国の二酸化炭素排出は、二酸化炭素情報分析センター(CDIAC)によると、中国が最も多く、次いで日本、インド、韓国、インドネシア、タイと続いている。
(4) 騒音
中国では、急速な工業化に伴い人口が都市に集中し、建設工事の激増及び自動車台数の増加によって都市における騒音問題が激化している。1993年(平成5年)の都市の騒音問題は引き続き顕著であり、測定の行われた39都市の平均等価騒音レベルは51.7〜72.6dB、そのうち5都市が60dB以上で、道路交通騒音は44の都市中36都市が70dBを超えているとされる。都市騒音を原因別に見ると交通騒音が27%、生活騒音が47.6%、工場その他の騒音が25.4%となっている。
韓国では、建設中のソウル〜釜山間の高速鉄道が、騒音・振動の問題を引き起こしているとともに、航空の便や路線の増加により、航空機による騒音が新たな環境問題となっている。タイでは、都市における交通機関、工場建設作業場からの騒音が問題となっていると言われている。主な騒音源としては、バスやトラック等の大型車、古く整備不良の乗用車、オートバイ、水上タクシー、最近の建設ラッシュが挙げられている。
(5) 水質汚濁
水質汚濁の問題は、ほとんどの国で最も大きな問題の一つとなっており、都市周辺の河川・湖沼が、未処理の生活排水、工業排水により汚染されている(第2-1-6図)。
中国では、公共用水域において各種の水質汚濁が見られている中、1993年(平成5年)の全国の廃水の排出総量は355.6億トン(1992年より3.0%減少)となっている。また、工業系廃水の排出量は219.5億トン(同6.2%減少)で、そのうち化学的酸素要求量は622万トン(同12.5%減少)、重金属は1,621トン(同6.9%増加)、ヒ素は907トン(同4.0%増加)、シアン化合物は2,480トン(同30.7%減少)、揮発性フェノールは4,996トン(同22.2%減少)、石油類は71,399トン(同9.7%増加)などとなっている。大河川の水質状況は良好とされているものの、都市部を貫流する水域では水質汚濁が高まっており、七大水系と内陸河川の水質評価に係る重点127地点の測定結果では、主要な汚染物質としてアンモニア性窒素、過マンガン酸塩消費量、生物化学的酸素要求量及び揮発性フェノール等が見られている。また、一部の支流でも、総水銀、銅、ヒ素化合物等による汚染も見られている。特に、松花江、遼河、海河流域の水質汚濁は深刻となっている。そのほか、湖では富栄養化に加え、一部の湖で総水銀汚染が深刻とされ、また、近海海域の油汚染や富栄養化、主要都市の地下水の汚染が起こっているとされる。銅、亜鉛、カドミウム等の重金属については、生物体内でその含有量が高くなっている。さらに、赤潮の発生も1993年(5年)には19件認められている。
韓国の1993年(平成5年)末の総排水量は一日当たり2,300トンであるが、そのうち処理されているものは約39%であり、工場や家畜場からの排水処理は十分なものではないとされている。漢江、洛東江等の4大河川のBODは第2-1-7表のとおりである。パルダン湖等の貯水池を含む6水源は、河川の上流では比較的良好とされているが、水源の67%は河川の下流にあるため、都市や工業地域からの汚染の影響を受けているとされる。このように経済の成長に伴い、工業排水中の重金属や有害物質が増加しているほか、農薬残渣の河川への流入により貯水池や海域の富栄養化が起こっているとされる。また、朝鮮半島の周辺に位置する黄海、南海に注ぎ込む河川により、閉鎖性水域では水質汚濁が起こっているとされている。
インドネシアでは、農村部を含む全国で、有機物と細菌類による水質汚濁が問題となっており、例えば、ジャワ島西部では、し尿による大腸菌濃度が970〜1,700MPN/100mlの範囲で検出され、また、ジャワとその周辺の河川では、有機汚濁によりBODやCODが国内の環境基準を上回っているとされる。家庭ごみや厨芥類による汚染も水質汚濁の主要な原因とされ、ジャボタベック地域では、人口の38.5%が河川に直接ごみを捨てており、河川への環境負荷は1日当たりのBODで約120トンにのぼるとされる。また、主要な河川水域の水質への環境負荷の50%は産業廃棄物によるものとされ、ジャワ島の北部沿岸では、工業中心地での深刻な水質汚濁が起こっているとされる。今後さらに、工業が発展し、またジャワ島に集中することになれば、このような水質汚濁は、適切な措置が取られなければ一層悪化する可能性があるとされる。
一方、インドネシアの海洋汚染で最も脅威となっているのは、産業廃棄物や一般廃棄物、川からの汚泥沈澱、船舶や沖合いの開発等からの油流出であり、例えば、ジャカルタ湾岸では、重金属による汚染も確認されている。ジャワ海での油汚染は海面上に層となっており、タンジュンプリオク港、ムアラカランの火力発電所及びシラチャプ精製所周辺の沖合いでは、その様相を毎日観測することができると言われている。
マレイシアでは、1992年(平成4年)の調査によると、水質指標(BOD、COD、NH3N、SS、pH)において、87河川中7河川の水質汚濁が深刻となっており、55河川に汚染が見られ、残りの25河川は汚染されていないとしている。
フィリピン国内の水環境における主な環境問題は、表流水の沈泥や汚染及び地下水の塩水化とされている。都市中心部近くの河川や湖においては、下水処理施設の普及が不十分であるため、生活排水による水質汚濁が問題となっており、一日一人当たりのBOD排出量は25〜53gとなっている。例えば、マニラ首都圏のパシグ川のBODの年平均値は20〜40mg/lとなっている。また、国内最大のラグナ湖は、汚水浄化槽からの一般廃棄物、農薬や肥料を含んだ農用地からの流出水及びマニラ首都圏の986の工場からの排水の影響を受け、また、河川の土手等からの土壤流出により水深平均約2mの浅い湖となっているとされる。フィリピンでは鉱業が主要な経済活動となっているが、鉱滓の堆積は深刻な環境問題とされ、シアン化合物や水銀のような副産物による水質汚染及び電気めっきやなめし皮工場などの中小工場からの有害廃棄物の水路への流入が問題となっている。また、海域の水質も下水、工業排水、鉱滓、船舶からの油、農用地から流出した肥料及び残留農薬により急速に汚染が進んでいるとされ、例えば、マニラ湾では下水が十分に処理されないまま直接流出している状況にあると言われている。
タイでは、国土を北から南に流れ、多くの支流と広大なデルタを形成してタイ湾に注ぐチャオプラヤ川の水質が、バンコック首都圏を流下する過程で悪化しているとされる。一日当たりのBOD排出量は183,634kgとなっている。また、1991年(平成3年)の工業排水におけるBODは525,235トンで、そのうち、29%は砂糖産業(153,740トン)、19%は紙パルプ産業(102,711トン)、18%はゴム産業(96,526トン)からとなっており、現在、70%相当の工場排水が処理されていると言われる。また、河川等の水質の悪化は工場排水だけに起因するものでなく、生活排水や農業排水にも起因しているとされ、下水処理施設の不足等による生活排水のたれ流しは、タイの河川水質の脅威となっている。
ベトナムでは、水質汚濁は都市部で特に問題になっている。主要な都市においては、し尿及び生活排水の大部分は未処理のまま排出されているため、河川、運河及び湖沼等の水質汚濁が起こっている。浄化槽設備は少なく、また充分に機能していない場合も多いため、ハノイ市とホーチミン市などでは、側溝等の開放型排水路や地下下水管から水路や河川等に直接流入しているところもあると言われている。
(6) 廃棄物
第2-1-8表においては、ESCAP加盟国地域の主要な都市について、廃棄物の排出と処理の状況を表している。
中国では、廃ガス、廃水、固体の3種類の廃棄物を「三廃」と呼んでいる。工業系固体廃棄物の大部分は未処理で都市郊外に堆積していたり、河川、湖沼、海岸に排出していると言われている。1993年(平成5年)の工業系固体廃棄物の排出総量0.2億トンのうち、0.1億トンが河川に排出されており、また、毎年の工業系固体廃棄物の累計堆積量は59.7億トン、堆積用地が52,052haで1992年(平成4年)より2,471ha減少したとされる。
韓国では、1992年(平成4年)の韓国全体の一日の廃棄物排出量は144,536トンとなっており、一般廃棄物の排出量は約75,000トン/日、産業廃棄物は約70,000トン/日となっている。一般廃棄物と産業廃棄物の処理は主に埋め立てにより処分されているが、地方公共団体にある602の処分場のうち358の処分場は3年以内に一杯になると予想され、産業廃棄物の中で重金属や有害物質を含む廃棄物は、固体化や焼却された後で埋立処分が行われている。
マレイシアでは、マレー半島で排出される有害廃棄物が工業発展に伴い増加し、その排出量は年間約28万m
3
となっている。主な発生源は、金属表面加工、電気めっき、化学、印刷、包装業となっているとされる。
フィリピンでは、廃棄物による汚染は人口集中が進み経済活動の活発な都市で起こっている。廃棄物問題は、不十分な廃棄物収集と処分システムによるとされている。1992年(平成4年)のマニラ首都圏では、約5,400トン/日、一人当たり0.63kgの廃棄物が発生しており、一日に排出される廃棄物のうち63%しか収集されていないとされるが、収集されたものの72%は都市及びその周辺において公有地等へのオープンダンピングとして処理されている。また、収集されない廃棄物は、焼却、スカベンジャーによる回収・再利用及び河川水系への投棄が行われている。産業廃棄物では、特に電子及び電気めっき産業からの廃棄物中に鉛及び水銀が見られている。マニラ首都圏には、全国15,000社の企業の2分の1以上が集中している。また、毎日、鉱業により250,000drymetric tons(DMT)の鉱滓が生産されており、その50%はセブ島とネグロス島の間のタニョン海峡の沿岸に積まれ、近くの農地を汚染するため、特に北フィリピンで社会問題となっていると言われている。
タイでは、工業の発展に伴い化学物質の使用が増加しており、環境中に排出された場合に人間の健康に影響を及ぼしうる有毒な化学物質が多くの廃棄物に含まれているとされる。1991年(平成3年)では、200万トンの有害廃棄物が発生しており、その72%が重金属の固体又はヘドロの状態となっているとされる。この重金属の90%は金属産業によって排出されていると言われる。
(7) 森林減少
アジア・太平洋地域諸国の森林面積を見てみると、中国では、1989〜93年(平成元年〜5年)の第4回全国森林資源調査によると、約1億3,370万ha(前年比277万ha増)で、国土面積に占める割合は13.9%(0.3%増)となっている。インドネシアの森林面積は、1984年(昭和59年)のコンセンサス土地利用計画によると14,400万haで、そのうち1,900万haは生物多様性の保護地域、3,000万haは流域の保護地域となっている。マレイシアの森林面積は3,280万haの国土面積の約72%となっている。フィリピンでは、1972年(昭和47年)の森林面積は1,040万haで、国土の約34%を占めたが、1992年(平成4年)には590万haとなっている。タイの森林面積は、30年前には国土の約50%以上であったが、1979年(昭和54年)には33%、現状では約28%、1,500万haより少なくなっているとされる。また、王立森林省の調査によると、1989年(平成元年)の植林地は70万haとなっている。
また、国連食糧農業機関(FAO)の資料によると、インドネシア、タイ、マレイシア、フィリピン等では、1981年(昭和56年)から1990年(平成2年)の間に著しく森林が減少している(第2-1-9表)。熱帯地域での森林減少の原因については、非伝統的な焼畑耕作、過度の薪炭材採取、不適切な商業伐採及び過放牧等が挙げられ、その背景には、人口増加、貧困及び土地制度等の社会経済的な背景など様々な要因が指摘されている。
例えば、ESCAPの環境の状況に関する会合に提出されたフィリピンの報告書によると、「フィリピンでは、人口圧力及び貧困によって脆弱な土地での耕作の増加及び農地への人口流入が起こり、その結果、急速な森林減少、野生動植物種の減少及び土壤の生産力の低下をもたらしてきた。森林減少の自然及び人的な要因として、森林火災、不法伐採、人口流入、非伝統的な焼畑耕作、害虫や病気等が挙げられる。森林の減少・劣化は、先祖伝来の土地からの移動、持続可能な森林の開発や流域の管理がもたらす経済的利益の喪失、管理不可能な季節的洪水による人命や財産に対する損害など、社会経済へ悪影響を及ぼしてきた」としている。
一方、タイの森林減少の主な原因には、農地への転用、管理がなされない状態での伐採が挙げられている。森林減少の割合は1960〜1970年代は年間3%、1980年代は2%、1988年(昭和63年)以降は0.3%であり、1988年から森林伐採は公式に禁止され、森林減少の割合はかなり減っているが、少量の不法伐採が未だに行われているとされる。また、国家森林保全法により保護されている森林も、自給農民の侵入を受けて減少しているとされる。
(8) 土壤劣化・砂漠化
アジア・太平洋地域においては、土地劣化や砂漠化も問題となっている(第2-1-10表)。
中国では、1989〜93年(平成元年〜5年)の第4回全国森林資源調査によると、全国の草原で砂漠化・土地荒廃、塩類集積、アルカリ化が進んでいるとされ、約9,000万haで土地荒廃が深刻な状態となっている。また、それは利用可能な草原面積の3分の1以上を占め、牧草の平均生産量は、第3回調査(1984〜88年)結果に比べて30〜50%の減少となっている。全国で汚染された田畑は1,000万haに達しており、そのうち灌漑用水の汚染の被害面積は330万ha、酸性雨とフッ素汚染を主とする大気汚染の影響は約530万ha、固体廃棄物やごみ、汚泥により農用地でなくなった田畑は90万haとなっている。こうした環境汚染による年間食糧減産分は1,200万トンと見積られている。また、中国林業部によると、砂漠化による影響は約3億3,270万ha、全国土面積の約34%に及び、およそ4億人の人々が砂漠化の影響を受けていると言われている。砂漠化の影響を受けている面積のうち、表土が吹き飛ばされる風による侵食の影響は約1億5,330万ha、流水による浸食の影響は約1億7,940万haとなっている。
韓国では、農業の生産性を上げるために有毒な農薬の使用と化学肥料の使用を増加させた結果、農用地が劣化してきているとしている。化学物質と肥料の使用増加は生態系や食物連鎖に影響を及ぼし、人間の健康を脅かしているとされている。
フィリピンでは、急速な人口増加が国内の生産性の高い土地の利用を促し、脆弱な生態系への影響、土壤侵食や塩類集積、土壤生産性の低下、受け継がれた資源の喪失などを引き起こしてきたとされる。少なくとも22の地方の土地はひどく侵食されており、1992年(平成4年)に中度から強度に侵食された土壤劣化の面積は1,360万haに及ぶとされている。また、ESCAPの環境の状況に関する会合に提出されたフィリピンの報告書によると、「農地においては、土壤侵食、塩類集積、農薬の誤使用により土壤が劣化しており、非農地への転換は最も生産的な農地の喪失を引き起こしている。農業生産を高めるために化学肥料や農薬が使用されているが、技術者や装置が不足しているために、残留農薬や肥料が十分に監視されていない状況にある。さらに、非伝統的な焼畑耕作等の不適切な土地利用及び、不適切な森林伐採と薪の過剰採取による斜面での森林減少は、農地侵食の主要な原因となっている。安定した土地所有権がなく労働力や資金力のない貧困な農民は土地の改善や栄養保持へのインセンティブを持たないため、非伝統的な焼畑耕作が行われている」としている。
タイでは、土壤劣化、酸性化、塩類集積が国内の農地の50%に影響を及ぼしているとされる。ESCAPの環境の状況に関する会合に提出されたタイの報告書によると、「適切に土地を管理する資金とインセンティブを持たない農民の不安定な土地所有が問題となっており、農地の40%以上が不法な土地所有によって占められている。タイでは土地の未所有、農村の貧困、森林への農民の侵入の問題があり、800〜900万ha相当の森林が土地なし農民によって侵入を受けている。また、タイの農業の急速な成長に伴い、土壤侵食、洪水、干魃(かんばつ)及び塩類集積の要因となる大規模な森林減少が環境問題となってきた。森林の減少の根底には貧困と収入の格差の問題があり、これは、他の多くの開発途上国で同様に見られることである」としている。
(9) 地盤沈下
中国環境保護局の調査によると、主要都市のほとんどで地下水の過剰採取が見られ、中国全土で地盤沈下が報告された都市は45都市に及ぶとされている。タイでは、首都バンコックにおいて、1970年(昭和45年)以来4,550km
2
の広域で最大累積沈下量1.6mを超える沈下が生じている。このほか、インドネシアのジャカルタなどで地下水のくみ上げによる地盤沈下が報告されている。
(10) 自然災害
中国では、1993年(平成5年)に局地的なものを除き、大規模な洪水災害は発生しなかったが、華南地区には台風が7回上陸しその損失が大きかったとされている。また、森林火災による被害面積は2.9万haとなっている。ESCAPの環境の状況に関する会合に提出されたフィリピンの報告書によると、「フィリピンの国土は、自然災害を受けやすく、自然や環境の損失による経済への影響が深刻な問題となっている。毎年、平均19の台風が到来し、台風がもたらす大量の降雨による洪水が植生を失った森林、山地、丘陵、平原の浸食等を引き起こしたり、また、ピナツボ火山の噴火により農地や養殖池に被害が出るなどの生態系への影響が出ている」としている。タイは、8月から10月にかけての雨期の間に通常洪水が起こるモンスーン地帯である。また、毎年森林地帯の約21%が森林火災の影響を受けているとされる。マレイシアで自然災害として脅威となっているのは洪水であり、土地作物が深刻な影響を受け、マレー半島では、国土面積の約12%が影響を受けているとされる。
(11) 海洋環境
中国の水産資源は、揚子江等の採卵場、越冬場が水質汚濁の影響を受け、衰退しつつあるとされる。揚子江のヒラコノシロ、松花江の大白魚が絶滅の危機にあり、浙江省では汚染で放棄された養場の面積が2.4万haに達したとされている。1993年(平成5年)には、全国の沿海でエビの養殖に感染性の病害が広がり、被害面積は約11.2万haに達したとされる。このため、エビの生産量が12万トン以上減少し、経済損失は35億元と見積られている。
マレイシアの沿岸域においては、魚類の過剰採取、海洋汚染、沿岸浸食、珊瑚の破壊、特にマレー半島の西側沿岸でのマングローブ地域の破壊などにより海洋環境の悪化が引き起こされているとされる。また、フィリピンの海洋環境における主な環境問題は、マングローブ林の劣化及び他の土地への転換、汚染によるサンゴ礁の破壊、破壊的な漁法の実施、持続可能性を超えた魚類の過剰採取及び赤潮の発生であるとされている。さらに、タイ沿岸の自然資源の減少は、マングローブ林の伐採、エビの養殖、鉱業から排出される沈澱物、深度のある港の建設、観光、サンゴ礁での爆発物を使った漁法によって起こっているとされる。
(12) 野生生物
中国では、人口の増加圧力による生息地の減少、剥製や薬品収集のための狩猟等により、トラ、ユキヒョウ、クチジロジカ、キンシコウ等の動物や韓国ゴヨウマツ、ドラゴンモミ等の植物が絶滅の危機に瀕していると言われている。これに対し、中国は自然保護区を設定しており、1993年(平成5年)末では766ヶ所(うち国家級自然保護区は77ヶ所)、総面積6,618.4万haで国土面積の6.8%を占めている。
韓国の野生生物には、8,000種の動物と総種数14,000種の植物が存在しているとされる。韓国では、1960年代から様々な開発が森林地域における種の減少と環境汚染をもたらし、結果として、南北朝鮮間の非武装地域を除いて、多くの野生生物が絶滅の危機に瀕しているとされる。
インドネシアの生物の多様性を保護することは、世界だけでなくインドネシアにとっても、きわめて重要なこととされている(第2-1-11表)。動物種の合計は30万種を下らないが、多くの動植物の種の減少が深刻な問題となっている。現在、絶滅の危機から動植物を保護するため、72種類の哺乳動物、346種類の鳥類、17種類の爬虫類、17種類の植物が法律で保護されている。また、インドネシアではコモドドラゴン等の固有種も多いとされている。
マレイシアは、野生生物の生息地が広く多様であるため、野生動植物の種類が極めて豊富となっている。マレイシアだけでも、60,000種のガや蝶に加えて、14,500種の顕花植物、20,000種の昆虫、10,000種の無脊椎動物が存在すると推測されている。現在、国立公園内の野生生物と鳥類の保護区は149万haで、新たに142万haを保護区とすることが検討されている。
フィリピンでは、地上の生態系をみると、8,000種の土着の顕花植物、約4,000種の菌類や苔類等が存在するとされる。また、2,500種の野生動物には、196種の哺乳動物、950〜975種・亜種の爬虫類と渡り鳥含む同数の鳥類があり、11種の野生生物が絶滅の危機に瀕し、6種の哺乳動物、12種の爬虫類、49種の鳥類の生態が脅かされていると考えられている。
タイでは、森林の伐採の影響及び農業や過去30年間の開発プロジェクトによる自然水資源の使用により、多くの野生生物が減少してきたとされる。1960年(昭和35年)に制定された野生動物保全保護法により現在保護されている地域は約236万haとなっている。しかし、貧困への根本的な問題対策が取り組まれておらず、野生生物の取引が大規模に行われているため、密猟が現在も続いているとされる。