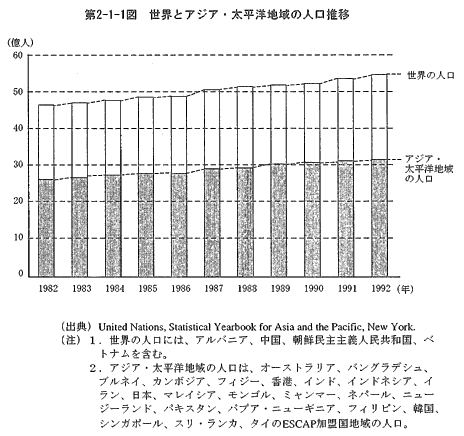
1 世界の中のアジア・太平洋地域
(1) 経済の高成長性と多様性
世界の人口は、国連の統計資料によると、1992年(平成4年)で約54億8千万人であり、このうちアジア・太平洋地域の人口は約31億5千万人と世界全体の半分以上の割合を占めている(第2-1-1図)。一方、アジア・太平洋地域の経済規模は、1991年(平成3年)のGDPで3兆4,810億ドル(一人当たりのGDPで2,001ドル)で、世界のGDP総額の約6分の1を占め、また、1991年(3年)のエネルギー生産については、世界の生産量は11,427百万石炭換算トン、アジア・太平洋地域の生産量は2,353百万石炭換算トンで、世界のエネルギー生産の約5分の1を占めている。これらは同地域の経済成長のポテンシャルの大きさを示唆しているものと考えられ、実際、1993年(5年)の世界の実質GDP成長率は2.3%であったのに対し、ESCAP加盟国地域の開発途上国におけるGDP成長率は、国連の推定によると6.7%と高成長を維持している。
アジア・太平洋地域では、地域内のすべての国が常に同様の経済発展をしているわけではなく、例えば、先進工業国の日本の他、OECD/DACの分類(1994年12月末現在)によると、高所得国の台湾及びシンガポール、高中所得国の韓国及びマレイシア、低中所得国のタイ、低所得国のインドネシア、フィリピン及びベトナム、そして、中国及びインドと多様な発展段階にある国々で構成されている(第2-1-1表)。特に、東アジア成長経済では、貿易自由化及び外資規制の緩和等の外向きの経済政策の下で貿易、直接投資が活発化し、輸出志向型の経済成長を遂げてきた。アジアNIEs(アジア新興工業経済群)からASEAN(東南アジア諸国連合)、そして中国へと、後発途上国が先発途上国へのキャッチアップを進める一方で、先発途上国はその産業構造を変化させるという、いわゆる雁行型経済発展が進んでいる。
このような経済発展段階の多様性や社会、自然などの地域特性の多様性も相互に関連し、各国の産業構造も、農産物や天然資源などの1次産品中心、製造業中心、サービス業中心など多様性を有している。例えば、製造業の中でも繊維、化学、鉄鋼、機械等様々な業種に広がっており、複雑な多様性を形成している(第2-1-2図)。
(2) 高い域内相互依存性
アジア・太平洋地域、特に東アジア地域の経済発展は、資本、労働、鉱物資源、技術等の生産要素の賦存状況が大きく異なっている国同士の貿易・投資による効率的な各生産要素の活用から生じたものであった。こうした国際分業構造は、先進国とNIEs間の分業に始まり、先進国とASEAN、NIEsとASEANの間へと広がりを見せ、アジア・太平洋地域における相互依存度は急速に高まり、経済成長を加速させてきた。現在では、貿易をはじめ、海外直接投資、経済援助、技術協力、人的交流など様々な側面で、様々な形の域内相互依存関係が形成されつつある(第2-1-2表)。今後、アジア・太平洋地域における成長を持続するために、域内市場の拡大、分業構造の深化が同時に行われるとともに、APECによる自由化の動きが促進され、貿易及び投資を通じた域内の相互依存関係が更に深まるものと考えられる。
(3) 工業化に伴う公害問題
アジア・太平洋地域では、急速に工業化が進み経済発展を成し遂げつつある国が多く見られるが、こうした国々では、これまで先進国が経験したような工業化に伴う公害問題が深刻化している。工業化の進展に伴い、工場等からの排出ガスや排水、廃棄物などが増大しているにもかかわらず、環境対策の優先順位の低さや環境への配慮の欠如から公害防止対策が追いつかず、硫黄酸化物等による大気汚染や、廃棄物、重金属等の有害物質による水質汚濁や土壤汚染などの公害問題が深刻化している。例えば、大気汚染を見ると、瀋陽、ニューデリー、ジャカルタ、クアラルンプールなどの都市においては、浮遊粒子状物質の濃度が高く、北京や上海では二酸化硫黄の濃度が高い(第2-1-3図)
(4) 都市への人口集中と環境悪化
アジア・太平洋地域の主な都市では、都市への人口集中が進んでいる。例えば、韓国の都市人口の割合は1970年(昭和45年)に50.1%、1980年(55年)に68.8%、1990年(平成2年)に79.8%、マレイシアでは1970年に27.0%、1980年に34.6%、1990年に43.0%というように、都市人口の割合が増加している(第2-1-3表)。こうした都市への人口集中は、都市環境に対する深刻な圧力となり、アジア・太平洋地域の多くの都市において深刻な環境問題を引き起こしている(第2-1-4図)。1990年(平成2年)のアジア・太平洋地域の環境の状況に関するESCAP報告書によると、都市化に関連する環境問題として、生活排水等による水質汚濁、自動車の都市集中等による大気汚染及び廃棄物の処理問題などに加え、都市の拡大による周辺部の肥沃な農地及び森林の減少、住居及び上下水道を含む都市基盤施設の不足による生活環境の悪化が挙げられている。
(5) 貧困と環境悪化
貧困に起因する環境悪化は、アジア・太平洋地域の地方の農村部と都市部において大きな問題となっている。例えば、前述のESCAP報告書によると、アジア・太平洋地域には、世界の可耕地面積の約30%しか存在しないにもかかわらず、世界の農業人口の72%が住んでいる。これに加えて、人口の急激な増加に比して農地面積の増加が小さいため、農業人口1人当たりの農地面積が減少し、土地を持たない農民が増えている。こうした問題は、都市への人口流入の原因となっているほか、土地を持たない貧しい農民が、丘陵斜面の生産性の低い土地を耕作することにより土壤侵食を悪化させ、洪水の発生や低地での水質汚濁を招き、また、森林へ侵入して非持続的な農業を行うことにより、森林の減少・劣化を招くとともに土地の生産力の低下を招いている。さらに、森林の減少・劣化による生態系への影響も懸念されている。
一方、都市部では、スラム等に住む貧困層が、都市の環境問題の影響を最も大きく受けている。環境対策があまりとられていない工業地域の周辺で環境汚染の影響を受けたり、不衛生な水と不適切な衛生施設による健康への影響を受けるなど、都市部の環境悪化により貧困層の人々は、特に大きな影響を受けている(第2-1-4表)。
(6) 地球規模あるいは地域にまたがるような新たな環境問題
アジア・太平洋地域では、今後、人口増加と経済成長に伴うエネルギー消費の増大が見込まれ、化石燃料の消費の増大により、大気汚染物質による環境悪化や酸性雨の影響、温室効果ガスの排出量増大による地球温暖化の影響が懸念されている。特に、地球温暖化に伴う海面上昇の影響を受けやすい沿岸地域においては、深刻な影響が懸念されている。また、アジア・太平洋地域には、多様な生態系が存在するがその中には脆弱な生態系もあり、人間の活動が森林の減少や土壤劣化などの影響を及ぼしている。このほか、海洋汚染や生物の多様性の減少などの影響も懸念されている。アジア・太平洋地域は、今後、加速的な経済発展が予測される一方で、地球規模あるいは地域にまたがるような新たな環境問題の出現を抱えている地域であると言える。