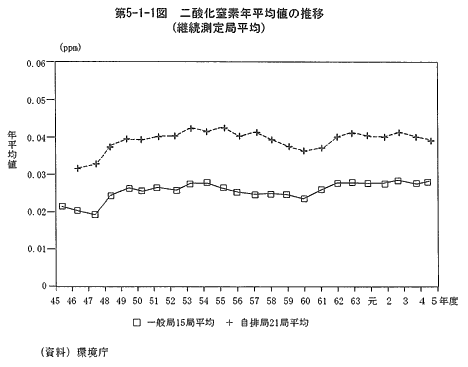
1 現代文明の地球的限界
(1) 現代文明の源としての西欧近代文明
現代文明の特色は、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会活動や生活様式が広まり、通常の活動による環境への負荷が環境問題において重要な意味を持つようになるとともに、貿易や国際投資等を通じ、また、世界各地の経済の規模が拡大することにより経済社会活動が地球全体の環境に影響を及ぼす規模にまで拡大しており、かつその活動規模が拡大し続けているという点に求められるであろう。このため、活動の拡大に伴って発生する環境問題に対して、技術革新などによって次々と対応を進めていくものの、それ以上の速度で問題が進展し、あるいは予期しない新たな問題が発生し、顕著な成果をあげた分野がある一方で、改善の遅れる問題が残り、現在では地球的規模に至るまでのさまざまの困難な環境問題を抱える状況となっている。
我が国は、省エネルギー、省資源対策を推進するなどして大きな経済成長を遂げつつ、かつて大きな問題となっていた工場を主な排出源とする硫黄酸化物については、約20年間に80%以上を削減するなど大きな成果をあげてきた(OECD環境保全成果審査報告書)。しかし、例えば、大都市地域における窒素酸化物については、その主な発生源である自動車からの排出ガスについて一台毎の排出量を規制実施前に比較して大幅に低減したにも関わらず、自動車交通量の増大などにより、改善がはかばかしくない状況にある(第5-1-1図)、(第5-1-3図)。また、我が国のエネルギー需要はほぼ一貫して増大を続け、あらゆる化石燃料の消費などにより発生する二酸化炭素の排出量もこれまでのところほぼ一貫して増大を続けており(第1-3-1図)、世界的な傾向としてもCO2の濃度はほぼ一貫して上昇している(第5-1-9図)。毒性がなく容易に分解しないとして冷媒、洗浄剤、発泡剤、スプレー剤などに便利に用いられたフロンも、予期しなかったオゾン層の破壊という深刻な問題を引き起こしていることがわかった。水質に関しても、工場・事業場の排水については規制が相当に効果を上げたものの、生活排水に起因する汚濁負荷が大きな割合を占めるようになっている。さらに陸上及び海上の両方からの汚染源による海洋汚染が国際的な問題となっている。また、廃棄物についてもその排出量及び一人当たり排出量が増大しており(第5-4-1図)、有害廃棄物の増大は有害廃棄物の国際間の国境移動という問題を発生させ、国際的な条約(「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」)により規制されるにいたっている。また、世界的には開発途上国を中心として人口が急速に増大しており、これが環境への負荷の増大の要因ともなっている(第1-3-2図)。
文明が興って以来、人類は他の生物と比較して大量の生産、消費、廃棄を行い、それを増大し続けてきたが、近年になってさらにその拡大速度を著しく速め、環境の面でも、資源の面でもついに地球的規模での限界が見えつつあるところにまで至った。
このような現代文明の源は、西ヨーロッパから発生した西欧近代文明であり、さらにはそれがアメリカで形を変えて全世界に広がったものと言われる現代文明は、西ヨーロッパから発生した西欧近代文明に由来したものであるという意味で「今日の世界はすべて近代文明の下にある」とも言われることがある。
では、その西ヨーロッパの文明が現代文明に至る経過を簡単に振り返ってみよう。(参考 湯浅赳男「環境と文明」他)
西ヨーロッパの風土は地中海世界や西アジア世界と異なり、湿潤かつ冷涼であった。その結果西ヨーロッパの文明が闘う相手は水ではなく、森であったと言われている。西ヨーロッパの豊かな森林を開墾して新しい農法(三圃式農業)により農業生産を拡大して人口を増やし、人口増加は更なる森林の開墾を促した。それにより一層人口が増加したが、農地の新たな開墾や生産性の向上は限界に達し、加えて14世紀からの気候の寒冷化もあって、不作の年には飢餓が発生し、多くの人が餓死したという。さらに、社会的条件の悪化によって利害の厳しい対立が生じ、戦争が多発した。加えてペストが流行して人口は大きく減少し、経済も衰退することとなった。1347年から5年間にわたって流行したペストでヨーロッパの人口の3分の1から半分は死亡したといわれる。しかし、15世紀以後西ヨーロッパ文明では、人口が減少し一人当たり耕地面積が増加することによって、農業において牧畜により高い比重を与えることが可能になり、これが新たな発展の一因になった。これにより生産力が増大するとともに、人口減による労働力不足の下で、農民は封建領主に対する立場を有利にしていったとされている。それによって農民などによる経済活動がますます活発化し木材などの資源の需要も一層高まり、これを周辺に求めて文明の領域を拡大することでさらに発展し、拡大した。こうして14世紀に崩壊しかかった西ヨーロッパ文明は16世紀に西欧近代文明へと発展して再起することになったのである。
やがて16世紀以後再び食糧不足、森林資源の減少等の制約に突き当たった西ヨーロッパ文明はさらに活動領域を広げて新たにアメリカ大陸、オーストラリア大陸を含む世界に活動領域を広げ、西欧近代文明として発展した。その文明は、貨幣を軸にした市場での価値を求める性格を持ち、その中で物の生産量(すなわち消費量、廃棄量)は拡大し続けた。この文明の維持発展のためにはエネルギー源及び素材としての多量の天然資源を必要とし、また、その活動は多くの汚染物質や不用物の排出を伴うものとなった。
このように、自然資源の利用により着実に経済や人口を拡大させ、それによって行き着いた資源等の制約による問題を活動領域の地理的拡大等によって解決してきたのが西ヨーロッパ文明に源を持つ西欧近代文明であると言えよう。そして、現代文明はその西欧近代文明を引き継いで、領域を地球上のほぼ全域に拡大し、世界中の国々がそれぞれ貿易、金融、投資、経済協力その他で多かれ少なかれ関連し合いながら、経済社会活動を展開しているのである。
(2) 現代文明の地球的限界
前節で見たように古代の文明は、自らの活動によって自らの存立基盤たる環境を損なうことにより、その文明が滅亡した場合でも、別の新たな文明が滅びた文明の遺産を引き継いで、新たな良好な環境の土地に文明を興してきた。
また、現代文明の由来する西欧近代文明は、発祥の地域である西ヨーロッパでの資源や環境の限界を、アフリカ、アジア、南北アメリカと世界各地に展開してその資源を利用することによって乗り越え、その文明を拡大、発展させてきた。
そして、現代文明は活動の規模を地球上のほぼ全域に持ち、地球上のあらゆる場所から資源を求め、地球全体の環境に影響を及ぼすに至った。
そして今、現代文明は、資源及び環境の問題に直面している。これまで見た古代文明の歴史から得られる教訓の一つは、自らの存立基盤である環境を損なえばそれが一因となって文明自体も危機に陥ってきたということであった。他方、西欧近代文明は新たな地に資源と環境を求めることによって資源や環境の制約を乗り越えてきたが、既に世界全体に拡大した現代文明は地球という制約をこれまでのようなやり方で乗り越えることはできなくなっている。また、古代文明は、地球全体の気候といったものにまで影響を及ぼすことはなかったが、現代文明はこのような地球的規模での環境にまで取り返しのつかない影響を及ぼすおそれを生じさせてきている。さらに、国際的な貧富の差などのいわゆる南北問題などの問題も抱えたまま、人口の世界的な急増という文明の存続にとって深刻な問題を同時に抱えている。
このように歴史の教訓と現在の状況を考えるときに、我々及びその子孫が生き続けていくためには、どのような考え方が必要となるであろうか。