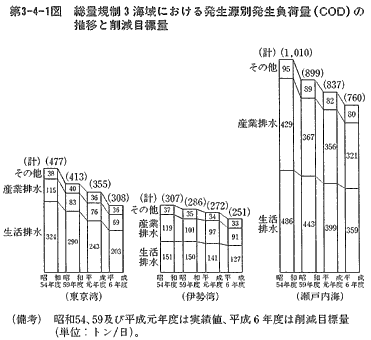
1 総量規制の推進
広域的な閉鎖性海域の水質改善を図るためには、その海域に流入する汚濁負荷量の総量を効果的に削減することが肝要である。
このため、昭和53年の「水質汚濁防止法」等の改正により、広域的な閉鎖性海域について、水質環境基準を確保することを目途として、当該水域への汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制を制度化した。これまで東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海について化学的酸素要求量(COD)を指定項目として総量規制を実施してきた。
第一次の総量規制は昭和59年度を目標年度として実施され、引き続き平成元年度を目標年度とする第二次の総量規制が実施された。しかし、依然としてこれら水域の水質改善が必要であることから、平成3年1月に策定された総量削減基本方針及び3月に策定された総量削減計画に基づき、現在6年度を目標年度とする第三次の総量規制を実施している。
第三次総量規制においては、総量削減基本方針及び総量削減計画により目標年度における発生源(産業系、生活系、その他)別の削減目標量等について定めており、平成元年度の負荷量に対し東京湾で13%、伊勢湾で8%、瀬戸内海で9%、3水域全体では10%の削減を図り、また発生源別にみると生活系12%、産業系9%、その他2%の削減を図ることとなっている(第3-4-1図)。その達成のため、下水道整備の促進を図るとともに、地域の実情に応じ、コミニティ・プラント、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の整備等の生活排水対策、工場等の総量規制基準の強化等の産業排水対策、その他の諸対策を総合的に推進している。
また、第三次総量規制の実施状況を把握しつつ、閉鎖性海域の一層の水質改善を図るための検討を行っている。