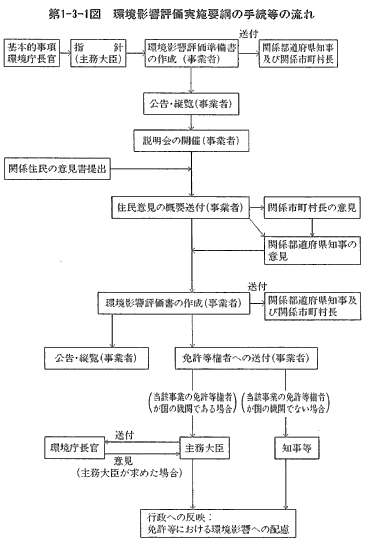
1 閣議決定に基づく環境影響評価について
悲惨な公害や自然環境の破壊を繰り返さないため、また、環境問題の根本的な解決のためには、環境汚染を未然に防止していくことが極めて重要である。
環境影響評価、いわゆる環境アセスメントは、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、その環境影響について事前に十分に調査、予測及び評価するとともに、その結果を公表して地域住民等の意見を聴き、十分な環境保全対策を講じようとするものであり、環境汚染を未然に防止するための有力な手段の一つである。
我が国においては、昭和47年6月に「各種公共事業に係る環境保全対策について」が閣議了解されて以来公有水面埋立法等の個別法、各省庁の行政指導、地方公共団体の条例、要綱等により環境影響評価が行われてきた。
さらに、昭和59年8月には「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行い、国の関与する大規模な事業に係る統一ルールとして「環境影響評価実施要綱」を定めた。
この実施要綱において、対象事業は、規模が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるもので、国が実施し、又は免許等で関与するものとし、道路、ダム、鉄道、飛行場、埋立、干拓及び土地区画整理事業などの面的開発事業等が定められている。
事業者が行う手続の概要は、次のとおりである(第1-3-1図参照)。
? 事業者は、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、主務大臣(対象事業を所管する大臣)が環境庁長官に協議して定める指針に従って事前に調査、予測、評価し、環境影響評価準備書を作成する。
? 事業者は、準備書を公告・縦覧し、説明会を開催する。
? 事業者は、準備書について関係地域に住所を有する者の意見の把握に努める。事業者は、関係都道府県知事に対し、関係市町村長の意見を聴いた上で、意見を述べるように求める。
? 事業者は、これらの意見を聴いて、準備書の記載事項について検討を加え、環境影響評価書を作成しこれを公告・縦覧する。
このような環境影響評価の結果を国の行政に反映させるために、行政庁は対象事業の免許等に際し評価書をもとに環境影響に配慮することとされており、主務大臣は、必要と認められる事項があるときは、評価書に対する環境庁長官の意見を求めることとされている。
この実施要綱に基づく環境影響評価は、主務省庁が事業者に対する指導等の行政措置を講ずることによって実施されるものであり、平成5年において手続が終了した環境影響評価は27件となっている(第1-3-1表)。