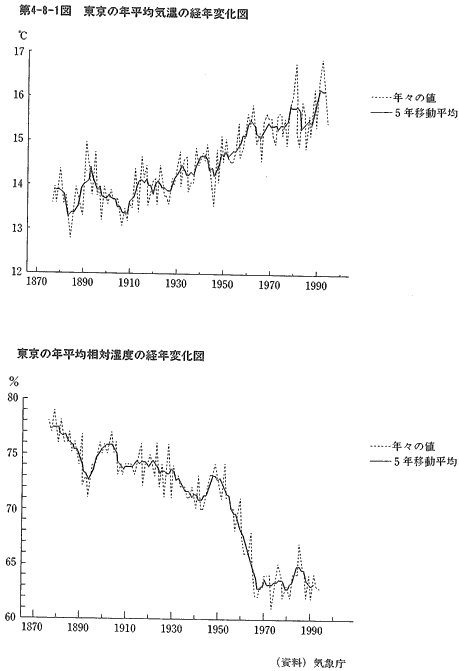
(1) ヒートアイランド
首都圏等の大都市圏においては、ヒートアイランド現象による温度の上昇など典型7公害以外の大気環境に係る現象がみられている。都市においてはエネルギーが高密度で消費されており、加えて都市の土地の多くがアスファルトやコンクリート等の乾いた物質により覆われているため水分の蒸発による温度低下が少なく、日射熱の蓄熱を夜間に放出するため夜間の気温低下が起こらないという特徴を持っている。この結果、都心部では郊外に比べて気温が高くなり、等温線を描くとあたかも都市を中心とした「島」があるように見えることからヒートアイランド現象と呼ばれ、東京等の大都市では日常生活で実感できるほどになっている。
第4-8-1図で表されているように、東京の年平均気温は1870年代の約14℃からこの120年余りで約16℃へと2℃程度上昇し、年平均湿度は約77%から約63%へと14%程度下がっているが、ヒートアイランドがその一つの要因となっていると考えられる。
ヒートアイランド現象が起こると、特に夏の気温の上昇により冷房のためのエネルギー需要が高まり、その結果ますます都市の気温が高まるほか、環境への負荷も高まるという悪循環が発生する。これに対し、緑地における植物は葉面から水が蒸発する際に周りの熱を吸収することから気温を調節する機能を有し、また都市内河川や海域などの水辺がヒートアイランド軽減効果への役割を果たすともいわれるなど、都市の生態系とヒートアイランド現象との関わりを把握することが今後の課題とされる。
(2) 日照阻害、風害、人工光害等
典型7公害以外の苦情の種類別苦情件数の推移を日照阻害、電波障害、風害(通風)についてそれぞれ見てみると、日照では平成4年度は324件で3年度に比べ62件増加しており、昭和59年度から急増を続け62年度には846件と過去最高を記録したが、翌63年度は一転して苦情件数は半減となり、元年度以降は増減を繰り返している。電波障害では、4年度は536件で3年度に比べ112件減少しており、53年度の475件をピークに54年度以降漸次減少を続け、59年度から再び増加の傾向を示し、以降300件台から600件台で推移している。通風では、4年度は12件で3年度に比べ9件増加しており、61年度の70件をピークに62年度以降急激に減少したが、その後は増減を繰り返している(第4-8-2図)。また、4年度の壁面反射や深夜照明などの光害に係る苦情件数は66件であった。
人工光害は、光が環境中に漂ったり蓄積したりするものではないため大気汚染や水質汚濁のように人の健康に直接影響を及ぼすものではなく、また騒音・振動や悪臭のように必ずしも不快感を与えるとは限らない点で、典型7公害とは性質が大きく異なる。環境庁で実施している「全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)」よると、都市の規模が大きくなるにつれて照明・ネオンサインなどにより夜空の明るさが増し、星が見えにくくなるという結果が得られている(第4-8-3図)。夜間の人工光は道路・航路等の安全確保は言うに及ばず、都市機能を維持する上で不可欠であるが、必要以上の照明は省エネルギーに逆行するのみならず、太古より我々の精神生活に関わりを及ぼしてきた星空の喪失、ひいては快適環境の消失につながる。このほか、天体観測が困難となることによる天文学の進歩の阻害、夜間の過剰な照明による動植物等生態系の変化などの影響が懸念される。
このような光の影響に対して、国内では岡山県小田郡美星町が平成元年に全国に先駆けて光害防止条例を制定し、星空を守るために野外の照明に対して様々な基準を設けているほか、NGOにおいても取り組みがなされている。一方、国外においてはアメリカのアリゾナ州ツーソン市をはじめ、欧米を中心に各地で光害防止条例が制定されている。