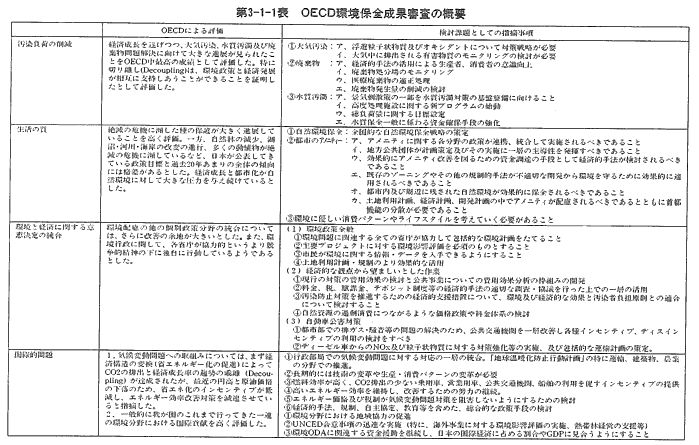
1 OECD環境保全成果審査
序章で見たように、我が国の経済社会活動は、地球的な規模においても大きな影響を与えるまでになっている。こうした状況下で、我が国の環境政策はどのように位置付けられるのだろうか。この点に関し、平成5年11月、OECD環境政策委員会により行われた我が国に対する環境保全成果審査(EnvironmentalPerformance Review)をもとに検討してみたい。同審査は、1991年(平成3年)1月のOECD環境大臣会合での合意に基づき始められた、環境政策委員会の主要な活動の一つである。被審査国の環境に関する国内目標及び国際約束の達成状況をチェックし、実施の成果を評価すると共に、さらに推進すべき課題を明らかにすることを目的としている。具体的には、OECD事務局及び審査国によるミッションが被審査国を訪問し、調査を行った後、その調査結果が環境保全成果グループ会合の場で検討され、最終的に報告書がとりまとめられるものである。1994年(平成6年)から定期的に加盟各国の環境政策実施の審査をすべく、1992年(平成4年)から1993年(平成5年)にかけて、前述の目的とともに審査方法自体の確立をも目的とした試験的なパイロット審査が日本、ドイツ、アイスランド、ノールウェー及びポルトガルの5ヶ国を対象として実施された。我が国は、1976年(昭和51年)〜1977年(昭和52年)にOECD環境委員会(環境政策委員会の前身)による環境保全成果審査を受けた経験を有するが、今回新たに開始されることになった本件環境保全成果審査の際には、1993年(平成5年)4月にOECD事務局及びカナダ、ドイツ、ニュージーランド、オランダの4ヶ国からの出席者からなる審査団による審査が行われ、同審査団は環境政策の各種分野につき、13の省庁、地方公共団体、産業界、労働組合及び環境NGOに対しヒアリングを行った。
報告書は、主として4部からなる。第1部は公害対策と自然資源の管理について、第2部は、政策の統合に関する審査である。第3部は国際社会における協力、第4部は以上を総括した結論部分である。
本節では、まず報告書の概要を見たのち、これに関連する施策の概観を試みたい(第3-1-1表)。
(1) 汚染負荷の削減
ア OECDによる評価
過去20年間に、我が国が先進国中で最大の経済成長をとげつつ、大気汚染、水質汚染及び廃棄物問題解決にむけて大きな進展が見られたことを高く評価した。この経済成長とSOx、NOx等の排出量の趨勢の「切り離し(Decoupling)」は、経済構造の変化、エネルギー効率の向上、及び効果的な環境政策により達成されたものとした。これらの成功は、環境政策と経済発展が相互に支持しあうことができることを証明したものとして評価している。
イ OECDによる指摘事項と我が国の関連施策
(ア) 大気汚染問題については、OECDの環境保全審査では、?浮遊粒子状物質及びオキシダントについて、NOxと同様な対策戦略が必要、?ベンゼン等の発ガン性物質、ダイオキシン、重金属等、大気中に排出される有害物質のモニタリングの検討が必要、等の指摘がなされた。
これに対し、我が国では、浮遊粒子状物質に関しては、従前の対策(一次粒子の排出抑制)に加えて、二次粒子も含めた総合的な検討が必要である。平成6年度からは、5カ年計画にて「浮遊粒子状物質総合対策検討調査」に着手することとしている。
浮遊粒子状物質のうち、ディーゼル排気微粒子については、早急な低減を図る必要があるため、平成6年度から5カ年計画で「ディーゼル排気微粒子低減対策総合調査」に着手することとしている。
また、ダイオキシン、有機塩素系溶剤等の有害な物質について、継続的に大気濃度を監視するためのモニタリングを実施しているところであるが、さらに、その他の大気汚染の可能性のある多種多様な物質に対処するため、優先的に取り組むべき物質を整理し、モニタリングの拡充をはじめとした体系的な取組をはかることとしている。
(イ) 廃棄物問題については、?経済的手段の活用による生産者・消費者の処理コストに対する意識の向上、?廃棄物処分場からの漏出や土壤汚染に関するモニタリング、?医療廃棄物の適正処理の確保、?長期的な技術開発戦略と教育を通じた廃棄物発生量の削減の検討が必要とした。
我が国では、関係省庁において、経済的手法の活用等について検討が進められているところである。
(ウ) 水質問題については、排水の収集、処理施設への投資計画を促進するため、景気刺激策のためのパッケージの一部を水質汚濁対策の基盤整備に向けると共に、高度処理施設に関する新プログラムの始動、総負荷量に関する目標の設定、等が必要とされた。また、水質保全一般について、離散的な排出源からの汚染の対応や汚水処理料金制度の拡大等を通じた資金確保手段の強化等が必要とされた。
こうした指摘に対して、河川・湖沼の水質保全に関しては、有害物質や農薬による水質汚濁を防止するため、排水規制を推進するとともに、水質監視測定体制の充実を図ることに加え、都市内中小河川、湖沼等の水質汚濁を改善するため、生活排水対策を引き続き推進することとしている。特に、水道水源の水質保全については、安全で良質な水道水を供給するために、重要な課題となっていることにかんがみ、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」及び、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」に基づき所要の対策を推進するとともに「農薬取締法」に基づく水質汚濁性農薬の指定とその規制や公共用水域等での水質の評価の際の安全性の目安となる指針値の策定等農薬による水質汚濁防止対策の充実・強化を図る等各種の対策を講ずることとしている。また、「保安林整備臨時措置法」に基づく保安林整備計画により水質の保全に資する保安林の計画的整備を進めることとしている。海域の水質保全については、富栄養化の原因物質である窒素・燐に関する排水規制、海域への環境基準の類型指定及び関係省庁と連携した総合的対策を進めるとともに、第4次の水質総量規制のあり方の検討を行うことになる。さらに良好な水環境の保全という観点から、瀬戸内海において、干潟、藻場の復元を始めとした快適環境の創出のための技術的方策及び砂利採取が生態系を含む水環境に与える影響について検討するとともに、生態系保全の視点を含め、水生生物の保護に関する環境基準の設定の調査・研究を進めることとしている。
(2) 生活の質
ア OECDによる評価
特に絶滅の危機に頻した種の保護が我が国において大きく進展していることが高く評価された。
イ OECDによる指摘事項と我が国の関連施策
(ア) 自然環境保全については、経済成長と都市化が自然環境を圧迫し、現実が政策目標から乖離しており、関係各省庁と地方公共団体・市民団体の協力による全国的な自然環境保全戦略の作成が求められるとした。
自然環境保全については、生物多様性の保全の推進のため、生物多様性に関する調査を充実させるとともに、多様な生態系や生物種の保全を図るため、保護地域の今後のあり方及び多様な動植物の生息・生育環境のネットワーク化に関する検討などを進めることとしている。また、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、生息地等保護区の指定・管理を推進するとともに、希少野生動植物の譲渡等の規制の対象を個体の一部にまで拡大するため、種の保存法の改正を行うこととしている。自然とのふれあいの推進という観点からは、国立・国定公園における公衆トイレ、長期滞在型野営場等の自然とのふれあいの場を整備するとともにパークボランティア、自然公園指導員その他のボランティアの育成を図るなど自然とふれあう活動を推進することとしている。
(イ) 都市におけるアメニティについては、多くの成果が認められる一方、私的な土地利用権の強さと経済成長がもたらした開発圧力がアメニティを阻害してきている。このような状況に対し、ゾーニングの改善や規制的手法の効果的な実施のための措置がとられているとしている。このため、?アメニティに関する各分野の対策が連携、統合して実施されるべきであること、?地方公共団体が計画策定及びその実施に一層の主導性を発揮すべきであること、?効果的にアメニティ改善を図るための資金調達の手段として、経済的手法(賦課金、使用料、地方税等)が検討されるべきであること、?既存のゾーニングやその他の規制的手法が不適切な開発から環境を守るために効果的に適用されるべきであること、?都市内及びその周辺に残された自然環境が効果的に保全されるべきであること、?土地利用計画、経済計画、開発計画の中でアメニティが配慮されるべきであるとともに首都機能の分散が必要であること、につき検討する必要があるとした。
以上に対しては、身の回りにある良好な自然の保全、美しい街並・身近な音環境の改善の創出など快適環境づくりに向けた施策を推進するとともに、地域における取組を奨励することとしている。
(ウ) 人々の所得と余暇の増加がより多くの自然資源を消費し、結果的に廃棄物の増加や汚染の原因となっていることに鑑み、環境に優しい消費パターンやライフスタイルを考えていく必要があると指摘している。環境に優しい消費パターンやライフスタイルの重要性については、第1章で見た通りである。
(3) 環境と経済に関する意思決定の統合
ア OECDによる評価
環境配慮の他の個別政策分野への統合については、他のOECD諸国と同様にさらに改善の余地が大きいとした。
イ OECDによる指摘事項と我が国の関連施策
(ア) OECDでは、環境と経済に関する意思決定の統合のために以下の対策を提案した。
? 環境問題に関連する全ての省庁が協力して包括的な環境計画をたてること。
? 環境影響評価は、より一層体系的かつ徹底して適用されるべきであり、主要な事業全てに対して必須のものとされるべきであること。
? 市民が環境に関する情報・データを入手できるようにすること。この一般原則への例外は、明示されたものに限られるべきであること。
? 土地利用計画・規制のより効果的な活用を進めること。
我が国では、21世紀に向け、我が国として環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していくため、政府全体の環境保全に関する施策を総合的・計画的に推進するための基本的方向を示すものとして環境基本計画の策定を推進することとしている(第2節参照)。環境影響評価制度については、内外の制度の実施状況等に関し、関係省庁一体となって調査研究を行い、その結果を踏まえ、経済社会情勢の変化等を勘案しつつ、法制化も含め所要の見直しについて検討する方針であり、このため、国、地方公共団体、諸外国等における環境影響評価の実施状況等について制度及び実態の両面から総合的な調査研究を推進することとしている。環境情報については、環境の保全に関する国内及び国外の資料の収集、整理を行うとともに、環境白書、各種の普及啓発用小冊子、その他により積極的に一般への情報提供を行っているところである。また、環境庁国立環境研究所環境情報センターでは、環境の保全に関する情報の存在箇所等についての情報(情報源情報)を整備し、環境情報ガイド(印刷物及び電子メディア)として、広く一般に提供するなど環境情報の普及に努めているところである。
(イ) 経済的な観点から以下の作業が望ましいとした。
? 現行の対策の費用効果の検討と公共事業についての費用効果分析の枠組みの開発
? 料金、税、賦課金、デポジット制度等の経済的手法の適切な調査・協議を行った上での一層の活用
? 汚染防止対策を推進するための経済的支援措置について、環境及び経済的な効果と汚染者負担原則との適合についての検討
? 自然資源の過剰消費につながるような価格政策や料金体系の検討
環境保全事業の経済波及効果及び雇用誘発効果については、第2章で詳述したように環境庁の試算によれば、長期的な生産能力の向上に直接結びつくものではないが、短期的には建設部門と同程度の効果が見られた。また、経済的手法の活用については、我が国においてもその重要性を認識しているところであり、現在、調査研究が進められている。
(ウ) OECD環境保全成果審査では自動車台数の増加は都市部で特に排ガス・騒音等の問題を惹起しており、その解決のために公共交通機関を一層改善し各種インセンティブ、ディスインセンティブの利用を検討すべきとし、また、ディーゼル車からのNOx及び粒子状物質に対する対策強化等を行うとともに、包括的な運輸計画を策定すべきとした。
これに対し、我が国では、NOx対策の推進という観点から、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づく総量削減基本方針及び総量削減計画に盛り込まれた車種規制、物流対策、交通流対策等の各種対策を関係省庁及び関係自治体との連携の下、総合的かつ計画的に推進することとしている。また、微粒子状物質対策の推進という観点から、大気中のディーゼル排気微粒子の汚染状況の把握、排出実態の把握等を通じ、総合的な低減対策の検討を行うこととしている。さらに、地方公共団体における公害パトロール車の導入補助を行うなど公的機関による低公害車の率先的導入を進めるとともに、民間事業者による低公害車の導入を誘導するための所要の措置を講じるなどにより、低公害車の普及促進に努めることとしている。そのほか、航空機の排ガスによる大気汚染についても、排出実態の把握及び対策の検討を行うこととしている。
(4) 国際的問題
ア 気候変動問題への取組については、まず経済構造の変換(省エネルギー化の促進)によって二酸化炭素の排出と経済成長率の趨勢の切り離し(Decoupling)が達成されたが、最近の円高と原油価格の下落のため、省エネ化のインセンティブが低減し、エネルギー効率改善対策を減速させていると指摘した上で、今後以下の提示につき、検討することが求められた。
? 行政部局は、気候変動問題に対する対応をいっそう統合すべき。「地球温暖化防止行動計画」を特に運輸、建築物及び農業の分野で推進すべき。
? 長期的には技術の変革や生産・消費パターンの変革が必要。
? 燃料効率が高く、二酸化炭素排出の少ない乗用車、営業用車、公共交通機関、船舶の利用を促すインセンティヴの提供。
? 高いエネルギー効率を維持し、改善するための努力の継続。
? エネルギー価格及び税制が気候変動問題対策を阻害しないようにするための検討。
? 経済的手法、規制、自主協定、教育等を含めた、総合的な政策手段の検討。
イ その他、一般的に我が国のこれまで行ってきた一連の環境分野における国際貢献を高く評価する一方で、以下の点につき今後積極的な検討が期待されると指摘した。
(ア) 環境分野における地域協力の促進
(イ) 地球サミット合意事項の実施の継続(特に、海外事業に対する環境影響評価の実施、海外の日本の活動に伴う環境リスク情報の提供、熱帯林経営の支援、等)。
(ウ) 環境ODAに関連する資金援助を継続し、日本の国際経済に占める割合やGDPと見合ったものとすること。
これら国際的問題については、平成5年12月に地球環境保全に関する関係閣僚会議で決定された、我が国の貢献についての国際公約ともいえる「『アジェンダ21』行動計画」を中心に考察してみたい。