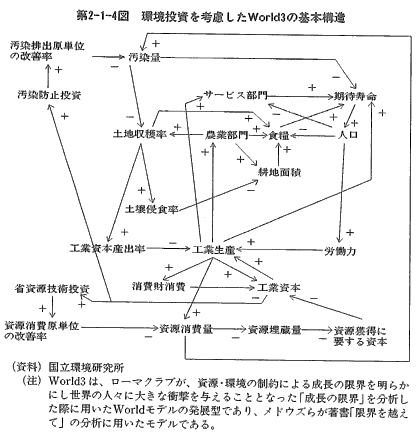
2 環境投資と経済の関係
次に、環境と経済の統合の鍵となる環境投資と経済との関係について見てみたい。環境庁では、環境投資に関し、平成5年11月から12月にかけて企業経営者や有識者など約600人を対象にアンケート調査を行った。本アンケート調査は、環境投資と景気刺激、雇用創出の関連についての認識を調査したもので、具体的には、「環境投資は、中長期的・マクロ的には経済を活性化し環境保全と活力ある社会経済の両立を図ることができる。1970年代には、公害防止投資が経済を下支えしたが、現在は、環境問題は社会経済のあらゆる分野での問題に変化しており、新たな視点からの投資等の誘発を図る必要がある。環境への投資こそ景気を刺激し、雇用を創出するフロンティアである。」という総論的な考え方に対する意見などについて聴取した。その結果によると、全面的に賛成する意見や条件付き(「国民のコンセンサスが得られればエコビジネス創出につながる」、「政府、公共セクターの主導性が必要」、「国際的協調が必要」など)で賛成する意見が多かったが、「短期的、ミクロ的には環境投資によるコスト負担増が景気抑制に働く」や「環境投資は従来の公共投資(道路、港湾等)に比べると景気浮揚への累進効果は薄いが、中長期的な効果が期待できる」といった意見も見られた。
このように、環境投資と経済との関係については様々な議論がなされており、従来のように環境と経済が相対するものではなく、両立し得るものであるとの見解も見られている。
こうしたことを踏まえつつ、ここでは環境投資と経済との関係について、システムダイナミックスモデルにより長期的な視点から、また、産業連関分析により短期的な視点から見てみたい。
(1) 環境投資と経済との長期的な関係
まず最初に、環境対策が世界経済の長期的な動向に与える効果について見てみよう。国立環境研究所では、経済と環境や資源との相互関係を明らかにするためシステムダイナミックスモデルを用いてシミュレーション分析を行った。システムダイナミックスモデルは、システムの各変数間の相互作用を動学的特性を重視しつつモデル化し、各変数がどのように変化するかを分析するものである。本分析に用いたシステムダイナミックスモデルは、メドゥズらによって開発されたWorld3を一部改良したものである。
World3は、将来の経済の姿を考えるに当たって重要である、人口、工業生産、農業生産、再生不能資源、汚染の5つの基本的変数の長期にわたる相互作用を分析した。
このモデルでは、環境と経済活動については、工業製品の生産に伴う資源埋蔵量の減少や資源の枯渇が工業生産に与える影響と、汚染排出量の増加による人口への影響が労働力の供給の減少を通じて工業生産を制約するという関係についてモデル化されている。なお、環境汚染については、通常の大気汚染やPCB、DDTなどによる汚染のように人の健康や農業生産に影響を与える公害などを想定しており、こうした汚染物質が生物などの環境中に蓄積し、被害が実際に顕在化するまでに時間がかかるといった汚染に関する一般的な特徴についてモデル化している。今回の分析では、環境投資として「省資源技術を促進させるための投資(以下、省資源化投資と略)」と「汚染排出量削減のための投資(以下、汚染防止投資と略)」を取り上げ、こうした環境投資を実施することにより、環境と経済活動の関係がどの様に改善されるかを明らかにするために、省資源化投資による省資源化技術の改良や、汚染防止投資による汚染排出量の削減率の改善といった新たなモジュールを付加することによってWorld3に改良を加えた(第2-1-4図)。
具体的には、省資源化投資の実施により、工業生産に投資される資本は短期的に減少し、生産活動は減少するが、一方で資源消費原単位が改善され、資源消費量が減少する。これに伴い、資源埋蔵量の減少率が緩和され、資源獲得に要する資本が減少し、その結果、工業生産に直接投下できる資本が増大し、工業生産の増大に寄与するようになる。また、資源消費量の減少に伴い、汚染量も減少する。一方、汚染防止投資によっても、工業生産に投資される資本は短期的に減少し、生産活動は減少するが、汚染排出原単位が改善され、その結果、汚染排出量が減少して、汚染が軽減される。これに伴って、期待寿命が伸び、労働力の供給が拡大され、工業生産が増大するようになる。こうした関係をモデル化し、今回の分析に用いている。
なお、経済社会のバランスを回復させる方向に働くものと考えられる技術の進歩・普及や市場を通じた需給調整機能は、本モデルにおいても一部組み込まれているが、革新的な技術の導入や資源間代替は盛り込まれていない。また、環境汚染と期待寿命の関係などの計測の困難な計数については暫定的な数値を与えている。
以上のモデルを用いて、環境投資を行わないケース(シナリオA)、工業投資に対する環境投資の比率が低いケース(シナリオB)及び比率が高いケース(シナリオC)、工業生産が安定的に増加するように工業投資に対する環境投資の比率を調整していくケース(シナリオD)の4つのシナリオを設定し、環境投資と経済との関係を今後およそ100年間の推移について分析してみた。ただし、各変数の変化の時期及び変化率はモデルで仮定されている暫定的数値に大きく依存するとともに、現状がどのケースに近いかについては定かでないことから、以下に示す変動の時期についての記述は予測ではなく、あくまでも想定に過ぎないことに留意する必要がある。なお、シナリオB及びCにおいては、2005年以降の工業投資に対する環境投資の割合はそれぞれ一定に保つものとし、また、全てのケースにおいて、省資源化投資と汚染防止投資の内訳は、50%ずつ均等に配分するものとする。
各シナリオによる結果は第2-1-5図のとおりであった。環境投資を行わないシナリオAでは、21世紀前半までは工業生産は急速に伸びているが、資源の枯渇を招き、工業生産が頭打ちになるとその後は急激に落ち込んでいる。また、汚染指数も21世紀中ごろを境に激減し、2100年には20世紀中ごろの水準に落ち込んでいる。シナリオBでは、シナリオAと比較すると工業生産の伸びはいくぶん鈍り、工業生産の最大値もいくらか低くなるが、環境投資を行うことで資源埋蔵量の減少率や汚染指数の最大値はかなり緩和されたものとなり、その結果、工業生産の落ち込みはシナリオAよりかなり小さくなっている。これは、1人あたりのサービス生産や消費財についてもあてはまり、その伸び率は減少するが、落ち込み方はシナリオAよりも緩やかなものとなっている。しかし、環境投資にあまりに多くの資本を投入し過ぎてしまうと、資源埋蔵量は多く、汚染指数が小さいにもかかわらず工業生産は21世紀を通じて減少傾向になる。また、一人当たりの消費財やサービスの生産も大きく減少してしまう(シナリオC)。最後に、工業生産が減少しないように工業投資に対する環境投資の投資率を第2-1-6図に示すように5年毎に変化させた場合は、2100年までの100年余りにわたって工業生産を増大し続けることが可能であり、人口も工業生産と同様に増加するので、1人当たりの消費財やサービス生産は21世紀はじめの水準で安定化させることが可能となる(シナリオD)。
以上のシミュレーション結果によれば、持続可能な経済発展が可能となりうる一つの方法として、早い段階からの環境投資に意義があることが示唆されよう。すなわち、シナリオDのように21世紀前半に多くの環境投資を行い、21世紀半ば以降は徐々にその投資を減らして工業生産に投資すると、21世紀後半になって工業生産を比較的高い水準で安定化させることが可能となっている。これは汚染発生原単位や資源消費原単位を早い時期に低い水準で安定させることにより、それまで環境に投資していた資本を再び工業生産に活用することで、21世紀後半においても環境に多大な影響を与えることなく、工業生産を維持し続けることが可能であることを示している。もっとも、こうした結果は、環境投資によって汚染発生原単位及び資源消費原単位が一旦低下すると、それ以上環境投資を新たに行わなくとも低水準の原単位が維持されると仮定していることなどに依存しているものである。
以上のことから、将来にわたり環境制約が予見される場合には、持続可能な経済発展の素地を形成するための一つのシナリオとして、資源消費原単位や汚染発生原単位が相対的に大きい状態で工業生産を拡大し続けるよりも、工業生産拡大の速度を少し緩め、省資源化や汚染防止を十分に行った後に工業生産の拡大、一人当たり消費財などの安定化に努めることが考えられる。
本分析は、単純化されたモデルにより行われたものであり、もとより現実の世界をそのまま表したものではないことに注意する必要がある。また、環境に関する将来の予測に当たっては、多くの不確実性が存在するため困難が伴う。本分析もその例外ではない。しかしながら、本分析は今後の地球的規模における環境と経済の統合を考える上で一つの示唆を与えるものであるといえよう。
(2) 環境投資の生産及び雇用への短期的な誘発効果
環境保全への投資は、コスト増による製品価格の上昇からくる需要の減少という影響もあり、一方で、新たな需要を発生させ、景気や雇用にプラスの効果を持つという影響もある。環境投資の経済への影響については、平成3年度の本報告書において、公害防止投資の国民経済への影響として、公害防止投資が積極的に行われた昭和40年から50年にかけての日本経済の状況について分析を試みている。そこでは、公害防止投資が経済に与える影響として、投資に伴う費用増が実質国民総生産に与える影響と投資のための需要増が実質国民総生産に与える影響の2つの側面から試算を行った結果、「高度経済成長時代のように、生産力増強投資にまい進していた時期ならばともかく、公害防止投資のピークと重なる石油危機後の不況時について言えば、公害防止投資の実施が停滞していた需要を喚起し、設備投資や雇用をある程度下支えする役割を果たしていたと考えられる」としている。
諸外国では、OECDにおいて環境保全投資の雇用への影響についていくつかの加盟国を対象にした調査が行われている。OECDによれば、「いくつかの調査の結果、環境保全事業への投資によるネットの雇用創出効果は、少なくとも短期的にはプラスまたは中立的である」としている。
環境庁では、産業連関表を用いて環境投資の短期的な生産誘発効果及び雇用誘発効果について分析してみた。産業連関表は、様々な産業部門間の複雑な相互依存関係を分析するために、各産業部門から産出された財が別の産業部門で中間財として使用されていくつながりをマトリックス形式で表したものである。産業連関分析では、ある産業部門で需要が発生したときに、それがどのように他部門に波及し、最終的に全部門でどの程度の生産が誘発されるかを知ることができる。ただし、需要増による価格上昇の影響や雇用増を通じた所得増による波及効果は捨象されている点に注意する必要がある。
具体的には、公共事業として環境保全事業が実施された場合、どの程度の生産誘発、雇用誘発などの短期的な経済効果を持つのかという点について、下水道事業(下水処理場・管渠の設置)、ゴミ焼却工場設置事業、環境研究調査事業(観測ステーション建設・機器購入・維持管理)、沿道緑化事業の4つの環境保全事業を例として取り上げ、産業連関分析を試みた。手順としては、まず各事業につき、投入費用の内訳を分析し、次に産業連関分析の考え方に基づいて、投入比率を整理し32産業部門へ計上、そして産業連関分析により、各事業の生産誘発額、就業者誘発数を分析した。
生産誘発額については、それぞれの環境保全対策事業に1,000億円投入したと仮定したときの各産業部門の生産をどの程度誘発する効果があるかを分析したもので、短期的な経済波及効果の指標である。
分析結果は第2-1-7図のとおりであり、例として取り上げた4つの環境保全事業の生産誘発額は、例えば建設部門の生産誘発額1,971億円と同程度であり、遜色のない程度の短期的経済波及効果を有しているといえる。
さらに、経済波及効果を短期的な雇用対策の面から見るため、それぞれの環境保全事業に1,000億円を投入した場合、何人分の雇用を誘発することになるのかについて分析した。
分析結果は第2-1-8図のとおりであり、これら環境保全事業4部門の就業者誘発数は、建設部門と遜色のない程度の就業者誘発効果を持つといえる。
以上のとおり、産業連関分析によると、例として取り上げた4つの環境保全事業は、長期的な生産能力の向上に直接結びつくものではないが、短期的には建設部門と同程度の生産誘発効果及び雇用誘発効果を有していることを示している。
また、こうした環境保全事業への投資は、近年台頭しつつあるいわゆるエコビジネス(環境関連産業)の育成にもつながるものと思われる。エコビジネスは、環境保全への企業、消費者の意識の高まりを背景に、その規模、範囲とも急速に拡大しつつあるが、産業として見れば、現段階では未だ黎明期にあると言える。こうした段階で、環境保全事業への投資が活発化し、エコビジネスの市場を広げることは、今後のエコビジネスの発展に好影響を与え、長期的に見れば、経済の活性化につながるものとなろう。
さらに、環境保全事業に投資することは、前項でも見たように、環境を改善、あるいは、環境の悪化を抑制し、長期的には、労働力、エネルギー・資源の安定的な供給に貢献するなど重要な経済効果を併せ持つことが指摘されよう。
短期的な経済波及効果について、諸外国の研究調査事例を見てみると、例えば、米国では1992年(平成4年)に約1700億ドル(約18兆7000億円)の環境保全支出により(第2-1-1表)、波及効果も含め約3550億ドル(約39兆500億円)の売上と約400万人の雇用が創出されており(第2-1-2表)、これは、全労働者の3%に当たる。また、OECDの調査によれば、旧西ドイツでは、1980年(昭和55年)、1984年(昭和59年)、1990年(平成2年)の3か年について、環境保全対策により直接的あるいは間接的に創出された雇用は、1980年(昭和55年)及び1984年(昭和59年)が約43万3千人(同1.9%)と推計されている(第2-1-3表)。また、同じくOECDの調査によれば、旧西ドイツにおいて、環境保全事業への公共投資のネットの雇用創出効果を調査した結果によると、軍事支出を削減して環境保全投資を行った場合、1980年(昭和55年)で約2万8千人,1985年(昭和60年)で約1万9千人の雇用増の効果があることがわかった(第2-1-4表)。
なお、本分析では、民間において今後活発な投資が期待される、脱硝・脱硫装置設置事業、コージェネレーションシステム設置事業、断熱材設置事業の3つの環境投資についても取り上げ、同様に短期の経済波及効果として生産誘発額と就業者誘発数を分析してみた。結果は第2-1-9図のとおりである。
民間による環境投資の場合は、投資の純増ではなく、他の何らかの投資(例えば、生産力増強や合理化など)の代わりに投資されることとなるので、他の分野に投資されていた場合の生産誘発効果や就業者誘発効果にも考慮する必要があるが、特に脱硫・脱硝装置設置事業、コージェネレーションシステム設置事業の生産誘発額や、同じく脱硫・脱硝装置設置事業の就業者誘発数を見ると、これらの分野への投資は、建設部門に比して遜色のない生産誘発効果、雇用誘発効果があると言える。
以上、短期的には、例として取り上げた4つの環境投資は相応の生産誘発効果及び雇用誘発効果を有しており、また、長期的には、システムダイナミックスモデルで見てきたように、将来にわたり環境制約が予見される場合には、継続的な環境投資は環境への負荷の少ない持続的発展の可能な経済社会の構築に貢献すると考えられるとともに、新しい産業の分野であるエコビジネスの成長に重要な役割を果たすものであると言えよう。
本項及び前項でみたとおり、継続的な環境保全投資は持続可能な経済社会の構築にとって重要な要素となっている。ところで、民間による投資の対象は、マクロ経済の効果ではなく、投資主体への効用によって決定されるものであるが、環境庁の前述の「平成5年度環境にやさしい企業行動調査」によれば、平成4年度と5年度を比較して、環境保全予算の額が増加している企業は、環境保全予算について区分して集計している企業166社中38.0%、ほぼ同額が35.5%、減少している企業が18.1%であった(第2-1-10図)。平成4年度の調査では、増加が18.0%、ほぼ同額が45.3%、減少が8.0%であったので、現下の不況期にもかかわらず環境保全予算を増額している企業の割合が20.0%ポイントも増えている。一方で、減少という企業の割合も10.1%ポイント増加しており、企業の対応は一様ではない。また、環境保全予算の全体予算に占める割合が、平成4年度と5年度を比較して増加している企業は37.3%、ほぼ同じが41.0%、減少が12.7%となっている(第2-1-11図)。さらに、環境保全費用の負担については、「業績に深刻な影響がなければできるだけ負担したいと思う」と回答した企業が最も多く68.6%(4年度は64.6%)、「業績にかかわらず負担したいと思う」と回答した企業が9.0%(13.3%)、「現在の諸規制をクリアできるだけの最小限の負担で十分だと思う」と回答した企業が9.9%(10.4%)となっており、不況の長期化の影響のため、「業績にかかわらず」と回答した企業の約3分の1が「業績に深刻な影響がなければ」という姿勢に変化したものと思われる(第2-1-12図)。こうした調査結果は、環境投資をコストアップ要因と位置づけて、長引く経済の低迷を受け削減を図ろうとしている企業が見られる一方で、環境保全意識の高まりを受けて、現下の不況下でも積極的に環境保全へ投資しようとする企業があることを示している。
今日、地球環境問題をはじめとする環境問題へ対応するために、継続的な環境投資が必要とされている。企業においても経済活動へ環境配慮を組み込む努力の一環として、環境保全への投資を継続的に行っていこうとする動きも見られている。持続可能な社会の構築には各主体が協力して取り組んでいく必要があるが、企業の一部にみられるこうした自主的な努力がさらに促進されるような社会的環境づくりが大きな課題となっている。