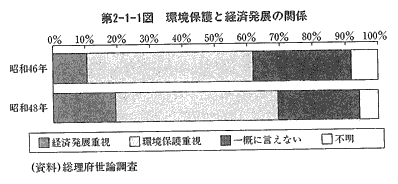
1 持続可能な開発−対立から統合へ−
1960年代から1970年代にかけて、重化学工業を中心に経済的に大きく成長した先進諸国では、大気汚染や水質汚濁などの地域的な公害が大きな問題となっていた。一方、開発途上国の間では、過度の焼畑農業による森林破壊など貧困による環境破壊も顕在化しつつあり、開発の促進による貧困からの脱却が急務となっていた。こうした背景のもと、1972年(昭和47年)にストックホルムで、国連人間環境会議が開催され、有限な地球における環境保全のあり方が討議された。その結果、環境問題を人類に対する脅威ととらえ、これに国際的に取り組むべきことを明らかにした「人間環境宣言」及び「行動計画」が採択されるなど大きな成果があった。しかし、その後、2度にわたるオイルショックと世界経済不況により、先進工業国では経済成長の確保が最優先の課題となり、また、開発途上国でも、主要な生産物である一次産品の価格の低迷などにより貧困から脱却するための開発が優先されがちであったこともあり、「行動計画」については効果的な実施には至らなかった。
昭和40年代(1960年代後半から70年代前半)の我が国でも、急速な経済成長に伴う激甚な産業公害が社会問題となりつつあった。こうした事態に対し、政府は昭和42年に公害対策基本法を制定し、事業者の公害防止の責務を明確化するとともに、様々な公害関係法令を整備することなどにより、生活環境の保全に努めた。また、企業においても、製造業を中心に積極的に公害防止設備に投資するなどの対策を実施し、激甚な産業公害は徐々に改善されていった。
しかし、国民の意識としては、ややもすれば環境保全よりも経済発展を重視する考え方が強い傾向にあった。例えば、制定された当初の公害対策基本法では、「生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとする」との、いわゆる「経済調和条項」が置かれていた。これは、現実の公害対策の局面においては産業発展との関連がきわめて深刻な調整課題となる事態が多いことにかんがみ、公害対策と産業発展の理念との関連については、何らかの規定を置く必要があるのではないかという意見を反映して置かれたものである。こうした意見の背景には、産業は厳しい国際競争に直面していてその負担には限度があるから、これに一方的に過重の負担を課して産業の存立を脅かすことのないよう、特に慎重な配慮を加え、産業の健全な発展と生活環境の保全との調和をはかる方針のもとに公害対策を推進すべきであるとする産業界を中心とした認識があった。しかし、この「経済調和条項」については、昭和45年に、ともすれば経済優先と誤解されがちであるとの理由で削除された。また、昭和46年と48年に実施された世論調査では、環境保護と経済成長の関係について調査しているが、46年の調査では、「経済発展重視」が約10%であったのが、第1次オイルショックを経験した48年の調査では、「経済発展重視」が約20%と倍増していた(第2-1-1図)。
このような状況にも見られるように、当時、国際的にも、国内的にも、経済成長と環境保全とは、それぞれ別個のものであり、相互にトレードオフの関係にあるとのとらえ方が一般的であった。
しかし、第1章第3節1で見たように、環境問題の質的な変化や地球的規模への広がりにより、世界の人々は、今日の経済社会活動がストックとしての環境にその基盤を置いていること、同時にその環境に大きな負荷を与えていることに気づき、人類の存続基盤である環境を保全することの重要さを認識するようになってきている。すなわち、環境へ大きな負荷を与える開発を続けていては、その負荷が蓄積し、ある一定の地域だけではなく地球全体に、あるいは、現在はよくても将来の世代に大きな影響を与え、結局、我々がその豊かな恵みを享受し、存続の基盤となっている環境を破壊することになってしまう。そこで、ストックとしての環境を将来にわたって継承するためには、開発のあり方を変え、環境への負荷の少ない持続可能な経済社会を構築する必要があるという考え方が見られつつある。
こうした考え方は、例えば、国際的には地球サミットのテーマである「持続可能な開発」という概念に、我が国では平成5年11月に制定された環境基本法の基本理念に現れている。すなわち、経済と環境の関係については、「経済成長か環境保全か」「開発か環境か」というジレンマとして捉えるのではなく、これまでの生産と消費のパターンを見直し、持続可能で環境負荷の少ない経済発展を目指すこと、具体的には資源やエネルギー等の面においてより一層の効率化を進め、物の再生産や再利用を更に組み込み、また、浪費的な使い捨ての生活習慣を見直すなど、その内容の変化を伴う健全な経済の発展を図り、環境負荷の少ない経済社会を構築していくことが重要であると認識されるようになってきているのである。
この持続可能な開発、あるいは持続可能な経済社会という概念は、我が国においても徐々に受け入れられつつあり、我々の経済社会活動の多くを占める産業界においても、経済団体や個別の企業でこの概念を取り入れた理念を制定する動きが広がっている。
例えば、国際的には、国際商業会議所(ICC)が、1991年(平成3年)に「持続可能な開発のための産業界憲章」を発表しているが、これは、企業にとって持続的な発展のために極めて重要な一側面である環境管理に関する16の原則から成り立っている。この憲章は、できるだけ幅広い範囲の企業がこれらの原則に従って環境対策を改善し、かかる改善活動を事業運営の中に組み込み、改善の進捗度を測定し、その進捗度を適宜、内外に発表することを促進することを目的としており、環境管理を企業における最優先事項の一つとすること、環境影響の事前評価の実施、環境にやさしい製品及びサービスの提供、環境に配慮した施設の開発、設計、運転を実施すること、技術移転への貢献などを求めている。
我が国では、東京商工会議所が、平成2年4月に「地球環境問題と企業活動について」と題する報告書を発表しているが、その中で、企業、政府、国民一人ひとりに求められる対応について提言しており、特に企業に求められるものとして、省資源と省エネルギーの推進、国際的な環境配慮、環境分野における人材の育成と対外協力、地球環境問題への意識高揚と実践活動をあげている。
経済団体連合会(経団連)では、日本の企業が環境問題に取り組む上での理念と具体的な行動指針を明らかにした「経団連地球環境憲章」を、平成3年4月に、経済団体として初めて取りまとめた。これは、日本の産業界として、持続可能な経済社会システムへの転換を念頭において国内の環境問題のみならず、地球環境問題に積極的に取り組むことを通じて、市民との共生、世界への貢献を目指したものである。この中で、行動指針として、環境問題に関する経営方針の確立、環境担当役員の任命や環境担当組織の設置、環境関連規定の策定や年1回以上の内部監査の実施、事業活動の全段階での環境影響評価の実施と環境負荷低減への努力、自主基準の整備等が盛り込まれているほか、企業が途上国で事業を展開する場合を念頭においた「海外進出に際しての環境配慮事項」として10の事項があげられている。本憲章は、その内容の先進性に加え、日本の経済団体が憲章として初めて発表したこともあって、国際的にも大きな評価を得た。また、国内においても、経団連が平成4年5月に会員企業を対象に行った調査(対象企業数948社、回収率57.0%)によれば、本憲章と同趣旨の社内憲章・指針等の制定について、回答企業の40.8%の企業が本憲章を契機に制定・改定したあるいは制定・改定の方向で準備中と回答するなど、本憲章をきっかけに各社の取組が一層進んだ(第2-1-2図)。
さらに、関西経済同友会では、平成5年10月に発表した「21世紀を視座に据えた企業経営の自己革新」と題する提言の中で、企業においてもマクロ経済においても、今後はその成長率及び成長の構造が地球環境保全や世界経済の均衡ある発展、国民の成熟した価値観と調和のとれたものであることが望まれているとの認識のもと、「企業は地域社会さらには人類社会の一員であることを認識し、”市民”としての倫理を持ち応分の義務を果たすとともに、社会に開かれた組織に変革すべきである」と提言している。
個々の企業においても、持続可能な経済社会の構築に向け、環境問題に積極的に取り組もうとする動きが広がっている。環境庁では、企業の環境保全活動の実態を把握するために、平成3年度より「環境にやさしい企業行動調査」を実施しているが、平成5年度の調査結果(対象は、全国の上場企業2080社、回収率は26.8%)によると、環境に関する経営方針を制定している企業は全体の47.8%を占め、平成5年度中に制定する予定の企業6.5%と合わせ、合計で54.3%と過半数を占めている。業種別では、製造業59.4%、サービス業52.6%、建設業50.0%などで多く、また、売上規模別では、1兆円以上で82%など売上規模が大きいほど制定している割合が高い(第2-1-3図)。
以上のとおり、内外の経済団体の憲章や、個々の企業の経営方針などに見られるように、経済活動に環境配慮を組み込み、環境負荷の少ない持続可能な経済社会を構築するという環境と経済を統合する考え方は、産業界においても着実に受け入れられつつある。特に、我が国の産業界においては、こうした理念の確立がバブル経済崩壊の時期と重なっており、量的拡大を追求したバブル経済への反省とともに、持続可能な経済社会の構築の重要性が認識されるようになってきている。