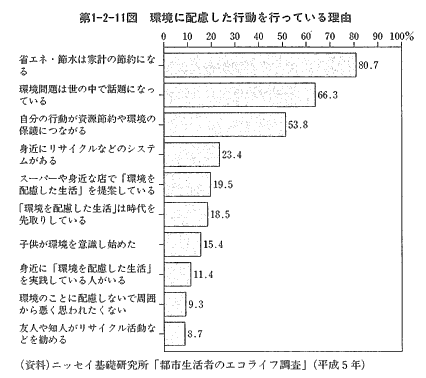
2 取組の支障を乗り越えるための工夫・努力
環境にやさしいライフスタイルが徐々に広がってきている状況について、見てきたが、前節で指摘したように環境保全に関する認識はあるものの行動に結びついていないという人も多く、まだ社会全体に行動が浸透しているとは言えない。また、環境にやさしいライフスタイルを進めようとしても社会的な理由や経済的な理由で行き詰まってしまうケースがある。そこで、ここでは環境にやさしいライフスタイルを促進させる要因、阻害させる要因とその対応について考えてみる。
人々が、日常生活で環境に配慮した行動を行っている理由については、省エネルギーや節水が家計の節約になるという経済的要因、環境問題の話題性、自らの行動が環境保護につながるという意識、身近なリサイクルの仕組みの存在や環境に配慮した生活を提唱している商店の存在といった理由が上位にあがっている(第1-2-11図)。
また、逆に、環境に配慮した行動を行っていない理由については、一人ひとりの行動の効果に対する疑問、環境に配慮した商品・サービスが身近にない、具体的に何をして良いかわからないといった理由が上位にあがっている(第1-2-12図)。
こうしたことから、人々の行動に際して阻害要因となっているのは、第一に一人ひとりが具体的に何をすればよいのか、また具体的な行動がもたらす効果はあるのかという点に関する情報が不足している点であると考えられる。このような情報を提供するために、地方公共団体や民間団体から、「エコライフガイドブック」、「生活環境チェック」など分かりやすく書かれた出版物が数多く配布されている。このように消費者に対して環境にやさしい消費についての普及啓発を進めていくことが重要である。
また、近年では、「環境にやさしい」をうたい文句にする商品が多くなっているが、その一方で消費者からは具体的に効果があるのかどうか分からないという疑問の声も上がっている。グリーンコンシューマー運動の進んでいるアメリカでは、「BIODEGRADABLE(生分解性)」と表示したごみ袋が実際に分解されない、「OZONE SAFE(オゾン層に安全)」と表示したスプレーにオゾン層を破壊する代替フロンが含まれていたとして裁判になるケースが相次いでいる。このため環境保護商品の表示・広告の適正化の観点から、1992年(平成4年)7月に連邦取引委員会と環境保護庁が環境に関する広告のガイドラインを作成した。同ガイドラインでは、「生分解性」、「リサイクル可能」といった表示を行う際に、商品が満たすべき基準を提示している。アメリカでは企業の側でも、消費者に商品の環境にやさしい特性を正確に伝えるため、曖昧な表現を避けて「リサイクルプラスチックを30%使用している」、「外箱に再生紙を100%使用している」と明確に表示する努力が始められている。
こうした中で、環境にやさしい商品を客観的な判断基準に基づきラベルをつけて表示するエコラベルが果たす役割が大きくなっている。消費者自身が商品の製造、使用、廃棄段階を通じた環境負荷を全て把握することは難しく、エコラベルによってこれらの情報が得られるようになることが期待されている。我が国では、平成元年より環境庁の指導の下、エコマーク制度が開始されてきたが、各方面からの意見等を踏まえ、平成6年2月にエコマーク事業の見直しを行い、エコマークの対象となる商品の該当要件として、(1)商品の製造、使用、廃棄等による環境負荷が、他の同様の商品と比較して相対的に少ないこと、(2)その商品の利用により環境保全に寄与する効果が大きいことという2つを明確にするとともに、事業運営の公開性、透明性を高めるための様々な改正が行われた。
第二に、身近に環境にやさしい商品やサービスがない、あるいはリサイクルを行おうと思っても身近にそうしたシステムがないといったことが阻害要因になっている場合も多い。逆に、身近なスーパーが環境にやさしい暮らしを提唱していたり、リサイクルシステムがあったりすると人々の行動を促すきっかけとなっていることが分かる。こうした要因については、消費者だけで解決できる問題ではなく、生産者たる企業や行政が協力して積極的な役割を果たしていくことが必要とされる。こうした中で、企業の側でも、第二章で見るように環境にやさしい商品の開発や流通、販売が行われるようになってきている。また、流通業においては食品トレーや空き罐、空きビンの回収も行われている。行政の側でも資源ごみの回収を進めるとともに、集団回収や再生資源業者に対して補助を行っている団体も多く、環境庁の調査によれば約4割の団体がこうした支援を行っている。
しかし、リサイクルなどの社会システムについては、こうしたシステムがあっても、消費者や事業者、行政が協力しあって支えていかないとうまく機能しなかったり、行き詰まってしまうおそれがある。例えば、古紙のリサイクルにおいては、回収が進み古紙が大量に集まる一方で、古紙の需要が伸び悩むという需給のアンバランスが生じ、古紙価格が低落するという事態が生じている。特に、雑誌の古紙価格はここ2年間で1kg当たり14円から7〜8円へと約半分にまで落ちている。古紙の需要が伸びない背景には、品質が落ちる、値段が高くなるものもあるといった理由で消費者が再生紙を利用しないという面も大きい。こうした中で、リサイクル活動を行っている民間団体の中には、回収するだけでなく、消費者としての意識を変えて再生品を積極的に使用し、再生品の需要を拡大していく運動に取り組んでいるところもある。牛乳パックの再利用を進める団体の中には、再生紙メーカーと協力して牛乳パックからの再生トイレットペーパー等を製造し、製品にマークをつけて利用の促進を図っている団体がある。また、企業が協力してオフィスにおける古紙の分別回収を行っているオフィス町内会では、雑誌古紙100%利用のトイレットペーパーを作成し、マークをつけて使用を呼びかけている。リサイクルのような社会システムをうまく機能させていくためにも、このように様々な主体が協力関係を深めていくことが重要になってきている。
第三に、経済的に得になる行為は人々の行動を促すが、その一方で経済的でない行為は行いたくないという人も多く、人々の行動を阻害する一つの要因になっている。こうしたことから、環境にやさしい行動が経済的にも得になるようにして、人々の行動を促そうという取組も行われている。例えば、無料で配布されていたスーパーの袋を、有料化したら使用量が削減されたという例もある。第3章で見るように、地方公共団体では、ごみ処理料を排出量に応じて有料化し、ごみの排出量の削減に成功した例もある。また、地域限定販売ビールを販売している事業者による罐のデポジット回収や、一部の地方公共団体や事業者団体等によって行われている空き罐回収器により預り金を返却したり、図書券等と交換したりする制度など経済的なインセンティブを活用した環境保全のための取組も進められている。通常のアルミ罐の無償回収では大消費地のスーパー1店あたり1カ月に100kg程度が回収されるが、(社)日本アルミニウム連盟が行った有償回収事業では1罐1円で、1トン以上集まるスーパーも出るなどの効果があった。
さらに、ソーラーシステムや断熱材の導入など、化石燃料使用に伴う大気への負荷を削減するのに非常に効果的ではあるが、かなり高価でなかなか手が届かないという場合も多い。そこで家庭における省エネルギー施設の整備等を支援するため、省エネルギー型断熱構造工事、省エネルギー型暖冷房設備工事、ソーラー住宅工事、太陽熱温水器設置工事等について住宅金融公庫による割増融資制度(環境共生住宅割増)が実施されている。また、住宅用ソーラーシステム及びソーラーハウス用システム等を設置する場合には、(社)ソーラーシステム振興協会により低利融資制度が講じられている。
また、アメリカでは、エネルギー使用量を計画的に削減するための支援も行われている。カリフォルニア州サクラメント市のエネルギー供給公社では、省エネルギーを進めることがもう一つの発電所になるという考えの下、省エネルギー計画を作成して、夏期のエアコンによる電気消費量削減契約を結んだ家庭への低価格での電気供給、夏期の消費電力節約のために家の回りに植える落葉樹の苗木の配布、エネルギー効率のよい電気冷蔵庫やエアコンへの買い替えに対する割引等家庭向けの様々なプログラムを実施している。1993年(平成5年)には電力供給量の約1%に当たる約9600万kWhを削減し、そのうち家庭部門では約4300万kWhを削減した。
今後もこうした経済的な手法の活用が、ライフスタイルを環境にやさしいものに変えていくためにも重要な役割を果たしていくであろう。