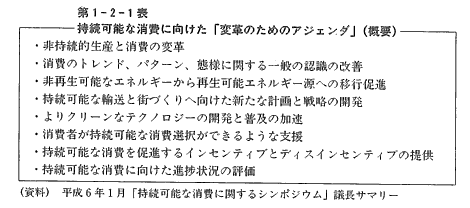
1 環境にやさしい生活行動様式の動向
第1節で見たように、現代日本に生きる我々の消費生活や経済活動は様々な資源を大量消費し、不用物を大量排出し、環境への負荷を増大させている。地球規模で見ると人口、エネルギー使用量、農産物の生産等は、特に第2次世界大戦後に急激に伸びてきている。こうした中で、世界の富める20%の人が全世界の80%の所得を占め、他方貧しい方の20%の人はわずか1.4%の所得しか得ていないことから、先進国が地球の環境資源をほとんど使い果たし、将来の世代や途上国の人々が発展する余地を残していないのではないかという指摘がなされている。
その一方、現在の生活行動様式を環境の観点から見直そうという動きが広がってきている。1992年(平成4年)6月の地球サミットでは、途上国の人口問題とともに先進国の大量消費、大量廃棄型の消費及び生産活動が地球環境に大きな影響を与えていることが認識され、リオ宣言の第8原則で「全ての人々のために持続可能な開発及び質の高い生活を達成するために、持続可能でない生産及び消費の様式を減らし、取り除く」べきであるとされ、アジェンダ21第4章では消費形態の変更に向けた行動計画が提示された。我が国においても平成4年6月に閣議決定された現行経済計画「生活大国5カ年計画」において、環境と調和した簡素なライフスタイルなど環境と調和した経済社会の構築を図ることとされた。平成5年11月に制定された環境基本法においては、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していくことが基本理念の一つに掲げられ、こうした社会を実現するための多様な施策を位置づけた。
1994年(平成6年)1月には、ノルウェー政府が主催し、各国の環境大臣やOECD、産業界及びNGO等が出席した持続可能な消費に関するシンポジウムが開催され、「変革のためのアジェンダ」が議長サマリーとして採択された(第1-2-1表)。我が国からも消費パターンの変更のための情報の必要性について、広中環境庁長官の演説が紹介された。また、議長提案により、OECDは1997年(平成8年)までに持続可能な消費に関するアクションプランを作成することとなり作業が開始された。
このように国際的、国内的に持続可能な消費に向けた取組の必要性が認識される中、我が国においても、政府及び地方公共団体による情報提供や資金援助等様々な支援が行われるとともに、企業においても環境にやさしい商品づくりや自主的な環境管理の推進等新たな取組が始まっている。本節では、消費の主役となる消費者の取組について見てみたい。
(1) 物質・エネルギーの大量消費、大量廃棄の見直し
日常生活で我々が自然から採取する資源量と不用物の排出量は一貫して増え続けており、これに伴う環境負荷も増加し続けている。こうした中で、我々の日常生活に伴う環境負荷を削減していくためには、現在の大量消費、大量廃棄を基盤とする消費生活から、環境に配慮した商品を選択し、長持ちさせて使うという「持続可能な消費」を目指していくことが重要となろう。日常生活では、物質の消費と排出、エネルギー消費等それぞれの場面において、環境への負荷を少なくしていくための取組が始まっている。
ア 商品購入の際の環境配慮
商品購入は家庭への物質の入り口であり、消費者の選択如何によって、家庭から排出されるごみなどの排出物が増えたり減ったりするため、これに伴う環境負荷も変わってくる。また、消費者が環境への負荷が少ない商品を選択するようになると、これらの製品の製造を促し、経済社会を環境に配慮した方向へ変えていくことができる。このように、消費者主権を発揮して経済社会を環境にやさしいものにしていくことを目指した運動、いわゆる「グリーンコンシューマー運動」が広がっている。こうした運動は、まず欧米で活発化し、1988年(昭和63年)9月に刊行された「TheGreen Consumer Guide(緑の消費者ガイド)」がイギリスでベストセラーとなるなど環境に配慮した買物のためのマニュアルが各国で相次いで出版された。我が国においても、京都市の市民団体が作成した「この店が環境にいい」という買い物のためのガイドブックなど、環境にやさしい買い物のためのマニュアルも出版されてきている。こうした環境に配慮した消費者の動きは先進諸国の間で広まってきており、1992年(平成4年)にギャラップインターナショナルが行った調査によれば、環境に悪影響を与える商品の使用を避けていると考える人は、スイス、ドイツでは8割以上、カナダ、イギリス、フィンランド、ノルウェーでは7割以上にのぼり、我が国ではやや割合が低いものの約4割にのぼっている(第1-2-1図)。
我が国においても、消費者の商品購入に対する価値観は変化してきており、今後、商品購入等の基準として、「価格」や「便利さ」以上に「ごみになる量の少なさ」や「環境への影響」、「耐久性・保存性」などに注意するようになると思う人が多く、「流行」や「見栄えのよさ」については、あまり注意しなくなると思う人が多くなっている(第1-2-2図)。
買い物の際の実際の環境への配慮状況をニッセイ基礎研究所が行った調査で見てみると、商品購入に関する行動については、フロン使用製品や使い捨て商品を買わないといった行動は6割以上の人が、詰め替え可能用品や再生紙使用商品を買うといった行動は6割近くの人が、またエコマーク商品の購入については4割近くの人が実行している。また、過剰包装の辞退についてもほぼ半分以上の人が実行している。一方、買い物袋を持参するといった自らの行動が必要な行動については、3割程度に留まっている。性別年代別で見ると、全体的に女性の方が男性より高く、特に30代から50代のいわゆる主婦層ではその実践度が高い(第1-2-3図)。
このような消費者の環境に配慮した商品の購入が進むにつれ、メーカーの環境に配慮した商品づくりも促進される。例えば詰め替え用台所洗剤は、平成2年後半から大手メーカーも製造を開始し、最近では、特定の台所洗剤のうち、詰め替え用商品が全体の半分を占めているものもある。環境にやさしい商品として、エコマーク商品を申請し、認定される商品も急増しており、平成元年末の955商品から、平成5年末には2599商品に増加している。
さらに、より積極的に、消費者と生産者が直結して環境に配慮した商品やサービスの提供を行うネットワークもつくられている。例えば、有機農産物の産地と消費者が提携を結んで供給を受ける共同購入活動、廃油から石鹸をつくる工場と消費者との注文生産といった活動が盛んに行われている。また、各地の生活共同組合においても、消費者が共同して商品の生産、流通、販売に関与する方式を活かして、粉石鹸や有機農産物の共同購入などを行ってきたが、近年では、森林資源の有効利用を図る再生紙文具や廃食油からつくった石鹸、詰め替え用商品等環境に配慮した商品の開発にも取り組むとともに、環境にやさしい商品に「環境商品」マークをつけて推奨するといった取組を行っている。また、兵庫県では消費者団体等が共同して環境にやさしい買い物運動を進めており、環境に配慮した事業活動を行っている事業者を表彰するとともに、環境にやさしい商品を選定し、その普及を図っている。
さらに、途上国の人々の自立を助け、持続可能な開発を実現していくために先進国の消費者が、途上国のコーヒー等の農産物や伝統工芸品を国際相場の数倍程度の価格で購入するいわゆる「フェアトレード」がイギリスやドイツ、オランダ等で盛んに行われている。価格設定には途上国の生産者が直接関わることができるため、価格に途上国生産者の自立を助けるための資金、低農薬で栽培することによる手間賃等環境負荷を削減するために要した資金などを含めることができるのである。我が国でも、民間団体により、途上国で生産された低農薬のバナナに1kg当たり20円の支援の基金を含めて購入するという共同購入運動が始められている。ヨーロッパ諸国ではこうした活動は教会のバザーや通信販売で行われていたが、近年では消費者の支援により販売ルートが拡大し、イギリスでは全国各地のスーパーや商店でもこうした商品が取り扱われるようになり、ドイツでも約2万軒の店舗で取り扱われている。オランダではフェアトレードで輸入されたコーヒーがコーヒー市場の7%を占めるに至っている。
イ 不用物排出の削減による環境負荷の削減
不用物排出の削減は、不用物を分解、浄化する段階での環境への負荷を減らすとともに、自然界から採取した資源を大切に使うことにより、自然界から新たに採取する資源の量を減らすことができる。不用物排出を減量するために、ごみを出すという最終段階だけではなく、商品購入の段階、使用の段階からの配慮が必要となる。不用物の量を少なくすること(Reduce)、使用できるものは繰り返して再利用(Reuse)すること及び再生利用すること(Recycle)という3つの方法、いわゆる3つのRが重要と言われている。
不用物の量を減らすために、商品購入の段階から、家庭に入ってくる不用物を少なくするという配慮が、第1-2-3図で見たように行われ始めている。
また、持続可能な消費を実現するためには、商品を長持ちさせて使うことが重要であるが、近年耐久消費財の平均使用年数は延長傾向にあり、平成3年4〜6月と平成5年10〜12月を比較すると、冷蔵庫は10.2年から11.4年に、エアコンは11.1年から12.5年に、テレビは9.1年から9.6年に伸びている。消費者の間には、バブル崩壊後の経済事情の悪化もあり、耐久消費財を買い控え、長持ちさせて使う傾向が見られる。また、(財)家電製品協会の調査によれば、消費者は冷蔵庫を平均11.7年、エアコンを11.8年、テレビを10.8年程度使用したいと考えている。
一方、長持ちさせて使うためには修理が必要となってくるが、企業に修理に持っていっても部品がなく修理に応じられないという場合もあり、今後、修理受け入れ体制の整備を望む意見もある。また、第1-2-2図で見たように、今後、消費者が商品購入の際に注意する点として、耐久性・保存性のよさをあげる者は6割以上に達している。こうした中、「百年かかって育つ木は百年使えるモノに」という考えに立ち、広葉樹の栽培を自ら手がけ、長持ちする木工家具や生活用品を作成、販売する工芸作業所の活動なども注目されている。
次に再利用の状況について見てみよう。近年、家庭からの不用品の交換や売買を行うフリーマケットが各地にでき、参加者も増加するなど、活発な取り組みが行われている。地方公共団体においても、リサイクルプラザやリサイクルショップなどを設け、市民から持ち込まれた家具や電気製品等の不要品交換情報を提供したり、フリーマーケットの場を提供するなどの取組を行っているところもある。フリーマーケットやリサイクルショップなど中古品や不用品を交換・売買する機会は広く人々にも知られており、積極的に利用したいあるいは利用してもよいと参加の意志を示す人も多い(第1-2-4図)。
また、ビン等容器の再利用を積極的に進めようという取組も始められている。我が国において、ガラスビン回収システムは100年余りの歴史があるが、昭和30年代半ば以降、各種素材の使い捨て容器が生産され始め、企業の販売戦略としての容器デザインの変化、物流コストの低減化、自動販売機による販売形態の普及、消費者のライフスタイルの変化などの理由から再利用ビン(リターナブルビン)の量は減少傾向にある。このような状況の中で、神奈川県の生活クラブ生活共同組合においては、平成5年11月から生協組合員とビンを回収するびん商と生産者の3者が共同して食酢、ジャム等食品ビン容器の再利用を進めるグリーンシステム計画を実施している。ビンの再利用を簡便化するために、ビンの容器の種類を従来の10種類から3種類に統一するとともに、今後1年でびん回収率80%を実現するという目標を掲げ、組合員への広報活動を積極的に行っている。現在、これらのビンについては逆流通ルートが未整備のため、びん商及び生協の負担で回収を行っている。
欧州諸国においても飲料容器の再利用容器の利用が積極的に行われている。デンマークでは1990年(平成2年)から国産のビール、ソフトドリンクは再利用容器を使用するよう法律で義務づけられた。また、フィンランドでは再利用できないすべての容器に対して課税することにより、再利用ビン使用のインセンティブを与え、ビールと炭酸ソフトドリンクについては90%以上が再利用ビンを使用している。再利用できないビンに対する課税強化は、ノルウェーやスウェーデン等でも実施されている。このように欧州諸国の中には、法律で再利用ビンの利用を義務づける規制的手法や、再利用できない容器に対する課徴金や再利用容器に対する課税の減免といった経済的な手法を活用することによって再利用容器の使用を支援している国々もある。欧州諸国の中には、重いために輸送エネルギーがかかる、壊れ易いといったガラスビンの短所を補うために、プラスチック製の再利用ビンを利用しているところもあり、我が国においても利用され始めている。
さらに、再利用できないものや使用できなくなったものの再生利用の状況を見てみよう。現在、再生資源あるいは資源ごみとして再生利用されているものには、ビン、罐、古紙、ペットボトル、紙パック、食品トレー、衣類等がある。リサイクルの効果は、ごみの量を減少させることと、新たな原材料の採取を減少させることにとどまらず、エネルギー使用量を節約する効果もある。例えば、紙、罐を再生利用した場合の生産過程におけるエネルギー節約量を見てみると、処女原料から生産する場合に比べて再生原料から生産する場合では、スチール罐では約3分の1、アルミ罐で約35分の1、紙では約4分の1のエネルギーで生産することができる。ビンについては、ガラスくずの利用を10%高めると、2.5%の燃料を節約できる。再生資源の回収に伴って輸送エネルギーもかかるが、製造エネルギーに比べればわずかな量である。全体的なエネルギー使用量の節減に伴い、二酸化炭素や二酸化窒素などの大気環境への負荷も削減される。現在地方公共団体による回収、住民による集団回収、スーパー等における拠点回収など、様々なルートで回収が活発化しており、回収量が増加してきている(第1-2-5図)。
また、家庭ごみのうち重量で半分近くを占める厨芥について、回収して堆肥化する取り組みも行われている。栃木県野木町では、生ごみの分別回収を実施しており、回収した生ごみは資源化センターで堆肥化し、農家や住民に配布している。岐阜県可児市等では、コンポストを使った生ごみの堆肥化を促進するため、家庭のコンポスト購入に際して補助を行っている。小学校で環境教育の一環として、給食の残りや調理屑が分解されて堆肥になることを学ぶとともに、花壇等の肥料に使うという試みを行っているところもある。
さらに、包装廃棄物は家庭からのごみの中で近年大きな割合を占め始めているが、ドイツでは、こうした包装廃棄物を削減するための取組が行われている。ドイツでは、消費者のグリーンアクションとして、不要な包装をスーパーのレジにおいてくるといった行動が始められ、包装材に対する生産者や販売者の意識を変える一つのきっかけとなった。1991年(平成3年)には包装材製造者及び販売者に包装廃棄物の回収、再利用及び再生使用を義務づける「包装廃棄物回避に関する政令」が制定され、1992年(平成4年)1月以降は、食品容器の外箱や贈答用の包装といった二重包装はスーパーマーケット等販売業者が店の中で回収している。また、こうした引取り義務は、事業者が参加した収集システムが整備され、一定の回収率を達成している場合は免除されることから、民間会社のデュアル・システム・ドイチェラント(DSD)による回収も進められている。ドイツ社会調査方法・分析研究所が1993年(平成5年)に行った調査では、最近1カ月の間に包装材を店に置いてきたという人は54%に達している。こうした行動を受けて、販売業者の側でも包装材を削減したり、なくしたりする取組が行われている。
ウ エネルギー消費に伴う大気への負荷の削減
第1節で見たように、家庭におけるエネルギー使用や自動車の使用の増加に伴って、一世帯当たりの二酸化炭素排出量は、10年前と比較すると約2割増加している。
こうした中で、エネルギーの使用や自動車の使用を削減していこうという試みが始まっている。例えば、個人の生活が環境に与える負荷の量をチェックし、ライフスタイルを変えて行くための試みとして「環境家計簿」が生協などの消費者団体や地方公共団体などの間で広まってきている。環境家計簿には、水への配慮や、ごみの減量、自然とのふれあいといった様々な項目があるが、その一つとして、省エネルギーや車の利用のチェックが行われている。
一例として、広島県地区衛生組織連合会では、特に家庭におけるエネルギー消費、二酸化炭素排出削減を目的とした環境家計簿を作成しており、モニターの家庭で電気、ガス、灯油、ガソリン等のエネルギー使用量等を記入して送付すると、自分の家庭からの二酸化炭素排出量が記入されて返送されるという仕組みになっている(第1-2-6図)。また、全世帯及び自分の家庭と同じ世帯人数の家庭の二酸化炭素排出量平均値も記入されているため、自らの生活がエネルギー多消費型で環境により多くの負荷を与えていないかどうか把握することができるようになっている。併せて情報誌を配布し、調査結果全体の報告や生活の中での環境への工夫についての普及啓発も行っている。二酸化炭素の排出は直接目に見えないため、なかなか普段の生活で実感されにくいが、こうした取組が人々の意識を高め、二酸化炭素排出の少ないライフスタイルへのきっかけとなっていくことが期待される。
また、第一節で見たように、電気製品や自動車等エネルギーを消費する耐久消費財の使用は家庭からの大気への負荷の量を左右する要因の一つだが、こうした耐久消費財に対する消費者意識の変化も見られる。消費者が電気製品に求めることを見てみると、多機能のものが増えるなどエネルギー消費量を増加させる要因も含まれているものの、5割以上の人が消費電力の小さいものを選びたいとしている(第1-2-7図)。
自動車についても、(社)日本自動車工業会の調査によれば、次に自動車を買い替える際に重要となる点として、多少価格が高くても燃費の良い車、排気ガスのクリーンな低公害車をあげる人は6割以上にのぼっている。ただし実際に購入したいと考えている具体的な車種として、大中型車や小型車など、現在保有している車より排気量の大きい大型の車を志向する傾向も見られ、意識の中の矛盾も感じられる(第1-2-8図)。
さらに、暖房時のエネルギー使用量を減らすことができる断熱材の導入や複層ガラス(ペアガラス)の使用も広がってきている。(財)住宅・建築省エネルギー機構の推計によれば、平成4年度の断熱化率は新築住宅については戸建住宅91.6%、共同住宅95.8%、住宅全体のストックとして見ると戸建住宅については27.7%、共同住宅については52.3%にのぼっている。また、建築用ペアガラスの年間販売数は、ビル及び家庭用を含めて、昭和62年の175万2千?から、平成4年には251万6千?へと増加している。住環境計画研究所の試算によれば、東京の戸建住宅で100mmの断熱材とペアガラスを導入した場合6割以上、集合住宅で25mmの断熱材とペアガラスを導入した場合には6割近くの省エネルギー効果が生じ、暖房機器の使用を減らすことによりエネルギー消費にともなう大気への負荷を削減することができる。また、北海道の戸建て住宅で100mmの断熱材とペアガラスを樹脂サッシで導入した場合には約75%以上の省エネルギー効果がある。
このようにエネルギー使用機器の選択や使用方法の見直しの意志をもっていたり、既に実践している家庭もあるが、国立環境研究所では、家庭におけるこうした取組でどのぐらい二酸化炭素排出量を削減できるか試算を行ってみた。試算の前提として、世帯数の増加、住居面積の増加、テレビや冷蔵庫などのエネルギー使用機器や自動車の普及や大型化、高性能化、冷房や暖房の使用や、お湯の使用量の増加が進み、平成22年(2010年)では日本全体の家庭でのエネルギー及び自動車使用に伴う二酸化炭素排出量は、平成2年(1990年)の排出量6460万トン(炭素換算)の1.4倍程度になると想定した。次に、日本全国の家庭で様々な対策がとられた場合を想定した。平成22年までに冷暖房の使用を10%削減すると約170万トン、またテレビのサイズや冷蔵庫のサイズを平成2年現在とほぼ同じぐらいにすると、約260万トンの二酸化炭素排出を削減できる。さらに、様々なエネルギー使用機器や住宅設備を購入する際に、何年で元をとることを考えるかによっても機器の選択が変わってくるため、二酸化炭素排出量は変化する。例えば、白熱灯と螢光灯では、実際の購入価格は白熱灯の方が安いため短期的な視点に立つと白熱灯が選択されるが、3年間ぐらいで元がとれればよいと考えると、電気消費量が少なく長持ちする螢光灯を選択する人が増えて、二酸化炭素の排出量も減る。また、断熱材の導入も、10年程度で元がとれればよいと考えるようになると、導入する人が増加して暖房機器の使用が減少する。さらに、給湯のためのソーラーシステムも、20年程度で元がとれればよいと考えるようになると導入する人が増え、二酸化炭素排出量は約1520万トン削減される。このように長期的な視点に立って、エネルギー使用機器等の選択が行われると、初期投資は高くなるが、二酸化炭素の排出量をかなり削減することができる。さらに、家庭で使用する自動車の選択に当たっても、現在普通車を保有している人のうち買い換えの際に10%の人が小型車を選択し、小型車を保有している人のうち買い換えの際に10%の人が軽自動車を選択すると、日本全体で約70万トン、自動車を買い替える場合にすべての人が現在の車より10%燃費のよい自動車を選択すると、日本全国では約390万トン二酸化炭素の排出を削減することができる。さらに、紙のリサイクルが進み、古紙利用率が現在より10%上昇すると、約50万トンの二酸化炭素の排出を削減することができる。これらのことが全て実行された場合には、家庭からの2010年の二酸化炭素排出量は1990年と比較して約1.1倍程度となると予想できる(第1-2-9図)。以上のように、エネルギー使用機器等の利用方法、購入の際の消費者の考え方が変化すれば、かなりの二酸化炭素排出量を削減できることが分かる。
(2) 水循環への配慮及び自然と共生したレジャー活動
日々の生活の中で我々が排出した排水は、微生物の働き等による浄化を始めとする水の循環の大きな流れを経て、再び水となって帰ってくる。こうした水の循環の恵みを持続的に利用していくために、水の循環に配慮した排出、利用に向けた様々な取組が始まっている。また、自然の中でのレジャー活動が活発化している今日、レジャーを通して自然とふれあう場合も自然環境への負荷を減らそうという取組が始まっている。
ア 水循環への配慮
第1節において、家庭から排出される生活排水が水質に対して大きな負荷を与えている状況を見てきたが、こうした負荷を減らしていくために、個々の家庭が果たす役割は大きい。ここでは水利用における家庭での取組事例を見てみよう。
埼玉県では、県内の河川の有機汚濁の73%が生活排水に起因しているが、平成4年に生活排水モデル地区を選定し、家庭に、(1)三角コーナーに水切りごみ袋を設置、(2)米のとぎ汁を流さない、(3)水質汚濁負荷の大きい味噌汁や酒等を飲み残さない、(4)廃食用油を流さない、(5)汚れた食器を拭いてから洗う、(6)洗濯の際の石鹸や無リン洗剤の適量使用、(7)風呂の残り湯の再利用、(8)シャンプーの適量使用といった対策を求めるとともに、水切りごみ袋や油の凝固剤等台所排水浄化セットを配布した。第1-2-2表に見るように、個々の家庭において、熱心な取り組みが行われた結果、モデル水域の排水が流入する水路において、BODは53.2%、SS(水中の浮遊物質量)は50.8%、窒素は40.9%、リン分は43.7%削減することができた。同地域では、河川の汚濁について90%の人が関心を持ち、汚濁の原因について生活排水が主原因であると考える人が57%を占めるなど、身近な川の水質汚濁への関心、汚染者としての自覚意識が高く、調査活動後も引き続き多くの人が取組を続けている。他の都道府県の調査でも、こうした家庭内対策により、家庭からの水質汚濁負荷の2〜3割の削減効果が報告されている。また、下水道が整備されている地域においても、家庭からの水質汚濁負荷の削減は、下水道の処理に対する負荷を削減する効果をもたらす。
特に、家庭からの水質汚濁負荷のうち最も大きな負荷を占める台所からの負荷を削減するために、煮汁を少なくする調理方法や煮汁の再利用を行うなどの「エコクッキング」が石川県など地方公共団体や消費者団体等により、各地で調理実習や勉強会が行われている。エコクッキングにおいては、この他にも、野菜の皮や切りくずを調理に生かしてごみを減らしたり、鍋の効率的な利用による省エネルギーなど、環境負荷を減らすために台所でできる様々な工夫が盛り込まれている例もある。
こうした家庭内での取組に加え、身近な河川や湖沼といった水環境をきれいにするための取組も積極的に行われている。住民の手による水質調査といった水質の状況を把握するための活動から、河川の清掃、ホタルなどの水生生物が生息できる環境を取り戻すための活動など地域の住民の知恵を凝らした活動が各地で進められている。
イ 自然と共生したレジャー活動の進展
第1節で見たように、近年の国民の余暇志向の高まりから様々なレジャー活動が活発になってきているが、こうしたレジャー活動においても、環境への負荷をできるだけ少なくしていこうという動きが芽生えている。
レジャー活動は、スキー場やゴルフ場などの大規模な利用施設整備のために自然環境の改変を伴う場合があるが、こうした大規模な施設を特に必要としない自然のフィールドを生かしたレジャー活動を楽しもうという動きがある。例えば、スキー場設備の必要なゲレンデスキーに対し、クロスカントリースキーで雪の野山を自由に歩き、あるがままの自然とのふれ合いを楽しむといった民間団体の活動が見られる。こうした活動の中には、大規模レジャー施設の整備に伴う自然環境への負荷の削減を意識して行われている場合もある。また、ネイチャーゲームを始め自然の中で五感を使って楽しむゲームは欧米諸国で広く受け入れられているが、我が国でも子供達が楽しめるレジャーとして普及活動が行われている。このように自然のフィールドを生かし、自然とふれあう活動を行っている民間団体は、首都圏においても年々増加してきており、平成3年には400団体以上に上っている。具体的な活動内容としては、自然や野鳥の観察を行うものが210団体と最も多く、ハイキングやウォーキング等の散策を行うもの、キャンプ等の野外レクリエーションを行うものも70団体近くに上る(第1-2-10図)。こうした自然とのふれあい活動を支える施設として、自然観察施設や自然歩道、自然のフィールドを活かした野外活動施設等についても注目が集まっており、その整備が進められている。
また、大勢の人が観光活動のために自然の中に一度に入り込むことで植生の破壊、交通渋滞による大気汚染、ごみの増加といった環境負荷が増加する場合があるが、こうした事態を避け、環境への負荷が小さく、より深く自然とふれあう観光としていわゆるエコツーリズムへの関心が高まってきている。
エコツーリズムは東・南アフリカ、コスタリカ、エクアドル、イギリス、アメリカなど諸外国においても盛んになってきている。一度に多人数が押し掛けないようエクアドルのガラパゴス諸島のように観光者の数を制限したり、また、観光客に自然や動植物についての解説を行うガイドがついて自然について深く知ることができるようになっているものもある。
欧米諸国では、1991年(平成3年)にドイツなどの環境保護団体や交通関係機関、宿泊関連事業等の連合により「欧州エコツーリズム連盟」が結成され、エコツーリズムに関する情報提供や教育活動、旅行業者や観光関係団体、宿泊関連業者へのアドバイス等の活動を行っている。イギリスでは、環境に対する負荷が少なく、地域の特性を生かして地域社会を発展させ得る持続的なツーリズムとしてグリーンツーリズムが提唱されている。グリーンツーリズムの条件としては、イングランド・カントリーサイド委員会が、小規模で、社会面、環境面での配慮がなされていること、地域の文化、生物等の特質に依拠したものであること、景観、環境を尊重しつつ、緩やかに発展するものであること、公共交通機関を利用することといった点をあげている。こうしたグリーンツーリズムの普及のために、民間団体によってグリーンツーリズムのためのガイドブックやチェックリストが作成され、観光客に配布されるといった取組が行われている。
我が国においても、野鳥やクジラ等野生生物の観察や自然観察、登山、自然の中でのキャンプや冒険などを目的とした自然をよく知り、ふれあいを楽しもうという旅行への参加が盛んになってきている。最近では、海外の国立公園で野生動物の観察を行う、原生自然の中で冒険を楽しむといった旅行への関心も高まってきている。
さらに、環境保全のための活動を旅行というレジャーの一つとして、楽しみながら取り組んでいこうという動きがある。日本沙漠緑化実践協会では平成3年から、ボランティア参加により中国において砂漠化防止のための植林などを行うツアーを行っている。平成3年度は70人が参加したが、5年度には345人と5倍近い人が参加し、内モンゴル自治区のクブチ砂漠に100万本の植林を行う計画を実施している。この他にも、ボルネオ等で熱帯林の植林、登山客の出すごみを片づけるヒマラヤ登山清掃、また国内においては空き罐拾いツアーや観光地のクリーンアップキャンペーンなど環境保全のための活動を実践する様々な旅行への参加が盛んになってきている。