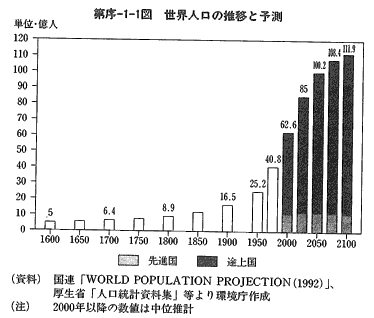
環境問題に関連の深い人口と社会経済活動の長期の趨勢についてみるといずれも今世紀に入って巨大化しており、特に第二次世界大戦後は幾何級数的な伸びが見られた。これに伴い、資源の状況の悪化や環境への不用物の排出も急激に増加している。これを地域的に見れば、先進国では、人口が安定し成熟化に向いつつあるが、既に二酸化炭素排出量等環境負荷が巨大な水準に達しており、また緩やかな伸び率でも増加する負荷の量は大きなものとなる状況にある。他方、途上国では、一人当りの環境負荷は低いが人口の爆発的増加を背景に環境への負荷の拡大が続いている。以下それぞれの事象毎に長期的な趨勢を検討することとしたい。
(1) 人口の増大
人口は人間社会の活動総量の基盤となる指標であり、当然のことながら人口の増大と人類による環境の改変とは深く関連して歩んできた。
世界の人口の増大は、長い間緩慢であり西暦元年頃には約3億人であったものが1500年に約4.3億人に増加した程度であった。しかし、近世に入って次第に増加の勢いを強め、産業革命の始まる時期に当たる1750年には7.3億人、その100年後の1850年には12.6億人となった。さらに20世紀に入って幾何級数的増大を示し、1950年の25億人から1990年には53億人に達している。特に、近年の開発途上国における伸びは顕著であり、途上国の人口は1950年に17.7億人であったものが1990年には42億人となり、その世界人口に占める比率も70%から79%へと増加している。人口の増加率は、貧しい国ほど高い傾向を示しており、貧困による環境破壊を加速させる結果となっている。
今後の世界人口については、人口増加率は次第に低下しているものの絶対数については引き続き大きく増加するものと見られている。これについては様々な推計がなされているが、国連の行っている推計の中でもっとも可能性が高いと考えられるケースである中位推計によれば、2025年には約85億人、2050年には100億人に達し、おそらく2150年ころ116億人程でピークを迎えるものと見られている。今後の人口増大の圧倒的な部分は開発途上国で起こると見られ、2050年までに増加すると予測される47.3億人のうち、97%は開発途上国において生じると予測されている。特に、アフリカにおける人口増加は爆発的であり、1990年の6.4億人から2050年にはその約3.5倍の22.7億人に増加すると見込まれている。一方、先進国の人口は、安定的に推移すると見られており、1990年の10.9億人から、2025年ころおおよそ12.4億人でピークを迎え、その後微減しつつ2050年には12.3億人ほどになると見られている。また、同じ国連の推計においても、高位推計では22世紀の初めには世界人口が200億人を超えると見積られていることにも注意する必要がある(第序-1-1図)。
世界人口が増大している一方で、世界的に人口の都市化が進んでいる。1950年には途上国の人口の83%が農村地域に住んでいたが、今世紀末にはこの割合が60%にまで落ちると見られている。さらに、21世紀の初頭には世界人口の半分が都市に居住するようになると見られる。ここ、20年間、開発途上国においては、メガシティーと呼ばれる巨大都市が台頭してきている。1950年には世界の10大都市の内7つは先進国の都市でそれも人口1500万人以上の都市はなかったが、1990年代の終わりには、10大都市の内、8つは途上国のものとなりその全てが人口1500万人以上のものとなると見られている(第序-1-2図)。
途上国の大都市においては、下水道、廃棄物処理施設、公共交通機関、道路などの公共資本の整備が進まないまま人口の爆発的な増大を見ており、その多くが深刻な水質汚濁や大気汚染問題を抱えている。
我が国の人口は、江戸時代の初期に大きく伸びた後、鎖国体制という閉じた系の中で約3000万人程度で安定していたが、明治以降急増し第二次世界大戦前の1940年には約7200万となり、1970年には1億人を超えた。一方、1970年代半ば以降人口増加率は減少しており、1992年の人口は1億2445万人でその前年との間の人口増加率はわずかに0.33%となっている。厚生省人口問題研究所の中位推計によれば、2010年ころ約1億3千万人でピークを迎え、その後2090年の9600万人に向けて減少していくものと見られている(第序-1-3図)。
このような中で、人口の高齢化が進んでおり、65歳以上人口は1950年の約5%から1990年には約12%ととなり、さらに、今後も上昇を続け、2040年頃約28%でピークを迎えるものと予測されている。また、これに伴って、生産年齢人口も、1993年の約8700万人から2050年には約6300万人にまで低下するものと予測されている。また、人口の高齢化は、家計に占める消費の割合を高め、投資余力が下がっていくと見られている。これから20世紀の終わりまで残された期間は環境保全関係のものを含め社会資本整備のための貴重な期間と考えられている。
(2) 経済規模
経済成長は、人口と並んで人間活動の総量の動向を示す基本的な指標の一つである。
世界総生産額は、第二次世界大戦後、二度の石油危機の時期を除いて大きく増大し、1950年から1990年の間に実質でほぼ5倍になった。他方、これを一人当りでみると、人口増大が大きかったことから同期間中の伸びは2.3倍となっている(第序-1-4図)。
一人当りの所得には世界的に大きな格差が存在している。1960年から1980年の間先進国と開発途上国の一人当りGDPの格差はほぼ10倍前後で推移していたが、1990年にはその格差は12.7倍に拡大している。開発途上国を地域的にみれば、南・東アジアでは、1960年から1990年の間に2.7倍に増加しており特に80年代以降大きく伸びている反面、サハラ以南のアフリカでは1960年から1990年の間に逆に0.9倍に減少している。
一人当りGDPの将来については国連事務局が予測したものがあるが、これによると、1990年から2000年の間に、先進国では1.29倍、途上国では1.22倍となり、南北間の格差は全体としてみれば大きな変化はないものと見られている(第序-1-5図)。
世界の経済成長の超長期の見通しとしては、IPCCが1992年に公表した地球温暖化の予測のシナリオとして用いたものがある。これによれば、先進国では安定的な成長が、開発途上国では人口増大を背景に高い成長が見込まれているが、いずれも2100年に向かって次第に経済成長率が低下していくものと考えられている(第序-1-1表)。
我が国のGNPは昭和30年(1955年)から平成2年(1990年)の間に、実質で9.3倍に増大した。これに伴い、我が国のGNPが世界のGNPに占める割合も増大しており、昭和47年(1972年)に6.8%だったものが平成4年(1992年)には15.3%となっている(第序-1-6図)。
昭和30年(1955年)から昭和45年(1970年)までの「高成長」の時期の実質GNPの年平均成長率は10.0%であったが、昭和45年(1970年)から平成2年(1990年)の「安定成長」の時期には実質GNPの年平均成長率は4.3%に低下し、さらに平成3年(1991年)のバブル崩壊以降は平成3年(1991年)3.6%、平成4年(1992年)0.7%と低下している。
我が国の経済成長率の将来については、経済審議会が平成3年に公表したものがあるが、これによれば、人口増加率の低下とそれに伴う高齢化等に伴い、我が国の経済成長率は、1980年代後半の年平均4.6%から2010年に向けて次第に低下すると見込まれている。
(3) エネルギー使用量の増大
次に、エネルギー使用量の長期的推移と将来の推計について概観する。エネルギー使用量は社会経済活動の最も基礎的な指標であるとともに、エネルギー使用に伴い二酸化炭素や窒素酸化物等の大気環境への負荷が発生している。
統計が整備されている1860年以降について見ると、薪等のバイオマスを除く一次エネルギー供給量は、1860年から第1次世界大戦のあった1910年代前半までは、年率4%程度の伸びを続けたが、その後、第2次世界大戦のあった1940年代前半までの時期は、世界的な景気停滞の時期に当たり、エネルギー供給も2%弱程度の比較的低い伸び率で推移した。第2次大戦後は、中東における大油田の発見とそれに伴う石油価格の下落に支えられて、1973年の第1次石油危機まで年率5%を上回る高い水準で急激に増加し、1950年約1900・石油換算百万トンであったものが、1970年には約4700・石油換算百万トンと20年間で、2.5倍に増大した。その後、1973年の第1次石油危機、1979年の第2次石油危機による石油価格の急激な高騰に伴って省エネルギーが進みエネルギー需要の伸びが鈍化したが、1986年以降石油価格が下落したため再び伸びが増大した(第序-1-7図)。
世界のエネルギー需要の将来推計の代表的なものとしては、国際エネルギー機関(IEA)が1993年4月に公表したものがある。その自然体ケース(新たな施策を見込まない趨勢ケース)によれば、1990年に7768・石油換算百万トンであった一次エネルギー需要は、2010年には11476・石油換算百万トンと約1.48倍に増加するものと見込まれている。その伸びは開発途上国において高く、これに伴い開発途上国の世界の一次エネルギー需要に占める割合は約26%から39%に高まるものと見込まれている。中でも特に南・東アジアで大きいと予測されている。また、一人当りの一次エネルギー消費量についてみると南北間の格差が大きく、1990年には先進国では一人当り4.78石油換算トン、開発途上国では0.53石油換算トンと9倍の開きがある。2010年においては途上国の一人当りエネルギー使用量の伸びが大きいためこの開きは縮まるが、6.9倍の開きがあるものと予測されている(第序-1-8図)。
我が国の一次エネルギー供給は、戦後高い伸びを記録し、昭和30年(1955年)から昭和48年(1973年)の間に6.01倍となった。その後、2回の石油危機を経験し昭和48年(1973年)から昭和61年(1986年)にかけてはGNPが1.6倍になったのに対し、一次エネルギー供給は1.04倍とほとんど横ばいで推移した。昭和61年以降は石油価格の低下とバブル期の景気拡大を背景に、高度経済成長期ほどではないものの再び高い伸びを見せている。一方、その将来について「石油代替エネルギーの供給目標」(平成2年10月)により見てみると、1989年に4.99億kl(石油換算)であったものが、2010年には6.57億klと約1.29倍に抑えることを目標としている(第序-1-9図)。
なお、以上エネルギー使用量の過去の推移と将来の推計等について概観したが、エネルギー源の構成における二酸化炭素排出の少ない又は排出のないものの導入等も重要であり、国では安全性の確保を前提とした原子力の開発・利用、天然ガスの開発・利用や水力、地熱の利用、また、コンバインドサイクル発電、太陽光発電の導入等を引き続き推進することとしている。
(4) 農林水産物の生産と消費の増大
農林水産業は、食糧や木材等の供給により人類の生存を最も基礎的なところで支えている重要な活動であり、また、農林水産業が営まれている地域においては、適切な農林水産活動を通じて農地、森林等が有する環境保全能力が維持されている。一方、その生産活動に伴い、途上国を中心に進んでいる森林から農地への改変といった資源利用や欧米諸国における肥料等の使用による水質汚濁、家畜等からの温室効果ガスの一種であるメタンガスの発生という形で、環境に負荷を与えている。
ア. 主食生産
世界の穀物生産量は、1965年の1006百万トンから1988年には1743百万トンと世界全体で73%増加し、特に、開発途上国では同期間に106%の大きな伸びを記録した。これは、新品種の導入が大きく、さらに肥料、農薬、農業機械の利用の増大が世界の食糧増産に寄与している。
一人当り主食生産量を地域的に見ると大きな地域間格差が見られる。86年から88年の3年間の平均について見ると、先進国及び東欧旧ソ連では、800kgを超えている一方、途上国では284kgに留まっている(第序-1-10図)。
また、経年的に見ると先進国及び東欧旧ソ連ではそれぞれ1.4倍、1.43倍に増加しているものの、開発途上国では約1.17倍の増加に留まっており、さらにサハラ以南のアフリカにおいては逆に減少している。
また、世界の穀物事情は次第に貿易に依存するようになっており、先進国から開発途上国への輸出が次第に増大している。
穀物生産の将来については、国連食糧農業機関(FAO)により予測がなされている。これによれば、開発途上国では生産が55%増加するものの人口増加がそれを上回るため純輸入量が拡大し、先進国(東欧旧ソ連を含む)では開発途上国の純輸入量を幾分超える輸出余力を維持するものと予測されている(第序-1-11図)。低所得国が穀物輸入を確保できるかどうかが大きな問題となる。
また栄養不足人口については、世界全体で88年から90年の3年間平均7.8億人から2010年には6.4億人に減少するものの、サハラ地域以南のアフリカでは急増することが予測されている(第序-1-12図)。
他方、農業生産の拡大に伴い、農業への資材の投入量も急増している。代表的な農業資材の一つである肥料は農産物の増産に大きな貢献をしてきた一方で、欧米諸国における地下水における窒素濃度の上昇等の水質汚濁問題や温室効果ガスの一種である一酸化二窒素の大気中への放出などに影響を与えている。
今世紀に入ってからの世界の肥料の消費量の推移について見てみると、1910年頃およそ300万トンであったものが次第に増加し第二次大戦前の1938年ころには900万トンとなった。第二次戦後は、幾何級数的に増加し、1955年ころ約2930万トンであったものが1970年ころには約4670万トン、1980年には約11670万トンに達した。
地域的に見ると、開発途上国では、先進国より半世紀以上遅れて1960年頃から肥料使用量が拡大を始めその後上昇の一途をたどっている。他方、先進国においては、1970年代の半ばから増大の勢いが弱まり、1980年代の後半になって、穀物の生産調整等から、肥料使用量が減少傾向に転じた。このため、世界全体の肥料使用量も1988年頃を境に減少傾向に転じている(第序-1-13図)。
肥料使用量の将来については、国連食糧農業機関(FAO)が中国を除く途上国について行ったものがあり、これによれば、1988年から1990年の3年間の平均使用量と2010年の使用量を比較すると2.2倍に増加するものと予測されている。
イ. 森林資源
世界の森林面積は、減少しつつある。昭和49年(1974年)から平成元年(1989年)までの15年間についてみると、先進国ではほとんど変化がないのに対し、開発途上国では6.8%減少している。特に、FAOの森林資源評価によれば、熱帯林の減少が大きく、昭和56年(1981年)から平成2年(1990年)の間に、年間平均15.4万km
2
の熱帯林が失われている。
林産物の消費は過去大きく増大している。主な林産物の消費量の推移についてみると、昭和45年(1970年)から平成2年(1990年)の間に、薪炭は11億m
3
から18億m
3
へ1.64倍に、工業用丸太は12.8億m
3
から16.5億m
3
へ1.29倍に増加している。
林産物消費の将来については、国連食糧農業機関(FAO)が予測したものがある。これによると、林産物消費は2010年に向けて引続き大きく増加する見込みであり、特に途上国の伸びが高いと予測されている(第序-1-14図)。
ウ. 魚介類
世界の魚介類生産量は、昭和25年(1950年)には海洋・淡水あわせて2000万トン強であったものが、平成元年(1989年)には1億トンに達した(その内、8640万トンは海洋)。その後海洋における漁獲が減少したため、平成2年(1990年)には9700万トンに減少した(第序-1-15図)。
魚介類の生産量の将来については、国連食糧農業機関が行ったものがある。これによれば、現在の形で漁業活動が続けば、海洋からの総漁獲可能量は1億トンを大幅に超えそうになくおそらくそれより低くなるだろうと見られ、海洋からの総漁獲量については大きな伸びは期待できない。2010年の海洋・淡水合わせた可能な漁獲量は9000万トンから1億1000万トンと見られている。また、養殖による生産は、平成元年(1989年)から平成3年(1991年)の3年間の平均で1200万トンであるが、近年の伸び率を考慮すると2010年には1500-2000万トンに増加するであろうとしている。開発途上国における人口増加等に伴う水産物需要の増大が見込まれる一方で、最近、世界の漁業生産量が停滞傾向に転じたことに見られるように、生産が資源変動等に左右されることの多い漁業にあっては、供給は必ずしも安定的に推移しないことから、世界の漁業生産の動向次第では、今後、世界的に水産物需給が引き締まることも考えられる。
したがって、持続可能な漁業活動のため、資源管理と沿岸域の環境保全の推進が重要である。