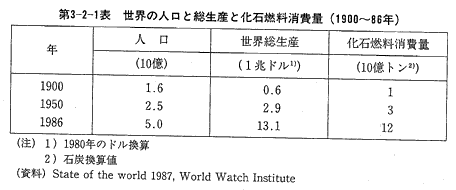
1 環境問題とその原因の構造の変化
前節でみたように、公害、自然環境破壊は、産業革命以降の人間活動の拡大により、自然界にない物質の製造・排出といった質的な面でも、また活動の規模という量的な面でも環境への影響が増大していったことによって顕在化してきた。環境を悪化させる人間の活動が比較的小規模な場合には、影響は地域的なものにとどまるものが中心で、地域における対策により解決が図られる種類のものであった。また、環境の汚染が蓄積せず一過性のものである場合には、対策の進展により以前と同様の良好な環境を回復できると考えられた。そして、地域的に直接に人間の健康や生活環境へ影響を引き起こすような環境負荷が主に着目されていた。これまでの環境対策は、概ね以上のような問題認識に沿って整備されてきたといえる。
このような考え方に重大な見直しが求められるようになったのが、近年の地球環境問題への関心の高まりをきっかけとしてであった。ここでは、地球温暖化問題や生物多様性の減少問題などを例に、今までの考え方では把えられない環境問題の新たな側面について整理したい。
地球環境問題が顕在化してきた背景には、人間の各種活動があらゆる分野で拡大し、このままでは地球全体としての様々な制約に突き当たり、人類と地球の将来に重大な危機が訪れるのではないかということが認識されるようになったことがある。実際、世界の人口は20世紀初頭の約16億人から現在の50億人超まで3倍以上に増え、また、世界の総生産は、20世紀始めの21倍となっている(第3-2-1表)。この点を人類の危機としてとらえた議論の嚆矢となったのが、昭和47(1972)年に発表された「成長の限界」(ローマクラブによる報告)であり、このレポートでは、世界の人口、工業化、資源・エネルギー利用は幾何級数的な成長を続けていて、このような成長率が不変のまま続くならば、来るべき100年の間に地球上の成長は限界点に到達し、人口と工業力の突然の減少をもたらすおそれがあることを予測した。また、昭和55(1980)年に発表された「西暦2000年の地球」(アメリカ合衆国政府特別調査報告)では、2000年までの20年間に予想される総合的な環境への影響は、人口、経済成長、資源等の見通しに深刻な影響を与えるおそれがあることを予測した。
「宇宙船地球号」という表現は、今日における地球全体としての様々な制約の中で、社会を営まなければならない人類の状況を表現したものであり、宇宙飛行士が、外部から資源やエネルギーの補給がなく、また、生じた廃棄物を内部で処埋しながら生活しなければならない宇宙船の中で生活する姿にたとえたものである。また、同様に、人間の活動のあり方についての発想を変える必要性を示したたとえとして、「カウボーイ経済」から「宇宙人経済」ヘということが言われる。「カウボーイ経済」とは、あたかも広大無辺な原野でカウボーイが振る舞うように、資源や環境の制約がないかのようにこれらを浪費する経済活動のことであり、「宇宙人経済」とは、地球が、資源についても廃棄物の捨て場としても、無限の貯蔵所があるわけではない宇宙船のようなものであることを表現したものである。
以下、このような状況を認識させることとなった大きな問題の変化について見よう。
第1に、地球温暖化の問題の顕在化は、以上のような人間活動の拡大に対する警告や、人間活動のあり方に対する危惧に対し、強い現実性を与えることとなった。地球の温暖化は、全世界共通に影響を受ける問題であること、さらに、現在の世代というよりも将来の世代になってはじめて影響が生じるような問題であるということである。地球全体としてみた大気は、その利用に当たって誰も経済的費用を支払う必要がなく、一方、園境を超えて自由に移動するので、何人も、また、どの国も占有できないという典型的な自由財としての性格を持っている。第3-2-1図にみるように、温暖化の大きな原因であると考えられている二酸化炭素の排出には、先進国を中心に、世界各国がその活動の規模に応じて関わっていることから、各国を通じた取組が求められる。しかし、大気の自由財としての性格から、ある国における対策の効果は他の全ての国に及び、一方、対策を取らない国があっても、その国に便益が及ぶことを排除できないという性格があり、フリーライダーが生じるおそれがある。このため、各国には自国の利害だけでなく、地球全体の保全を図る努力を払う意識が必要であるとともに、世界の協調した対策を確保するための枠組みを作ることが求められるのである。そして、現在の行為が現在の生活に与える影響だけではなく、将来の世代に与える影響をも勘案した意思決定を行うための枠組みが必要となる。
地球温暖化の問題は、過去及び現在排出される二酸化炭素等の蓄積によって生じるものであり、ゆっくりと進行し、いったん顕在化してから対策を取っても回復することが困難な不可逆的な現象である。このため、これまでにも増してより予見的な対応が求められるものであり、科学的な知見を充実していくとともに、科学的に未知の部分が残る中でも、将来に備えできるだけ影響の少ない経済社会活動を行っていく考え方が求められる。
また、地球温暖化の主要な原因物質であると考えられている二酸化炭素は、エネルギーの消費など日常生活や事業活動全般に伴って排出されるものである。このため、特定の活動についての対策のみでは二酸化炭素の排出を減らすことは困難が大きく、二酸化炭素排出に直接、間接に関わる各種活動について幅広く対策を取っていくことが求められる。すなわち、これまでの環境政策が主要な手法としていた直接に環境負荷を与える活動を規制していくということだけでは解決が非常に困難となっている。そこで、経済社会の隅々まで環境への配慮を組み込んでいく方法が必要となる。このような環境問題と経済社会活動の複雑な構造との関係は、都市構造や物流のあり方全体が原因となって生じている大都市の窒素酸化物問題等の都市・生活型公害や廃棄物の問題等にも共通にみられるものであり、環境負荷の少ない経済社会の構造を作っていくことは、様々な環境問題の解決に求められる共通の課題である。
しかしながら、これまでの制度の枠組みでは、将来の世代や人類全体の福祉に関わる問題を扱う考え方、国際的な対応を進めるための枠組みと責任、さらに経済活動全体を環境保全型にしていくための体制については、いずれも全く不十分であったと言わざるを得ない。
第2に、保全するべき環境の内容に関しても、直接的な人の健康の保護や生活環境の保護を超えて広がりを見せている。このような例を生物多様性の保護の問題について見てみよう。地球の生態系は、単純なものから複雑なものへと進化を重ね、多様な生物が共存する中で保たれてきた。生態系は、種が多様であればあるほど、その安定性が高いとされている。人類もまたこのような生態系の中から生まれたものであり、様々な形で多様な生態系の恩恵を受けて活動してきた。経済的に利用されている生物資源の一面についてみても、環境と開発に関する世界委員会報告によれば、現在、利用されている処方薬の半分は野生生物にその起源を持ち、アメリカにおけるこれら医薬品の商業的価値は、年約140億ドルになり、全世界では、処方薬・非処方薬合わせた商業価値は推定年400億ドルを超えるとされている。このほか、生物の遺伝子資源は、農作物の改良や、工業製品の開発などに大きく寄与している。しかし、このような生物種が急速に減少しつつあり、世界資源研究所の1989年(平成元年)の報告によれば、1990年(平成2年)から2020年(平成32年)までの間に、地球上の全ての種の5〜15%以上が、主として熱帯林の破壊により絶滅するおそれがあると懸念されている。熱帯林は野生動植物の宝庫であり、前出の「西暦2000年の地球」によれば、地球上の生物種は300万〜1000万種と推定され、そのうち約25%が熱帯林に生息しているといわれている。この熱帯林が、この10年間で年平均およそ1,540万ha(我が国の約4割の面積に相当)の割合で減少し続けていると推測されている。
しかし、このような生物種の減少は、短期的には人間の活動へ影響を及ぼすことが少ないことから、その保全の必要性が認識されにくく、人の財産や生活の利便性がこれに優先されることがこれまで往々見られた。また、生物の多様性による恵みは、単にその地域のみならず、より広く世界全体にも及ぶため、全世界的な視点からみた価値は高いが、具体的に保全を図るべき地域においては社会的犠牲、努力や費用に便益が見合わないという問題が生じる。例えば、途上国に産する熱帯林とそこに育まれる豊かな生物相を保護しようとする機運が先進国を中心に盛り上がっているが、熱帯林を有する途上国では、熱帯林の保護を強制されることは当該地域の開発による発展の権利を奪うものとして反発を生じている。生物種は絶滅してしまえば回復されることはないため、早期に保全の施策を実施することが必要である。生態系の多様性の保護を図るために、人類と地球生態系との間に共存共栄を図る考え方の確立と、生態系の保全を図る方法とその実施を可能にするための仕組みを作りあげることが大いに望まれる。
これまでの制度では、生物多様性のような長期的、広域的な意味で重要な価値を保全の対象として位置づけることや、その保全と受ける便益を勘案して保全対策とその負担をバランスさせる仕組みが十分とは言えなかった。
第3に、経済活動その他を通じて、世界各国の関係が深まるなかで、途上国での環境問題の解決が世界的な課題として重要になっている。途上国もその発展の状況に応じ様々な問題を抱えており、一括りにして述べることは困難であるが、農村部における森林、農地等の質の低下、これとも関連した土壤の流出、水資源の枯渇、砂漠化の進行、野生生物の減少等の自然資源の破壊、質の低下等の問題に直面している。また、都市を中心に、居住環境の悪化が生じている。さらに、急速な工業化により、かつて我が国が経験した以上の深刻な環境汚染や自然破壊もみられる。
これまでの先進国における豊かさゆえの環境破壊とは異なり、途上国における環境問題の解決を極めて困難にしているのは、貧困が環境問題の大きな原因となっていることである(第3-2-2表)。例えば途上国において、生存のために農業用地開発や燃科採取の目的で森林を伐採したり、家蓄の過度の放牧を行ったりして自然資源を悪化させ、環境を破壊し、そして危うくなった環境の下で、人々が一層貧困に陥っていくような状況が見受けられる。他方、都市の貧しい人々は、環境の良くない地域で生活を余犠なくされ、水質汚濁、ごみ問題を生じさせるとともに、こうした問題に生活を脅かされている。途上国は、基礎的な生活の必要を満たすための開発を達成しつつ、環境保全を図っていかなければならないという困難な状況に直面している。
一方では、途上国においてもまた、地球規模の環境保全のための対策が求められており、前述のような地球温暖化対策や生物多様性の保全のための対策も重要となってきている。
しかし、途上国では、このような問題を解決するための資金、技術、人材等が絶対的に不足し、法制度等も不備であることから、先進諸国による支援が不可欠となっている。先進国は、貿易を通じて、世界の資源に依存し、また、直接投資等で途上国への進出を進めている。もとより国境のない環境の仕組みを通じ、また、相互依存を強める経済の働きを通じ、途上国の問題は、世界全体への影響を持つものとなっている。このような中で、途上国の環境問題の解決に向けて、適切で効率的な支援を行い、健全で豊かな地球社会を築くための協力の仕組みが強く求められている。しかしながら、これまでの枠組みは国内での問題の対応を念頭に置いて作られており、このような自国と関係があるが、自国以外の地域について、積極的に関与していくための観点は十分ではなかった。