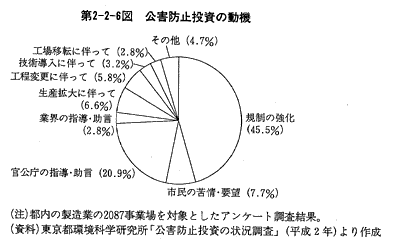
4 生産活動に伴う環境負荷を減らす努力
(1) 環境負荷を減らすための対策の障害
これまで見てきたように、生産活動は様々な形で環境への負荷を生み出しており、今、これを減らして行くための一層の対策が求められている。この対策には、個々の企業には当然何らかのコストがかかるが、一方では環境の悪化が防げることにより社会全体に利益が生じるため、そのコストよりも社会の利益が大きい限り、対策が促進されるべきである。
しかし、生産者は、市場経済の自由競争の中に置かれており、コストの上昇が競争力の低下や売上の低下につながるのではないかとの懸念が生じるため、個々の企業が独自に対策を行うことには障害がある。過去の例では、企業は、環境対策を行った理由として、技術の導入や工程の変更などではなく、規制の強化を第一に挙げており、こうした社会的な共通の枠組みがないと、個々の企業としては対策に踏み切りにくい状況が見て取れる(第2-2-6図)。
このように、生産活動を行う企業が、市場の競争原理のままに行動すると、個々の企業の損失をおそれて対策が取られないために、社会全体としての損失はむしろ大きくなることになる。このため、こうしたことを避けて社会全体の利益を確保するためには、対策を取った企業のみが経済的な面での損失を被ることがないように、社会としての枠組みを用意することが重要である。こうした枠組みづくりに当たっては、環境政策の基本原則である汚染者負担の原則(P.P.P.)に十分留意する必要があることは言うまでもない。これは、資源配分の最適化の達成と国際貿易のゆがみの回避の観点から国際的に合意されている原則であり、「環境汚染防止の費用は汚染者が支払うべきである。換言すれば、その費用は生産と消費の過程において、汚染を引き起こす財及びサービスのコストに反映されるべきである」とするものである。
また、個々の企業においても、こうした枠組みづくりに積極的に協力、参加するとともに、枠組みが用意されていない分野についても、いたずらに自らの利益のみを追求して対策に後向きになることなく、他の企業等と協力しつつ、可能な限り自主的に対策を行っていくことが望まれている。
(2) 活発化している自主的な取組
我が国の生産活動においては、過去の悲惨な公害経験を踏まえ、政府による排出規制等に対応して、各種の産業公害防止のための努力が行われてきた。この結果、我が国の公害対策は世界でも最も進んだものとなり、特定の汚染物質によるフローの、いわば一過性の公害は相当に改善されてきた。
しかし、今日の環境問題は、環境を構成する要素が互いに関係しあって悪化し、また、より長期的、広域的に影響が及ぶものとなっており、環境の性質自体に短期間では元に戻せないような変化が及ぶ局面を迎えている。こうした状況の中で、生産者に対しても、直接的な健康被害の防止の観点から物質ごとに定められた排出基準を遵守するだけでなく、より長期的な見地に立って、事業活動に関連して発生する環境負荷全体を自主的に極力減らしていくことが求められるようになっている。
事業者においても、自らの活動と環境との関係は認識されている。東京商工会議所による企業経営者の意識調査の結果では、自社の企業活動が環境問題と「非常に関係がある」と考えている経営者は15.7%、「かなり関係がある」と考えている経営者は45.6%であり、過半数の経営者が環境との関係を認識している。特に、建設業、運輸・通信業、製造業での割合が高くなっている(第2-2-7図)。
こうした認識に立ち、また、消費者の意識の高まりも受けて、詳しくは第4章第2節に述べるように、自らの事業活動に伴う環境負荷を減らすための自主的な取組が始められている。
例えば、環境保全に取り組むための体制整備として、環境保全担当の組織を設けたり、環境に関する基本的な方針を定めるといった取組が進められている。具体的に自らの活動に関連する環境負荷を低減するための方策としては、特定の環境負荷の削減目標を定めたり、自社の活動がどれだけの負荷を環境に与えているかを包括的に把握するために環境の観点から監査を実施したりする取組も始められている。
また、自社の事業活動に伴い直接発生する環境負荷にとどまらず、消費や廃棄の段階も含めて負荷を低減しようとする自主的な動きもでてきている。例えば、経済団体連合会が平成3年に定めた「経団連地球環境憲章」では「製品等の研究開発、設計段階において、当該製品等の生産、流通、適正使用、廃棄の各段階での環境負荷をできる限り低減するよう配慮する」ことが定められており、こうした方向に従って、自社の製品が生産、流通、消費、廃棄段階を通じてどれだけの負荷を環境に与えているかを調査するライフサイクルアナリシスを実施するといった取組も、欧米諸国に続き、我が国でも始められてきている。
このように、自らの事業活動に関連する環境負荷全体を視野にいれた自主的な取組が事業者により一層推進され、これが、事業者、消費者など社会の構成者全体が協力して環境負荷を低減していく取組へとつながっていくことが期待される。