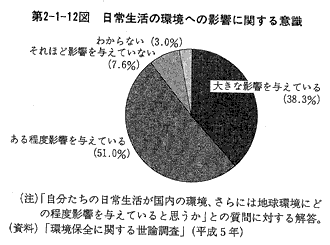
5 消費生活に伴う環境負荷を減らす努力
これまで見てきたように、消費生活と環境とは密接に関連している。生活から直接に発生する負荷だけでも、特に水質汚濁問題において顕著なように、環境にかなりの影響を与えているが、さらに、消費活動により間接的に誘発される負荷をも加えて考えれば、消費生活が環境に与える負荷はより大きなものとなる。
消費生活が環境に大きな影響を与えているという事実は広く認識されてきている。自らの日常生活が環境にどの程度影響を与えていると思うかを問う世論調査の結果を見ると、「大きな影響を与えている」と考えている人は38.3%にのぼり、「ある程度影響を与えている」という人と合わせると、90%近くが自らの日常生活による環境への影響を認識していることが分かる(第2-1-12図)。
こうした認識に立って、詳しくは第4章第2節で見るように、消費生活に関連する環境負荷を減らそうとする様々な取組が始められている。中でも早くから始まったのが、生活からの負荷による環境への影響が目に見えやすい生活排水に関する分野である。例えば琵琶湖を抱える滋賀県では、昭和50年代前半から洗剤の使い方の見直しなどにより生活排水による負荷を減らしていこうとする運動がはじまっている。
近年では、より広域的、長期的な環境への影響を視野に入れた取組が展開されている。使い捨て製品の不買などによるごみの減量化、集団回収への協力などによるリサイクルの推進、自家用車の使用方法の見直し、家庭における様々な省エネルギーなどである。こうした取り組みには、昭和40年代末以降に石油危機の影響を受けて、資源、エネルギーの節約の観点から着手されていたものも多いが、昭和60年代になって地球環境問題が深刻に意識されるようになると、環境への負荷を減らすという新たな観点から一層活発化してきている。
さらに、自らの消費生活から発生する負荷を減らすという取組にとどまらず、消費者としての製品の選択を通じて、生産などの段階で発生する環境負荷をも減らしていこうとする取組が広がっている。これまで見てきたように、生産段階で発生する環境負荷は、消費者が対価を支払って財やサービスを購入することにより誘発されている面があり、このため、消費者が購入する財やサービスの量や種類を変えることにより、生産段階での負荷の発生量に影響を与えることができるのである。
ここで、財やサービスに対して消費者が支払う対価について考えてみると、これは、その財やサービスの生産に要する様々な費用に利潤を加えたものに対する支払いであると考えることができる。例えば、料金の使途が明らかにされている東京都の水道事業について見てみると、第2-1-13図のように、消費者が支払う対価は、上水を家庭に供給するために要する様々な費用に充てられている。具体的には、鉄やセメントでできている取水、浄水、配水のための施設の建設費、さらには、こうした施設を運転するための電気代、薬品代、人件費などからなる費用である。
水道の蛇口から出る普通の水の例からも分かるように、財やサービスの価格の背景には膨大な産業活動があり、その産業活動のそれぞれの段階での生産に要する費用の中には、環境負荷を減らすための対策に要する費用も含まれることになる。このため、企業において環境対策が進められることとなり、これに今以上の費用がかかる場合には、この費用が反映されれば、価格が高くなる製品も出てこよう。消費者においては、いたずらに価格の安いものを求めるのではなく、環境対策に配慮して生産を行った場合には価格がある程度上昇することがあることを理解しておく必要がある。特に先駆的な取組を行っている場合には、他の商品に比べて価格が高くなることもありうるが、それを容認することも対策を促す上で意味があるのである。現在では、さらに、こうしたことを認識した上で、環境への負荷のより少ない製品を積極的に選択することを通じて、生産者などの行動にも影響を与え、経済全体を環境への負荷の少ないものに変えていこうとする考え方が広がってきている。
これまで見てきたように、消費活動に伴う環境負荷は、間接的に誘発されるものをも含めて考えれば、負荷の総量の中でも相当に大きな割合を占めている。このことは、消費者が環境に対して重要な責任を負っていることの証であると同時に、消費者の行動により減らしうる負荷が大きいことをも示しており、消費者の主体的な取組が求められている。