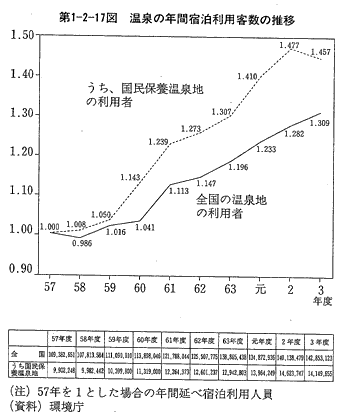
3 その他の自然資源等
我々及び我々の祖先は、豊かな自然を上手に利用し、精神的に生活を豊かなものとしてきた。最近では星空、青空等、当たり前のようにあったはずの環境を見直し、再注目していこうとする活動も見られる。ここでは温泉、海水浴場等、名水百選、星空に関する活動、巨樹・巨木林について紹介する。
(1) 温泉
我が国は世界でも有数の温泉国であり、温泉地は古くから保養、休養に利用され、既に述べた優れた自然景観地とともに、我が国の行楽の中心地を構成してきた。近年は、温泉ブームに加え、地方振興の核として温泉に対する注目が集まっている。
温泉の現状は、温泉地数、源泉数ともに一貫して増加している。しかし、その内訳を見ると、利用源泉のうち、自噴泉の数は一定である一方、動力による揚湯が増えている。また、温度別に見ると42℃未満の源泉の増加が著しい。この背景には、温泉利用者の増加に伴い、動力によって揚湯量を増大させていること、より深層からの揚湯が進んでいることといった要因が考えられる。
温泉地の利用者の増加も著しい。平成3年度1年間における温泉地の延べ宿泊利用者数は1億4,285万人に上り、昭和59年度以来の増加傾向が続いている。温泉地のうち、環境庁長官は国民が豊かな自然の中で保養のために利用する温泉地として国民保養温泉地を指定し、その振興を図っている。この国民保養温泉地の利用の伸びは特に著しく、昭和57年から平成3年までの約10年間で1.46倍となっている(第1-2-17図)。これは自然の中で余暇を過ごしたいという国民の意識の現れであると考えられる。
(2) 海水浴場等
海水浴等の水浴は明治以降夏のレクリエーションとして、人々に親しまれてきた。海岸などが水浴に適したものであるためには、水質、景観が保持されていることが必要になる。環境庁が行っている主な水浴場の水質調査によると、全国の主な水浴場(川での水浴場を含む)は411か所であり、近年は水浴場の水質が安定し、平成3年度及び4年度に水質の改善の必要な水浴場は0か所であった。
(3) 名水
環境庁は昭和60年に、身近で清澄な水であって古くから地域住民の生活に融け込み、住民自身の手によって保全活動がなされてきた全国の湧水や河川の中から、北は利尻島から南は沖繩まで100か所を選定し、「名水百選」として発表した。地域社会にとって水は、飲料用水や農業用水の確保にとどまらず、生活の一部として、保全、利用を通じて、日常の精神生活を豊かなものとしてきている。地域社会に守られている水への関心の高まりは、良好な水質への関心を高め、水質保全活動への参加を拡大する上でも重要である。
(4) 星空
かつてはどこでも見ることのできた星空であるが、大気の汚染、照明・ネオンサインの普及とともに、次第に肉眼で見える星が少なくなってきた。星空の暗さを概観したものは第1-2-18図のとおりであり、都市地域で星が見にくくなっていることがわかる。空はその大気が我々の健康に影響を及ぼすだけでなく、青い空と眺望、星降る夜といった景観を与え、我々の精神生活の背景を形作ってきた。空の持つこうした役割に関心を高めてもらい、大気汚染や照明の影響を考えてもらおうと環境庁は、昭和63年度より、毎年夏期と冬期に「全国星空継続観察(スターウオッチング・ネットワーク)」を実施している。平成4年度夏期には247団体、7,186名の参加を得て実施された。
(5) 巨樹・巨木林
巨樹、巨木は、我が国の森林・樹木の象徴的存在であり、良好な景観の形成や野生生物の生息環境、地域のシンボルとして人々の心のよりどころとなるなど、生活と自然を豊かにする上でかけがえのない価値を有している。このような巨樹の実態を把握するために自然環境保全基礎調査の一環として巨樹・巨木林調査を実施したが、この中で幹回り3m以上の木として巨樹は全国で55,798本あることが報告された。樹種別で見るとスギ(13,681本)、ケヤキ(8,538本)、クスノキ(5,160本)の順に多く、幹回りの大きい上位10本のうち9本をクスノキが占める。また、巨樹の生育環境として社叢林の果たす役割が大きいこと、信仰対象となっている巨木は約30%であることなどが明らかになった。