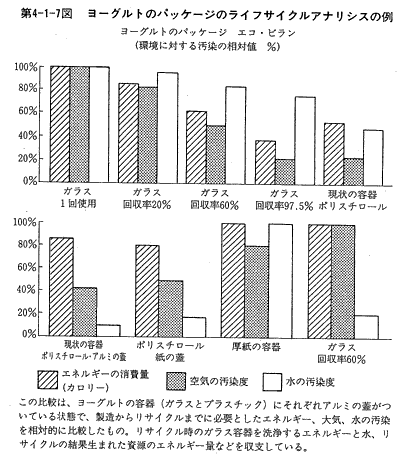
2 企業における取組
企業は現代の経済活動の主要な担い手である。企業の活動が環境保全的なものになるか、そうでないかは、経済社会の持続可能性を高める上での鍵となる。ここでは、企業が法令に基づき当然に遵守すべき義務を超え、積極的に環境保全の役割を担うべく行っている自主的な取組を見てみよう。
(1) グリーン経営方針(環境憲章等)
企業の中には、専ら環境保全に資する製品やサービスを製造し、あるいは販売する企業もある。こうした企業が行う事業は、一般にエコ・ビジネスと呼ばれ、徐々に大きな活動を担うようになってきている。その扱う製品やサービスも、従来の公害防止機器といったものから、最近は、金融商品にまで広がってきている。例えば、金利は低いが環境保全活動にのみ貸し付けられることとなっている預金を扱うエコ・バンクといったものも出てきている。さらに、近年は、環境保全の動きが、本来は必ずしも環境保全的ではない製品やサービスを扱う会社にも及んできている。こうした中で、特に、業界団体や個々の企業においては、環境問題への取組に関する憲章、ガイドライン等を作成したり、企業の経営理念に「環境保全」に関する埋念を付け加える動きが国内外で活発化している。
国際商業会議所では、世界中の企業が環境面での実績を改善していくことを支援すべく、産業界の代表で構成された特別作業部会を設置し、「持続的発展のための産業界憲章」を作成した。この憲章は、企業にとって持続的な発展のために極めて重要な一側面である環境管理に関する16の原則から成り立っている。これは、1991年(平成3年)4月に開催された「環境管理に関する第2回世界産業会議(WICEMII)」の場で正式に採択された。この憲章の制定目的は、できるだけ幅広い範囲の企業がこれらの原則に従って環境対策を改善し、更に一層の改善を事業運営の中に正式に位置づけ、組み込み、改善の進捗度を測定し、その進捗度を適宜、内外に発表することなどを約束することにある。国際商業会議所では、会員及びその他の企業によってこの憲章が支持されるよう、精力的に活動しており、また、いくつかの国際機関にも支持表明を働きかけている。
我が国の有力な経済団体である経済団体連合会では、「環境問題の解決に真剣に取り組むことは、企業が社会からの信頼と共感を得、消費者や社会との新たな共生関係を築くことを意味し、我が国経済の健全な発展を促すことになる。また、企業も世界の『良き企業市民』たる事を旨とし、また、環境問題への取組が自らの存在と活動に必須の要件である」との認識に基づき、平成3年4月に、経済団体としては世界初の「経団連地球環境憲章」を制定した。憲章では基本理念として、「企業活動は、全地球的規模で環境保全が達成される未来社会の実現につながるものでなければならない」と明記し、11分野24項目(?環境問題に関する経営方針?社内体制?環境影響への配慮?技術開発?技術移転?緊急時対応?広報・啓蒙活動?社会との共生?海外事業展開?環境政策への貢献?地球温暖化への対応)にのぼる企業行動指針を示し、これらに即した具体的な行動計画を練るように会員企業及び業界団体に求めている。
また、経済同友会では、同じく3年の10月に「地球温暖化問題への取組み一未来の世代のために今なすべきこと」を取りまとめ、企業、政府、市民それぞれに対しての提言を行った。この提言の中では、基本理念として、温暖化対策のためにはエネルギーや物質の大量消費をべ一スとする「現代文明そのものについての軌道修正が必要である」とした上で、特に、企業への提言の中で、「現代のエネルギー消費社会、使い捨て社会を成り立たせてきた責任の相当部分は企業が追わなければならない」ととの深刻な認識を示している。さらに、企業がこのような視点から行うべきこととして、?環境マネージメントシステムの確立、?省エネルギーヘの一層の取組、?技術・商品開発の積極的な推進、?技術協力への取組を挙げている。
このような憲章作成の動きは個別企業においても出てきており、業界他社に率先して憲章を作成した企業の中には、憲章に基づいて各事業部ごとの実施基準を作成したり、さらに憲章や実施基準の遵守を確実なものにするため罰則規定を設けるなど、従来の憲章の概念から更に踏み込んだものも見られる。ちなみに、このような先進的な内容の憲章を定めたG工業では、平成3年6月から「グリーン戦格」と名付けた経営刷新活動が展開されている。このグリーン戦略は、10年後を目標に、地球環境に負荷を与えている現在の企業活動を徹底的に見直すものであり、具体的には、?工場からの有害物質を一切出さない?特定フロンの使用を5年に全廃?省エネルギー目標を30%として8年に達成?二酸化炭素の排出抑制対策を同じく8年に完了?産業廃棄物の50%削減を同じく8年に達成、を重点テーマに掲げている。特に、省エネルギーと二酸化炭素抑制対策としては、国内にある主力工場にコージェネレーション(熱電併給設備)を導入してエネルギー効率の向上を目指すほか、燃科転換や工場建屋の堅ろう化などの対策を徹底的に行い、会社全体の二酸化炭素排出量を6年以降は元年のレベルに抑制し、生産高が2倍になってもそれを維持する方針を固めるなど、活動の内容は詳細かつ具体的なものとなっている。
既に第2章第2節で見たとおり、企業におけるトップの方針や全社的な行動は環境保全のための具体的な行動の裏付けとして重要である。この意味で、憲章などの制定の動きは大いに歓迎されるべきものである。一般に「憲章」とは、あくまでその企業及び業界団体の自主的努力目標であり、その遵守等の結果については外部には公表されないことが多いが、今後は、憲章が数多く定められるだけでなく、その実行状態や達成成果の把握や評価に努めるとともに、その結果を企業の外部にも公開するなどし、規範性を一層強め、企業の取組が社会の中で一層信頼されるようになることが期待される。
(2) 工コラベリングと商品の環境へのやさしさ度評価(ライフサイクルアナリシス)
エコラベリングとは、機能上は区別のない製品の間に存在すると思われる環境への影響面での差異に着目し、同種の製品の中でも環境への負荷が少ないと思われる製品について、これを容易に識別できるようなマークやラベルを添付するような仕組みである。既に、ドイツでは1978年(昭和53年)にエコラベルが導入され、カナダ、フィンランド、ノルウ工ー、スウェーデンでも導入されている。日本でも平成元年に(財)日本環境協会のエコマーク制度が発足しており、4年3月31日現在、47品目1987商品が認定されている。1990年(平成2年)7月、ベルリンで開催された西ドイツ政府主体の「環境保護ラベルに関する国際会議」には、26カ国、6国際機関が参加し、「環境保護ラベルに関するベルリン声明」が出され、今後ドイツを中心に各国間の情報交換を進めていくこととされた。また、1991年(平成2年)9月、ギリシアのレスボス島で開催されたUNEP主催の「環境保護ラベルに関する国際会議」には、10カ国、3国際機関が参加し、各国のエコラベル制度の実施状況について情報交換をするとともに、今後定期的に各国間の情報交換と交流のための国際会議を開催していくことを合意した。
これらのエコラベリング制度の目標については、OECDは次のように整理している。
? ラベルを表示した製品の売上またはイメージを向上させること
? 消費者の意識を高めること
? 正確な情報を消費者に提供すること
? メーカーにおいて製品の環境上の影響についての責任感を養うこと
? 環境を保護すること
我が国のエコマークについて、エコマーク製品の製造企業や販売会社における意識や問題点、制度改善の要望を環境庁が調査した結果によると、エコマーク商品の今後の取扱については、製造企業で7割以上、流通業者で8割以上が「積極的に取り扱いたい」としていた。また、制度改善の要望については、認定商品の範囲拡大、認定基準の明確化、消費者、国民を中心とした普及啓発活動の強化などを求めるものが多かった。
商品の環境へのやさしさ度評価(ライフサイクルアナリシス)は、原材料の採取から商品の廃棄までの各過程についての環境負荷を推計し、商品の設計段階から環境負荷の低減を図ること、あるいは環境負荷の少ない商品選択(容器等)を図ることを目指すものである。個別の地域における環境負荷の状況(地域の公害、自然破壊等)は考慮に入れない点で、個別事業に対する環境影響評価(環境アセスメント)と異なる手法である。
ライフサイクルアナリシスを行うには次の3つの段階が必要であると考えられている。
? 分析対象、分析項目の確定
・商品を分析する際に比較すべき原単位の検討
・個別の商品に係わる製造から廃棄までの各段階の把握
・副産物の環境負荷の算入についての検討
・製品のリサイクルに伴う環境負荷の変化の検討
? 環境負荷の定量化
・各プロセスにおける投入物(原材料、エネルギー、水)と産出物(商品、副産物、排ガス、排水、廃棄物)の把握
・個別の商品に関わる製造から廃棄までの各段階の環境負荷の集計
・環境負荷の集計手法の検討
?環境負荷の低減方策の検討
・容器包装材の選択、商品設計の変更等
1960年代末(昭和40年頃)から、アメリカで、特に省エネルギーのための手段として、個別の商品についてのライフサイクルアナリシスが試みられ、ヨーロッパにおいてもエコラベリング制度の発達とともにライフサイクルアナリシスが導入されてきた。特に、スイスのミグロス生協においては、スイス政府の「包装材科エコバランス」報告をもとに、包装材科に関するライフサイクルアナリシスの手法を開発し、アルミ箔の廃止、プラスチックボトルの採用、牛乳紙パックの排除など、実際の商品開発や選択に活用している(第4-1-7図)。
1991年(平成3年)には、ライフサイクルアナリシス協会がECの協力機関として設立され、ライフサイクルアナリシスの標準化の動きが活発化しているが、こうした動きは、ECのエコラベリング(第4-1-8図)に関する指令にも反映されている。
また、アメリカにおいても、連邦環境保護庁が積極的に関与し、「環境の毒性と化学の研究会」(SETAC)においてライフサイクルアナりシスの体系化に関する検討が進められつつある。
日本においては、環境庁がエコマーク制度の指導育成を行っているが、この一環として、エコマーク認定の要件に対し広く製造段階から消費段階に至るまでの環境負荷の総合的な評価を組み込んでいくための検討が始められている。
環境へのやさしさ度評価の手法は有効なものではあるが、その評価の過程、特に、環境負荷の集計や総合評価に関し恣意的な判断が入り込む余地がある。このため、手法の標準化、体系化に努め、標準手法に最大限準拠した形で進めることや第三者の客観的なチェックを受けることが必要となっている。
(3) 預り金(デポジット)の上乗せ
企業の製品が、ごみとして散乱することを防止し、再生資源として回収するリサイクルシステムを形成する上での経済的手段の一つとしてデポジットの仕組みがある。デポジットとは払い戻される預り金のことであり、製品の購入時に預り金を徴収し、あるいは預り金を価格に上乗せして製品を販売し、使用済みの製品等が返還されるとその預り金を返還するものである。
我が国においては、古くから、ビール業界が各社共用瓶を開発した上、自主的なデポジット制を全国的に採用しており、大瓶1本5円、20本入りプラスチックケース300円(ケース分200円、瓶分100円)の保証金を上乗せして販売し、平成元年現在では回収率が92%となっている(第4-1-9図)。
また、次節で見るとおり諸外国では、制度化されたデポジットの仕組みが採られて成果を収めている事例がある。このようにデポジットの仕組みは、有益なものである一方、使用済み製品の回収拠点や保管場所の確保、回収の手間及び特に中小企業において問題となるコストの増加、新たな資源の消費が必要となること、見かけ上の小売価格の上昇による売上の低下懸念などの問題点が指摘されている。諸外国におけるデポジット制度の成功例、失敗例を参考にしつつ、対象商品、実施地域、関係者及び社会にとっての費用と役割の分担、環境保全上の効果等を勘案し、社会的な理解を促進し、受容される仕組みを検討していくことが課題となっている。
預り金のように便用済み製品の回収に資するインセンティプ効果は期待できないが、非環境保全的なサービスや製品については、通常の無料サービスと区別し、消費者に特別の負担を求める仕組みがある。このような非環境保全的サービスの有科化の例としては、スーパーマーケットの買い上げげ商品を持ち帰るためのバッグの有料化などがある。バッグの有料化にいち早く取り組んだHスーパーマーケットでは、来客数に対してバッグの使用量が65%減少したことが分かっている。
(4) 環境監査
企業活動を環境保全に配慮したものに変えていくためには、自らの事業活動の環境に与える影響を十分認識するとともに、定期的にチェックする体制を作ることが欠かせない。環境監査とは、経営管理の方法の一つであり、国際商業会議所(ICC)によると、「環境に関する経営管理上のコントロールを促進し、会社が定めた環境に関する方針(法律の要求する基準を満たすことを合む)の遵守状況を評価することにより、環境保護に資する目的の組織・管理・設備がいかによく機能しているかを組織的・実証的・定期的・客観的に評価するもの」とされている。
ニューヨークに本拠を置くコングロマリットのITTは、1960年代(昭和年代後半)に環境準拠性監査と呼ぱれる仕組みを開始した。これは製造工程の清浄度や安全性を高めようという品質管理の視点から生まれたものであったが、現在は、国際商業会議所のモデルに沿いつつ、環境関係の法律の遵守状況を確認するとともに、環境上、健康及び安全上の問題点を明らかにする目的で活用されている。その実際面では、3〜5人の監査チームが1〜2日をかけて工場などに立入りし、現場において帳簿や経営実態、機器の稼働状況などのチェックを行うこととされており、監査の頻度は、その工場などの重要性及び危険性を考慮して個々に決められるが、定期的な監査が原則となっている。
定期的な環境監査とは別に、アメリカで発達した新しいタイプの環境監査として、土地の購入あるいは企業買収に先立って行われるものがある。いわゆるスーパーファンド法により、汚染された土地と認定されると現所有者が過失の有無を問わず汚染浄化責任を負わされる可能性が出てきたため、購入前に汚染の有無を確かめようとの趣旨で環境監査を行うケースが増えてきたものである。不動産の購入に先立つ環境監査を義務づける州も現れた。先進例はニュージャージー州で、1983年(昭和58年)に発効した環境浄化責任法(ECRA)は、事業及び不動産の譲渡を完了させるための条件として、環境監査の実施を義務づけ、汚染が発見された場合には浄化計画の提出と補償金の支払いを要求している。コネチカット州とイリノイ州においても同様の法律が制定されている。
北米では、環境保護団体からの提言の動きも活発である。米国のNGOエルムウッド研究所は、1989年(平成元年)に発表したレポートで、法的適合性の確認という消極的なチェックを主体とする現在の環境監査に代わるものとして、より積極的なエコ監査という概念を提唱し、環境保全に積極的に配慮した経営の必要性を説いた。また、投資家としての立場から企業に環境配慮を求める団体であるCERESが提唱する前述のバルディーズ原則においても、その遵守状況の確認を超え、企業の自主的な環境保全活動の成果の多寡などの評価を行う特徴的な年次環境監査の実施を要求している。このほか、企業の内部監査ではなく、外部の専門的な監査人による一層客観的な監査を行う動きもある。
ヨーロッパにも古くから環境監査を実施している企業がある。例えば、イギリスのブリティシュ・ペトロリアムでは、自社の環境ルールが守られているかどうかをチェックするシステムが1970年代初頭(昭和40年代半ば)から用いられ始め、1985年(昭和60年)には監査という位置づけが明確になった。
他にも、ロイヤル・ダッチシェル、チバガイギーなど、環境に大きな影響を与える潜在的な可能性がある業種の大企業を中心に、先駆的な実践例が見られる。一方、最近はこれらより規模が小さい企業にも環境監査を試みる事例が出てきている。その一つの類型は、北米と同様、企業買収に先立って行われるものであり、フランス、イタリア、オランダななどで発展しつつある。
このような動きの中で、デンマークの投資信託が投資先に年次環境監査の実施を求めるなど、ヨーロッパでも企業の利害関係者による環境監査への要求は高まっており、近い将来一層の普及が進むと思われる。
我が国では、環境監査という概念が未だ普及していないが、環境監査を実施している先駆的な企業もある。例えば、ある大手機器会社では昭和47年に公害防止環境管理監査基準を制定し、社内監査体制を発足させて、毎年、自社工場や子会社を対象に、事前書類審査、現場視察などを行い採点している。採点項目は、社内の環境基準の達成度や環境事故を未然に防止するための仕組みに関するもので、監査人の主観が入る項目も残るものの、かなり詳しい内容となっている。
我が国産業界で、今後、環境監査の導入が広がる可能性は高い。平成2年に経団連が発表した地球環境憲章でも、社内体制の項目で内部監査の実施が盛り込まれており、国内での認識も高まっている。
(5) 環境分野での社会貢献
近年、日本においても、企業の環境面に関する社会貢献活動の必要性が叫ばれるようになり、現実に企業の寄附による公益法人、公益信託や環境保全基金の設立が盛んになってきている。また、ボランティア活動のための有給休暇制度を設ける企業も出てきている。環境庁が平成3年末に一部、二部上場企業を対象に行った調査の結果によると、回答企業のうち7割近くが環境面に関する社会的貢献活動を実施しており、同じく7割近くが市民との共同作業の必要性を感じていることが示されている(第4-1-10図)。この背景には、企業が長期的に繁栄するためには本業の活動の改善だけでは不十分で、消費者、地域、地球社会ともより良い関係を築くため、社会公益に直接に貢献する「良き企業市民」たるべきである、という考え方が浸透してきたことがある。
他方、イギリスでは、企業の一層多面的な社会貢献としてグランドワーク事業が行われている。グランドワーク事業は、企業が金銭だけではなく人的にも関与できるものであり、日本においてもこのような企業参加の枠組みを発展させることで企業の一層の社会貢献が期待されよう。
グランドワークとは「生活現場からの創造活動」をテーマに、行政・企業・市民を、対立する者としてではなく共同して努力を分かち合う者として、連携させ、身近な地域の環境づくりを進める公益事業体である(第4-1-11図)。「グランドワーク事業団(グランドワーク・ファウンデーション)」を母体として、イギリス環境省、地方公共団体等の出資により、各地にグランドワークトラスト(事業所)を設け、その資金で運用される。各トラストは、商法上は「有限責任会社」として登録されると同時に「チャリティ(奉仕団体)」としても登録される。有限会社であることから会計、監査、保健、安全性などの面では会社法に従わなければならないが、これにより専門的な運営が確保され、さらに契約の締結についても利潤を比較検討するなど注意深い事業運営が促されている。一方、チャリティ団体であることから、社会的な信用と共感を得ることが可能となり地域の利益となるプロジェクトの円滑な実施が保証されるほか、チャリティ団体への寄附に対しては税の優遇措置があることから企業からの支援が得やすいものとなっている。個々のトラストの事業内容としては、環境保全や改善、レクリエーション、環境教育が3本柱になっており、特定地域で事業を行い、その収益によってチャリティ目的を達成する。事業実施にはまず5年計画を立て、当初は大部分の必要経費を政府と自治体が出資し、トラストが軌道に乗り、独自の収益が得られる能カが次第に高まると、行政からの補助が2割位まで縮小される(第4-1-12図)。
グランドワークの第1号は1981年(昭和56年)、リバプール市郊外で始められた。現在、英国内各地で28のグランドワーク・トラストが活動している。1990年(平成2年)度、グランドワーク全体で手掛けた事業数(継続中のものを含む)は3,821に達し、これらに何らかの形で参加した市民ボランティアは2万5千人、学校生徒の参加は8万1千人という数字となっている。グランドワークヘの企業の参加の輪も年々広がりつつあり、同年度について見ると、トラスト・ネットワークヘの事業委託や事業スポンサーとしての投資が270万ポンド(約6憶2千万円)、資材などの物品での寄附が71万ポンド(約1億6千万円)相当となっている。さらに、グランドワーク事業団では1989年(平成元年)にEC委員会の助成を受け、フランス、オランダ、旧西独、イタリア、ポルトガル、アイルランド、ベルギーの7カ国で事業化調査を実施した。このうち、1991年(平成3年)3月末までにフランス、オランダ、ベルギーのそれぞれの調査対象地で、イギリスと同じシンポルマークを用いてパイロット事業等が実施されている(第4-1-2表)。
このように、企業は資金を提供するだけでなく、社員や物資を提供するなど多面的な参画を行っている。土地の貸与やノウハウ、情報の提供も行われている。この結果、個々の環境保全活動と企業との関係は緊密なものとなり、企業の社会的評価を大きく左右するものとなっている。
地域活動への企業参加と言っても一方的には難しく、地域社会が変わろうとする動きと連動させることで、その実現も容易になる。この意味で、グランドワークを介して地域全体が環境保全活動に参加できる仕組みが生まれ、企業経営者自らが「地域のために何ができるか」を自問しやすい状況を作ったことが企業参加を大きく進める背景となった。さらに、グランドワークと企業が協力できたことで、個別の企業だけでは到底なし得なかった領域にまで広く踏み入り、企業の社会貢献の可能性を大きく広げる結果となっている。企業にとってのグランドワークとは、施工業者であり、企業の生産性向上のためのよきアドバイザーであり、広告代理店であり、また企業の社会的責任を企業に代わって実践してくれるパートナーということになる。