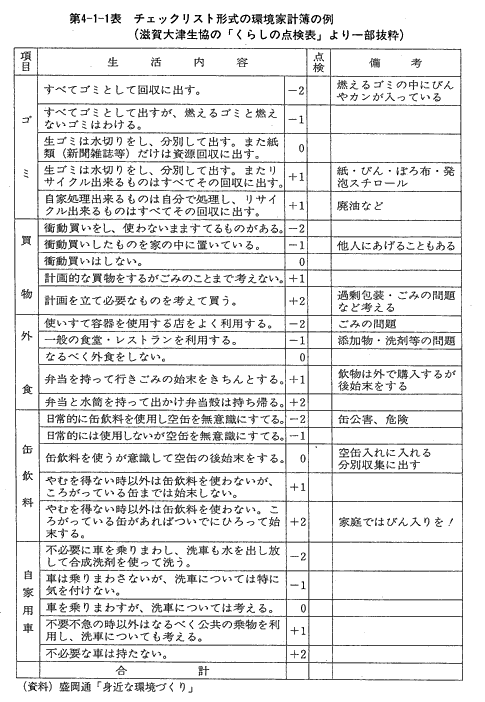
1 消費者、市民における取組
市民一人一人の行為が積み重なり、環境には大きな影響が生じる。他方、市民がそれぞれに自らの行為について賢明な判断を行えば、環境を守り、育てる活動の責任ある担い手となれるのである。単に政府や自治体の対策に協力するだけでなく、積極的に環境の守り手として進んで行動する市民が最近増えてきている。
(1) 環境家計簿
国民一人一人が、生活に伴う環境への負荷を減らし、環境にやさしいライフスタイルを形成して行くためには、その第一歩として、自らの日常生活と環境とがどのように係わっているのかをよく知ることが必要である。そのための手段の一つとして、市民の手により自主的に「環境家計簿」をつける試みが広がりつつある。「環境家計簿」とは、日々の生活において環境に負荷を与える行動や環境に良い影響を与える行動を記録し、必要に応じて点数化したり、収支決算のように一定期間の集計を行ったりするものである。家計簿で金銭をめぐる家庭の活動を把握し記録するのと同じように、「環境家計簿」によって、金銭では表せないものも含め、環境をめぐる家庭の活動を把握しようとするものである。こうした試みを幅広く普及するために、洗剤の使い方、廃食油の処理などいくつかの項目に絞り込んだチェックリストの形式の簡便な環境家計簿も工夫されている。
こうした手法は、10年以上も前から提案されており、例えば滋賀県の大津生協や兵庫県の灘神戸生協などでは昭和50年代の後半からチェックリスト方式の環境家計簿普及の試みが工夫を重ねつつ続けられ、成果を挙げてきた(第4-1-1表)。
今日の複雑化、分業化した経済社会の中では、日常の行動と環境の関係はなかなか実感しにくい。例えば、排水については下水に流れるまで、ごみについては清掃車が運び去ってくれるまでしか意識されないことが多く、これが環境負荷が安易に増大する一囚ともなっている。
しかしながら、市民の一人一人の生活と環境とは密接に関わっている。例えぱ、水質への影響の一例としては、使用済みの天ぷら油0.5リットルをそのまま流すと、その汚れはBOD1kg/リットルとなり、これを魚が住める水質にするには浴槽330杯分の水で薄めなけれぱならない。また、暖房の温度は近年徐々に高くなっているが、大気への負荷を考えると、この設定温度を家庭やオフィスで1℃下げると、日本全国では原油に換算して約80万kリットルの節約になり、CO
2
排出量が約64万t、NOxの排出量が約3100t削減される計算になる。同様に、シャワーの使用を1回につき1分短くすると、全国で、原油70万kリットルの節約、CO
2
約57万t、NOx約2700tの排出削減につながる計算になる。しかし、こうした効果は、意識的に自らの生活を考え直してみない限り気づかれないものである。
「環境家計簿」は、自分の生活を点検し、環境との関わりを再確認するための有力な試みであり、国民一人一人が環境保全上の貴任を果たしていく上での良い手掛かりのひとつとなっている。
(2) 環境保全型商品の選択
市場経済は需要と供給という二つの基本的な要因により動いていくが、消費者の購買行動はこのうちの需要を形成するものであり、市民が経済システムに最も直接的に係わる機会の一つである。この購買の際に、同種の製品の中から環境への負荷のより少ない商品を選択して消費生活に伴う環境影響を減らすとともに、消費者主権の発揮により経済社会を環境にやさしいものにしていくことを目指した運動が広がっている。
こうした運動は、グリーンコンシューマー運動とも呼ばれ、1988年(昭和63年)末にイギリスで出版され、ベストセラーとなった「TheGreen Consumer Huide(緑の消費者ガイド)」が定着化のきっかけとなったと言われている。同書では個別の商品名を挙げつつ商品の環境影響を評価しており、環境にやさしい消費行動の具体的なマニュアルとなっている。これに前後して、ドイツ(「(DerOko-Kniggeeエコ生活法)」)とアメリカ(「Shopping for a Better World(よりよい世界のための買い物)」)で同様の趣旨のガイドブックが出版され、いずれもベストセラーとなった。
環境に配慮した商品は、生産量が少なく規模の利益が得られないことなどの埋由で、一般の製品より高価にならざるを得ない場合もあるが、米国や旧西独では5割以上高価格でも買うという消費者が1割以上もいるとの調査結果もあり(第4-1-1図)、こうした環境保全型商品を選択する動きは着実に根付いてきている。欧米には及ばないものの、我が国でも2割高いくらいまでなら買うという消費者が多く、消費者の意識が確実に高まっている。
環境保全型商品を選択することは、個々の消費生活からの環境負荷の発生を削減するのみならず、需要の動向を変化させることを通じて、企業がより環境にやさしい製品を環境にやさしい方法で製造、販売するよう促し、経済構造全体を変革する効果を持つ。例えば、フロンガスを使用したスプレーの消費量の減少(第4-1-2図)や、過剰包装の見直し、購買額の一定割合が環境保護団体等に寄附される仕組みのクレジットカード、利子の一定割合が同じく自然保護団体等に寄附される仕組みの信託や預金が登場するなどの近年の動きも、その要因の根本には消費者の商品選択の変化がある。
商品の選択に当たっては、どの商品が本当に環境にやさしいのかが消費者に分かりにくいことが障害となっている。商品は製造、消費、廃棄のそれぞれの段階で大気、水、土壌などに多様な影響を与えるため、これを総合的に把握するのは、消費者個人が通常入手できる情報の範囲内では不可能である。さらに、企業が、科学的裏付けが十分になくとも、「環境にやさしい」と称して販売促進を図る例がしばしば見られ、これが消費者の判断を混乱させるおそれもある。
これらの問題に対処するには、消費者に対して正確な情報が提供されることが必要である。こうした観点から、次項で詳しく触れるように、政府や民間団体などによる、環境にやさしい商品への環境ラベリング表示や商品の環境影響を総合的に評価するライフサイクルアナリシスの取組が世界的に広がり始めている。
(3) モラルファンド、環境株主
国民一人一入が持っている資金や財産の運用を通じて環境保全に努める動きもある。米国では、例えば軍需産業や人種差別政策をとる国と関係する企業への投資を抑制するなど、企業の社会性を考慮して投資を行う動きが古くからある。こうした投資家のために、特定の趣旨にかなった企業を選択して投資する投資信託がモラルファンドである。米国では、こうした社会的な配慮をした投資に振り向けられる資金の額は、現在、5000億ドルを超えると言われている。1980年代(昭和50年代後半)になると、投資先を選ぶだけでなく、自ら株主として、株主総会における議決権、提案権を行使して、企業経営に一般生活者の意志を反映させようとする動きが出てきている。
中でも注目されるのが、環境保護団体や投資関係団体などからなる連合組織である「環境に責任をもつ経済のための連合(Coalitionfor Envi-ronmentally Responsible Economies(CERES)」の活動である。CERESは、1989年(平成元年)に起きたアラスカ湾沖におけるタンカー(バルディーズ号)の座礁による原油流出事故を契機として、企業が環境保全のために遵守すべき原則を公表した。これは、バルディーズ原則と呼ばれ、?生活圏の保護、?天然資源の持続可能な活用、?廃棄物の処理と削減、?エネルギーの賢明な利用、?リスク削減、?安全な商品やサービスの提供、?損害賠償、?情報公開、?環境担当役員及び管理者の設置、?評価と年次監査、の10箇条からなるものである。CERESは1500憶ドルを越える運用資金を有していると言われ、株主としての権利を用いて、企業にバルディーズ原則の採用を求めている。これまでにこの原則に署名したのは30社ほどである。
我が国においても、平成2年には、投資信託会社によって、環境保全技術の開発に熱心な企業への投資を行う投資信託が新設され始めた。さらに、平成3年には、ある電力会社の株主総会において環境保護のグループが株主提案権を行使した結果、環境保全が議題として取り上げられた。
こうした動きは、自らの経済活動が環境に及ぼす影響を考え直し始めた市民の動きが、日常の消費活動の改善のみならず、預金や投資などの金融の分野にまで広がってきものと考えられる。さらに、株式という経済の基本的な仕組みを活用するところにまで広がる気配も見られている。
一方、投資ではなく寄附という形での市民からの資金の提供についても、公的な受け皿が作られてきている。平成3年度には、信託銀行等8社を共同受託者とする公益信託地球環境日本基金が、開発途上地域における環境保全に寄与する事業に助成を行うことにより地球環境保全への貢献を行うための寄附金の受け入れ先として設立された。郵政省においても、利息の一部が環境保全分野を含む国際協力を行う非政府機関に寄附される仕組みの国際ポランティア貯金が設けられ、既に平成3年度には約10憶円が配分されたほか、郵便葉書等に付加された寄附金についても平成4年度以降は地球環境の保全を図るために行う事業の実施団体に配分することが計画されている。こうした仕組みが、環境保全のための寄附活動の活発化につながることが期待される。
(4) 地域に根ざした集団的環境保全活動
国民は、環境保全に関する自身の責任を果たすだけでなく、志を同じくする者が集まり、所有する知識や経験、時間や労力、資金などを融通し合って広く第三者や社会のために用いることもできる。
こうした活動は、個々人が失われた権利や当然享受できたはずの利益を回復する運動とは異なり、積極的に新しい利益を社会に生み出していこうとするものである。
我が国における環境保全活動の例を見ると、例えば、霞ケ浦などの湖沼周辺地域などでは生活排水による環境負荷を減らす運動が展開されている。中でも滋賀県では、琵琶湖浄化のための生活排水の見直しから発展して、地球環境までを視野にいれた「環境生協」が市民の手で設立されるに至った。各地の海岸、河川などでは一斉清掃や緑化などの環境美化運動が行われている。近年は、缶、びんなどの集団回収や牛乳パックによる葉書作り、廃食油による石けん作りなどのリサイクル運動が全国的に活発化している。例えば、東京都目黒区では、区民の運動が契機となって、行政と住民の協力によるびんとアルミ缶の分別収集が行われている。また、自然公園などで美化清掃、利用指導などに当たるボランティア活動も活発に行われている。
こうした環境保全活動については多くの市民が関心を示しているものの、現状では時間的余裕のある高齢者が中心となっており、若年者では関心を持っていても現在は活動に参加していない人が多くなっている(第4-1-3図)。環境保全活動を行う障害となっているのは、?情報がないこと、?時間がないこと、?仲間がいないことなどである(第4-1-4図)ことから、市民の環境保全活動の一層の促進のためには、十分な情報の提供や労働時間の短縮などが求められている。
一方、優れた自然環境地域や身近な自然等を守るため、市民の浄財を寄附として集め、その資金で自然の豊かな土地等を買い上げる「ナショナル・トラスト」活動も次第に広がっている。環境庁が報告を受けているだけでも、和歌山県の天神崎保全市民運動や北海道のしれとこ100平方メートル運動など、既に70以上の事例があり、買上げ、あるいは借上げ等により自然保護が図られている土地の面積は、全国で約4900haにものぼる。
ナショナル・トラストの推進に当たっては、我が国の地価の高さがあい路となっている。例えば、埼王県のトトロのふるさと基金では、対象地が東京近郊であることから、市民の高い関心を背景に1億円にものぼる寄附が集まったものの、約1200?の土地しか買い上げることが出来ず、買上げのほかに土地所有者との契約により自然保護を図ろうとしている。このように、土地の買い上げという活動の性格上、目標金額が巨額に上ることになり、特に都市周辺地域の保全を行おうとする場合には、市民の自主的な寄附のみでは目標が達成できない例が多い。このため、ナショナル・トラストを一層促進していくためには、社会全体としてこれを支援していくことが必要である。
現在、ナショナル・トラストを行う団体を特定公益増進法人として認定し、これに対する寄附金について損金算入を認める等の税制上の優遇措置を講じる制度が設けられており、このような団体の育成が課題となっている。
以上のような市民の環境保全活動は、都市の希薄な人間関係を回復し、コミュニティ形成の一助となる効果も持っている。「地球規模で考え、足元から行動を」の考えに立ち、地域の住民が互いに協力し、自らの生活の場で積極的に地球にやさしい社会づくりを担っていくことが望まれる。
(5) 国境を越えた地球市民を目指す団体とその活動
途上国における環境問題や地球的規模の環境問題については、国際活動を行う市民の自主的組織(NGO(非政府団体))の果たしている役割が大きい。NGOとは、広義には、非営利の活動を行う民間、市民の団体一般を含むが、国連の定義によれぱ、政府間協力によって設立されたものではなく、なんらかの目的を持つ国際組織であるとされている。こうした組織は、国境に画された領域について責任を負う政府とは異なって、国境の内外を問わず自由に活動することが特色となっている。
早くも1900年(明治30年頃)前後に設立された米国のシエラクラブや全米オーデュボン協会を始めとして、欧米では古くから環境NGOの活動が行われてきたが、1970年頃(昭和40年代半ば)から新たな設立が相次ぎ、内外の環境問題について、キャンペーン、圧力行動、援助活動の実施、調査研究など活発な活動が展開されてきた。例えば、米国の世界資源研究所(WRI)、ワールドウォッチ研究所等による地球環境に関するデータ整備、評価、政策提言等は、地球規模の環境問題に関する基礎的な資料となっている。世界自然保護基金(WWF)等は野生生物保護などの分野で各種のキャンペーンを実施している。また、米国では、NGOの活動が各種の環境保全に関する法案の成立などの成果をもたらしている。このほか、国際的な広がりを持つ地球の友、グリーンピース、世界自然保護連合や米国のコンサベーション・インターナショナルなどが様々な活動を行っている。こうした欧米のNGOの活動は、欧米以外の国に対して自らの価値観を押し付ける傾向があるとの批判もある一方、環境問題に関する知見の集積、政策決定への影響、援助などの直接的な活動などを通じて環境保全の進展の上で欠くことのできない役割を果たしてきた。平成4年の地球サミットは、準備の過程からNGOの協力が取り入れられ、本会議においても、NGOの公式参加と発言が認められる画期的な国際会議となる。NGOの果たす役割はますます大きくなっていくと考えられる。
我が国においても、昭和60年代から環境NGOの活動が盛んになり、国際協力などに実績を挙げている。例えば、熱帯林保全、野生生物保護のキャンペーン、湖沼、マングローブ等の科学的調査・研究などが行われており、また、植林ボランティアの派遣、マングローブ植林パイロット事業などに現地住民とともに取り組む団体もある。湾岸危機後の環境の回復や被害を受けた生物の救助には我が国のNGOも世界のNGOとともに参加した。また、地球サミットに向けては、多くの団体、個人が集まり、市民独自の提案を行うべく「92国連プラジル会議市民連絡会」が結成され、政府の用意したナショナル・レポートに意見を述べたり、自ら世界に向けた提言を準備するなど、その活動はますます活発化している。
しかし、豊富な会員を有し、各種財団からの財政援肋により様々な活動を展開している欧米諸国のNGOと比較すると、我が国の環境NGOは、未だ歴史が浅いこともあり、財政基盤が脆弱で、専門家の確保が十分でないなどの課題を抱えている。欧米の環境NGOの中には数10万、数100万の会員を擁するものもあるが、我が国では最大の(財)日本野鳥の会でも会員は約3万7千人に過ぎない。また、欧米では、年間予算が数十億円を越える団体もいくつかあるのに対して、我が国では、10億円弱の予算を持つ団体が散見できるに過ぎない(第4-1-5図)。この背景には、我が国では社会貢献のための寄附という伝統が浅く、寄附金の総額が少ないこと、これに関連して、税制上の支援措置が十分活用されていないこと、NGOが有益な活動を行っても、いわゆる官尊民卑の風潮の名残から社会的に十分な評価が与えられないことなどがあると考えられる。
先進国から途上国への資金の流れを見ると、環境に関係しないものも含め、全世界では年間約45億ドル、我が国でも約1億ドルの資金がNGOを通したものであり、NGO活動が途上国の二一ズにきめ細かく対応し得ることを考え合わせると、NGOは国際環境協力において大きな役割を果たしていると言えよう。
我が国が、今後、地球環境保全の分野で世界に貢献するためには、NGOによる環境協力が重要な位置を占めることになる。既に外務省において国際的活動を行うNGOに対する資金援助を開始しているが、今後とも、政府がNGOとの連携を強化していくとともに、市民、企業においてもNGOが有効な活動を展開できるよう支援することが望まれる。
環境国際協力を行うNGOの新しい取組として自然保護・債務スワップがある。自然保護・債務スワップは、国際的NGOが中心となり、開発途上国の抱える対外債務を途上国の国内通貨による自然保護事業に転換(スワップ)する仕組みであり、具体的には、国際的NGOが民間金融機関から途上国の債務の一部を購入し、途上国政府に対しては債務を消減させる代わりに自然保護のために現地通貨による投資を行ってもらうというものである(第4-1-6図)。
自然保護・債務スワップは、1987年(昭和62年)に米国のNGOであるコンサベーション・インターナショナルによりポリビアにおいて初めて実施されて以来、平成3年末までに11カ国において21件の案件が成立し、額面で合計約1億ドルの債権が購入され、約7000万ドルの自然保護事業のための資金が生み出された。これにより、自然保護プロジェクトとして、自然保護区や国立公園の保護管理、植林、環境教育などが実施されている。我が国においても、平成3年に、東京銀行グループが100万米ドルの債権を世界自然保護基金米国委員会(WWF-US)に寄附し、フィリピンの自然保護プログラムなどに充てるという初めてのスワップ案件が成立した。さらに、平成4年3月には(株)第一勧業銀行が100万米ドルの債券を世界自然保護基金日本委員会(WWF-J)に寄附し、ガラパゴス諸島の自然保護プロジェクトなどに充てることを決定した。これは日本のNGOとして初めてのスワップヘの参画となる。
累積債務を抱える途上国は、自然保護に回す資金が不足していることに加え、外貨獲得のために自然資源が過剰に開発され、将来の発展の基盤を一層悪化させるという悪循環に陥っている。自然保護・債務スワップは、1兆3,400億ドルを超える累積債務総額に比べ微々たるものとはいえ、こうした悪循環を断ち切る一石二鳥の手法であると言える。一面では、債務国の内政干渉、モラルハザード(債務国の債務返済意欲の減退)やマネーサプライ増加によるインフレにつながるおそれがあるなどの指摘もあるものの、途上国では、わずかな資金がねん出できないために貴重な自然が失われており、その資金をもたらす点で自然保護・債務スワップには大きな意義がある。例えは、エクアドルの自然保護・債務スワップによって調達された資金だけでも、同国の国立公園の総予算に等しい額であった。
自然保護・債務スワップの円滑な推進を図る上では、環境NGO、金融機関、資金提供者の間の円清な情報交換が不可欠であり、こうした観点から環境庁においても(社)海外環境協力センターに自然保護・債務スワップ情報ネットワークを整備している。国際的環境NGOを中心として、企業、途上国政府、途上国現地のNGOなどの協力の下に、自然保護・債務スワップがさらに進められることが望まれる。