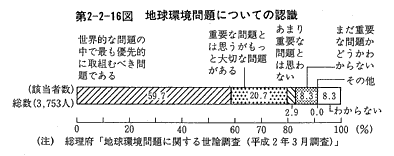
2 環境への配慮が不十分になりがちな理由
既に日本の経済成長の過程では、公害や自然破壊の形で経済社会の持続可能性を損ねた不幸な経験が生じた。なぜそのようなことが生じたのか、その背景を探ってみよう。持続可能な社会をつくっていくためには、こうした背景事情が改められる必要があるからである。
背景事情として重要なのは国民や企業の選択である。
環境保全に対する国民、企業の意識は一般的には高いと言えよう。総理府「地球環境問題に関する世論調査(平成2年3月調査)」によれば、59.7%の者が、地球環境問題を「世界的な問題の中で最も優先的に取り組むべき問題である」と回答しており(第2-2-16図)、また、経済企画庁が実施した平成2年度国民生活選好度調査によれば、58.7%の者が、「経済成長率を低下させることになっても資源・環境保全に努力すべき」という考えに自らの考えが近いと思っていると返答している(第2-2-17図)。また、同調査において、国民生活に係りのある数多くの具体項目について、今の、あるいは、これからの生活にとってどのくらい重要なことであるかを調べた結果を見ると、「大気汚染、騒音、悪臭などの公害がないこと」が、常に重要度が高い上位10位以内に入っており、かつその順位が年々上がってきている(第2-2-3表)。
しかし、総論としては環境保全について積極的な意識が見られるとはいえ、具体的な問題についての選択になると必ずしも環境保全が優先されているとは言い難い。
環境庁長が、昭和55年に行った調査によれば、空き缶のぽい捨ての経験のある者(調査対象中27.8%)が挙げた空き缶ぽい捨ての理由は、「近くにごみ箱などがなかったから」、「自動車に乗っていて始末に困ったから」、「ごみ箱などのあるところや家にまで持っていくのが面倒だったから」といったものが主な理由で、環境保全についての責任感が乏しく、空き缶を直接ごみ捨て場まで持っていく手間を惜しみ、些細な利便を環境より優先していることが分かる。
企業においても同様の傾向が見られる。環境を守ることの大切さは、一般的には認識されるようになってきており、平成3年度に、環境庁が行った調査によれば、環境問題対策組織を常置している企業は、回答のあった企業の65.2%を占めており、このうちの、56.8%が2年以降に組織を設置したものである(第2-2-18図)。しかし、企業にとっては、単なるムードで環境保全に努めるわけにはいかない。平成2年度に通商産業省の行った「企業経営力実態調査」によれば、企業にとって、成果としての目標とするのは「利益の最大化」、「売上高の最大化」である(第2-2-19図)。また、上記の環境庁の調査によれば、62.7%の企業が環境保全の費用について、「業績に深刻な影響を与えなければできるだけ負担する」と答え、「重大な問題であり、会社の業績等に関わらず負担する」と回答した会社は、7.5%にとどまった(第2-2-20図)。また、具体的に、年商や経常利益に比較した場合の環境保全のための経費負担の意識を見ると第2-2-21図のとおりである。これらのことは、企業にとっては、売上高や経常利益の最大化が主たる目標であって、環境保全の費用は、業績に深刻な影響を与えない限り負担するという一つの配慮事項と考えられていることを示している。
また、警察庁の調べによると、公害事犯の検挙件数の9割以上を占める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反の原因動機としては、「処理経費節減のため」、「最初から営利目的で」という経済的な理由によるものが多い(第2-2-4表)。
これらのことは、環境への適正な配慮を払うことがなぜ困難かを考える上での良い手がかりとなる。すなわち、具体的に環境保全と経済的利益との選択に迫られるような場面では、どうしても経済的な利益が重視される傾向がある点では、国民も企業も同様である。短期的な経済的利益は明白である一方、自らの行為が社会にもたらす悪影響を考慮に入れるような動機や長期的な視点を人々は欠きがちなのである。こうした事情の下で環境の悪化が生じているものと推測される
我々は、生産活動の中で、様々な商品を「財」として生産し、日常生活の中で消費している。通常の財であれば、市場機能を通じて、その原価に即して需給量が調節され、過剰に消費されることはない仕組みとなっている。
しかし、環境資源は、一般の生産要素とは違った性格を持っており、このため、市場による効率的な資源配分の実現には困難がある。
大気を例にとってみよう。我々は、特別の規制が課されない限りは、代価を支払うことなく、大気を生産活動の過程で利用し、汚染物質を大気中に排出している。そしてこの活動から誰も排除することはできない。すなわち、仮に工場や自動車の増加により、例えば、窒素酸化物等の汚染物質の排出量が増加したとしても、それに応じて、一人一人の汚染物質排出量を低減しなければ各人が大気を利用できなくなるというわけではないのである。国民や企業は、大気などの環境施減の使用の対価を負担することは一般的にない。このため、環境資源が過剰に消費されがちになり、また、環境は無限に汚染物質を受容できないため、汚染問題が発生することとなる。市場の失敗、外部不経済といわれる現象である。
このように、環境資源の利用を自由な経済活動に任せていては、環境は保全されることなく汚染が進行していってしまう。環境保全に向けた動機づけが、日常行動の中にまで浸透する必要がある。環境の利用に伴う責任などに関する環境教育や普及啓発活動による意識への働きかけはそのための不可欠な手段である。しかし、それだけに依存するのでは、確実を期し難い。環境への配慮をあえて怠っても特別の不利益がなく、かえって経済的利益が生まれるので、せっかく、正直に環境への配慮を尽くす者との不均衡が避けられない。
環境の保全に当たっては、国民や企業に対して環境保全に配慮するような動機付けを行う社会的な仕組みをつくることが欠かせないのである。このような社会的な仕組みとしては、大きく分ければ環境保全意識を高める教育、環境を損ねる行為を不利にし環境に資する行為を有利にし奨励するような社会的、経済的な誘因、そして、環境に悪影響のある具体的な行為を制限する規制といった種々の政策手段がある。こうした政策手段の体系として発達してきたのが、環境行政である。社会公益の観点に立った政策なくしては、環境保全は期し難い。今後とも、広く国民的な議論を行い、必要な政策手段については積極的にこれを講じていくことが肝要である。
特に、環境のもたらす恵みを長期的に確保していこうとする場合には賢明な政策が是非とも必要である。これは、将来を見通すためにはそれなりの科学的な予測が必要であることや、環境悪化による不利益を被るのは将来世代であって、現在は発言権を持っていないためである。
温暖化やオゾン層の破壊等の地球環境問題の場合においても同様のことが言える。例えば、特定の国が、温暖化防止のために温室効果ガスの排出を削減した場合、排出削減を行った当該国だけでその利益全部を享受できるのではなく、利益は、世界全体に流出してしまう。このような条件の下では、各国の自主的な取組に任せていたのでは、積極的な環境保全への取組に対するインセンティブは少ないと言える。特にこの場合、主権を有する国家が当事者となるため、国内環境問題と異なり、一元的に調整し、対策を強制する機関が存在しない。多国間の自発的政策協調がなければ、地球環境は守られない。こうしたことから、既に、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン・ダンピング条約、昭和47年採択)、「絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約、48年採択)、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(「オゾン層の保護に関するウイーン条約」に基づき、62年採択)、国連ヨーロッパ経済社会理事会(ECC)の下での「長距離越境大気汚染条約」(54年採択)等の国際条約が結ばれている。
さらに、国家の管轄権が及ばない地域については、例えば、南極地域は、南極条約の下で各国の領土権の主張は凍結されているが、南極条約締約国の協議により、動植物の保存に関する合意措置、アザラシ保存条約、海洋生物資源の保存に関する条約が、さらには、平成3年10月に南極地域の包括的な環境保護を目的として「環境保護のための南極条約議定書」(未発効)が採択されるなど、同地域における諸活動に関する国際的取決めが行われている。
地球の環境を、国家の枠を超えて国際機関あるい国際的な取決めの下に置いて管理していこうとの考え方は、各種の地球環境問題への対応の基本の一つとなるものと考えられる。