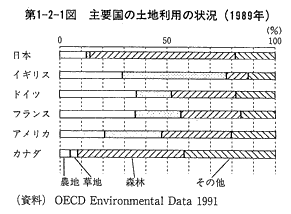
1 自然環境の現状
(1) 我が国の土地利用
日本における土地利用の状況は国土庁の推計によると平成元年度において森林2,526万ha(総国土面積の66.9%)、農用地538万ha(同14.2%)、宅地159万ha(4.2%)などとなっており、、先進諸外国の中でも森林の割合が著しく大きいことが特徴である。これは、山岳地の多い急峻な地形と、多雨多湿の気候風土によるものと考えられる。他の先進工業国では農地の割合が最も多い(第1-2-1図)。
このように日本においては森林が多いため、土地利用に関する問題の在り方が諸外国と異なっている。小麦などの農地の多いアメリカやヨーロッパでは、土壌流出が大きな問題となっている。アメリカでは1980年代(昭和60年前後)には毎年1ha当たり10.5トンの土壌が流出したと見積もられている。こうした土壌流出問題は、日本においては、沖縄における赤土流出問題があるが、土壌の流出そのものというより、海域への流出による海中生態系への影響という点で問題となっている。
自然公園は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図る観点からの土地利用ということができる。我が国の自然公園は、国立公園が28箇所、国定公園が55箇所、都道府県立公園自然公園が299箇所指定されており、総面積約533万ha、国土面積の14.11%を占めている。国立公園は昭和9年から、国定公園は25年からそれぞれ指定が開始されたが、年々その面積は拡大していった(第1-2-2図)。自然公園の利用者は特に昭和30年代後半から40年代中葉にかけて急激に増加し、利用者の集中による植生破壊などの問題が発生するなど各地で観光開発による自然破壊が見られた(第1-2-3図)。
(2) 自然の環境の状況
我が国は、その複雑な地形、四季を通じて豊かな降雨量に恵まれ、森林が広がり、また、多彩な気候条件のもと、豊かで変化に富む植生を持ち、これを基礎として数多くの野生生物が生息している。
我が国は島国であり、本州ほかの主要な島(本土部域)以外にも数多くの島々があり、海岸線は極めて長い。こうした海岸には、砂浜や干潟、岩礁など様々な景観が見られ、漁業活動やレクリエーションなどの人間活動の格好の舞台となる一方、数多くの野生生物に生息地を提供している。
しかしながら、我々の経済、社会活動の中で、我が国の自然環境は大きく変化してきた。
植生を例にとれば、自然性の高い地域から人為の影響を受けた植生が成立している地域、宅地等自然が改変された地域まで様々であり、原初的な状態を保っている地域は限られている。また、自然改変の集中、大規模化が進み、逆に薪炭材やカヤの採取のような従来の自然利用の衰退による植生の変化も顕著となっており、日本の自然環境は大きく変化しつつある。
環境庁はこうした自然環境の現状とその変化を調査するため、概ね5年ごとに自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)を実施しており、陸域(植物、動物、地形、地質)、陸水域(河川、湖沼)及び海岸域(海岸線、干潟、サンゴ礁等)について、昭和48年度より調査を実施している。
以下その成果をもとに現在の日本の自然環境の状況を明らかにする。
ア 植生
63年にとりまとめた調査結果によれば、日本の国土のうち、自然植生や耕作地植生などなんらかの緑で覆われている地域は、92.7%を占め、森林地域は国土の67.5%を占めている(第1-2-1表)。
しかし、その内訳を見ると、自然状態を保った緑は必ずしも多くはない。自然度の高い緑は、高山植物などに代表される寒帯・高山帯植生、トドマツ、ダケカンバなどの亜寒帯・亜高山帯植生、ブナ林に代表されるブナクラス域自然植生、シイ・カシなどの照葉樹林に代表されるヤブツバキ域自然植生、そして河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生といった緑に分けられるが、その合計は全国土の19.3%となっている。こうした自然性の高い緑は、その6割近くが北海道に分布しており、また、急峻な山岳地帯や半島、離島といった限られた地域に集中している。森林は、緑のダムと呼ばれるほど水源かん養能力を有し、特に自然性の高い森林は、数多くの野生生物の生息地として、今日では貴重なものとなっている。
平地、丘陵地など我々の活動領域に近い地域では、薪炭材の採取など人間活動の影響を受けた二次林や、人為的に作られた植生である植林地、耕作地が多い。二次林は、ブナクラス域ではミズナラ林、ヤブツバキクラス域ではコナラ、クヌギ等の雑木林、マツ林、シイ・カシ萌芽林などによって構成されるが、これらの総計は全国土の約4分の1、24.6%になる。こうした二次林は、薪炭材を採取するなど人の生活領域であった林であり、我々の生活の場にも近く、必ずしも自然性は高くないものの、身近な自然として貴重な緑となっている。
一方、人為的に作られた植生である植林地や耕作地は国土の半分近く、47.4%を占める。植林地の多くはスギ、ヒノキ等の林である。
第1回調査の行われた昭和48年から、54年の第2回調査、58年から61年の第3回調査の間の植生の推移を見ると、森林面積全体はほとんど変化していないが、自然林・二次林が3.9%ポイント減少し、植林地が4.1%ポイント増加している(第1-2-2表)。
我が国は、国土の大半を緑で覆われた国であるが、緑の多くは人工的な緑が占め、自然性の高い緑は限られた地域に残されているに過ぎない。
イ 湖沼
我が国には湖沼も数多く存在している。環境庁は全国の湖沼(1ha以上の天然湖沼)を対象に調査を行っているが、調査対象湖沼の面積は、2,380.08km
2
、国土面積の0.63%にあたる。我が国の湖沼は山岳地帯にあるものから、海が後退してできた海跡湖のように平野部、海岸近くに存在するものまで多様である。
湖沼の透明度は、第1-2-3表のとおりであり、カルデラ湖、溶岩流などによる堰止湖では一般に透明度が高いものが多い。
湖岸はその土地利用状況を反映して、改変を受けている。人工湖岸率が50%以上であり、かつ市街地・工業用地に利用されている湖岸の割合が30%を超える湖沼を「改変が進んだ湖沼」と分類しているが、54年から60年にかけて「改変の進んだ湖沼」に分類された湖沼は、19湖沼から27湖沼に増加した。これらはいずれも平野部にある海跡湖である。また、昭和20年以降なんらかの干拓・埋立の行われた湖沼は57湖沼、面積は約344km
2
であり、20年以降、湖沼総面積の約13%が干拓・埋立によって縮小したことになる。湖沼は農地、工業用地、市街地など様々な土地利用によって置き換えられていった。
湖沼は、生物の生息地としても重要である。生息魚種類数の多い湖沼は第1-2-4表のとおりであり、汽水魚、沿岸魚の侵入する海跡湖の魚類相が豊かであることが分かる。
一方、外国産の移入魚も各地の湖沼で定着しつつあり、湖沼の魚類相を変化させる要素の一つとして今後もその推移を注目する必要がある。
ウ 河川
河川の自然環境については、環境庁が昭和54年と60年に、一級河川の幹川等113河川に関して調査を実施した。
調査した河川の水際線、11,412.0?のうち、人工化された水際線(平水時に護岸等人工構造物と接している水際線)の延長は、60年度では2,441.5?であり、総水際線の21.4%を占める。54年から比べると、249.3?が人工化され、構成比で見ると2.2%の増加である(第1-2-4図)。
河原の土地利用の状況は、自然地が約3分の1を占め、農業地、施設的利用地の順に利用が行われている。ここでも自然地が減少し、農業地や施設的利用地の割合が増加している。
ダムや堰などの河川横断工作物は、魚類の遡上を助ける適切な措置を講じない場合には、魚類の生息域を分断させることがある。調査河川113河川のうち、河川横断工作物がない河川、または魚道がうまく作動するなど、魚類の遡上を妨げる要素のない河川は、網走川、釧路川、浦内川、常呂川、留萌川、後志利別川、雄物川、天神川、高瀬川、名取川、十勝川、久慈川及び土器川の13河川である(第1-2-5表)。また、河口からの遡上可能区間の割合が流路延長の90%を超える河川が、上記の13河川に加え、揖保川、日野川、岩木川、長良川、円山川、四万十川、最上川、米代川及び那珂川の9河川あり、合計22河川になる。これは調査河川数全体の19%を占める。一方、河口からの遡上可能区間割合が10%に満たない河川は芦田川等6河川ある。遡上可能区間の調査河川延長に占める割合の平均は、全体では58.9%となっている。
河川も魚類ほか多様な生物の生息地である。生息魚種類の多い河川は第1-2-6表の示す通りであり、本州の河川が多い。
エ 海岸
我が国の総海岸線は、昭和59年に実施した調査によれば32,472?であり、本土域海岸がその58.3%を占め、島しょ域海岸が41.7%を占める。なお、総海岸線は埋め立ての結果前回53年調査に比べ若干増加している。海岸の区分比は、総海岸線でみると、自然海岸が56.7%を占め、人工海岸が28.6%、半自然海岸が13.9%と続いている。島しょ部を除く本土部のみで比較すると、自然海岸の占める割合が46.0%、人工海岸の割合が36.5%である(第1-2-5図)。昭和53年から59年までの変化を見ると、自然海岸が565?減少し、人工海岸が696?、半自然海岸が171?増加している。この増減の内訳をみると、砂浜、岩石海岸が減少し、埋め立て海岸が増加している(第1-2-6図)。
オ 自然景観
我が国において、滝や渓谷、山岳地などの景観として優れている地形、地質、自然現象は、地域のシンボル、観光資源、学習、さらには感動を得、人間性を回復する場として貴重な存在である。昭和63年に取りまとめた調査結果によれば、こうした自然景観資源は全国で15,468件あり、最も多いのは滝(2,488か所)、ついで火山(1,158か所)、峡谷・渓谷(996か所)、非火山性孤峰(993か所)、湖沼(872か所)、海食崖(734か所)、砂浜・磯浜(632か所)となっており、これら7つの自然景観資源で全体のほぼ半数を占める。
こうした自然景観資源のうち、自然公園、自然環境保全地域、天然記念物等何らかの保護の下にあるものは57.8%であり、それ以外のものについても、風致保安林や国有林については保護林等で、また、地方公共団体では条例等によって保護措置がとられている。また自然景観資源の約3分の2は既に開発行為等何らかの人為による影響を受けている。影響の種類として最も多いのは、人の立ち入りであり、ついで、農林業開発、観光開発の順である。
(3) 都市周辺の自然環境の状況
我々の生活の周りにある緑や馴染みの深い動植物の存在は、見過ごされがちであるものの、自然と親しみつつ日常生活を営む上で不可欠な要素である。また、こうした都市周辺の自然環境は、ヒートアイランド現象の緩和など都市地域の気象条件や環境の改善に役立つほか、それ自体が、都市の大気、水質、土壌の環境の状況を映し出す役割も持っている。
自然環境保全基礎調査は、植生をその人為の影響の度合に応じて10に分類し、調査を行っているが、これを自然植生、二次植生、植林地、農地等、市街地の5区分にまとめて、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、愛知県、大阪府の自然状況を分析すると、こうした地域のいずれもが全国平均に比べ圧倒的に自然植生が少なく、逆に緑の少ない市街地の割合が多いことが分かる(第1-2-7図)。また、都市近郊では、二次植生がいわゆる里山として身近な自然、野生生物の生息地を形作っているが、こうした植生も全体的に少ない。昭和55年以降の首都圏の土地利用の変化を見ると、二次植生、農地が減少し、市街地が増大している。
(4) 途上国における自然の状況
開発途上国の国民の多く(アジア・アフリカ平均で人口のおよそ3分の2)は、農業、林業、漁業といった第1次産業に従事し、自然資源に多くを依存した生計を営んでいる。森林、野生生物、土壌といった自然環境は、住民に燃料、食糧、水、建築資材、家畜の餌等を提供するとともに、洪水の防止、気象の調節などに役立ち、また経済活動の対象ともなって人々の生活や環境を守る働きを持っている。さらに、途上国には豊かな自然資源を持つ国が多く、地球的価値を有する貴重な遺産を形成している。しかし、途上国においても、産業の進展、工業化に伴い自然資源を失ってきた先進国と同じ過程をたどって、また、途上国の貧困や人口増加を背景とした自然資源の過剰利用等の過程によっても、自然資源のストックが失われつつある。以下、森林、土壌に分けて、アジアを中心に、途上国の自然資源の状況を見ていこう。
ア 森林
1987年(昭和62年)現在で世界には森林が40億6,853.6ha存在していると見積もられている。こうした森林のうち、日本を除くアジアには5億1,370.1万ha、南アメリカには8億9,996.1万ha、アフリカには6億8,633.7万ha、アメリカ合衆国とカナダを除く北アメリカには6,651.5万haの森林が存在し、これらを合計した途上国の森林は21億6,651.4万haであり、世界の森林の53.25%を占めている(第1-2-7表)。
こうした途上国の森林の多くは熱帯林であり、その減少が世界的な関心事となっている。1991年(平成3年)9月に開かれた第10回世界林業大会に、FAOによって実施されている「1990年森林資源評価プロジェクト」の第2次中間報告が提出された。この報告書では、特にアフリカ諸国のデータが揃っておらず、あくまでも暫定的なものだが、熱帯地域に位置する87か国についてその森林面積と1980年(昭和55年)から1990年(平成2年)にかけての森林減少率を評価している(第1-2-8表)。これによると、調査対象87か国で、年平均1,700万haの森林が減少し、森林面積の0.9%が毎年失われている計算になる。1981年(昭和56年)にFAO/UNEPが公表した1980年森林資源評価では1980年(昭和55年)から1985年(昭和60年)までの熱帯林減少率を推測している。この1980年評価と現在の1990年評価でともに調査対象となっている76か国について1980年から1985年までの森林減少率を比較すると、1980年評価では年0.6%の減少と予測されていたが、今回の中間報告段階では、0.9%であった計算になる。また、森林劣化についても、同プロジェクトで実施中の研究によれば、森林劣化による熱帯林のバイオマスの減少は、森林面積の現象よりもかなり高い比率で生じていることが予測されている。
イ 土壌
土壌は、農業、牧畜といった経済活動の基盤であり、その状況が悪化したり、土壌が失われると、これらの経済活動が不可能になるだけではなく、人間の生活自体にも大きな影響を与える。サヘル地方をはじめとするアフリカ各地などでは、貧困等により、他に燃料確保策、収量増加策がないため、樹木や草の再生力を超えた薪の採取や牧畜、移動式耕作の周期の短縮等により、土壌の劣化、喪失を招き、土地が乾燥する。人々はしばしば襲う干ばつに備えるだけの資力もないため、環境難民として他の土地へ、あるいは都市へさまようことになる。土壌劣化と喪失の問題は、各地で見られ、それは砂漠化に止まるものではない。砂漠化のほか、風・水による土壌の風化、灌漑の副次的影響である土壌の塩害、アルカリ化、灌漑水の水はけ不良による堪水化と様々な形を取る。またヒマラヤ山系、エチオピア高地に代表されるような山岳地では植生の失われた土壌の流失が激しい。UNEPは1992年(平成4年)のUNEP管理理事会特別会合に「砂漠化の現状及び砂漠化防止行動計画の実施状況について」というレポートを提出した。以下このレポートに基づき、乾燥地における土壌劣化問題を見てみよう。
世界には61億ha以上の乾燥地が存在し、地球の陸地の40%近くを占める。そのうち9億haが極めて乾燥している地域で、いわゆる砂漠である。残りの52億haの一部が人間活動の結果、砂漠化している。こうした乾燥地域で世界人口の約5分の1の人々が居住し、生活を営んでいる。1991年にUNEPが行なった評価によると、乾燥地域における農地の69.0%、35億6,217万haが乾燥化により影響を受けている。その内訳は、灌漑地の劣化が4,315万ha、これは乾燥地における総灌漑農地の30%を占める。同じく雨水に依存する耕作地の47%に当たる2億1,556万ha、さらに牧畜地の73%に当たる33億3,346万haで砂漠化が進行している。地域別にみると、劣化している割合が高いのは、北アメリカ、アフリカ、南アメリカの順であるが、面積で見るとアジアが最も多く、アフリカがそれに次ぐ(第1-2-8図)。
土壌の劣化にさらされている地域は11億3,830万ha、極めて乾燥している地域を含めた乾燥地全体の18.3%を占める。土壌劣化の態様は、降雨による土壌の流失など水による侵食が最も多く、次に表土が吹き飛ばされるといった風による侵食が多く、塩害やアルカリ化といった化学的な劣化、堪水化など物理的な劣化と続いている。大陸別で見ると、被害を受けている面積が最も広いのは、アジアであり、アフリカ、ヨーロッパと続くが、乾燥地面積に占める土壌劣化の割合を見ると、アフリカが81.1%とずば抜けて多く、アフリカの乾燥地の8割以上の土壌が劣化しつつある。