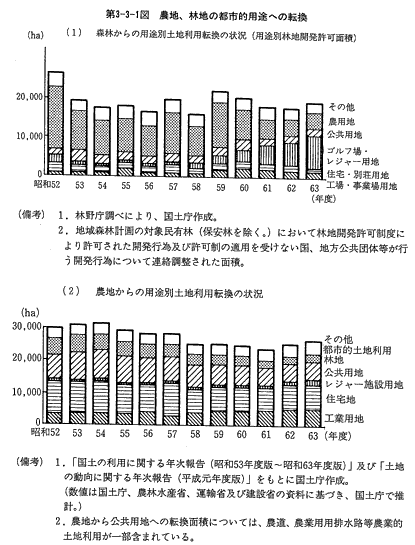
3 自然とのふれあいの推進
(1) 自然とのふれあいの機会の創出と適切な配慮
現在を生きている我々は、これまでの地球の歴史の所産であり、自然環境との相互関係の中で発展してきた存在である。次の世代及びそれ以降の世代の発展もこのような地球生態系の中の人類という視点を欠くことはできない。このため、人と地球生態系の関係を学際的、総合的に理解しようとする研究を振興することによって自然への正しい理解を深めていくとともに、人間が理性のみによって自然と結ばれるのではなく、感性をも通じて交流することができるよう、自然とのふれあいの機会を増大し、人々の心の中に自然を慈しむ心を育んでいくことが不可欠である。
しかし、世界では、都市化の進展や、国土の荒廃などによって、人々が自然にふれあう機会が減少しており、自然とのふれあいの機会を意識的につくっていかなければならない。
一方、交通手段の発達や余暇の増大等によって日本をはじめとして欧米においてもリゾートや有名国立公園に多くの人々が出かけるようになり、過剰利用による自然の破壊が問題となってきている。
欧米等の国々では、経済活動の高度化がもたらすゆとりへの希求が、都市の中に快適な環境を創造しようという動きになって現れてはいるが、いまだにその途上にあり、多くの人が都市生活によるストレスを癒すために自然を求め、長い休暇を取って家族又は友達同士で自然の豊富なリゾートや国立公園等の自然公園に出かける傾向がみられている。
一方、開発途上国では、急激な工業化、都市化に伴って、都市人口が急増し、快適な都市生活を営むために必須の道路等の基盤整備が立ち遅れており、都市周辺部の農地や林地が無秩序に住宅、工業用地等に転換され、古くからの自然とのふれあいの場であった環境が失われている。自然とのふれあいの場の確保については、国立公園制度やバード・サンクチュアリーの制度はあるものの、その管理が不十分であり、利用者を受け入れる施設も未整備のため、ふれあいの機会は少ない。他方、ケニアやタンザニア等のアフリカ諸国では、道路や空港が整備され、ふれあいの機会の増大が図られているが、一部では利用者の急増が野生生物に悪影響を与えている例もある。
本来、自然を楽しむには、適正利用密度という考え方がある。特に野生生物の姿を追う楽しみの場合、低密度利用が必要条件であり、広大な自然を必要とする。自然とのふれあいを推進するに当たっては、ふれあいの対象となる自然を損なうことのないような配慮が必要である。
(2) 自然環境と暮らしとの関係の希薄化
ア 経済社会活動と自然との分離
自然は人為によって大きく変化する。日本の自然は、明治維新による近代化以降、日本の経済社会活動の変化に伴って、大きく変化していった。
日本には、森林が比較的多く残されているが、これは、山村住民の努力によって森林の管理が行われてきたことや里山の森林の存在を前提とした農業生産様式がとられてきたことに加え、これまで日本の社会経済活動が急傾斜のため利用しにくいところが多い日本の森林を他の用途として必要としてこなかったことによると考えられる。
森林は、利用しやすい場所から次第に農地などになっていった。農業は、本来的に生態系循環に依存して成り立つ産業であり、また、農業、農村には国土・自然環境を保全する機能を有しているが、経済活動面における農業の占める割合は他産業が世界に類をみないほど急速に成長したこともあって日本で急激に小さくなっている。また、農業生産は、人力や畜力に依存していた農業から、機械、設備などの資本財と化学肥料などを使用し、生産性の向上を図る形態へと変化していった。
さらに、農地は急速な経済成長を背景に、他産業等の旺盛な土地需要に応え、商工業用地、住宅地などの都市的用途に転換され、また、土地の価格が高騰するにつれ自然が残されていた土地も減少した。(第3-3-1図)。建物等は敷地いっぱいに建てられるようになり、屋敷林や庭にあった高木等も伐られ、人々は、ますます自然から離れて生活するようになった。
イ 日本の自然の変化
日本の経済発展、産業構造の変化は、日本の自然環境を変えてしまった。
まず、身の回りから野生生物が減少し、多くの種の絶滅が危機に瀕している。特に、第二次世界大戦後の急速な経済成長は、急速な都市への人口集中によって都市地域における雑木林などの自然を消失させ、また、農村地域も拡大や都市周辺における林地の開発等によって野生生物の生息地を減少させていった。(第3-3-2図)。野生生物の生息地と人の経済社会活動の場所との住み分けは十分になされず、すみかを追われた野生生物が移るべき場所は、多くの場合、用意されていなかった。既に絶滅した野生生物はオオカミなど多種にのぼり、小説や記録上でしかその痕跡をとどめていない。(第3-3-3図)。
また、日本の風景は絵画や歌など日本の文化の中に残されているが、経済社会活動の活発化に伴って失われていったものである。
従来、自然景観は、自然と人間の生産活動の場との接点で観察され、これが一つの眺望点となっていた。しかし、これまで到達できなかったところまで簡単に人が行けるようになったことによって、優れた景観が失われてしまったところもある。
河川、海岸線についても大きな変化が生じている。海岸の人工化が進み、景勝地が失われたところもある。特に、臨海部が経済社会活動に適した地域であったために大都市圏にあった遠浅の海では多くの埋め立てが行われた(第3-3-4図)。このような地域では、自由なアクセスが制限され、人々が海岸線に出て海と接することができる場所が少なくなっている。
さらにゴルフ場などの豊かな自然の中での大規模なレジャー施設の造成は、一方で国民の余暇利用の欲求に応えるものであるが、広い面積にわたる木竹の伐採、土地の形状の変更を伴い、野生生物を含めた生態系、景観等自然環境への影響が大きい。
現在、我が国には、ゴルフ場が約1,700か所、約17万haあり(第3-3-5図)、この面積は、佐渡島の面積(約8万5,700ha)の2倍に相当する。
また、昭和62年に施行された「総合保養地域整備法」に基づいて、平成3年2月現在、27道府県の基本構想が承認を受けているが、承認された基本構想による特定地域の中で施設の整備を特に促進することが適当な地域とされている重点整備地区は27地域合計で206か所、約56万haとなっており、この中には増設を含めて新たに約180か所のゴルフ場が計画されている。
一方、平成2年10月に地球環境保全に関する関係閣僚会議で決定された「地球温暖化防止行動計画」においては、国内においても二酸化炭素の吸収源である森林や都市等の緑の適切な維持及び拡大を図るため、森林の生態的な多様性の保全と持続可能な利用に配慮しつつ、その量、質等を把握して、森林・都市等の緑の保全整備を総合的、計画的に推進することが盛り込まれている。
このような観点から、計画的な緑の質的、量的な保全整備、公共財としての自然に対する国民一般のアクセスの確保と、余暇需要への対応、地域振興などの要請を共に満たしていく方策が必要となっている。
ウ 自然環境と暮らしとの関係の希薄化
多くの人々の生活活動が自然に依拠しないで行われるようになり、また、自然の方も縮小していったことから、自然環境と暮らしとの関係も希薄化してきた。
生活環境の都市化に伴って、子どもの自然体験に変化が生じてきている。平成2年版の青少年白書によれば、昭和29年当時には、小学生の遊びとして、「鬼ごっこ、縄跳び、野球、かくれんぼ、魚とり」など戸外で、多人数で、活動量の多い、自然を素材とした遊びが上位を占めていたのに対し、現在では、「テレビ、マンガ、趣味の雑誌や本、テレビゲーム」などが上位を占めている。花や草を摘んで遊んだことのない子どもが73%、蛙や虫を捕まえたことのない子どもが59%となっている。このような傾向は他の調査でもみられ、国立那須甲子少年自然の家が小中学生を対象に行った調査でも、子どもの自然とのふれあいが少ないという結果が出でいる。
人類学では、「自己家畜化」という言葉が使われる。ドイツの人類学者E・アイクシュテットが提唱した概念で、ヒトが文化を創りあげるが、できあがった文化がヒトに影響を与えるということで、それは野生生物を家畜化する過程と同じであるというのである。このような意味での家畜化は学問上の議論としてあるが、子どもがエアコンディショナーが行き届いた建物の中で生活し、自然との隔絶することによって、生態系の中のヒトが持っていた野性の喪失または退行といった面で家畜化現象が起こっているのではないかという危惧も一部に出ている。子どもたちがよく骨折するのは、跳び下りる、転ぶ、つまずく、といった身体状況の急変に対し、とっさの身構えができないことに原因があるというのである。
自然との関係の希薄化は、子どもたちの心のみならず、身体まで影響を及ぼしているおそれもあり、自然の回復・保全とともに、自然とのふれあいが子どもたちにとって、極めて重要となっている。
このような現象は、日本に限られたことではなく、米国やヨーロッパ諸国の大都市でも社会問題として取り上げられて久しい。児童心理学者の指摘を受けて、3か月余の長期の夏休みには、サマーキャンプと呼ばれる活動が盛んである。子どもたちだけを野外の自然豊かな環境に連れていき、数週間の集団生活をおくらせるが、単に自然との接触をさせることのみならず、集団の中で生活する技術を取得することを目的の一つとしており、昨年日本でも出てきた山村留学などとともに高度に発達した社会の注目すべき現象である。
(3) 人と自然のふれあい
ア 自然環境と人の経済社会活動との関係
人と自然のふれあいは、都市においても地方においても必要であり、都市内の身近な自然から大自然まで保全していかなければならない。しかし、都市地域においては、宅地や工場・事務所用地など経済社会活動のための土地利用が優先され、ふれあいの場としての自然の保全が特に必要となってきている。また、自然豊かな地域においても、余暇産業のための土地利用等によってふれあいの場としての自然が減少している。自然環境保全のため主として規制的手段が講じられてきたが、自然と人の経済社会活動との関係については、概ね次のような考え方があったように思われる。
? 自然環境保全の利益は全国民または都市住民にあるが、負担は地元に大きい。
? 経済社会活動は自然環境に破壊的に作用する。
? 自然環境の保全は地元の経済的発展に寄与しない。
現在、地球規模でも自然環境保全が必要になっている。自然環境保全に関する開発途上国との国際協力を推進していくに当たっては、自然環境保全と同時に開発途上国の人々の生活の向上をあわせて実現できる方策を講じなければ、結果的に自然破壊が進んでしまうものと考えられる。国際協力に当たっては、保全すべき地域の中に、多くの人々が生活していることを認識し、次のような考え方への転換が必要である。
? 自然環境を生かし、保全しながら地元民の生活向上を図る方法を探る。
? 自然環境の保全のために、利用者や国際社会もそれを支援する。自然環境の保全は、手間も費用もかかる大事業である。国際協力を進めていくに際して重要なことは、相手国の経済的、社会的、文化的背景を十分に理解することである。しかし、自然を共通の財産として保全していくに当たっての基本的考え方は、国内においても国外においても共通である。地球規模の自然環境の保全対策への認識は、国内の自然環境の保全対策にも生かされていかなければならない。
イ 生活の場における自然とのふれあい
(ア) 身近な自然の保全
現在、国民の4分の3は都市に住んでいる。これらの人々にとって最も身近な自然は、家の周りの緑である。庭があれば庭の、マンションで庭がなければベランダの緑が最も身近な自然であり、地方公共団体ではこのような緑を増やすために、苗木を配布する等様々な活動を行っている。
次に身近な自然は、近くにある雑木林や水辺である。大都市圏では、宅地等の都市的利用うが優先されがちであるが、日照や緑は都市での生活であって必要不可欠である。これらについては、土地政策でも十分配慮されることが重要である。地方公共団体や市民団体においても、これらの緑を保全する施設や活動が行われている(第3-3-1表)。このような動きはイギリスをはじめとする先進国の経験に学んだものが多いが、地域の特性に応じた独自のアイデアも数多く生まれている。
また、身近な自然を活用しての「自然観察の森」や「母と子の森」や、身近な生き物との接触を図るための「ふるさといきものふれあいの里」など、人々と自然とのふれあいを増進するためのプロジェクトを織り込んだ整備が進められている(第3-3-2表)。
(イ) 都市公園の整備
都市における緑とオープンスペースの確保のため、都市公園の整備が進められている。街の緑は、公園以外の緑も含めて総合的に評価されるべきものであるが、世界のいくつかの代表的な都市について一人当たりの都市公園の面積を比較してみると、東京23区は一極集中で人口が過密になっているという事情があるものの、わずかに2.5m
2
しかなく、ボン、ロンドン、ベルリン、パリなどの15分の1から5分の1程度という状況である(第3-3-6図)。
こうした状況を踏まえて、平成2年度で国費1,138億円(一般公共事業費2,896億円)をもって都市公園等の重点的整備に務めており、第1次都市公園等整備5箇年計画が策定される直前の昭和46年度末に約2万3,600haであった都市公園面積は63年度末には6万2,200haにまで増加した(第3-3-7図)。この間に、日比谷公園約2,400か所に相当する面積の都市公園等の整備されたことになる。しかし、全国平均でみても、一人当たりの公園面積は5,4m2にとどまっており、21世紀初頭までに概ね20m2を確保することを基本とし、2000年を目途に概ね10m2を確保することを目標に整備を図ることとしている。
一方、開発途上国においては、植民地時代に、その宗主国の手によって美しい都市公園が整備された例も多い。しかしながら、都市化の進展によって新たに拡大した都市地域は、十分な都市計画も作成されておらず、快適な生活環境確保のために公園をはじめとする都市基盤の整備が緊急の課題となっている。
(ウ) 都市の生態系環境への配慮
都市における人間活動と環境の関係を有機的な一つの系としてとらえ、都市における様々な活動や構造を生態系が有する自立・安定的・環境的なしくみに近づけるという視点に立って環境にやさしいものにしていこうという取組も始まっている。
平成元年度には、滋賀県と神戸市において、緑の空間の保全と創出、生き物の生息環境の整備、地域の水環境構造の保全等を柱とする「エコポリス計画」が策定された。また、山形県朝日町では、住民の生活と自然環境・社会環境の発展を歴史的に探求し、自然と文化遺産を現地において保存・育成し、展示することを通じて町全体を発展させていこうという「エコミュージアム構想」が進められている。このようにまちづくりにおいても、快適性や美しさに着目するだけでなく、都市の生態系の保全にも配慮した取組が各地で行われるなど、快適環境づくり施策の幅広い展開がみられている。
(4) 旅における自然とのふれあい
ア 旅における自然への欲求
自然公園等の豊かな自然が残れている場所へは、多くの都市に住む人が訪れる。都市に住む人にとって雄大な自然とのふれあいは旅であり、地方にとってはこれらの人々は旅人である。
国民の余暇における自然への欲求はますます強まっている。総理府の「国民生活に関する世論調査」(平成2年5月調査)により、今後の生活の力点に関する調査結果の推移をみると、昭和50年代の初めまでは住生活や食生活を重視していきたいとの回答が多いが、58年にはレジャー・余暇生活が第1位となり、現在では国民の3分の1がそうした意向をもっている。(第3-3-8図)。余暇をどのようにすごしたいかに関する調査をみてみると、「健康や体力の向上を目指す」が39.7%、「自然にふれる」」が34.9%となっている(第3-3-9図)。さらに「2〜3日滞在して余暇を自由に過ごせる場所を選ぶとしたらどのようなことを考えて選ぶか」については、「温泉などで休養・休息がとれること」が62.5%、「美しい風景が楽しめること」が59.2%、「水辺や緑陰など自然と接することができること」が55.5%で上位3つを占めている(第3-3-10図)。
また、近時、自然とのふれあい等を取り入れた修学旅行を企画するところがみられており、中学校を対象に「今後どのような体験的修学旅行を実施したいか」についての調査においても、社会科・自然等調査やスキー、登山、ハイキング、など自然とのふれあいにかかわるものへの希望が多くなっている(第3-3-11図)。しかし、実態をみてみると、自然とのふれあいにかかわるものは必ずしも多くはなく、希望と実態との間に差異がみられている。
自然と都市的施設との関係をみてみると、「余暇を過ごすには遊戯施設など都市的な設備や雰囲気が欲しい」という答えは8.6%であるのに対し、「余暇を過ごすには多少不便なところでも自然に囲まれた環境のところが好きだ」という答えが30.7%を占めている(第3-3-12図)。しかし、現実の旅行会社の商品である旅をみてみると、ただ、自然の中でゆったりと過ごすだけの旅は余りなく、自然に囲まれている快適なホテルや特別な食事などがセットになっているものが多い。
日本の旅の一つの特徴は、旅と宴会が結びついていることである。江戸時代、伊勢参りやお寺参りが旅の一つの型であり、旅人の間では神社仏閣への参拝とお清めの宴会とはいずれも旅の楽しみであった。旅と宴会、そして旅行に行ってきたことを示す土産と記念写真は、日本人のライフスタイルの中に織り込まれており、社内旅行のような団体旅行において特に顕著にみられる。しかしながら、家族づれ、夫婦単位の旅も増加し、遠く北海道までタンチョウを見に行くようなたびも増え、多様化してきている。旅人を受け入れる側においても、自然とのふれあいよりも豪華なホテルやゴルフ場など様々な都会的な設備の造成による自然破壊への誘惑に流されない工夫も必要である。自然とのふれあいの機械を増やすため、先進国、開発途上国を問わず、旅行の目的地に国立公園やサンクチュアリーを含めその国の自然や動物を楽しむことが期待される。
イ 自然とふれあう旅・エコツーリズム
自然豊かな地域では、都市生活の利便性をそのまま持ち込むのではなく、自然とのふれあいを楽しむように旅のスタイルが変わっていくことが、自然環境の保全と地元の発展との両方に寄与する。
余暇を美しい自然の中で過ごしたいという欲求は、世界の人々が持っている。自然が豊かな地域に、国境を越えて自然を満喫したい人、調査研究をしたい人などが訪れている。「エコツーリズム」と呼ばれる自然とふれあう旅は国立公園などをその活動の場として世界各地でみられる。
中米のコスタリカは、動植物相が多様であり、この豊かな動植物相を保護するため、国土の総面積の11.2%にあたる土地が国立公園や保護区として指定されている。ここに多くの動植学者が訪れ、彼らの出版物などを通じて、豊かな自然が世界に知られるようになり、近年では、科学者にとどまらず、幅広い観光客がこの国を訪れ、国立公園などでゆっくりと過ごすという旅行形態が多くなてきた。1985年のコスタリカ観光局の調査によれば、観光地としてコスタリカを選んだ理由として、「自然の美しさ」が約75%、「文化・政治環境」が66%、「動植物相」が36%となっており、3分の1が美しい自然とふれあうために訪れている。
「エコツーリズム」は「野生生物とそれを取り巻く環境を損なうこと無く、自然の領域に足を踏み入れること」といわれているが、このような旅行形態は、ケニアのアンポセリ国立公園、オーストラリアのカンガルー島国立公園、ルワンダのポルカン国立公園など他の国でもみられる。エコツーリズムは自然の中に勝手に入っていくことではなく、野生生物とそれを取り巻く環境を損なわないための措置や、自然を楽しめるようにするための措置が講じられており、これらの国立公園では、有能なガイドの養成、野生生物の保護、フェンスなどの施設整備などに力を入れている。
このような、エコツーリズムが生まれる背景には、訪れる人々が長期の休暇をつれる環境にある等の理由があるが、基本的には、これらの人々が国内においても、国立公園に自然とのふれあいの場として接し、また国立公園がそのような要望に応えられるように整備されているということがあり、それが、各国に拡大していると考えることができる。
(5) 自然との触れ合いの場としての国立公園の整備
ア 国立公園の国際比較
国立公園は、主要なエコツーリズムのフィールドである。国立公園は、1872年米国のイエローストーン国立公園が設けられたのが世界最初である。我が国では、昭和6年に制定された「国立公園法」(現在の「自然公園法」)に基づいて、9年に阿寒、大雪山、日光、中部山岳、阿蘇等の8国立公園が指定された。
国立公園を含む自然公園の制度は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健・休養・自然保護教育を進める制度である。昭和61年10月の総理府「自然保護に関する世論調査」により国民の自然公園に対する意識をみると、自然公園の制度を知らない人が3割近くあり、また、自然公園へでかける目的についても、「風景を楽しむため」が45.7%、「登山、ハイキング、キャンプ、海水浴、森林浴などを楽しむため」32.3%「ドライブを楽しむため」が22.8%と上位を占め、自然公園とは優れた風景地であるとの漠然とした理解した得られていないことがうかがわれる(第3-3-13図)。
国立公園や野生動物保護区は、アウトドア思考をも持つ米国やワンダーフォーゲル発祥の地ドイツなどにおいては、そこを訊ねる人々にある種の野生動物が絶滅の危機にあることを認識させ、それが自然保護運動の強化に役立つとともに、一人一人のライフスタイルを変えることにも多大な貢献をなしたといわれている。今後、日本人の生活に日本の国立公園がプラスに作用するな政策が検討されねばならない。
我が国の自然公園を、欧米の自然公園と比較すると、国民一人当たりの国立公園面積は、カナダは約7,100m
2
、米国は800m
2
、英国は約240m
2
であるのに対して、日本は約160m
2
となっている。国土の広さとの関係をみると、カナダは2%、米国は約2%、英国は約6%であるのに対し、日本は約5%となっている。国立公園の管理運営に携わる職員数及び管理運営費等については英国では管理を主にカウンティ(郡)が行っていること、カナダでは季節によって管理員数変動があるため人・年での集計が行われていること、カナダ、米国の国立公園の一部は有料となっていることなど各国の事情により単純な比較はできないが、管理員数では、国民10万人当たりカナダは約16人、米国は約4人、英国は約1.1人に対し、日本は約0.1人となっている。また、職員一人当たりの担当面積でみると、カナダは約4,500ha、米国は約2,000ha、英国は約2,000haに対し、日本は約1万8,000haである。また、国民一人当たりの管理費用は、カナダは約2,000円、米国は約800円に対し、日本は約30円となっている(第3-3-3表)。
イ 自然公園の整備・公園サービスの充実
豊かな自然を損なうことなく、自然とのふれあいを行うためには、その地域の自然環境についての調査研究とそれに基づく保全、訪れる人々に対する解説の充実、保全と自然解説などを効果的に行える施設の整備などが必要である。
まず、自然とのふれあいに重要な役割を果たす人々についてみると、国立公園の現地管理業務に当たる環境庁職員である国立公園管理(レンジャー)が全国11の管理事務所にいるほか、無償で公園の美化清掃・利用指導・解説等に従事する民間のボランティア、主として夏期等の利用者が集中する時期に報酬を得て公園の美化清掃・利用指導・解説等に従事するナチュラリスト(季節レンジャー)、利用者の案内・引率・技術指導等を報酬を得て業として行うガイドなどがいる。現在、国立公園への来訪者は約4億人であり、公園利用者に対し自然とのふれあいに関するサービスを提供する国立公園管理官は114人、管理事務所長委のパークボランティアが約1,000人、環境庁自然保護局長委嘱の自然公園指導員約2,000人、管理事務所が雇用するナチュラリストが約4,000人・日などとなっている(第3-3-4表)。
次に公園管理の形態については、我が国の国立公園は、米国やカナダと異なって国の土地の上に国立公園を設置しているわけではなく、土地所有形態を問わない地域性の国立公園制度であるが、国有地や公有地が国立公園面積の大部分を占めている所では、国民からみれば、国または地方公共団体が、土地を所有し、国立公園サービスを提供しているのであって、米国やカナダと同じ条件にみえる(第3-3-14図)。国立公園の大部分を占める森林は、環境保全の観点から確保する事が重要な資源であり、特に自然保護の観点から保全することが必要な森林は、自然にふれあう場所として、国の各機関、地方公共団体等が一体となって、保全し、活用していくことが重要である。
また、国における地方の豊かな自然の保全・利用を進めるための自然公園の整備費は、約35億円前後で推移している(第3-3-15図)。豊かな自然とのふれあいの大切さを考えると、身近な自然と豊かな自然、さらには里山などの自然を等しく保全していく必要がある。
これらの施策の充実を通じて、人々は自然とふれあい、自然を大切にする気持ちを持つようになることが、自然環境保全の基本である。「人類共有の自然」という認識があれば、自分だけが独占するために野に咲く貴重な花をつみとることがなくなり、その美しさが多くの人に共有されることとなる。
(6) 自然体験とインタープリテーション
ア 自然体験を通じた自然保護教育の重要性
自然環境と暮らしの関係の希薄化により子どもたちに様々な悪影響があるのではないかという危惧がある反面、これに対応し様々な自然とのふれあいを増加させる試みがなされていることは既に述べた。しかしながら、都市部において自然と切り離された人々、特に子どもたちにおいては旅行その他の機会に自然とのふれあいの場が提供されても、自然との遊び方がわからないという現象が生じている。
野草、昆虫、木材、果実等の自然の恵みを採取し、それを食べたり、遊具としたりする体験は、人間活動への自然の恩恵と自然への親しみを感受する最も原初的体験であり、こうした体験の上に次のレベルでの自然保護教育や環境教育が根付いていく。また、より身近な自然を体験し、自然への感覚が磨かれることにより、厳格に保護されるべき優れた自然にふれた感動も倍加するものである。
環境庁が概ね5年ごとに実施している自然環境保全基礎調査いわゆる緑の国勢調査の一貫として全国から一般国民のボランティア参加を得て行っている「身近な生きもの調査」は、日常生活の中で観察しうる動植物の分布をほぼ一年かけて調査し、全国の都市化や外来種の侵入による自然環境の変化を把握しようとするものである。前回は昭和59年度に10万人余りの参加を得て実施されたが、第2回目は平成2年度に前回をはるかに上回る参加者を得て実施され、現在、調査結果の集計が行われている。このように、国民一人一人が自ら動植物を観察し記録するという意識をもって身の回りの自然と出会い、歓びを感じることは、年代を超えた自然保護教育の基本である。
今日、こうした自然体験を取り戻すためには、身近な自然から原生的な自然まで、自然のレベルに応じたフィールドの整備及び機会の創出が緊要であるとともに、既に親、教師等にもそうした体験が希薄化している状況から、自然と子どもの間をつなぐ指導者の存在が必要となってきている。
イ 国立公園等におけるインタープリテーション
各国においては、国立公園等も重要な自然体験のフィールドとして位置付けられている。米国の国立公園等においては、我が国でいう「自然解説」より広く、遊びやレクリエーション的側面も持つ利用指導・普及活動を「インタープリテーション」と称し、その活動に当たる者を「インタープリター」と呼んでいる。米国では、国立公園の利用そのものが、こうしたサービスを受ける事と密接に関係している。具体的には、展示物、道端の掲示、視聴覚プログラム、出版物等様々なメディアにより行われているが、いずれの場合も単なる情報提供にとどまったり、逆に過度の宣伝活動にならないよう、各分野の専門家を擁する「ハーパーズ・フェリー・センター」という国立公園局内の専門機関により入念に企画され、編集されたものとなっている。さらに、各公園においては、ビジターセンターや博物館、レンジャー駐在所などで案内施設を整備するとともに、インタープリターの確保、研修等を実施することとされている。日本に類似した国立公園制度を有する英国においてもレンジャーによる国民とのコミュニケーションが重視されており、レンジャーの資質を高めるための研修施設が設置されている。
ウ インタープリテーション推進のための条件整備
我が国においては、こうしたインタープリテーションのための人材も著しく不足している。しかし、自然志向の高まりと環境保全意識の高揚のなかで、このような活動に従事する意欲のある若者や経験豊かな高齢者が増加し、一方で需要サイドの様々な自然とのふれあいのためのフィールドの整備も順次進んでいることから、今後、国、地方団体、民間の連携により人材の充実を図る余地は大きいと思われる。
このためには、人材の需要と供給を結びつける派遣システムの構築、質の高いインタープリテーションを確保するための研修の充実等が必要である。このようなことから、環境教育の一環として現場を持つ実践者や研究者が中心となって、様々な問題点をフォーラムの形で数年前から討議してきており、平成2年度には学問的追求を深めるために日本環境教育学会が設立された。また、平成2年度に国立公園におけるパークボランティア活動を支援する等のため「上高地公園活動ステーション」が民間団体により開設された。こうした試みを契機として、これらの活動、施策を効率的かつ円滑に実施するとともに、永続的なものとするための全国的な組織化、制度化を検討する必要がある。
このようにして、全国に多くのインタープリター配置することにより、国民が、国立公園等に含まれる原生的な自然から都市周辺の身近な自然まで、自然レベルに応じた様々な自然体験を通じて、希薄化した人と自然とのかかわりを回復し、ひいては地球生態系の中にある人類の生活に対する認識を新たにすることが期待される。