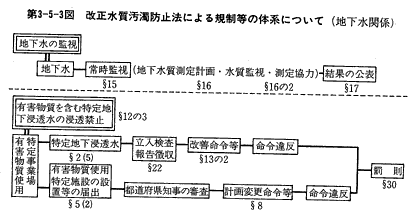
2 地下水汚染の対策
地下水は一度汚染されるとその回復が容易ではないので、汚染が進行しないうちに予防策を講じていかなければならない。このため、環境庁ではトリクロロエチレン等3物質について、昭和59年8月以降、これらの物質を取り扱う工場・事業場からの排出抑制に関し暫定指導指針を設定して指導を行ってきた。また、厚生省及び通商産業省においては関係業界に対する指導を、さらに、建設省においても指導及び地下水の調査を行っている。
しかしながら、その後の調査結果をみても、トリクロロエチレン等による地下水汚染が依然として各地でみられること等から、地下水質保全対策のあり方等について中央公害対策審議会に諮問し、平成元年2月、答申が取りまとめられた。
この答申を踏まえ、有害物質による地下水汚染の未然防止を図ること等を目的とした水質汚濁防止法の一部を改正する法律案を第114国会に提出した。同法律案は、全会一致で原案どおり可決成立し、平成元年6月28日公布され、同年10月1日から施行されている。
改正法により、有害物質を含む水の地下への浸透の禁止及び都道府県知事による施設の改善命令等の規定の整備、都道府県知事の地下水の水質の常時監視等の措置がとられた(第3-5-3図)。
環境庁では、改正法の施行に伴い、都道府県知事が作成する地下水の水質測定計画に基づく水質調査に要する経費について、平成元年度から助成を行っている。
また、トリクロロエチレン等以外の化学物質による地下水汚染対策として、環境庁では、四塩化炭素について、その汚染の未然防止を図るため、平成元年4月、暫定指導指針を設定し、工場・事業場からの排出抑制の指導を行ってきており、さらに、ジクロロエチレンについては、元年12月、各都道府県・政令市に対し地下水汚染の実態把握に努めること等を要請した。
地下水汚染問題については、改正水質汚濁防止法の着実な施行を図ることはもとより、今後さらに、地下における物質の挙動の解明等の検討が必要であり、環境庁において地下水の汚染機構の解明のための調査を行うとともに、地下水質の管理のあり方についてもさらに検討を進めている。