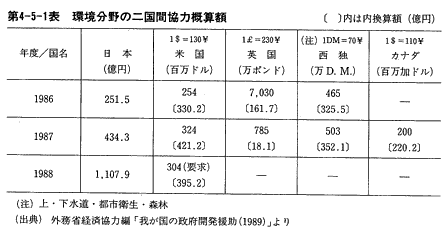
1 政府ベースの環境協力−政府開発援助(ODA)を中心に
(1) 我が国のODAと環境問題
我が国の開発途上国に対する経済協力には、大別して、政府開発援助(ODA)、その他の政府資金協力(OOF)及び民間ベース協力(PF)の3種類あるが、ここでは二国間の有償・無償の資金協力及び技術協力を含むODAを中心に、その現状をみてみよう。
我が国のODAは、経済力と国際的地位の高まりを反映して、ここ十数年来着実かつ急速に伸びてきたが、1988年の91億3,400万ドル(支出純額ベース)と、アメリカに次いで世界第二位であった。また、我が国は既にアジア、アフリカを中心とした29の開発途上国において、最大の援助供与国となっている。対GNP比率でみると1988年で0.32%とOECDの開発援助委員会(DAC)加盟国平均の0.36%を下回っているが、他の主要国の対GNP比率が概ね横ばいで推移している中で、我が国の対GNP比率は着実に改善している。
政府はODAに関する第4次中期目標を策定し、1988〜92年の5年間のODA実績総額をその前の5年間の実績の倍額以上、すなわち500億ドル以上とするよう努めている。
第4次中期目標においては、この他今後ともODAの量的拡充とともにその質的改善を図ること、援助実施体制の充実を図ること、効果的・効率的運営に努めること、民間活動との連携強化を図ること等が示されている。
環境問題との関連では、環境保全分野への協力を量、質ともに拡充・強化していくこと、援助に当たっては開発途上国の発展の基盤である環境への配慮を徹底していくこと、「要請主義」を弾力的に運用し、開発途上国に対し環境保全の重要性について啓発するとともに、開発途上国のニーズを十分踏まえた協力プロジェクトの立案を支援するため、途上国への積極的働きかけを行うこと等が、一昨年の当日書において提唱されたところである。
(2) 環境協力の現状
それでは、我が国のODAにおける環境協力の現状はどうなっているか、次にみてみよう。
我が国の環境分野における二国間ODAの実績は、第4-5-1表に見るように、1987年年度において約434億円、1988年度において約1,108億円に達した。また、ODA供与総額に占める割合をみると1988年度では、無償資金協力については債務救済を除く一般無償資金協力の約19%、有償資金協力については全プロジェクト借款の約8%となっている。何が「環境援助」かについての定義づけが統一されていないので、単純に国際比較することは出来ないが、少なくとも金額においては欧米の主要援助国と同等か、それ以上の環境援助を行っていると言えよう。
さらに、政府は昨年7月のアルシュ・サミットの機会に、今後3年間に環境分野に対する二国間及び多国間援助を3,000億円(1ドル=133円として約22.5億ドル)程度を目途として拡充・強化に努めることとし、地球環境問題への一層の貢献を図る旨表明し、開発途上国自身が環境問題と取り組む努力を積極的に支援していく方針を明確にした。1986〜88年度の3年間の平均で600億円程度であったので、今後年平均1,000億円というのは相当大幅な増額になり、内容も格段に充実されることが期待される。
さて、その内容であるが、これまで我が国の環境分野における開発援助は、途上国においては身近な環境問題への対応が緊急の課題であることを反映して、上・下水道や廃棄物処理施設などのハードな施設整備に重点がおかれてきた傾向があるが、加えて最近では、森林保全・造成、防災、公害防止などの分野や途上国の人材育成、技術移転及び開発、研究協力等を目的とした技術協力にも力が注がれるようになってきている(第4-5-2表)。特に世界的な関心を集めている熱帯林の保全に関しては、先の「地球環境保全に関する東京会議」においても指摘されているように、計画的な森林管理、大規模な森林の再生への協力に加えて、生態系の保全、種の多様性の維持の観点からの協力推進の必要性が高まっている。
また、昨年の環境週間前後に東京で開催された「オゾン層保護アジア太平洋地域セミナー」や「アジア地域環境大臣シンポジウム」を機に、アセアン地域の環境専門家会議に我が国も専門家を派遣して援助問題について話し合ったり、援助案件発掘のための調査団を派遣するなど、被援助国との政策対話も始まっている。
(3) 開発援助と環境配慮
地球環境保全のための開発援助を推進することと併せて、開発援助政策そのものや援助や事業の選択・実施が地球環境保全に十分配慮したものとなる必要がある。我が国における政府援助実施機関である国際協力事業団(JICA)においては、開発援助に際しての環境アセスメントに関するOECD勧告や1988年以来検討を行ってきた「環境援助研究会」の報告を受けて、現在、各分野別の環境配慮ガイドラインを策定中であるなど、環境配慮の実施体制の強化を図っている。
円借款を担当する海外経済協力基金(OECF)においても環境専門家を配置し、「環境問題検討委員会」を設置するとともに、昨年11月には、環境配慮のためのガイドラインを公表した。その他、日本輸出入銀行においても、融資の形態に応じた環境配慮の推進に向けて準備が行われている。
(4) 開発途上国のニーズに対する国際的対応
開発途上国においても地球環境保全に積極的に取り組んでいくことが重要であり、多国間・二国間の開発援助等の仕組みを通じて、こうした途上国の努力への支援・協力が行われている。また、地球環境保全のための新たな国際協力の推進方策については、現在、国際的にも様々な角度から検討が行われているが、これらの国際的な検討作業には我が国も積極的に参加していく必要があろう。
例えば、既に世界的な対策推進のための枠組み条約が作られているオゾン層の保護については、1989年5月のモントリオール議定書締約国会議の決議に基づき特別の作業部会が設けられ、フロン代替技術等の移転促進のための方策等が検討されている。
また、同年11月の大気汚染及び気候変動に関するノールトヴェイク宣言は、「資金供給の仕組みの必要性についてはクリアリングハウス・メカニズム、新たな国際基金の可能性及びそれらの既存の多国間・二国間の資金供給メカニズムとの関係を含め、更に検討がなされるべきである」旨述べるとともに、開発途上国への国際的な資金供給は、当面、フロンの段階的廃止、エネルギーの効率的な利用、非化石燃料の利用の拡大と温室効果ガスの排出の少ないエネルギー源への転換、再生可能なエネルギー源利用の拡大、熱帯林行動計画、砂漠化防止計画、国際熱帯木材機関その他の国際機関等を通じた森林保全と森林管理の改善、研究及びモニタリングの推進等に向けられるよう勧告している。