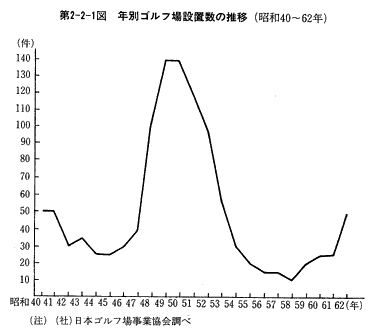
4 ゴルフ場と自然環境等の保全
近年、ゴルフ場の新設等が環境保全上問題を引き起こすのではないかとの懸念が各方面から出されている。我が国のゴルフ場は、昭和63年4月現在で総数約1,600か所、総面積は15万2千haで国土面積の0.4%(都市公園の総面積の約2.8倍)を占める。新設されるゴルフ場は、48年以降急増し50年をピークに急減したが、最近また増加の傾向がみられる(第2-2-1図)。その背景には、国民の間にゴルフに対する根強い需要があることがあげられる。
ゴルフ場の建設は、広い面積にわたる木竹の伐採、土地の形状の変更を伴い、野生生物を含めた生態系、景観等自然環境への影響が大きいこと等から、国立、国定公園においては、48年にゴルフ場を公園事業の対象となる施設から削除し、翌年からは特別地域内でのゴルフコースの造成を目的とした土地の形状変更は許可しないこととされている。また、森林の開発においては、森林法に基づいて規制しているところであるが、さらに、47都道府県のうち32都府県においては、ゴルフ場の造成に関する指導要綱等を整備し、森林確保率等に関して審査、指導が行われている。40年代後半には、多くの都道府県でゴルフ場の抑制、凍結が行われていたが、50年代末、緩和を行うところが相次いだ。最近は、兵庫県、長野県のように規制の強化を図っているところもある。
一方、ゴルフ場の管理においては、良質な芝生を維持するために、農薬、化学肥料の使用が一般化し、近年、農薬による周辺の水質への影響について関心が高まってきている。このような中で、平成元年11月、北海道の養魚場のヤマメ等が上流のゴルフ場で不適正に散布された農薬により被害を受けるという事故が起きた。ゴルフ場で使用される農薬問題の重要性に鑑み、ゴルフ場周辺の水質について実態把握を行うとともに、更に一層の農薬の適正使用を図るため、行政機関等による指導の推進が必要である。