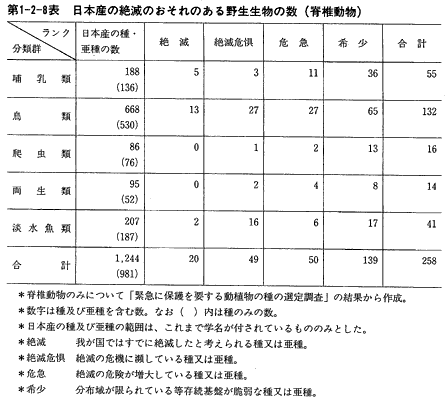
2 野生生物の現状
(1) 我が国の生物相の特徴
我が国は自然環境の変化に富み、これを反映して動植物相も多様である。
我が国に生息する野生生物の種の数は、哺乳類136、鳥類530、爬虫類76、両生類52、淡水魚類187、昆虫類約29,000、種子植物及びシダ植物5,565となっている(これまで学名が付けられているものに限る)。このような我が国の動植物相は、大陸との連続と分断という歴史的過程を通じて形成されたものであり、同じ緯度にある他の地域と比較して種類が多く、また多くの固有種を含んでいることが特徴である。
一方、狭小な国土に多くの人口を有する我が国では、高密度の土地利用が行われており、野性生物の生育・生息環境は人間活動により大きな影響を受けている。開発や産業活動に伴い、かつては身近にみられた野性生物の多くが姿を消しつつあり、絶滅の危機に瀕しているものも少なくない。
(2) 絶滅のおそれのある種の現状
日本列島において生き続けてきた野生生物の種は、その遺伝子に長い進化の歴史を内蔵しており、貴重な情報源であるとともに、生態系の構成要素として、物質循環のバランスを維持したり環境変化に対応し得る多様性を確保する上で不可欠な役割を果たしている。種は、一旦失われると人間の手で再び作り出すことは不可能である。野生生物への圧迫が強まっている今日、種の絶滅を防ぐことが緊急の課題となっている。
このため、環境庁では、昭和61年度から3か年をかけて日本産の絶滅のおそれのある動植物の種を選定するために「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査」を実施した。
調査の結果を脊椎動物についてみると、我が国においてすでに絶滅したと考えられる動物の種又は亜種の数は20、また、絶滅のおそれのある種・亜種の数は238、また、脊椎動物以外の動物を含めると絶滅のおそれのある種・亜種の数は合わせて600を超えることが明らかになった(第1-2-8表)。
主な分類群について、絶滅に瀕していたり絶滅の危険が増大している種を見ると、哺乳類ではニホンカワウソ、イリオモテヤマネコ、ケナガネズミ等が、鳥類ではアホウドリ、イヌワシ、ノグチゲラ、シマフクロウ等が、両生類・爬虫類ではホクリクサンショウウオ、セマルハコガメ等が、淡水魚類ではミヤコタナゴ、ムサシトミヨ、イトウ等が選定されている。
これら、今回の調査で絶滅のおそれがあるとされた種・亜種の中には、分布の限られた種が多く含まれている。もともと分布が狭い範囲に限られた固有種や特産種は、乱獲や生息環境の変化、外来種の侵入等の生息条件の変化によって容易に絶滅に追いやられやすい性格を有しているが、今回の調査で選定された種・亜種の中には、特に南西諸島、小笠原、対馬などに生息する種・亜種が多いことが目立っており、これら地域における野生生物の生息条件が悪化していることを示している。
一方、今回の選定種の中にはかつては各地で普通に見られたが、乱獲や生息環境の悪化に伴い、急速に姿を消していったものも含まれている。
ニホンカワウソは江戸時代には、北海道、本州、四国、九州の海岸や河川に広く生息したことが史料にも記されている。しかし、毛皮を目的とした乱獲によりすでに昭和初期には生息数が激減しており、さらに戦後における河川や海岸及びその周辺環境の改変、河川の汚染と餌となる魚類の減少等により、わずかに残存していた瀬戸内海や宇和海でも姿を消したと見られる。現在、高知県の南西部にごく少数が生息するのみといわれており、絶滅の危機に瀕している。
コウノトリやトキもかつて本州の各地で広く生息していた。平野部の水田や沼沢地で魚類、カエル等の小動物を捕食し、付近の丘陵の大木に営巣していたが、乱獲や農薬などによる汚染、生息環境の改変によりいずれも激減し、現在、トキは日本産のものは2羽を数えるのみ、コウノトリは大陸産のものがときどき飛来するのみとなっている。
かつては関東地方で広く見られた淡水魚のミヤコタナゴは、湧水のある天然の小水路を生息環境としている。小川の改修等によりこのような生息環境は急激に減少し、現在ごくわずかの生息地を残すのみとなっている。
以上のようなかつて国内に広く生息していた野生生物の急速な衰退には、過去の乱獲も寄与しているが、主要な原因は全国的な開発の進行とこれに伴う森林の伐採、原野・湿地の消滅、河川や小川、海岸等の改変、水質の悪化等とみられる。これらの環境の変化は野生生物の営巣地や産卵地の消滅、行動圏の縮小・分断、餌となる小動物の減少等をもたらし、全国的な種の衰退が進行したものと考えられる。
(3) 渡り鳥の現状
我が国は渡り鳥の飛来ルートの上に位置しており、我が国で観察される鳥類の約75%は渡り鳥である。特に冬鳥のガン・カモ・ハクチョウ類については、代表的な渡り鳥であるとともに狩猟の対象となっている種も含まれているため、環境庁が全国の都道府県に呼び掛け、毎年1月中旬に一斉調査を実施してきている。
平成元年1月の調査によると、ガン・カモ・ハクチョウ類観察数は全国合計で171万羽であり、調査が開始された昭和45年の103万羽から基本的には増加傾向にある。特にハクチョウ類は45年から59年まで1万羽から2万羽で推移していたが平成元年には4万羽を越え、また、ガン類は45年から61年まで5千羽から1万羽で推移していたが平成元年には2万羽を越えており、いずれも近年観察数が急増している。