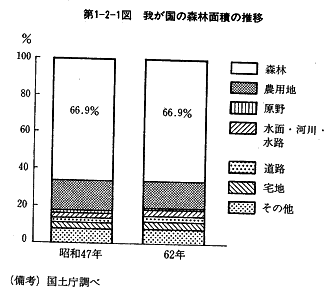
1 自然環境の現状
(1) 自然環境
南北約3,000kmに及ぶ日本列島は、数多くの火山、起伏の大きな山地、変化に富んだ海岸線等複雑な地形を持ち、気候的には亜寒帯から亜熱帯まで広がり、四季を通じて降水量も豊富である。このような気候風土から、我が国は豊かで多様な植生とそこを主な生活基盤とする各種の野生動物、多様な植生と複雑な地形がおりなす優れた景観がみられるなど、豊かな自然に恵まれている。
しかし、これらの自然は人間活動の長い歴史の中で各種の影響を受け、国土の自然環境は自然性の高い地域から低い地域まで、様々な状態となっており完全に自然の状態を保っているものは極めて少なくなっている。
また、近年の自然改変の広域化、大規模化、あるいは逆に、かつての薪炭材やカヤの採取のような自然利用の衰退による植生の変化等に伴い、我が国の自然環境は著しく変ぼうしつつある。
このように急速に変ぼうしていく自然環境を適切に保全するためには、まず第一に自然環境の現況とその変化の方向を的確に把握することが必要である。
このため、自然環境保全基礎調査(「緑の国勢調査」)では、陸域(植物、動物、地形、地質)、陸水域(河川、湖沼)及び海岸域(海岸線や干潟、サンゴ礁などの浅海域の生態系)について、自然環境に関する情報を体系的かつ時系列的に収集、蓄積しており、これまで昭和48年度の第1回調査以降、概ね5年ごとに3回の調査を終え、昭和63年度より、第4回調査を実施しているところである。
ここでは、これまでの調査結果を中心にして、全国の緑や自然景観の状況をみてみる。
ア 全国の植生の状況
我が国の湿潤な気候・風土は、高山の岩石地等の一部の特殊な環境を除けば、全国にわたり、豊かな森林を育む。その意味で、森林がわが国の緑の主体をなすと言える。
森林は木材生産のほか、国土保全、自然環境の保全等の多面的な機能を有しており、第2回(昭和54年度)・第3回(58〜62年度)調査における「植生調査」によれば、森林全体は国土の67.5%と世界的にみても高い割合を保っている。また、国土全体に占める森林の割合は、近年横ばいの状況が続いている(第1-2-1図)。しかし、その内訳をみると、スギ、ヒノキ、カラマツなどの植林地(国土の24.7%)や薪炭材採取などの人為影響を受けて成立した二次林(国土の24.6%)が多くを占めており、自然林は国土の18.2%にとどまっている。わが国の緑の大きな特徴の一つとして、広範な気候帯や複雑な土地条件に応じ、多様なタイプの森林が生育することがあげられる。気候帯毎に森林の状況をみると、寒冷で標高の高い高山帯や亜高山帯では、自然林や自然草原が多くの割合を占めるが、東北日本を中心に広がる冷温帯では、ブナ林などの落葉広葉樹林を主体とする自然林の割合は29.6%となり植林地や二次林の割合が多くなっている冷温帯での自然林の主体はブナ林などの落葉広葉樹林である。さらに、西南日本を中心に広がる暖温帯では森林全体の割合は、58.8%であるが、自然林の残存割合は2.3%と極めて低く、傾斜地、離島などの人間が利用しずらい場所や社寺林などにわずかに残存するに過ぎない。この自然林の主体はシイ、カシ、タブなどの照葉樹林である。また、南西諸島や小笠原諸島は亜熱帯域となり、亜熱帯性のヤブツバキクラス林やマングローブ林などがみられるが、この地域では自然林の割合が47.1%と高い一方、森林全体の割合は50.1%と低いことが特徴である(第1-2-2図)。
わが国の多様な森林は、また多種多様な動物相を育む。生息する動物相は、各々の森林のタイプや規模により異なっており、多様な動物相の安定的な維持の観点からも、それらが生息環境として必要とする様々なタイプの森林の確保が必要である(第1-2-3図)。
その中で、国土の24.6%と多くの割合を占めている二次林は、人間活動の影響を受けて成立した森林であるが、核となる自然林とともに良好な動物生息環境を形成するものや、それ自体に特有の動植物種を育むものもあるなど生物種の多様性を維持する上で、様々なタイプの自然林とともにその適切な保全が必要と言えよう。
次に、全国の緑の保全状況を自然公園及び国指定の自然環境保全地域を合わせた指定割合でみてみると、寒帯・高山帯自然植生(89.0%)、亜寒帯・亜高山帯自然植生(46.2%)の順に高く、自然植生では最も多くの割合を占めるブナクラス域自然植生に対する指定割合は、21.3%と最も低い割合となっている(第1-2-4図)。
イ 巨樹・巨木林の状況
第4回自然環境保全基礎調査(昭和63年度〜)では、地域のシンボルであり、豊かな自然の代表ともいえる巨樹・巨木林について、はじめて全国的なレベルで調査を行った。その概要は以下のとおりである(第1-2-5表)。
(1) 幹周3m以上の木として報告された巨木は総数61,441本であり、調査が不可能だった山間部のものを加味すると総巨木数は10万本近くなることが予想される。
(2) 樹種にかかわらず幹周の大きさを比較してみると、ベスト10のうち9本をクスノキが占めた。全国一の巨木は鹿児島県蒲生町のクスノキである。
(3) 各都道府県のベスト3をみると、出現する樹種は比較的限られ、クスノキ、スギ、ケヤキ、イチョウが多い。地域的には、クスノキが近畿以南、ケヤキ、イチョウは東日本に集中し、スギは全国広範囲に広がっている。
(4) 我が国の主な高木である樹種19種に関し、樹種別の代表的巨木をベスト10まで抽出してその立地環境、保護状況を分析してみると、イチョウ、カヤ、ケヤキ、クスノキ等、身近にあって相対的に大きな木は保護指定がいきとどき、信仰の対象だったり、故事、伝承のいわれとなっているものも多いが、相対的にはそれほど大きくならないムクノキ、タブ、ハルニレや、山地に多いブナ、ミズナラなどは保護の手がいきとどいていないものも多い。
(5) 大都市地域における巨木の状況をみるため、政令指定都市毎に測定巨木総数を比較してみると、東京23区1,257本が最も多く、京都市228本、札幌市123本がついでいる。東京には、皇居、浜離宮、新宿御苑など歴史のある大面積の緑地が多いことから、巨木も相対的に多いものと考えられる。
この調査を契機として、「巨木を守ろう全国フォーラム」の開催等全国で巨木の保護や活用に関する様々な取組が行われている。
ウ 自然景観の状況
自然景観とは、「地形、地質、植生および野生生物といった環境要素が統合され、人間の目に映ずるもの」であり、自然環境保全上重要な要素である。このため第3回自然環境保全基礎調査から新たに自然景観に関する全国レベルの調査を行った。
調査は、自然景観の基盤をなす地形等を10類型80種類に分類し、それぞれ視覚に訴える特徴的なものであること等の選定基準を設けて、これに該当するものをすべてリストアップした。
これによると抽出された我が国の自然景観資源の数は15,468件、そのうち陸景6,668件、水景8,800件である。
景観の種類別分布状況をみると、最も多いのは滝(2,488)であり、次いで火山(1,158)、峡谷・渓谷(996)、非火山性孤峰(993)、湖沼(872)、海食崖(734)、砂浜・礫浜(632)の順で、これら7種類で全調査資源のほぼ半数を占めている。
また類型別の地方別分布状況をみると、火山景観は東北地方に最も多く、山地景観は中部地方、東北地方に特に多い。また、河川景観は中部地方、東北地方に特に多く、山地景観と類似の分布傾向を示す。湖沼景観は東北地方に最も多く、海岸景観は海岸線延長の長い九州地方で多い。(第1-2-6表)。
見られかたで分類すると、近景から望む景観資源が44%、つづいて中景が34%、遠景が22%である。視点の種別では、不特定の地点からの資源が32%、歩道からのものが26%である。一般に希少性が高く規模が小さいほど、特定の視点に限定される傾向がある。
景観資源の広域的な利用形態としては、リクレーション利用が37%、一般観光が35%、自然学習・自然探勝が28%である。
地域との係わりでは、人々の憩い・行楽の場としての利用が40%とやや多く、地域のシンボルとしての利用が37%、学習の場としての利用が23%となっている。間欠泉、天然橋・岩門・石門、潮吹穴など希少性が高いもの、火山、非火山性孤峰、滝などのような印象の強い景観などはシンボルとしての比率が高い。一方、鍾乳洞は学習の場としての利用が多い。
全景観資源の58%は、何等かの保護制度下にあり、各領域の全部または一部が国立公園内にある資源は23%、国定公園内にある資源は15%である。とりわけ火山地域や高山地域などは国立公園に指定されていることが多い。一方、河成段丘および海成段丘のような日常的な景観や石灰岩景観は保護制度下にないものが多い。
河川景観、海岸景観など標高が低く人々の生活空間の近くに在る景観資源を中心に、全景観資源の3分の2近くは人間活動により何等かの影響を受けている。特に、地表面の土石が幾何学模様の配列を形成する「構造土」などのように、その自然景観としての価値が十分に理解されていない資源は、各種の人為により影響を受けている例が多い。
エ 身近な自然環境の状況
我が国を代表する優れた自然の保全ばかりでなく、身近な自然を良好な状況に保っていくことも重要な課題である。
このため、首都圏を例にとって自然環境の状況をみてみる。
首都圏は、明治時代以降の近代的な工業化、都市化の進展、さらに戦後の復興、高度成長期を通じての工業化、都市化の一層の推進に伴い、都市的な土地利用への転換が進んでいる。
東京湾では、その2割に及ぶ埋め立てが行われ、海岸線は湾全体で82%、内湾では95%が人工海岸となっている。この結果、かつては有明海に次いで2番目に大きな面積を有していた干潟の89%が失われた。しかしながら、東京湾に残された江戸川河口部、小櫃川河口部等の数少ない干潟は、底生生物、魚類、鳥類の豊かな生育環境となっており、我が国最大級の渡り鳥飛来地になっているほか、潮干狩りやバードウォッチングなど人々が自然とふれあうことができる場所としても大きな価値を有している。
首都圏での土地利用の状況をみると、戦争直後から高度経済成長政策の始まった昭和35年頃までは、急速な市街地の拡大が起った東京都や神奈川県で都市的な土地利用への転換が進み、農地や樹林地が高い比率で被覆地に変わった。その後は、東京都では、被覆地への転用は減少しているものの、周辺の埼玉、千葉、茨城、栃木等の県で都市化の進展が著しく、被覆地(非透水性の土地)への転用が進んでいる。1980年以降の首都圏の自然植生度の変化をみると(第1-2-7図)、自然植生度7、8の二次林の地域及び2の農耕地(水田、畑地)が減少し、自然度6の造林地及び1の市街地、造成地が増大している。この中で、特に自然度7、8の二次林の地域は、自然林の地域と並んで多様な植物種を有し、それらに支えられた野生植物の種も豊かである。したがって、身近なところに存在する貴重な財産としてその保全を図ることが重要である。
また、人々の生活と生産活動を支えるかけがえのない資産である湖沼については、自然環境保全基礎調査によると、面積が1ha以上のものは首都圏に51個、合計で約290km
2
(山手線内側の面積の4.7個分に相当)存在している。しかし、首都圏の天然湖沼の面積は干拓・埋め立てにより減少の一途をたどっており、昭和20年以降の干拓・埋め立て面積は約54km
2
、18湖沼にのぼり、20年当時の約16%にあたる水面が消滅している。例えば霞ヶ浦では、かつては東京という大都市の膨張を食料供給の面から支えることを目的として農地開発が盛んに行われた結果、1918年から現在までに約25km
2
の湖面が失われている。