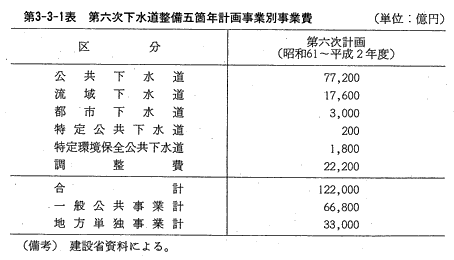
4 下水道整備
下水道は、都市の健全な発達と公衆衛生の向上を図り、良好な生活環境を確保するとともに、公共用水域の水質保全を図るために、欠くことのできない基幹的施設である。
下水道の整備は、下水道整備五箇年計画に基づき推進されているが、現行の第六次下水道整備五箇年計画は、計画年度を昭和61〜平成2年度とし、総事業費12兆2,000億円をもって、公害防止計画、閉鎖性水域における総量削減計画及び湖沼水質保全計画への対応、水質環境基準の達成、地方都市の普及促進、市街地等における浸水の防除及び生活環境の改善、湖沼等の自然環境の保全、農山漁村の生活環境の改善、並びに下水処理水及び下水汚泥の有効利用の促進等を目標とした下水道事業に重点をおいて下水道の整備を推進することとしている。なお、同計画の事業費内訳は第3-3-1表のとおりである。
第六次下水道整備五箇年計画の第三年度に当る昭和63年度においては、以下の施策を講じ、下水道整備の促進を図った。
(1) 下水道事業
昭和63年度においては、公共下水道事業実施977か所、流域下水道事業実施93か所、都市下水路事業実施681か所、特定公共下水道事業実施3か所、及び特定環境保全公共下水道事業実施172か所(簡易な公共下水道15か所を含む)で整備の促進を図った。この結果、63年度末における処理人口普及率は約41%になる見込みである。
また、下水道の整備による公共用水域の水質保全効果に着目し、住民と清らかな水との結びつきを深めることを目標とした「カムバックアクアトピア構想」を28都市で推進するとともに、下水道未整備地域において、都市下水路雑排水対策モデル事業を4か所(新規2か所)で、湖沼等における雑排水対策緊急モデル事業を4か所で実施した。
また、都市の住民のやすらぎや潤いのある生活へのニーズにこたえ、雪国での冬期の都市機能の維持や、都市内にせせらぎを回復するため、下水処理水を活用したアメニティ下水道モデル事業を12か所(新規3か所)、水需給のひっ迫する都市域において、下水処理水を水洗便所用水等の雑用水として活用する下水処理水循環利用モデル事業を7か所(新規1か所)、都市内を流れる公共下水道の雨水渠等の付近の緑化、遊歩道の設置を行うことによって下水道施設をより親水的にする下水道水緑景観モデル事業(ウォータースクウェアプラン)を15か所で実施した。
さらに、昭和63年度より新たに、下水汚泥の建設資材利用を促進するため、下水道の建設事業に汚泥製品を積極的に用いることを内容とする、下水汚泥資源利用モデル事業を愛知、三重、岐阜の3県で実施した。
(2) 流域下水道整備総合計画
公共用水域の環境基準を達成、維持するために必要な下水道整備に関する基本計画である流域別下水道整備総合計画の策定のため、昭和62年度までに174か所の調査が行われており、63年度においては、江の川等12か所の調査を実施した。
流域別下水道整備総合計画は、昭和62年度までに57か所について策定されている。
(3) 技術開発及び調査研究等
下水道事業の円滑な推進に資するため、下水道整備基本方針と合理化、下水道施設の合理的設計施工法、下水道における雨水対策、水処理技術の効率化と高度処理、下水道の維持管理とその適正化、下水道整備の効果と評価、下水道における環境対策、下水道資源の回収と利用、下水道の役割とその多様化への対応等の諸課題について調査を実施し、更に、昭和60年度からバイオテクノロジーを活用した新排水処理システムの開発(バイオフォーカスWT)に取り組んでいる。
また、民間における新技術の積極的な活用等を目的とした建設技術評価制度において、下水道管渠用高精度流量計の評価を行った。
(4) 日本下水道事業団
地方公共団体等からの委託により終末処理場の建設事業等を実施したほか、下水道技術者の研修、技術検定、下水道に関する技術開発、試験研究等を行った。また、新技術評価のための調査を実施した。
さらに、昭和61年度に創設された、下水汚泥広域処理事業(エースプラン)については、財政投融資金を活用し、63年度には3か所において実施した。