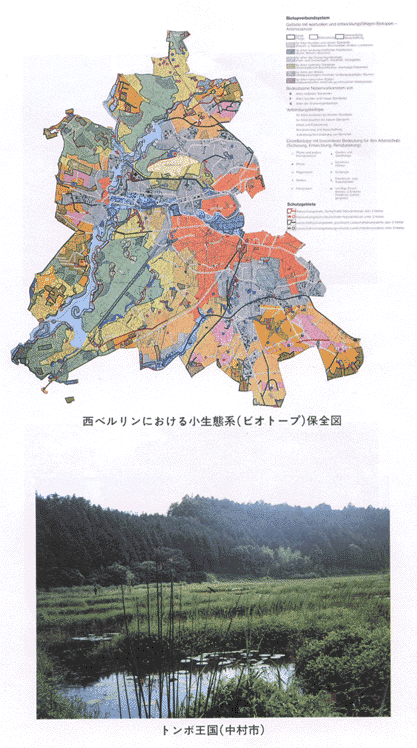
2 新しいライフスタイルと環境保全活動
近年、暮らしの中からの発想に根ざした環境保全のための実践活動や地域環境づくり、さらには地球環境をも視野に入れた活動等いわば新しい型の環境保全活動が芽生え、大きな輪を広げつつある。
また、情報化、ハイテク化が進展している中で、環境や自然との共生を目指したライフスタイルへの志向も国民の中に生まれつつあるとともに、近年の国際社会における地球環境問題への認識の高まりに呼応して、我が国においても急速にこれに対する関心が高まり、我が国の国民の環境観にも大きな進展がみられる。
ここでは、こうした新しい環境保全活動やライフスタイルについて、?暮らしの中から発想に根ざした環境保全活動、?地域の環境資源の保全・再生を目指した活動、に分けてその動向等を述べる。
(1) 暮らしの中からの発想に根ざした環境保全活動
豊かになった国民生活において、環境とのかかわりの中で暮らしを見直していく活動として代表的なものに、リサイクル活動と生活雑排水活動等の水環境保全活動がある。
ア 国民生活の向上に伴い、家庭において消費し、利用する消費財の量及び種類は増大しているが、これらの多くは有限な自然資源をその原料としたり、また、ものによってはごみとして処理する際に環境汚染をもたらし、あるいは埋立てることにより自然環境を損なう可能性がある。こうした考えのもとに、特に昭和50年代からいろいろな地域で多様なリサイクル活動が行われるようになった。
地方公共団体の廃棄物行政と連携するもの、再資源化産業と連携するもの、不要品交換を地域で組織的に行うもの等地域レベルの全くのボランティア活動から、広域的な組織化によって事業化するようになったものまで様々な活動形態がある。また、地域レベルのごみの分別から、空き缶、故紙、廃テンプラ油、牛乳パック等その扱う品目も様々である。
ごみ問題をきっかけにして、身近な暮らしの中から環境・自然と共生するライフスタイルをも追求するこうしたリサイクル活動は、そのネットワークを広げている。
イ 水質汚染は、第2節でみたように、生活雑排水による負荷がその要因として大きなウェイトを占めるようになってきた。こうした汚濁に対し、地元の地方公共団体等と連携しながら進められているのが、生活雑排水運動である。台所からの食物残さ等を排水管に流さないように、きめの細かい流し台三角コーナーやろ紙袋等による水切り、廃テンプラ油の回収・石けんづくり等が進められている。
また、これらと併せて、暮らしと環境とのかかわりを「環境家計簿」をつけて点検する活動、アオコの発生等の水質汚濁の状況を記録する活動、木炭を活用した小河川の直接浄化、各種イベントで河川や湖等の保全活動を行う等多様な活動が展開されている。
例えば、滋賀県下では、琵琶湖の汚染問題をめぐって様々な環境保全活動が展開されており、「琵琶湖富栄養化防止条例」の制定後は、洗剤問題から琵琶湖の環境管理へと活動の視野を広げ、環境家計簿、暮らしの点検運動を生み出している。
様々なきっかけから出発した水環境の保全活動は、今、大きなネットワークを形成しつつある。
(2) 地域の環境資源の保全・再生を目指す活動
損なわれた都市の生態系環境の再生や残された自然の保全等地域の環境資源を保全・再生するための活動は、近年大きな潮流となりつつある。いくつかの例をみる。
ア 水環境の保全活動は、先に述べた暮らしの中からの水質汚職防止の観点のみならず、河川、湖沼等の水辺環境の保全・再生、雨水利用等による都市地域の水循環の回復、湧水の保全・復活等を目指した活動としても展開されている。
水環境は、地域住民にとって重要でわかりやすい環境資源であり、その保全・再生に向けての活動は新しいコミュニティーを形成するとともに、そのネットワークづくりも図られている。例えば、水郷の街として知られる福岡県柳川市では、昭和52年、水路を埋め立てて下水溝を設置する計画が生じたのをきっかけにして、自治会等から成る排水路維持管理実施委員会により、行政と市民による底ざらえ活動等が行われ、水郷再生のための取組が実施されている。また、59年に組織された「水郷水都全国会議」は、様々な水環境保全・再生団体約150団体が参加し、全国各地で大会を開催している。
イ 一方、自然の保護等の分野においても新しい型の環境保全活動が展開されている。
ナショナル・トラスト(国民環境基金)活動は、市民による自然保護活動の代表的なのもであり、活動団体も年々増加している。広範な国民から寄せられる資金によって、地方公共団体、民間団体が良好な自然環境を有する土地の取得・管理を行い、その保全を図っていこうとするものである。例えば、北海道斜里郡小清水町では、地元有志が(財)小清水自然と語る会を設立し、全国からの寄付によりキタキツネ等の生息する樹林地を買い取り、保全している。都市近郊においても、埼玉県、神奈川県等において地方公共団体の主導の下にナショナル・トラスト活動が推進されている。
また、近年、ホタル、トンボ、チョウ等の身近な小動物とその生息環境の保全・回復を図るための活動が各地で進められている。例えば、埼玉県嵐山(らんざん)町では、地元有志が中心となって小学校、PTA、関係団体等からなる「オオムラサキの森づくり協議会」を設け、オオムラサキの保護増殖、生息環境保全調査等を実施している。また、高知県中村市では、(社)トンボと自然を考える会、(財)世界自然保護基金日本委員会(WWFJ)が中心になり、60種類に及ぶトンボを観察できるトンボ自然公園としてトンボ王国(中村市トンボ自然公園)を昭和63年に開園した。環境庁では、63年度より、このような小動物の生息環境の保全・回復に関する活動を支援するため、「ふるさといきものの里」の選定に着手している。
身近な生きものに対する国民の関心には極めて高いものがあり、例えば昭和59年度に実施された第3回自然環境保全基礎調査「身近な生きもの調査」には約10万人の調査協力者を得、約190万のデータが寄せられた。
ウ 一方、都市近郊に残された身近な自然地としての農地を、土とのふれあいの場、環境教育の場、新しいコミュニティーづくりの場等として市民に開放するものに、いわゆる市民農園があり、ドイツのクラインガルデン運動を一つのモデルとしている。地方公共団体が中心になって運営しているもののほか、農協が運営するもの、農地の所有者と市民が相対で契約するもの等様々な形態がある。
エ バードウォッチングや自然観察会は、自然に親しむとともに、自然生態系のしくみを学習する機会として、都市近郊等で盛んになってきているが、青空や星空を観察することによって星座等を学習し、任せて地域の大気の汚れ具合を知る活動が近年生まれている。
オ また、アメニティ活動は、多くの場合、以上述べてきた各種の活動をも包含するものであり、行政レベルでは、昭和63年6月に「全国アメニティ協議会」が設置されている。また、アメニティ活動を通じた地域の国際交流も進んでいる。例えば、60年から毎年実施されている「日仏アメニティ会議」は、現在、日仏科学技術協力協定に位置付けられ、共通の課題であるアメニティ施策について両国の地方公共団体を中心とした交流を深めている。