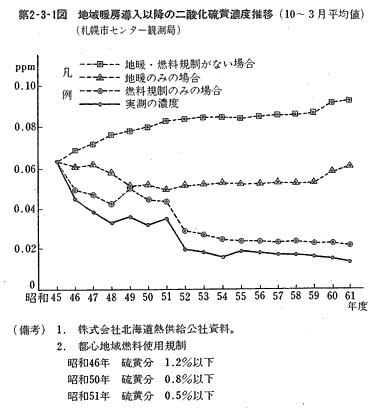
1 都市システムからの試み
都市を一つの系としてとらえると、都市活動を支える水や物資を循環的に利用し、エネルギーを効率的に利用するためのシステムを導入するとともに、都市の中に自然を保全・創出し、生態系に準じたシステムを構築することが、自立的、安定的な生態系循環を取り戻し、良好な都市の環境を形成していくこととなる。水の循環利用、エネルギーの効率利用のシステム等は、それぞれの背景をもって導入されつつある。ここでは、諸外国の事例をも含め、その背景を踏まえつつ、分野別に以下のように整理してみる。
(1) 各種交通対策
都市交通に起因する環境問題、混雑問題等の解消のため、都市において様々な取組がなされている。
まず、自動車走行の時間、地域、車種等に応じた制限である。
例えば、大型トラックの都市中心部への乗り入れ規制については、パリにおいて、原則として全面的に禁止しているほか、英国のロンドンでは夜間及び週末において、東京では環七の内側について土曜日夜から日曜日朝にかけて、それぞれ規制している。また、イタリアのミラノにおいては、土、日、祭日を除く平日の7時から18時まではタクシー、市営バス及び許可証をもつ自動車以外の都心部乗り入れを規制している。シンガポールでは、午前中のラッシュアワー時の中心部への乗用車の乗り入れに関して、4人以上の乗車の乗用車以外には料金を徴収している。また、米国ワシントンD.C.では、市内への主要通勤経路においては、午前6:30〜9:00、午後4:00〜6:30の間、3人以上乗車した乗用車以外は通行禁止となっている。その他、ギリシャのアテネ市、ブラジルのサンパウロ市、米国のデンバー市等においては、ナンバープレートの末尾番号に応じた侵入規制等を実施している。
また、西ベルリンでは、1987年1月末から2月初めにかけて、硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質の濃度が急激に高まったことに伴い、排出ガスの多い自動車の走行を禁止した。
都心や居住地域への通過交通量を制限する手段として「トラフィック・セル・システム」がある。これは、都心や居住地域をいくつかの区域に分けて、公共バス、救急車等を除く一般車両は直接区域間を往来することができず、一旦通過交通用の循環道路を経由して限定された入り口から侵入することを義務づけられる制度であり、スウェーデンのエーテボリで最初に導入され、西独のブレーメン、イタリアのボローニャ、フランスのブザンソン等の都市において採用されている。
このほか、各種の公共交通機関の共通運賃制度によって、乗用車の利用を抑制する制度が欧州、北米のいくつかの都市で実施されている。また、西独のフランクフルトでは、自動車による大気汚染を抑制するため、1988年10月から、主要交差点において12秒以上停車する場合には自動車のエンジンを切ることを指示する特別の信号が設置されている。
また、集配達を共同で行う共同輸配送、トラック・ターミナルの環状道路周辺への整備、自家用トラックから営業トラックへの転換等貨物輸送の合理化が推進されている。
第2節でもみたように、サービス経済化、生活様式の変化、業務ビルの整備等大都市の都心部における自動車の運行を派生させる要因は今後とも増大するとみられる。したがって、特に大都市においては、従前からの対策の充実・強化を図っていくことはもちろん、今までにない新たな対策についても検討を進め、逐次その具体化及び実行を図っていく必要がある。
(2) 水循環の再生のためのシステム等
先にみたように、都市における水循環は、様々な要因により損なわれている。その結果、まず問題視されたのが、都市洪水である。都市における舗装面、建物等の増大に伴い不透水地が拡大し、雨水は地中浸透せず、一気に都市河川や下水道に流れ、河川流出量の増大となって都市洪水が生じやすくなった。このため、透水性舗装、浸透マス等の雨水浸透施設や調整池等の雨水貯留施設が導入されるようになったが、これらによる雨水の地下浸透は、
a 地中水分の蒸散による都市気温の低減
b 地下水のかん養、湧水の保全・復活、植生の保全
c 土壌生物の保全の効果をもっている
一方、都市活動の高度化に伴う水需給のひっ迫に対応するため、ビル等の中水道設備や雨水利用施設の導入も進みつつある。雨水貯留や雨水利用は、降雨時の下水道への流入負荷を低減するとともに、都市内に貴重な水空間を生み出すことになる。また、中水道や雨水利用は、都市における水資源の有効利用・自立的利用を推進することとなる。また、水質が悪化したり水源のなくなった都市内の水路に下水道の処理水を導入して、せせらぎをよみがえらせ、市民の憩いの場、子供の水遊び場としての水辺を復活させたり、下水処理水をビルのトイレ用水等として利用する事業も進められている。
これらのシステム等の例をみると、例えば、新国技館(東京都墨田区)では、8,360?の大屋根に降った雨水を地下の1,000m
3
の雨水そうに貯留し、トイレ用水等、冷却塔補給水に利用している。これにより、雑用水の70%程度を賄っている。
また、東京都昭島市の昭島つつじが丘ハイツでは、住宅地、駐車場、広場等に雨水浸透マス、浸透トレンチを敷設して雨水の地下浸透を図っている。昭和61年8月4日〜5日に降った雨の流出量は、通常の下水管を敷設した地区では840m
3
/haであったが、地下浸透工法を実施した地区では121m
3
/haであり、低減率は約85%であった。
このように、都市洪水対策として導入されつつある各種のシステムは、都市の水循環を取り戻し、都市の生態系循環の再生に寄与することとなる。
(3) エネルギーの効率的利用のためのシステム等
エネルギーの効率的利用は、エネルギーフローの中のエネルギーロスを低減することと、自然エネルギーを利用することにある。エネルギー消費を低減したり、自然エネルギーを利用することは、窒素酸化物、二酸化炭素等の排出を低減するとともに、都市気候の緩和をもたらす。
近年、都市再開発の増大等に伴い、大都市を中心にして地域冷暖房システムの導入が進んでいる。我が国の地域冷暖房システムは、昭和40年代における都市地域の二酸化硫黄等による大気汚染への対応策として導入されはじめた。いくつかのビル等で共同して地域的に冷暖房することにより、エネルギーの利用効率を高め、また、集中的な環境対策が実施できる。同時に、エネルギーコストの低減、冷暖房施設のスペースの節約等の効果が得られる。地域冷暖房システムの環境保全効果を、公害防止事業団が融資してきた株式会社北海道熱供給公社の札幌都心部地域暖房の例でみると第2-3-1図のとおりであり、地域熱供給の普及と低硫黄分の重油の使用があいまって二酸化硫黄の環境濃度が改善されていることがわかる。地域暖房は、冬の寒さが厳しく長い北欧、中欧等で発達してきた。西独では、19世紀末から地域暖房が発達し、都市内の小規模な発電所や工場からの排熱を利用している例が多い。また、スウェーデンのストックホルムでは、海水や下水を熱源としてヒートポンプを利用する方法が多く、現在では、地域暖房の割合は50%を超えている。
ヒートポンプは、ポンプの駆動エネルギーとして電気、ガス等のエネルギー(商業エネルギー)を投入し、熱源として低温排熱等を利用するため、得られるエネルギー量は投入エネルギー量よりも大きい。これにより、豊富にある都市の低温排熱資源を有効に利用することが可能である。東京都の練馬区、板橋区にまたがる光が丘パークタウンでは、光が丘清掃工場(焼却能力150t/日×2)内の蒸気復水排熱(45℃程度)と超高圧地中送電線の冷却排熱(20℃程度)を熱源として、ヒートポンプにより暖房・給湯用の60℃温水及び冷房の7℃の冷水を得て、住宅に対しては暖房・給湯を、病院、商業施設等に対しては冷暖房・給湯を行っている。
コージェネレーションは、エンジンやガスタービンの動力等によって発電を行うとともに、その排熱を有効に利用し、熱供給するシステムである。これまでの発電システムでは、エネルギー利用効率は35〜40%程度にすぎなかったが、コージェネレーションは排熱を有効に利用することにより、電力需要と熱需要が適切に組み合わされた場合、エネルギー効率が70〜80%にまで向上し、エネルギー利用の効率化に寄与するものである。また、コージェネレーションとして、燃料電池を利用する方法も、近い将来可能になってこよう。燃料電池は、水素と酸素から電気を作るものであり、環境負荷も極めて少ないとされている。
太陽エネルギー等の自然エネルギーの利用については、太陽熱を利用した、給湯、冷暖房システムが普及しつつあるほか、太陽光による発電、風力による発電等が少しづつ利用され始めている。
このように、技術開発やこれに伴う経済性、制度等の進展により、エネルギーの効率利用の可能性は広がりつつある。当然のことながら、例えばエンジン、ガスタービン等によるコージェネレーションのように新たな環境負荷を地域的に増大させることとなるものもあり、この面での環境負荷の増大を極力低減するようなシステムづくり、技術的対応等に引き続き取り組む必要がある。
(4) 都市の自然の保全・創出に関する施策
都市における樹林地、草地等の自然は、気候緩和、大気浄化、地下水のかん養等都市の生態系循環にとって不可欠の要素であり、これらが損なわれているなかで、保全・創出のための各種の施策が講じられている。
まず、制度的なものとして、都市公園(都市公園法)、緑地保全地区(都市緑地保全法)、近郊緑地保全区域(首都圏近郊緑地保全法等)、風致地区(都市計画法)等が都市の樹林地等を保全あるいは創出することを目的としている。
また、近年、小動物等の生息環境を都市内につくり出すための事業が推進されつつある。
すなわち、身近な自然の喪失の著しい大都市及びその周辺において昆虫や野鳥等の小動物が生息できる環境を自然を損なわないように整備し、自然観察の拠点とするため、「自然観察の森」が昭和59年度から環境庁の補助によって整備されるとともに、62年度からは、建設省により都市公園とし「自然生態観察公園(アーバン・エコロジー・パーク)」が整備されている。
また、身近な場所に実のなる木等野鳥の好む樹木を植栽すること等により、野鳥の成育に適した環境の創出と野鳥に親しむ場の整備を図る「小鳥がさえずる森づくり」運動が、昭和59年度から実施されている。
ここで、都市の自然を保全・創出する施策の例として西独と英国の取組をみる。
西独では、1976年に「連邦自然保護・ラントシャフト保存法」が制定され、多くの都市で「ラントシャフト計画」が策定されている。例えば、西ベルリンでは、1984年に計画が策定され、そのなかで「種の保全計画」が定められている。「種の保全計画」は、特に動植物相の小生態系(Biotop)を保全、再生するためのものであり、小生態系が孤立しないようそれぞれの間に緑地帯等を配し、それぞれの小生態系をネットワークすることに主眼を置いている。
また、英国では、エコロジカル・パーク(生態系公園)の造成が盛んであり、民間の活動によって推進されている。これは、廃棄物処分場跡地、都市再開発等によって創出されたオープンスペースを利用して、小さな丘、小川、沼等をつくり、自然に生えてくる草、低木を利用するとともに、草花の種子を播いたり、植栽したりするものであり、都市における自然の創出をねらいとしている。
このように、西独等では、都市に自然を保全・創出する取組が進められており、我が国においても、公園、緑地の整備とともに、こうした方向への一層積極的な対応が必要である。
以上みてきたように、都市における生態系循環の再生に向けての試みは、我が国の都市においても萌芽が現れている。これらの試みを整理すると次のようなことがいえよう。
第1に、水循環の回復、エネルギー効率化等のシステムにみられるように、本来の目的である洪水対策、省エネルギー等の観点と生態系循環の視点とが一致し、当該システムが「環境保全型」であるということである。対症療法的な対策が新たな問題を惹起している面もあることからすると、本来の目的と環境の保全とが両立するシステムが徐々にではあるが開発され、導入されていることは、今後の環境政策の展開に大きな方向性を示すこととなろう。
第2に、これらのシステム等が導入されつつあるということは、経済性を有してきていることを示しており、環境対策=不経済という従来の図式から、「環境保全型」のものにも経済性を有するものが現れるという新たな段階が到来しているとみられる。
第3に、システム・技術開発やその経済性が進展している一方で、受け入れる制度面がこれに伴わない事例は多いが、環境保全型のシステムの導入についても、整合のとれた導入・整備ができるよう、政策面でも十分な対応が必要である。
第4に、都市の自然の保全についても、緑地を増やすとともに、都市における生きものの生息環境、小生態系を保全・整備し、これらをネットワーク化することにより、積極的に都市の中に自然を保全・創出する施策が重要になる。